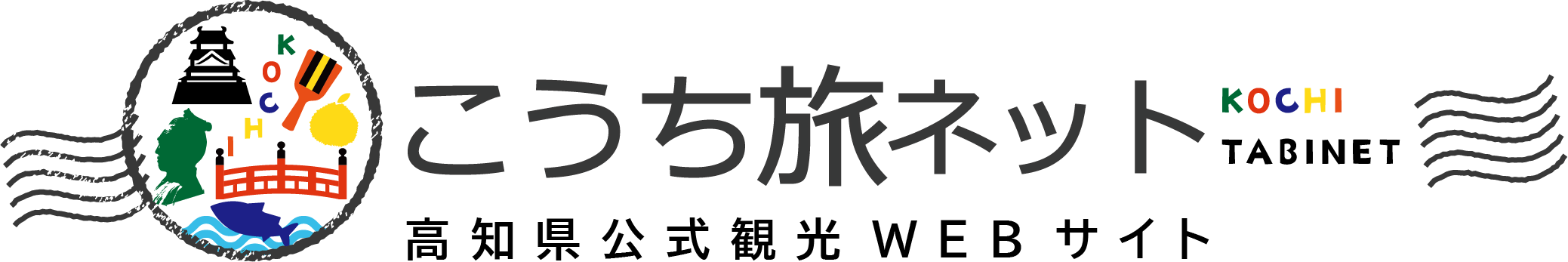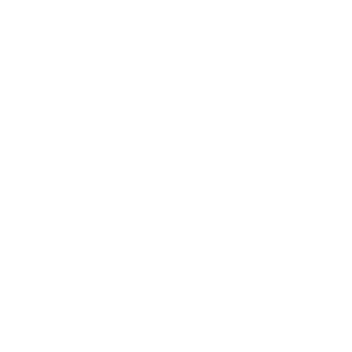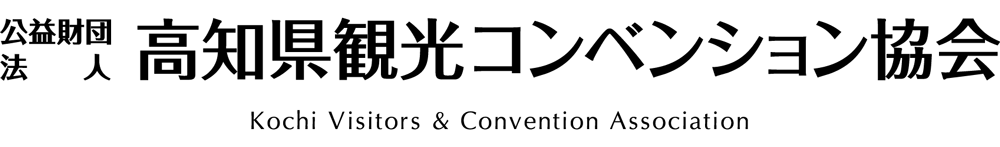観光案内所・観光協会検索Destination search
- 指定なし
- 閲覧数順
- タイル
- リスト
- マップ
-
賛助会員1. 香南市観光協会土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線のいち駅構内にあり、旅行で訪れた方、お遍路さん、地元住民の皆様に日々ご利用いただいている観光協会です。33.56183 133.69809
のいち駅売店をはじめ、香南市ギフトカタログで香南市の特産品の山北みかんや地元で捕れたちりめんじゃこ、四季折々の商品を紹介・販売・発送もしています。 -
2. 馬路村ふるさとセンターまかいちょって家馬路村の観光案内所であり、ゆず製品や魚梁瀬杉の木工芸品などを数多く販売しています。33.549717 134.04941
むらの案内人クラブの受付も行っており、事前予約していただくと村のガイド人が隅々まで案内してくれます。
また、2階には旧魚梁瀬森林鉄道の資料を展示しており、当時の写真やビデオとともに村の歴史を学ぶことができます。 -
3. さかわ観光協会(うえまち駅)佐川町の観光案内や情報発信を行っています。33.49886 133.2879
佐川町内の観光案内パンフレットはもちろん近隣の市町村等の観光パンフレットもあります。
隣の旧浜口家住宅ではカフェや特産品・お土産物の販売も行っています。 -
4. 桂浜観光案内所ガイドマップやパンフレットでより詳しく桂浜公園を知ることができます。33.499195 133.57489
ガイドボランティアがお困りごとにお応えします。 -
5. 足摺宇和海国立公園竜串ビジターセンターうみのわ竜串湾、桜浜を臨む絶好のロケーションにある足摺宇和海国立公園のビジターセンター。32.79109 132.8633
国立公園内の観光情報や自然解説を行っており、土佐清水ジオパークの拠点施設も兼ねています。フリーWi-Fi、キッズコーナー、授乳室、シャワーなどが完備されており休憩にもご利用いただけます。館内では無料の体験プログラムのほか、有料のガイド付きプログラムを実施。オリジナルグッズの販売も行っています。
地域をよく知るスタッフが、旬の情報やこの土地ならでの自然体験をご紹介します。 -
6. なはりの郷奈半利町を活気ある町にしようと立ち上げた、集落活動センターです。33.42479 134.02153
住民の方々の憩いの場でもあり、観光パンフレットも置いていますので、奈半利町へ観光に来ていただいた方のための「観光案内所」の一面もあります。
また、事前予約が必要とはなりますが、街並みの案内ガイドもあります。 -
7. 仁淀ブルースクエアJR西佐川駅にある交流スペース。33.512638 133.28651
仁淀川流域6市町村のパンフレットやイベント情報を提供、仁淀川流域の商品販売もしています。
観光する場所をゆっくり探せるテーブル席のほか、列車や線路を望めるカウンター席もあります。 -
賛助会員8. 土佐清水市観光協会土佐清水市内の総合観光案内の窓口。32.781464 132.93271
市内の宿泊施設や観光スポットなど情報提供可能。
市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。
(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットもご用意しています。) -
賛助会員9. 室戸市観光協会室戸市の観光情報を一堂に集めた総合観光案内所です。33.24604 134.1773
案内カウンターでは、手荷物を預かるサービスや室戸ユネスコ世界ジオパークを地元ガイドのガイド案内、シェアサイクルなど様々な体験ができます。
室戸市内や東部地域のパンフレットをご用意しています。(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットも多数ご用意しています。) -
賛助会員10. 土佐市観光協会土佐市の最新観光情報を窓口はもちろんのこと、各種SNSでも発信しています。33.4948 133.42424
お遍路さんの手荷物一時預かりを無料で行っています。
札所までの交通案内等、お気軽にお立ち寄り、お問い合わせください。
土佐市特産品の販売も行っており、御中元・御歳暮のギフト発送も可能です。 -
賛助会員11. 宿毛駅観光案内センター(宿毛市観光協会)土佐くろしお鉄道・宿毛駅1Fにある観光案内施設です。観光案内、特産品の販売、高速バスチケットの販売、周辺観光に便利な電動自転車、ロードバイクのレンタルなどを行っています。32.932552 132.71329
-
12. 伊尾木洞観光案内所伊尾木洞駐車場内にある観光案内所は、伊尾木洞散策の拠点施設です。洞窟の見どころや注意事項が分かる情報を入手できるほか、建物周辺ではフリーWi-Fiが利用可能。散策の様子をSNSでシェアするのにも便利です。特に人気なのが長靴の無料レンタルサービス。洞窟内は足元が濡れているため、長靴があれば安心して探検を楽しめます。夏場はヘビ対策としてもおすすめです。使用後は洗い場で泥をよく落としてご返却ください。ただし、洞窟内が増水している時は危険ですので、長靴着用時でも入洞はお控えください。快適で安全な伊尾木洞探検をサポートする、必ず立ち寄りたいスポットです。33.49025 133.93231
-
賛助会員13. 四万十町観光協会四万十町内の観光案内を行っています。33.21071 133.1366
まち歩き体験やレンタサイクル、コインロッカーなど、観光のお客様に便利にご利用いただけるよう整備しています。
無料の観光パンフレットや地図、イベント情報を掲示・配布しておりますので、観光のお客様以外にもお遍路さんや地元住民にもお越しいただいています。
訪日外国人旅行客の対応も可能です。 -
賛助会員14. 東洋町観光振興協会日本随一のサーフスポット「生見サーフィンビーチ」や、鮎釣りスポットで有名な「野根川」を有する東洋町。夏には白浜海水浴場に、四国最大級の海上アスレチックも出現。33.54217 134.29146
海、山、川に囲まれたこの町で、豊かな自然を活かした観光事業を発信しています!
様々なパンフレットやイベントのチラシを常設しています。
タブレットをおいているので、MAPや宿泊先への行き方もわかりやすくご案内できます。
日本人スタッフしかいませんが、翻訳アプリを使用し外国人観光客への対応も可能です。
町内各所にあるレンタルサイクルを観光協会にもご用意しています。
■レンタサイクルPIPPA
レンタサイクルの貸出あり。(要アプリダウンロード)
隣接す ... -
15. 四万十川ふるさと案内所JR江川崎駅構内にあり、列車やバス等を利用する観光客の方に対して観光案内を行っています。33.17807 132.78336
-
16. すさきまちかどギャラリー 旧三浦邸高知県須崎市の古商家・三浦家の元邸宅を利用した市民ギャラリー。33.389927 133.28955
観光案内所と地域の憩いの場を兼ねた総合交流施設です(平成22年2月12日から運営)。
大正時代中期に建てられた、高知を代表する商家建築と評される貴重な建造物を、無料で見学することができます。
周辺地域の案内のほか、市街地散策に便利なミニサイクルの貸出し、まち歩きガイドツアー、須崎の伝統文化「わら馬」づくり体験プログラムを実施しています。(いずれも要予約) -
17. 道の駅ビオスおおがた情報館高知市方面から土佐西南大規模公園への入口となる浮鞭地区にある、公園施設や観光情報の案内施設。33.03464 133.02695
観光・道路案内、入野松原キャンプ場の受付(NPO砂浜美術館)、浮津キャンプ場の受付((一社)黒潮町観光ネットワーク)、写真展などの企画、その他公園施設の利用案内を行っています。
館内にはミンククジラの標本展示や休憩スペースがあり、多数のチラシやパンフレットも設置しています。
隣には黒潮町が地域の物産などを販売する「物産館」も併設されています。 -
18. 佐川駅無人観光案内所JR佐川駅構内にある無人観光案内所。33.50011 133.2925
各種パンフレット有り。
デジタルサイネージで、佐川町の観光案内と牧野博士の紹介をしている。
コインロッカー有り(有料) -
19. 高知県バリアフリー観光相談窓口高齢の方や障害のある方など、誰もが高知県観光を楽しめるお手伝いをさせていただきます。33.560165 133.54256
事前予約制で車いすやシルバーカー、ベビーカーも貸し出しています。 -
20. 安芸観光情報センター ~彌太郎こころざし社中~2020年3月28日、三菱グループ創業150周年に合わせて、安芸市出身である岩崎彌太郎の一生涯を追体験できる全長約13mのVRシアターや、船とコンパスをイメージしたタッチパネル式情報収集機器を新たに設置。33.50236 133.90788
また、安芸市を中心に高知県東部地域(芸西村、安田町、北川村、馬路村、田野町、奈半利町、室戸市、東洋町)の観光情報発信や特産品の販売、無料レンタサイクルも行っています。 -
賛助会員21. 西土佐四万十観光社四万十市西土佐地域のありとあらゆる観光情報を網羅。四万十・川の駅カヌー館内にあり、カヌースクール、キャンプ場、屋形船、サイクリングの案内などもしています。33.16873 132.79234
-
22. 仁淀川町観光協会高知県の奇跡の清流「仁淀川」の最上流域、愛媛県との県境に位置する町の観光案内所です。33.57454 133.16785
-
23. 柏島観光情報発信センター柏島を訪れる多くの観光客が最初に立ち寄る、観光案内所兼販売施設です。柏島観光の際は、まずここの駐車場に車を停めるのが基本となっています。島内の飲食店、宿泊施設、ダイビングショップなど、柏島観光に必要な情報がすべて揃う便利な拠点です。32.767708 132.62717
柏島観光の際は、この観光案内所の駐車場を利用するのが基本です。車を停めたら、島内の観光情報をここで収集してからスタートしましょう。
観光案内だけでなく、柏島オリジナルグッズや軽食の販売も行っており、休憩スポットとしても最適です。周辺地域の観光パンフレットも豊富に用意されています。 -
24. 足摺岬観光案内所営業時は、観光ボランティア会の方が対応。32.72581 133.01976
市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。
(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットもご用意しています。) -
賛助会員25. 須崎市観光協会須崎市の総合観光案内所です。33.392376 133.29266
須崎市の飲食店や観光地の情報はもちろん、ツアーや体験イベントの案内等も行っております。 -
26. 南国市観光協会土佐のまほろばと呼ばれる南国市の楽しい観光情報を発信しています。「なんごく」と誤読されることが多いですが、本来の読み方は「なんこく」です。33.575638 133.6415
-
27. 北川村文化観光公社95%が山。そんな自然がいっぱいある北川村の魅力を紹介している。33.44849 134.04199
ここは、モネと中岡慎太郎の面影残る山里であり、現在、柚子玉がフランスへ向けて輸出もされている、日本でも有数の柚子の産地でもある。
観光案内は、お電話やHP等からのお問合せのみ対応しています。 -
賛助会員28. 四万十市観光協会四万十市内の観光地や飲食店、宿泊施設の紹介をはじめとした観光案内全般を行っています。32.983925 132.94423
各種パンフレットや地図を配架しており、四万十川観光遊覧船のお得なチケット、Shimanto Ashizuri Bus Passのお取扱いもございます。
また、通年でレンタサイクル、夏季限定でライフジャケットの貸出をしています。
レンタサイクルは全部で5種類、約80台を取り揃えており、英語での貸出対応も可能です。 -
賛助会員29. 大月町観光協会魅力あふれる町!大月町の観光情報を集めた観光案内所。32.828587 132.70932
町内にてイベントの開催や大月町の情報を県内外に発信しています。 -
30. 竜串観光案内所営業時は、観光ボランティア会の方が対応。32.78871 132.867
市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。
(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットもご用意しています。) -
31. こうち旅広場高知での旅をサポートしてくれる高知観光情報発信館「とさてらす」、人気のフォトスポット「三志士像」など、高知に着いたらまず立ち寄りたい旅の拠点です。33.566925 133.54272
●高知観光情報発信館「とさてらす」
高知県の観光情報を一堂に集めた総合観光案内所で、英語対応可能なスタッフが常駐しています。
手荷物を宿泊施設へ配送するサービス(有料)、はりまや橋・牧野植物園・桂浜など高知市内の観光スポットを回る周遊バス「MY遊バス」や路面電車等のチケット販売のほか、県内を7つのエリアに分け旬の観光情報や見どころを紹介するコーナーでは400種類を超えるパンフレットをご用意しています。(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパン... -
賛助会員32. 土佐さめうら観光協会国道439号沿いにある道の駅「土佐さめうら」内にある。ここでは、土佐町の地元産品や民工芸品の展示・販売も行う。豊かな自然と早明浦ダムを生かした観光を目指し、「活力のあるまちづくり」活動を推進する嶺北の道案内や観光の見どころを発信しています。33.742626 133.54427
-
33. 村の案内所ひだか日高村の「村の駅ひだか」の駐車場内にある「村の案内所ひだか」です。133.35501 33.53156
日高村観光協会が運営しており、村内・広域の観光情報案内・村内体験観光の実施を行っています。
外国語のできるスタッフは常駐していませんが、翻訳ツールなどを使って可能な限り外国人観光客の対応も行っています。 -
34. 香美市いんふぉめーしょん『香美市いんふぉめーしょん』では香美市の観光情報はもちろん、お隣の南国市や香南市といった物部川エリアや高知市内など、高知県の楽しい情報が盛りだくさん!33.60703 133.6849
パンフレットやイベント情報もたくさんご用意しております。 -
35. 仁淀ブルー観光協議会高知県仁淀川流域6市町村(土佐市・いの町・日高村・佐川町・越知町・仁淀川町)の、自然や歴史文化、伝統産業など、それぞれの観光素材を組み合わせた広域的な着地型旅行商品の組み立てや企画などを行っていて、「仁淀川」を中心にした山から海までの流域6市町村の魅力の発信をしています♪33.512596 133.28656
JR四国・西佐川駅の駅舎の中にあります。 -
賛助会員36. いの町観光協会JR伊野駅から徒歩5分、とさ電伊野駅から徒歩30秒の場所にあります。33.548252 133.42792
仁淀川観光の玄関口として、観光情報の発信や案内、レンタサイクルなどを行っております。 -
賛助会員37. ゆすはら雲の上観光協会梼原町は、高知県と愛媛県の県境にある小さな町です。33.391556 132.92686
この小さな町に、歴史、森林・自然、隈研吾建築など、見どころが詰まっています。
案内所では、翻訳システムを使用することで外国の方も対応が可能となっており、多言語の観光パンフレット(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語)も用意しています。
また、森林・自然ガイドツアー、隈研吾建築ガイドツアーなど(要予約)があります。 -
38. 高知龍馬空港総合案内所空の玄関、高知龍馬空港1階到着ロビーにある案内所です。33.547333 133.67427
県外、県内、外国のお客様からの観光案内、落とし物、各地へのアクセス情報、館内施設等の様々なお問合せに対応しています。
また、龍馬パスポート(青パスポートのみ)の交付や、牧野植物園、竹林寺、桂浜などの主要な観光地を巡る「MY遊バス」の乗車券販売もしています。
各観光施設のパンフレット、イベント情報等も取り揃えています。 -
39. こうち観光ナビ・ツーリストセンター高知駅前すぐ、「こうち観光ナビ・ツーリストセンター」は、高知県内34すべての市町村の観光情報を集めた広域観光案内所。英語対応スタッフも常駐しているので、海外からのお客様も安心です。33.5601 133.53662
県内の観光スポット案内はもちろん、手荷物預かり(有料)、龍馬パスポート(青)の発行、「MY遊バス」のチケット販売など、観光に便利なサービスが充実。パンフレットは日本語に加え、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語もご用意しており、郵送サービスも行っています。
観光の計画を立てるのにぴったりのスポットです。 -
40. 越知町観光協会越知町観光協会は、越知町の魅力をたくさんの方々に知っていただく為に、様々な活動を行っています。33.530483 133.25092
より魅力的なご案内ができるよう努めてまいりますので、お気軽にお立ち寄りください。 -
41. 大豊町観光開発協会高知県の嶺北地域にある、吉野川と山地に囲まれた自然あふれる大豊町。「おいでよおおとよプロジェクト」を立ち上げ、四国山地の中央部・大豊町の観光やイベントの情報を発信しています。33.76428 133.66417
-
42. 本山町観光協会板垣退助の先祖ゆかりの地である本山町にあり、周辺のオススメスポットを発信。また、気軽に楽しく参加できる企画もしており、さまざまな学習や体験メニューを用意しています。33.759697 133.59