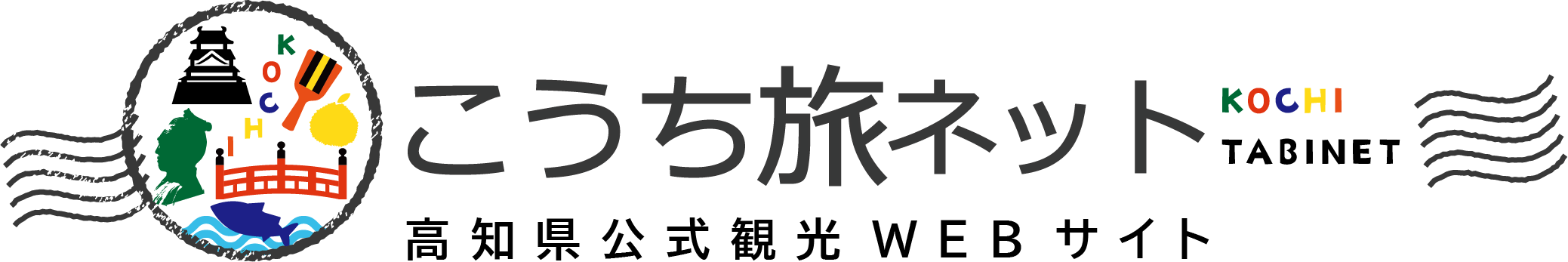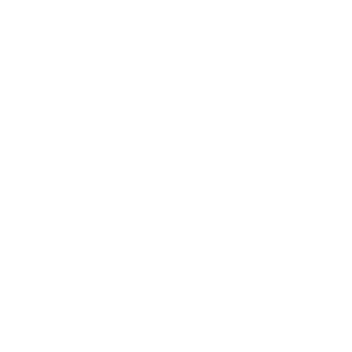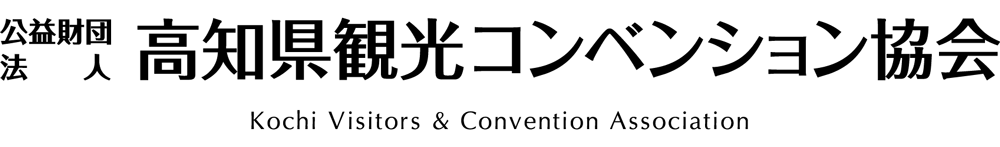伝統行事・年中行事Destination search
- 指定なし
- 閲覧数順
- タイル
- リスト
- マップ
-
1. 池川神楽池川神社社家を中心に伝承されてきたもので、文禄2年(1593)の「神大神楽記」に土佐の神楽としては最古のものと記されています。中でも「児勤の舞」は土佐神楽の中でも池川神楽にのみ見られる特異な舞。0.0 0.0
所要時間4時間。国指定重要無形民俗文化財 -
2. 大川村 謝肉祭村のビックイベント・謝肉祭(しゃにくさい)。33.829464 133.47
年に1度、大川村が開催する村最大のお祭りです。
1983年から続く伝統的なイベントで、村民が一丸となってお客様をおもてなし!
幻のお肉を求めたリピーターも多く、全国各地から1,500人(村民のおよそ4倍!)が訪れます。
秋空のもと、宴好きな1,500人が集います。紅葉で色づく山々に囲まれてのBBQは格別の美味しさ!
超レアな大川黒牛とはちきん地鶏をお腹いっぱい食べられます。そして、なんと地酒は飲み放題!
宴に欠かせない音楽や、村人手作りのお料理も楽しめます。 -
3. 津野山神楽国指定の無形民俗文化財。町内4ヶ所の神社(2ヶ所の三嶋神社、三嶋五社神社、河内白王神社)で「宮入り」「山探しの舞」等の演目をそれぞれ5時間程奉納します。0.0 0.0
-
4. 都の太鼓踊り屋島の戦いに敗れた平家一門は、仁淀川町都へ落ち延びたと伝えられます。その時伝授されたのが「太鼓踊り」で、安徳天皇の御霊を安んじ奉るために皇陵塚前で円形になって唄と太鼓に合わせて優美な踊りを繰り広げます。0.0 0.0
踊りは別名“都踊り”とも言われ、数百年前より絶える事なく行われています。 -
5. 土佐の太刀踊り(椎名太刀踊)室戸岬町椎名にある椎名八王子宮にて奉納されます。0.0 0.0
楽器は拍子木だけで、踊りの中の太刀さばきは豪快です。
県の無形民俗文化財に指定されています。 -
6. 鼓踊り・花取踊り春に開催される鹿島神社大祭では、神輿戻しや子どもたちによる鼓踊りが奉納されます。同じく佐賀地区で古くから伝承される天満宮曽我神社大祭では、2体の神輿が練り歩き、幼児のかわいらしい花取り踊りと鼓踊りが奉納されます。0.0 0.0
-
7. 安居神楽安居川沿いの集落の秋祭りに奉納される神楽。寛永2年(1790)の神楽本、天保9年(1838)の神楽面が資料としてあり、古くは社家岡林家が伝承したものと伝えられ、大正5年頃、安居の神職安居宝定氏がその伝承を受け、保存伝承しています。演目は舞出しの舞、悪魔払いなど15通り。国指定重要無形文化財。0.0 0.0
-
賛助会員8. 土佐赤岡 絵金祭り2024(令和6)年7月20日(土)~21日(日)33.54172 133.72298
強烈悽惨な魅力を放つ、幕末の絵師金蔵の血湧き肉おどる芝居絵屏風を一挙に公開展示!
年に1回の機会です!!
1977(昭和52)年、当時の赤岡吉川地区商工会青年部が商店街の発展を願い始めました。町内の須留田八幡宮で行われていた神祭にならい、幕末の絵師金蔵、通称絵金の芝居絵屏風23点を商店街に並べながら、さまざまな催しを実施しております。 -
9. 大川村さくら祭・しばざくら祭さくら祭・しばざくら祭は、大川村に暮らす川上さんご夫婦が主催するお祭りです。0.0 0.0
Uターンしてきた当時は、村には桜があまりなく、「ここでみんなが桜を見られたら、素敵だろうになぁ」と思ったそう。
夫の文人(ふみと)さんとともに、10年もの月日をかけて自宅の裏山を切り拓き、100本もの桜の木を、自分たちで植えたのが始まりです。
ふたりの粋な企てにはサポーターも多く、会場の装飾や出店も、みなで手作りしたものばかり。
桜を愛で、音楽を聞きながら、美味しいごはんを食べられる。そんなお祭りです。 -
10. いざなぎ流(舞神楽・御祈祷)数百年も前から住人により守り伝えられてきた民間信仰「いざなぎ流」。0.0 0.0
太夫は一般の住民で、その知識は師匠から代々受け継がれています。内容は神祭り、虫供養、狩猟、鍛冶、杣、雨乞、病人祈祷など多方面。個人宅でなされるので不定期となっています。国の重要無形民族文化財指定の舞神楽は太鼓、錫上、数珠に合わせた7~8名の氏子による舞。 -
11. 津野山古式神楽津野山古式神楽は延喜13年(913年)藤原経高が京より津野山郷に来国したときに、神話を劇化したものを神楽として伝えたことが始まりとされています。「宮入り」から「四天の舞」まで全部で17の舞があり、すべての舞を舞い納めるには8時間ほどもかかります。秋祭りに氏子が五穀豊穣、無病息災を祈願して神社へ奉納しますが、その他氏子が願ほどきに奉納することもあります。11月には町内各地の神社で奉納されています。33.36834 133.00935
-
12. 津野町の花取り踊り花取踊りは、高岡郡や幡多群の中世津野氏文化圏に多く伝承されています。踊りの起源については諸説あり、津野氏と一条氏の戦いの際に敵を油断させるために舞われたともいわれています。10月の終わりには姫野々三嶋神社や津野氏ゆかりの神社などで奉納されます。県の無形民俗文化財に指定されています。33.444748 133.20872
-
13. 佐喜浜俄団尻内からの芸題の口上がつげられ、拍子木打ち・大ぼん(脚本)読みが位置みつき、数人の演者によって演ぜられます。演題は町内の出来事から古今東西あらゆる問題をとりあげ、毎年「新版」が作られています。0.0 0.0
-
14. シットロト踊り古来鰹漁業の「夏がれ」に当たる旧暦の6月10日に漁師や漁業関係者たちが集まり、魚の供養と漁招きを兼ねて旧室戸町内の神社や仏閣など28ヶ所を早朝から一日中廻って奉納する念仏系盆踊りの一つです。0.0 0.0
揃いの浴衣に大小の猿を形どった花笠(難を去る、災いを去るという意味)をかぶった踊り手数十人が、太鼓と鉦、音頭の歌に合わせて「シットロト、シットロト」と囃しながら円になり扇子を振って踊ります。 -
15. 蓮池の太刀踊り県指定無形民俗文化財。蓮池西宮八幡宮の秋祭りで奉納されます。 南北朝時代に武将が戦勝の報告を行った際に祝賀行事として即興的に奉納したのが起源であるという伝承があります。 演目は11通りあり、太刀のほかにザイ棒を手に踊る演目もあります。踊り子のなかに鉦一名、締太鼓一名がおり、音頭は列外に立って歌います。33.4901 133.40773
-
16. 堂の口開け津野町宮谷地区にある明王寺薬師堂の開帳日に行う行事。地区民が藁を持ち寄り、「魔よけの大わらじ」や「注連縄」をつくり奉納します。この「大わらじ」は国道197号沿いの地区の入口に飾られています。33.567238 133.54367
-
17. 秋葉まつり仁淀川の最上流域の集落でおよそ200人が古式の衣装を纏い神輿(みこし)に秋葉神社の神様を乗せてゆかりの地を巡る美しい行列「練(ね)り」が早春の山里を彩ります。33.53257 133.05637
高知県保護無形民俗文化財に指定されていて、土佐三大祭りに数えられています。
秋葉神社は「火産霊命」(ほむすびのみこと)を祀っていて防火の信仰があります。元々は、平家の落武者である佐藤清岩が遠州秋葉山から勧請して岩屋集落の大巌の洞窟で祀ったのが始まりで、その後、法泉寺、関所番の市川家で祀られてきました。寛政6年(1794)に現在の秋葉神社に祀られるようになってから、毎年1回、それまでゆかりのあった岩屋神社、市川家、法泉寺、中越家にご神幸を行うようになり ... -
18. 赤野獅子舞高知県の安芸市にある赤野では、夏と秋に獅子舞の奉納が行われます。33.51601 133.83505
担い手の減少で途絶えかけた伝統を赤野の人たちが再び築きあげています。
夏祭りは7月22日(大元神社)と7月23日(住吉神社)に、
秋まつりは10月第2日曜日(住吉神社)に獅子舞奉納が行われています。
赤野獅子舞の始まりは分かっていませんが、600年以上の歴史があると言われています。
1969(昭和44)年に高知県保護無形民俗文化財に指定されました。
2014年に結成された「赤野獅子舞保存会」の活動に地元の小学生らも加わって、郷土と文化を作り上げています。
夏祭り、秋祭り共に一般の観覧ができます。 -
19. 大谷花取踊毎年10月18日、須賀神社境内で奉納されます。多ノ郷の太刀踊と同じく津野山系の踊り。33.385883 133.3183
-
20. 太刀踊り【三原村】0.0 0.0
-
21. 手結の盆踊8月15日、夜須町ヤ・シィパークで行われます。0.0 0.0
-
22. 興津八幡宮の古式神事高知県指定無形民俗文化財。毎年10月15日に行われる秋祭りの神事。宮舟、花取踊、流鏑馬の3つが中心。33.1675 133.20903
-
23. 斗賀野花取り踊り古来より神社の祭礼に奉納された太刀踊りの一種。0.0 0.0
戦国時代一条勢が津野氏の花取城(須崎)を攻めたとき、城兵をあざむくため、軍中の美青年を選んでこれを躍らせ、城兵が門を開いて城下に出て踊りに見とれている隙に討入り落城させたことで、花取踊りの名が残っています。 -
24. 仁井田神社の花取り踊り地元に古くから伝わる郷土芸能。仁井田神社の大祭(11月25日)に披露されます。0.0 0.0
-
25. 椎名(八王子宮)みこし洗い椎名地区で行われる神祭での神事。神輿が海へ入る前には多くの人が訪れ、その姿を見守ります。他に太刀踊なども見ることができます。0.0 0.0
-
26. 太刀踊り【大月町】町の無形文化財。平家の落人によって伝えられたといわれる軽快で勇壮な踊り。0.0 0.0
-
27. 瑞応の盆踊り県指定を受けた唯一の盆踊。0.0 0.0
五穀豊穣を神に感謝し、豊年踊りを奉納します。 -
28. 太鼓踊り胸にかけた大きな紋太鼓を両手で太鼓を叩きながら踊る。21通りの演奏があります。0.0 0.0
-
29. 花取り太刀踊り室町・江戸時代よりの長い伝統をほこる郷土芸能で、県指定の無形民俗文化財ともなっています。女性の手踊りと薙刀を手にした薙刀踊り。日本刀を得物とする男性の太刀踊りの3種類があり、これらを総称して「花取り太刀踊り」と呼んでいます。0.0 0.0
-
30. 手結のつんつく踊り現在伝えられているのは、玉草(たまずさ)、とおばしり、君が代、綾踊り、若き姫たちの5通りの踊り。0.0 0.0
踊り子は、烏帽子(えぼし)に白上衣、白袴姿で、締太鼓を手にした太鼓打ちと、摺鉦(すりがね)を手にした鉦打ちほかの踊り子多数は扇子を手にして、終始円形で踊ります。 -
31. 佐川町太刀踊り高知県の無形文化財に指定されている四ツ白太刀踊り。起源は、平家一族が屋島を逃れて越知町横倉に入り、安徳天皇を慰めるために踊ったことが始まりといわれています。0.0 0.0
剣士姿に白鉢巻、乱舞する白紙片が吹雪を思わせます。 -
32. 若一王子獅子舞鎌倉時代から伝わる獅子舞。秋の大祭に五穀豊穣、悪疫退散を祈願し、奉納されます。33.556816 133.73463
-
33. 沖名の花採太刀踊県無形民俗文化財指定。入れ葉、、シノギ、鎌倉山、清盛、忠臣蔵など十二通りの踊りがあります。県の無形民俗文化財に指定されています。0.0 0.0
-
34. 三番叟津野神社の秋祭りに奉納される貴重な郷土芸能。百年余の歴史を有すると推定されます。0.0 0.0
-
35. 立山神社棒術獅子舞1221(承久3)年、承久の乱で土佐国幡多へ流された土御門上皇が、土佐から阿波へ遷る途中、ここで名月を眺めて都をしのんだという伝承から月見山の名が生まれ、これを記念して立つ碑。0.0 0.0
「鏡野やたが偽りの名のみにて恋ゆる都の影もうつらず」(「土御門院御集」) -
36. 岩原神楽・永渕神楽国の重要無形民俗文化財に指定されています。0.0 0.0
-
37. 山北棒踊り白装束にタスキがけ、鉢巻姿の青年が191cmの長棒で華々しく演じます。棒打ち、棒術とも呼ばれます。33.58293 133.74034
-
38. 下津井の牛鬼四万十川流域に伝わる「牛鬼(うしおに)」は、魔除けと五穀豊穣を願い、秋祭りに登場する伝統的な神事。鬼のような顔と牛の胴体をもつ異形の存在が、集落を練り歩くその姿は圧巻です。西土佐半家天満宮では、牛鬼が先頭に立ち神輿を導き、半家沈下橋を渡る様子が地域の秋祭りの象徴となっています。0.0 0.0
さらに、竹筒で鳴き声を響かせながら田畑を踏みならす様子や、振舞われる地酒、疲れ果てて脱落する担ぎ手の姿までもが祭りの一興。地元に根ざした暮らしと信仰が織りなす、まさに“生きている伝統”です。年々担い手が減る中、地域と企業が一体となって守る貴重な文化を、ぜひその目で確かめてみてください。 -
39. 若井の花取り踊り貴重な民俗の姿で畑地の生命と豊作を神に祈る踊り。33.18331 133.1001
昭和41年5月に四万十町指定無形文化財に指定されました。 -
40. 椿山太鼓踊り平家落人伝説の里であり、また最近まで焼畑耕作の残されていた椿山集落に伝わるもので、平家の武将や公達を慰める踊りとして古くから受け継がれてきました。0.0 0.0
6月20日虫供養、8月3日氏佛祭、8月14日若仏祭、9月5日先祖供養で踊られます。 -
41. 四万十町古城の施餓鬼大念仏毎年8月6日、四万十町古城にある観音堂で行われる「施餓鬼大念仏(せがきだいねんぶつ)」は、地域に長く受け継がれてきた供養行事です。夕暮れから夜にかけて、太鼓と鉦(かね)の響きが境内に鳴り響き、独特の雰囲気に包まれます。0.0 0.0
この行事は「神念仏」と「御刀念仏(おとうねんぶつ)」の二部構成。神念仏では、太鼓と鉦にあわせて念仏を唱え、静かにご先祖さまや地域の守り神に祈りを捧げます。
後半の御刀念仏では、山伏が登場し、東西南北に向かって口上を述べると、太刀や団扇、箒(ほうき)などを手にした人々が登場。それぞれが太鼓のリズムに合わせて所作を行いながら境内を巡ります。草を刈る動きや掃き清める動きなど、自然や空間... -
42. 五ツ鹿踊り地吉八幡宮だけに伝えられている、伊予文化の影響を受けた踊り。0.0 0.0
-
43. 川又神社の花取り踊り川又神社境内に筵を敷き18演目をおどります。0.0 0.0
大太刀が長い鳥毛を、小太刀が烏帽子をかぶり踊る、江戸後期から伝わる踊りです。県の無形民俗文化財に指定されています。 -
44. 竜ケ迫獅子舞明治25年、旅の行商によって土地の若者に伝えられたという獅子舞。年2回、夏秋祭りで定期披露されます。県の無形民俗文化財に指定されています。0.0 0.0
-
45. 加領郷の獅子舞大土之御祖神を祀り、加領郷の氏神である信守神社の神事。勇壮な神道鹿島流棒術と雌雄の獅子舞を土地の青年が奉納。0.0 0.0
-
46. 多ノ郷の太刀踊毎年10月20日、賀茂神社境内で奉納されます。頭に鶏、山鳥、雉などの尾羽で作った鳥毛を冠って踊ります。33.411713 133.27736
-
47. 幡多神楽昭和55年に国の重要無形文化財に指定された「土佐の神楽」の一つ。0.0 0.0
旧十和村久保川の神職であった平野清記が、津野山神楽より伝授されたものを基本として、他の演目を加え安政元年(1854)の秋祭りに奉納したのが始まり。4~5時間に及ぶ大神楽で、現在の津野山神楽には見られない古吟の舞も残されています。 -
48. 花取太刀踊り踊り子は青年男子で、八幡宮の紋を染め抜いた黒の紋付、稿の袴、手甲、脚絆に白鉢巻姿。0.0 0.0
踊りは12通りがあり、各々に歌がある。太刀の踊り、シデの踊りがあり、太刀でシデを切り払う妙技は見事。 -
49. 寺内太刀踊り明治の終り頃土佐山村中切出身の西本仲次によって伝えられたもの。33.755566 133.5644
演技は切太刀と受け太刀と2人1組(7.8組)となりそれぞれ白鉢巻、赤欅、白足袋をつけ白衣・黒袴姿で抜刀して約10分踊ります。
若一王子宮では、旧暦の9月12日に奉納されています。