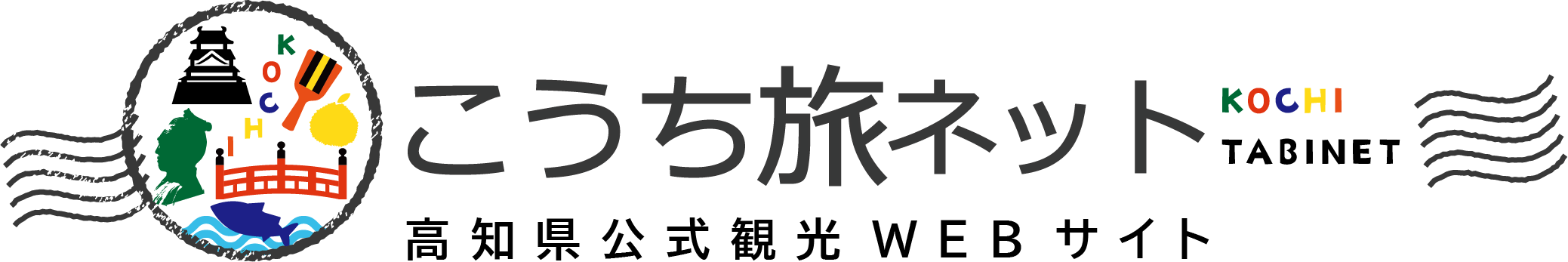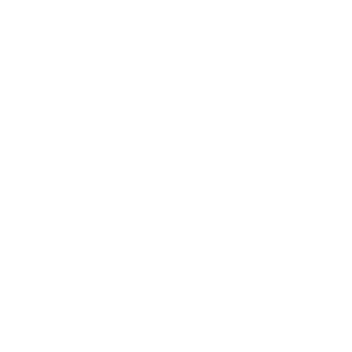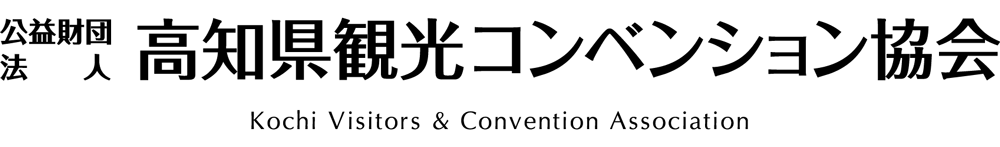検索結果:
780
件
並び順:
表示切替:
- タイル
- マップ
-
賛助会員1. ひろめ市場高知市中心部に位置する「ひろめ市場」は、約60店舗が軒を連ねる屋台村スタイルの観光名所。カツオのたたきをはじめとする高知グルメを、地元の人々と肩を並べて楽しめる独特の空間です。観光客も地元客も分け隔てなく集い、高知の食文化をダイレクトに体感できます。33.560616 133.53572
高知市中心部に位置する「ひろめ市場」は、約60店舗が軒を連ねる屋台村スタイルの観光名所。カツオのたたきをはじめとする高知グルメを、地元の人々と肩を並べて楽しめる独特の空間です。観光客も地元客も分け隔て ...
#定番
#市場・直売所
#高知県産
#レストラン・食堂
#おみやげ
-
2. 桂浜高知市にある太平洋に面した美しい海岸で、古くから「月の名所」として知られる高知県を代表する景勝地です。弓状に広がる砂浜、青い海、背後の松林が織りなす風景は日本の渚百選にも選ばれています。幕末の英雄・坂本龍馬の銅像が太平洋を見つめる姿は、高知観光のシンボル的存在。高知を訪れたら必ず立ち寄りたいスポットです。33.49773 133.57565
高知市にある太平洋に面した美しい海岸で、古くから「月の名所」として知られる高知県を代表する景勝地です。弓状に広がる砂浜、青い海、背後の松林が織りなす風景は日本の渚百選にも選ばれています。幕末の英雄・...
#定番
#景観(海)
#作品ゆかりの地
-
賛助会員3. 北川村「モネの庭」マルモッタン印象派の巨匠クロード・モネが自ら絵を描くために作り上げ、こよなく愛したフランスのジヴェルニーの庭を高知の自然の中に再現。33.439728 134.03426
睡蓮の咲く池と緑の太鼓橋が印象的な「水の庭」など、約3万平方メートルの敷地に約10万本の草花が植栽され、四季折々の美しい景観を楽しむことができます。
毎年6月下旬から10月下旬ごろまで、モネが夢見た青い睡蓮を愛でることができます。
印象派の巨匠クロード・モネが自ら絵を描くために作り上げ、こよなく愛したフランスのジヴェルニーの庭を高知の自然の中に再現。 睡蓮の咲く池と緑の太鼓橋が印象的な「水の庭」など、約3万平方メートルの敷地に ...
#定番
#花・植物
#水族館・動植物園
-
4. にこ淵「仁淀ブルー」という言葉を全国に広めた、仁淀川支流にある神秘的な青い滝壺です。太陽の光や季節により刻々と変化する幻想的なブルーが、訪れる人々を魅了し続けています。水神の化身とされる大蛇伝説が残る地元の聖地でもあり、静かに見守る心で訪れたい特別な場所。写真愛好家、自然を愛する方、パワースポット好きにおすすめです。33.704685 133.34143
「仁淀ブルー」という言葉を全国に広めた、仁淀川支流にある神秘的な青い滝壺です。太陽の光や季節により刻々と変化する幻想的なブルーが、訪れる人々を魅了し続けています。水神の化身とされる大蛇伝説が残る地元...
#定番
#景観(川)
-
5. こうち旅広場高知での旅をサポートしてくれる高知観光情報発信館「とさてらす」、人気のフォトスポット「三志士像」など、高知に着いたらまず立ち寄りたい旅の拠点です。33.566925 133.54272
●高知観光情報発信館「とさてらす」
高知県の観光情報を一堂に集めた総合観光案内所で、英語対応可能なスタッフが常駐しています。
手荷物を宿泊施設へ配送するサービス(有料)、はりまや橋・牧野植物園・桂浜など高知市内の観光スポットを回る周遊バス「MY遊バス」や路面電車等のチケット販売のほか、県内を7つのエリアに分け旬の観光情報や見どころを紹介するコーナーでは400種類を超えるパンフレットをご用意しています。(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパン...
高知での旅をサポートしてくれる高知観光情報発信館「とさてらす」、人気のフォトスポット「三志士像」など、高知に着いたらまず立ち寄りたい旅の拠点です。 ●高知観光情報発信館「とさてらす」 高知県の観 ...
#銅像・記念碑
#観光案内所
#レンタサイクル
#おみやげ
-
6. 柏島高知県大月町の先端に浮かぶ柏島は、エメラルドグリーンの海と驚異の透明度で「船が宙に浮かんで見える島」として話題の絶景スポットです。黒潮と豊後水道が交わる特別な海域に位置し、日本国内の魚種の3分の1が生息するという、世界有数のダイビング・シュノーケリング天国として知られています。32.76801 132.62653
透明度抜群の海では、浅瀬でもサンゴやカラフルな熱帯魚を観察でき、シュノーケリングだけでも十分に海中世界を楽しめます。夏には白浜やキャンプ場が賑わいを見せ、家族連れやアウトドア愛好家で溢れます。
島内にはノスタルジックな町並みが広がり、のんびりとした散策も魅力の一つ。海の絶景と素朴な島の暮らしが融合した、まさに"高知の楽園" ...
高知県大月町の先端に浮かぶ柏島は、エメラルドグリーンの海と驚異の透明度で「船が宙に浮かんで見える島」として話題の絶景スポットです。黒潮と豊後水道が交わる特別な海域に位置し、日本国内の魚種の3分の1が生 ...
#定番
#景観(海)
-
7. 高知城(天守・懐徳館)高知城は、天守、本丸御殿(「懐徳館」)、追手門といった15棟の建造物が国の重要文化財に指定されています。33.560715 133.53156
天守は、高さ18.5mの3層6階、屋根入母屋造り本瓦葺きの望楼型です。
現存12天守の1つであり、その中で本丸御殿も残る唯一の城です。
土佐藩の初代藩主である山内一豊によって1603年(慶長8年)に築城されましたが、城下町の大火事で一度消失しました。
その後、1749年(寛延2年)に再建され、戦火をくぐり、270年の時を超えて、当時の息吹を今に伝えています。
高知城は、天守、本丸御殿(「懐徳館」)、追手門といった15棟の建造物が国の重要文化財に指定されています。 天守は、高さ18.5mの3層6階、屋根入母屋造り本瓦葺きの望楼型です。 現存12天守の1つであり、その中 ...
#定番
#文化財・史跡
#作品ゆかりの地
-
8. 日曜市江戸時代から300年続く、毎週日曜日に開かれる街路市。33.561455 133.53766
高知城へと続く追手筋で、約1kmにわたり300ものお店が並びます。
地元の新鮮な野菜・果物や、手作りの田舎寿司に芋天など、高知の特産品が盛りだくさん。
高知のディープな魅力を感じられるとあって、地元の人だけでなく観光客も多く訪れます。
高知市では場所を変えて、火曜、木曜、金曜にも街路市が開かれています。
江戸時代から300年続く、毎週日曜日に開かれる街路市。 高知城へと続く追手筋で、約1kmにわたり300ものお店が並びます。 地元の新鮮な野菜・果物や、手作りの田舎寿司に芋天など、高知の特産品が盛りだくさん。 高知 ...
#定番
#町並み
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
9. 鳴無神社須崎市浦ノ内湾の美しい海を背にそびえる「鳴無(おとなし)神社」は、鎌倉時代の創建と伝わる歴史を秘めた縁結びの名所。33.41427 133.36885
赤い鳥居が青い海と空を鮮やかに彩り、かつては船でしか参拝できなかった“土佐の宮島”の風情を今に伝えます。
参拝者は心願成就を祈り、海へ流すおみくじや水に溶けるお守りで、海と神社が織りなすロマンチックな儀式を体感できます。観光客を優しく包み込む静謐な空間が、こころに寄り添う縁を結んでくれるでしょう。
須崎市浦ノ内湾の美しい海を背にそびえる「鳴無(おとなし)神社」は、鎌倉時代の創建と伝わる歴史を秘めた縁結びの名所。 赤い鳥居が青い海と空を鮮やかに彩り、かつては船でしか参拝できなかった“土佐の宮島” ...
#定番
#寺社
#作品ゆかりの地
-
10. 高知県立坂本龍馬記念館坂本龍馬の第一級の資料が揃う「龍馬の殿堂」。33.49643 133.57184
2018年のリニューアルで本格的な博物館施設として新館が登場。
本館は体験型展示へと進化、以前よりさらに魅力的な場所となりました。
2つの殿堂の館で龍馬をさらに深く楽しく知ってください。
坂本龍馬の第一級の資料が揃う「龍馬の殿堂」。 2018年のリニューアルで本格的な博物館施設として新館が登場。 本館は体験型展示へと進化、以前よりさらに魅力的な場所となりました。 2つの殿堂の館で龍馬をさら...
#定番
#ミュージアム
-
11. ゴトゴト石大きな石なのに押せば簡単にゴトゴトと揺れる。けれどどんなに押しても決して落ちない不思議な石です。いつの頃からか「落ちない祈願」をするために、願掛けに受験生などが訪れるようになりました。近くには山姥の滝もあります。33.644543 133.50407
大きな石なのに押せば簡単にゴトゴトと揺れる。けれどどんなに押しても決して落ちない不思議な石です。いつの頃からか「落ちない祈願」をするために、願掛けに受験生などが訪れるようになりました。近くには山姥の...
#景観(山)
-
12. 四国カルスト愛媛・高知県境にまたがる「四国カルスト」は、東西約25kmにわたる標高1,000〜1,500mの高原地帯。このエリアは、白い石灰岩が点在する草原風景と放牧された牛たちが織りなす、牧歌的で雄大な絶景が魅力です。33.481106 133.01495
特に「四国カルスト公園縦断線(県道383号)」は“天空の道”と呼ばれ、天狗高原・五段高原・姫鶴平・大野ヶ原と続くドライブルートは、四国屈指のパノラマスポット。ハイキング、キャンプ、星空観賞、牧場グルメまで、自然と癒しを満喫できる四季折々の体験が待っています。
愛媛・高知県境にまたがる「四国カルスト」は、東西約25kmにわたる標高1,000〜1,500mの高原地帯。このエリアは、白い石灰岩が点在する草原風景と放牧された牛たちが織りなす、牧歌的で雄大な絶景が魅力です。 特に「 ...
#定番
#景観(山)
#ジオスポット
#作品ゆかりの地
-
賛助会員13. 龍河洞山頂近くの盆地に降り注いだ雨水が永い歳月をかけて刻んだ全長約4km(観光コース約1km)の龍河洞は、1億7,500万年もの歴史を秘めた石灰岩鍾乳洞。33.603542 133.74516
国の天然記念物および史跡に指定され、出口付近からは弥生時代の土器や石器、古代人の「神の壺」など貴重な遺物が発見されています。
洞内には石筍や石柱が林立し、2019年夏にリニューアルされた照明と音響が幻想的な世界を演出します。
さらに予約制の冒険コースではヘルメットとヘッドランプを装着し、ナビゲーターと共に漆黒の闇を探検できます。
地下水の流れを肌で感じる「西本洞/水の洞窟」コースでは、龍河洞を形づくった自然の営みにも触れられる、本格的な洞窟探検が楽しめます。
静寂と...
山頂近くの盆地に降り注いだ雨水が永い歳月をかけて刻んだ全長約4km(観光コース約1km)の龍河洞は、1億7,500万年もの歴史を秘めた石灰岩鍾乳洞。 国の天然記念物および史跡に指定され、出口付近からは弥生時代の土器 ...
#定番
#ジオスポット
-
14. 四万十川津野町不入山に端を発し、中土佐町、四万十町、四万十市を流れる四国最長の大河(全長196km)。32.99484 132.92345
『最後の清流』として知られ、火振り漁や柴づけ漁など現在でも伝統的な漁が行われています。
上流から下流に数多く残っている沈下橋は、欄干がなく川の増水時に水面下に沈むことで流失しないように作られた橋で、今も住民の生活道であるとともに、四万十川の景観の魅力の1つとなっています。
津野町不入山に端を発し、中土佐町、四万十町、四万十市を流れる四国最長の大河(全長196km)。 『最後の清流』として知られ、火振り漁や柴づけ漁など現在でも伝統的な漁が行われています。 上流から下流に数多く残...
#定番
#景観(川)
#作品ゆかりの地
-
賛助会員15. 高知県立牧野植物園高知県出身の植物学者・牧野富太郎博士の業績を顕彰するため、1958年に高知市五台山に開園しました。約8haの園内では、西南日本の植物や博士ゆかりの植物など、四季折々3000種類以上が楽しめます。珍しい熱帯植物があるジャングルさながらの温室や、博士の業績や魅力を紹介した展示も必見。園内を散策した後は、緑に囲まれたレストランやカフェで和みのひとときを。オリジナルグッズが充実するショップもおすすめです。33.547512 133.57924
高知県出身の植物学者・牧野富太郎博士の業績を顕彰するため、1958年に高知市五台山に開園しました。約8haの園内では、西南日本の植物や博士ゆかりの植物など、四季折々3000種類以上が楽しめます。珍しい熱帯植物があ ...
#定番
#花・植物
#水族館・動植物園
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
-
賛助会員16. 桂浜水族館「桂浜」の浜辺に建ち、土佐湾の海水魚を中心に飼育展示。33.497055 133.5736
釣り人のあこがれ巨大魚”アカメ”の迫力ある郡泳は必見。
様々ないきものにエサやりを通してふれあいながら学ぶことができ、大人から子どもまで楽しめるほか、個性豊かなスタッフによるおもしろPOPやお魚解説板も見逃せない、アットホームな水族館です。
「桂浜」の浜辺に建ち、土佐湾の海水魚を中心に飼育展示。 釣り人のあこがれ巨大魚”アカメ”の迫力ある郡泳は必見。 様々ないきものにエサやりを通してふれあいながら学ぶことができ、大人から子どもまで楽しめ ...
#アミューズメント
#水族館・動植物園
-
17. 高知市卸売市場マグロ・カツオをはじめとする鮮魚部、干物・ちりめんじゃこなどの塩干魚部、野菜・果物を扱う青果部があり、地元でとれた四季折々の選りすぐりの新鮮な食材を買い求めることができます。33.544685 133.56442
また、場内で市場業者向けに営業している各飲食店等は一般のお客様も利用可能です。
市場内施設やセリの見学を希望する場合は事前連絡をお願いします。
マグロ・カツオをはじめとする鮮魚部、干物・ちりめんじゃこなどの塩干魚部、野菜・果物を扱う青果部があり、地元でとれた四季折々の選りすぐりの新鮮な食材を買い求めることができます。 また、場内で市場業者向 ...
#市場・直売所
#施設見学
#高知県産
-
18. 海洋堂Space Factoryなんこくものづくりの人材育成や観光を目的に2021年にオープンした施設。33.57501 133.64832
1階の工場では、ここでしか見られない海洋堂のソフビフィギュアが生まれる瞬間が見学できます。
生命をテーマにした4mを超える大きなモニュメントや、「古代・現在・未来」の巨大なジオラマの展示を見ることができます。
フィギュアの色塗りやジオラマづくりといったものづくり体験もできます。
ものづくりの人材育成や観光を目的に2021年にオープンした施設。 1階の工場では、ここでしか見られない海洋堂のソフビフィギュアが生まれる瞬間が見学できます。 生命をテーマにした4mを超える大きなモニュメント ...
#アミューズメント
#作品ゆかりの地
#施設見学
-
19. 竜串海岸約2000万年前の砂岩からなる浸食台地で怪岩奇岩の景勝地として有名な竜串海岸。32.78594 132.86584
昭和45年に日本で初めて海中公園に指定されました。
また、千尋岬の突端には弘法大師が見残したもので見残しと名付けられた奇石怪石の景観がみられます。
難所のため、弘法大師さえ見残したということからこの名がついたといわれています。
周辺に足摺海底館、足摺海洋館SATOUMI、海のギャラリー(竜串貝類展示館)、グラスボードなど多くの観光地があります。
約2000万年前の砂岩からなる浸食台地で怪岩奇岩の景勝地として有名な竜串海岸。 昭和45年に日本で初めて海中公園に指定されました。 また、千尋岬の突端には弘法大師が見残したもので見残しと名付けられた奇石怪石...
#定番
#景観(海)
#ジオスポット
-
20. 佐田沈下橋佐田沈下橋は、四万十川に架かる数ある沈下橋の中でも最下流・最長を誇る橋で、雄大な自然と川の流れに溶け込む風景が魅力です。33.014927 132.88364
増水時に橋が沈むことで流失を防ぐ構造のため、欄干がなく、水面との一体感が独特の風情を生み出しています。今なお地域の生活道路として使われており、橋の上からは四万十川の広がりと美しい里山の景色を一望できます。
四万十川の自然と人の暮らしを感じられる、象徴的なビュースポットです。
佐田沈下橋は、四万十川に架かる数ある沈下橋の中でも最下流・最長を誇る橋で、雄大な自然と川の流れに溶け込む風景が魅力です。 増水時に橋が沈むことで流失を防ぐ構造のため、欄干がなく、水面との一体感が独 ...
#景観(川)
#定番
#建築
-
21. 安居渓谷高知県の名勝、安居渓谷は「仁淀ブルー」と称される透き通った青い水が美しい渓谷です。33.672657 133.18906
清流仁淀川の支流に広がるこのエリアは、透明度の高い水と豊かな自然に包まれ、ハイキングが楽しめます。特に夏は水の青さが際立ち、四季折々の山の緑と調和して、訪れる人の心を癒します。ゆったりと流れる時間の中で、四国の大自然を感じられるおすすめスポットです。
高知県の名勝、安居渓谷は「仁淀ブルー」と称される透き通った青い水が美しい渓谷です。 清流仁淀川の支流に広がるこのエリアは、透明度の高い水と豊かな自然に包まれ、ハイキングが楽しめます。特に夏は水の青 ...
#定番
#景観(川)
-
賛助会員22. 香美市立やなせたかし記念館 アンパンマンミュージアム<2025年3月29日(土)より、入館予約が必要です>33.647663 133.78369
詳しくは公式ホームページをご覧ください。
平成8年7月に開館した、香北町出身の漫画家・やなせたかしさんの記念館。
アンパンマンの絵本原画やタブローを展示した「やなせたかしギャラリー」やアンパンマンの住む世界をジオラマで再現した「アンパンマンワールド」など、アンパンマンの世界を楽しめるミュージアムです。
豊かな自然に囲まれた落ち着いた雰囲気で、子どもだけでなく大人も楽しめる施設です。
<2025年3月29日(土)より、入館予約が必要です> 詳しくは公式ホームページをご覧ください。 平成8年7月に開館した、香北町出身の漫画家・やなせたかしさんの記念館。 アンパンマンの絵本原画やタブローを展 ...
#定番
#ミュージアム
#アミューズメント
-
23. はりまや橋「よさこい節」の純信お馬の道行で有名。江戸時代初期、土佐藩の御用商人の播磨屋宗徳と櫃屋道清が両家を往来するために設けた私設の仮橋が最初と言われています。現在は周辺がはりまや橋公園として整備されており、東側には、よさこい節のメロディとともに龍馬や桂浜が現れるからくり時計もあります。33.55988 133.54268
「よさこい節」の純信お馬の道行で有名。江戸時代初期、土佐藩の御用商人の播磨屋宗徳と櫃屋道清が両家を往来するために設けた私設の仮橋が最初と言われています。現在は周辺がはりまや橋公園として整備されており...
#定番
#建築
#文化財・史跡
#作品ゆかりの地
-
24. インクライン(観光ケーブルカー)世界でも珍しい、水の重みで動くケーブルカー。33.55473 134.04848
昔はこれで木材を運びました。
かなりの急傾斜をゆっくり登り降りします。
登っている途中や、登った先では、馬路村ののどかな風景を楽しめます。
世界でも珍しい、水の重みで動くケーブルカー。 昔はこれで木材を運びました。 かなりの急傾斜をゆっくり登り降りします。 登っている途中や、登った先では、馬路村ののどかな風景を楽しめます。
#文化財・史跡
#乗り物
-
25. 五台山展望テラス高知市の中心部から車で約20分ほどの五台山は、四国88カ所の31番札所「竹林寺」や「牧野植物園」が知られていますが、山頂近くに展望テラスがあります。33.54655 133.57423
高知市街や、浦戸湾・高知港などの絶景が一望できます。
JR高知駅前から出ているMY遊バスでアクセスできます。
夜の高知市街を楽しめる隠れた夜景スポットでもあります。
高知市の中心部から車で約20分ほどの五台山は、四国88カ所の31番札所「竹林寺」や「牧野植物園」が知られていますが、山頂近くに展望テラスがあります。 高知市街や、浦戸湾・高知港などの絶景が一望できます。 J ...
#景観(海)
#町並み
-
26. 岡﨑牧場(DEER LAND FARM)高知県円行寺の山あいで、ディアランドファーム・岡﨑牧場が山地酪農にこだわり、雨と高温で育つ野芝を食む元気な乳牛を放牧しています。運動量豊富でストレスフリーな牛たちの新鮮なミルクを、朝イチにしぼって使用した自家製スイーツが大人気。33.588364 133.50793
クラシックな濃厚ソフトクリームやふんわり牧場ロール、なめらかプリン、サクサクのシュークリームのほか、旬のアイデアを取り入れた限定メニューも登場。
さらにヤギへの餌やり体験も楽しめるので、家族連れやお子さまにもぴったり。
店内併設の直売コーナーでは、しぼりたてミルクやオリジナルジャムも購入可能です。十頭十色の牛たちと山あいの大自然を感じながら、ドライブがてらぜひお立...
高知県円行寺の山あいで、ディアランドファーム・岡﨑牧場が山地酪農にこだわり、雨と高温で育つ野芝を食む元気な乳牛を放牧しています。運動量豊富でストレスフリーな牛たちの新鮮なミルクを、朝イチにしぼって使...
#アミューズメント
#施設見学
#カフェ・スイーツ
-
27. UFOライン四国山地の雄大な峰々をつなぐ約27kmの山岳ドライブコースは、もともと「雄峰ライン」と呼ばれていました。33.78327 133.229
登山者がこの道で撮影した写真にUFOが映り込み、地元新聞で大きく報じられたことで話題に。以来、「UFOライン」として親しまれています。
標高1,300〜1,700mの尾根沿いを走る道からは、四季折々の絶景が広がり、特に春のアケボノツツジや秋の紅葉が見どころです。晴れた日には遠く太平洋まで見渡せる、四国有数のドライブスポットです。
四国山地の雄大な峰々をつなぐ約27kmの山岳ドライブコースは、もともと「雄峰ライン」と呼ばれていました。 登山者がこの道で撮影した写真にUFOが映り込み、地元新聞で大きく報じられたことで話題に。以来、「UFOライ...
#定番
#景観(山)
#作品ゆかりの地
-
28. 久礼大正町市場100年以上の歴史を持つ、漁師町の市場。33.329025 133.23062
起源は明治の中頃。大正時代の大火で焼失後、大正天皇から復興費が届けられたのを機に、通りを大正町と改名、以来大正町市場と呼ばれています。
地元でとれた新鮮な魚をはじめ干物や野菜、果物などを購入できます。
また、地元の新鮮な魚を中心に提供する食堂もあり、季節ごとに旬の味覚を楽しめます。
100年以上の歴史を持つ、漁師町の市場。 起源は明治の中頃。大正時代の大火で焼失後、大正天皇から復興費が届けられたのを機に、通りを大正町と改名、以来大正町市場と呼ばれています。 地元でとれた新鮮な魚をは...
#町並み
#市場・直売所
#高知県産
-
賛助会員29. 大方ホエールウォッチング(砂浜美術館)四万十川からの栄養豊富な水が流れる土佐湾黒潮町沖。体長が約14mのカツオクジラが1年を通して暮らしていると言われています。その他にも、ハセイルカ・ハナゴンドウ・ハンドウイルカなどの100頭を超える群れにも出会うことが出来ます。案内人は地元の優しい現役漁師。クジラたちに出逢えた時の感動はきっと一生忘れられない思い出になるでしょう。33.034836 133.02698
四万十川からの栄養豊富な水が流れる土佐湾黒潮町沖。体長が約14mのカツオクジラが1年を通して暮らしていると言われています。その他にも、ハセイルカ・ハナゴンドウ・ハンドウイルカなどの100頭を超える群れにも ...
#アミューズメント
#海あそび
-
賛助会員30. 天然温泉 はるのの湯高知駅から車で30分ほどのところにあります。33.507595 133.49513
広い露天風呂は大変人気があります。
また、露天風呂付客室もあり、温泉をゆっくりお楽しみいただけます。
春野総合運動公園が近くにあり、スポーツ合宿としてもご利用いただいています。
高知駅から車で30分ほどのところにあります。 広い露天風呂は大変人気があります。 また、露天風呂付客室もあり、温泉をゆっくりお楽しみいただけます。 春野総合運動公園が近くにあり、スポーツ合宿としてもご利 ...
#ホテル
#温泉
#レストラン・食堂
-
賛助会員31. 黒潮本陣鰹乃國の湯宿 黒潮本陣は、江戸時代の本陣(大名宿)をイメージした趣ある造りと、太平洋を一望する絶好のロケーションが魅力。日帰りでも利用できる露天「汐湯」や本場の鰹のタタキを堪能できる食事、さらには宿泊者向けのゆったりとした客室が揃い、観光の拠点として最適です。33.321297 133.23566
「高知家の食卓」県民総選挙2014選抜店舗。
鰹乃國の湯宿 黒潮本陣は、江戸時代の本陣(大名宿)をイメージした趣ある造りと、太平洋を一望する絶好のロケーションが魅力。日帰りでも利用できる露天「汐湯」や本場の鰹のタタキを堪能できる食事、さらには宿...
#温泉
#和食
#旅館
#コテージ・グランピング
-
32. アンテナショップ 満天の星「高知家の食卓」県民総選挙2014・2015・2016選抜店舗。33.572403 133.56288
高知市にある、津野町の魅力が詰まったアンテナショップ。
レストランでは、柔らかい肉質の「つの山牛」の料理など、ここでしか味わえないメニューが並びます。
津野町特産のほうじ茶を使った、全国的に有名なほうじ茶大福は、控えめな甘さで男性にも人気。
隣接するマルシェには朝どれの新鮮野菜や果物、お土産が並び、朝から多くのお客さんで賑わいます。
「高知家の食卓」県民総選挙2014・2015・2016選抜店舗。 高知市にある、津野町の魅力が詰まったアンテナショップ。 レストランでは、柔らかい肉質の「つの山牛」の料理など、ここでしか味わえないメニューが並びます ...
#市場・直売所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
-
33. 足摺海底館足摺宇和海国立公園に位置する足摺海底館は中四国唯一の海中展望塔。32.785976 132.86014
独特のデザイン性は建築物としても高い評価を得ています。
階段を降りれば16個の丸窓から大自然を鑑賞できます。
メジナやニザダイ、ブダイやソラスズメダイなどの一年を通して見られる魚から、イワシやキビナゴ、カマスなどの回遊魚を始め、ウミガメや海鵜といった生物も観られます。
海中の中という非日常の空間でゆったりとできるので、家族やカップルなど親しい人とのんびりとした時間を過ごしてもらえる施設です。
足摺宇和海国立公園に位置する足摺海底館は中四国唯一の海中展望塔。 独特のデザイン性は建築物としても高い評価を得ています。 階段を降りれば16個の丸窓から大自然を鑑賞できます。 メジナやニザダイ、ブダイ ...
#定番
#景観(海)
#アミューズメント
-
34. 室戸岬室戸岬は古くは海の難所として知られ、海岸は奇岩が乱立し、亜熱帯性樹林や海岸植物が茂り、1964年6月に室戸阿南海岸国定公園の指定を受け、2011年9月に世界ジオパークに認定されています。33.24473 134.1757
室戸岬は古くは海の難所として知られ、海岸は奇岩が乱立し、亜熱帯性樹林や海岸植物が茂り、1964年6月に室戸阿南海岸国定公園の指定を受け、2011年9月に世界ジオパークに認定されています。
#景観(海)
#定番
#ジオスポット
-
35. 湖畔遊「湖畔遊」は、自然とともに在ることの心地よさを五感で感じられる癒やしの空間。大地が育んだ天然温泉、無添加の野菜や穀物、丁寧に調和された食事、やさしく流れる音楽、湖畔に広がる四季折々の景色──。どれもが自然体であることを大切にし、訪れる人を日常の喧騒からそっと解き放ってくれます。身体と心がゆるやかに整っていく、湖畔遊ならではの静かな贅沢をぜひ体験してください。33.652977 133.7719
「湖畔遊」は、自然とともに在ることの心地よさを五感で感じられる癒やしの空間。大地が育んだ天然温泉、無添加の野菜や穀物、丁寧に調和された食事、やさしく流れる音楽、湖畔に広がる四季折々の景色──。どれも...
#温泉
#レストラン・食堂
#旅館
-
賛助会員36. TheMana Village太平洋の絶景を望めるリゾートホテル。32.725204 133.00272
日帰り入浴やレストランの利用も可能で、露天風呂やレストランからどこまでもひろがる大海原を眺めることができます。
太平洋の絶景を望めるリゾートホテル。 日帰り入浴やレストランの利用も可能で、露天風呂やレストランからどこまでもひろがる大海原を眺めることができます。
#温泉
#レストラン・食堂
#ホテル
-
37. 土佐神社(しなね様)土佐神社には土佐一ノ宮として古くより土佐の人々の心の拠りどころとされる社です。長宗我部元親再建御造営の現社殿は入りとんぼ(入蜻蛉)という特殊な建築様式で神社建築としても注目を浴びています。33.59247 133.57684
御祭神は味鋤高彦根神(一言主神)であり、農具の鋤にかかわる開拓神であることから開運招福のご利益があります。
境内は約一万坪。300メートル程の参道の奥に大きな社がひっそりとたたずんでいます。
2010年に放送されたNHK大河ドラマ『龍馬伝』ではロケ地になりました。
土佐神社には土佐一ノ宮として古くより土佐の人々の心の拠りどころとされる社です。長宗我部元親再建御造営の現社殿は入りとんぼ(入蜻蛉)という特殊な建築様式で神社建築としても注目を浴びています。 御祭神は ...
#寺社
-
38. 坂本龍馬像桂浜の龍頭岬に立つ、近代日本の道を大きく開いた幕末の志士・坂本龍馬の銅像。33.498665 133.5755
高さ5.3m、台座を含めた総高は13.5mにも及びます。
昭和のはじめ、高知県の青年有志の募金活動によって建設されました。
和装に懐手、そしてブーツ姿で太平洋を見つめています。本山白雲の作。
桂浜の龍頭岬に立つ、近代日本の道を大きく開いた幕末の志士・坂本龍馬の銅像。 高さ5.3m、台座を含めた総高は13.5mにも及びます。 昭和のはじめ、高知県の青年有志の募金活動によって建設されました。 和装に懐 ...
#銅像・記念碑
-
39. 梼原町立図書館(雲の上の図書館)「人と自然が共生し輝く梼原構想」の中核を担う施設として、平成2018年度に開館した梼原町図書館。33.39393 132.92801
館内には梼原産の木材を贅沢に用い、千百年余にわたる町独自の文化を保存・継承しながら、情報発信のハブとしての役割を果たします。
知の拠点として蔵書を手に取るだけでなく、ボルダリング設備で体を動かし、カフェスペースでゆったりと過ごすことで、新しい発見や学びが日常に溶け込む空間です。
世代を超えた交流の場、語り合いの場としても設計され、訪れるすべての人が“森と文化の共生”を体感できる憩いの場となっています。
「人と自然が共生し輝く梼原構想」の中核を担う施設として、平成2018年度に開館した梼原町図書館。 館内には梼原産の木材を贅沢に用い、千百年余にわたる町独自の文化を保存・継承しながら、情報発信のハブとして ...
#定番
#建築
-
40. 伊尾木洞国道55号沿い、安芸市の郊外に突如現れる「伊尾木洞」は、まるで数万年前にタイムスリップしたかのような景観が広がる天然の海食洞。33.4918 133.93414
かつてこの地が海だった頃に、波の浸食で形成された全長約40mの洞窟は、現在は渓谷へとつながり、壁面には貝の化石が残るなど、地球の記憶を感じさせるスポットです。
洞窟の先には、国の天然記念物に指定された40種以上の熱帯性シダが自生するシダ群落が広がり、その景観は幻想的。ひんやりとした空気と豊かな緑に包まれながら、太古の自然と向き合う静かな時間を味わえます。
併設の観光案内所では、パンフレットや周辺の観光情報の入手はもちろん、長靴の無料レンタルも可能。ごめん・なはり線「伊尾木...
国道55号沿い、安芸市の郊外に突如現れる「伊尾木洞」は、まるで数万年前にタイムスリップしたかのような景観が広がる天然の海食洞。 かつてこの地が海だった頃に、波の浸食で形成された全長約40mの洞窟は、現在 ...
#ジオスポット
#定番
#花・植物
#作品ゆかりの地
-
41. 馬路森林鉄道高知県馬路村の馬路温泉前で、かつて魚梁瀬杉を運んだ森林鉄道の蒸気機関車を再現した車両が走っています。昭和30年代まで実際に村内を走っていた森林鉄道の記憶を今に伝える、ノスタルジックな観光アトラクションです。33.557068 134.04909
駅弁片手に楽しむ約10分の小さな鉄道旅
約300mのコースを2周する乗車時間は約10分。小さな谷を走る蒸気機関車の車窓からは、馬路村の豊かな自然が楽しめます。
かつて魚梁瀬杉の運搬を支えた森林鉄道は、道路の普及により廃線となりましたが、この再現車両が当時の面影を今に伝えています。
高知県馬路村の馬路温泉前で、かつて魚梁瀬杉を運んだ森林鉄道の蒸気機関車を再現した車両が走っています。昭和30年代まで実際に村内を走っていた森林鉄道の記憶を今に伝える、ノスタルジックな観光アトラクション ...
#乗り物
#文化財・史跡
-
賛助会員42. 土佐龍温泉 三陽荘太平洋の絶景を眺められる天然温泉宿。33.432808 133.45197
黄金色の温泉は「熱の湯」とも呼ばれ、保温効果がとても高くぽかぽかになります。
日帰り入浴も可能で、海を見ながら浸かれる無料の足湯も人気です。
太平洋の絶景を眺められる天然温泉宿。 黄金色の温泉は「熱の湯」とも呼ばれ、保温効果がとても高くぽかぽかになります。 日帰り入浴も可能で、海を見ながら浸かれる無料の足湯も人気です。
#温泉
#旅館
-
43. よさこいふるさと市場農家がつくり、農家が経営する産直市。年間を通じて、新鮮野菜・果物・おいしい惣菜・各種弁当・活きのいい鮮魚が並びます。33.564938 133.56529
オーガニックコーナーを設けるなど、お客様が商品を選びやすいように工夫しています。
農家がつくり、農家が経営する産直市。年間を通じて、新鮮野菜・果物・おいしい惣菜・各種弁当・活きのいい鮮魚が並びます。 オーガニックコーナーを設けるなど、お客様が商品を選びやすいように工夫しています。
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
44. むろと廃校水族館小学校の廃校舎を改修して再利用した水族館で、約50種類1,000匹以上の魚を見ることができます。33.32627 134.19554
とび箱や手洗い場など学校の設備を活かした展示が楽しく、懐かしさも感じます。
屋外のプールにはたくさんのカメが泳いでいます。
小学校の廃校舎を改修して再利用した水族館で、約50種類1,000匹以上の魚を見ることができます。 とび箱や手洗い場など学校の設備を活かした展示が楽しく、懐かしさも感じます。 屋外のプールにはたくさんのカメが泳 ...
#アミューズメント
#水族館・動植物園
-
45. 大瀧の滝手箱山登山口の「大瀧の滝(おおたびのたき)」。標高1806mの手箱山を背に、夏は水しぶきが涼を呼ぶ清流の滝が、冬には一転、全体が氷結する見事な“氷瀑”となります。南国・高知にこんな世界が?と驚かれる幻想的な景観は、まさに秘境の絶景。期間限定でライトアップも実施され、澄んだ空気のなか、凍てついた滝が青白く輝く様は息をのむ美しさです。33.74856 133.20195
手箱山登山口の「大瀧の滝(おおたびのたき)」。標高1806mの手箱山を背に、夏は水しぶきが涼を呼ぶ清流の滝が、冬には一転、全体が氷結する見事な“氷瀑”となります。南国・高知にこんな世界が?と驚かれる幻想的 ...
#景観(川)
-
賛助会員46. 三翠園高知城下のかつて土佐藩主・山内家下屋敷があった場所にある宿。33.556156 133.53404
美しい日本庭園や天然温泉、地元食材のお食事で高知らしいひとときが過ごせます。
本格温泉施設「湯殿 水哉閣」は、高知市中心部では珍しい天然温泉で、高知市中心部にありながら鏡川と筆山を望む抜群のロケーション。日帰り入浴も可能で、市内観光の合間にくつろげます。
高知城下のかつて土佐藩主・山内家下屋敷があった場所にある宿。 美しい日本庭園や天然温泉、地元食材のお食事で高知らしいひとときが過ごせます。 本格温泉施設「湯殿 水哉閣」は、高知市中心部では珍しい天然 ...
#温泉
#ホテル
#旅館
-
47. 名越屋沈下橋仁淀ブルーの愛称で知られる仁淀川で最も下流にある沈下橋。33.57245 133.35606
日高村といの町を結ぶ生活道で、交通量が比較的多く、待避所が4ヶ所設けられています。
橋の中央からは川面に立ったかのような絶景を楽しむことができます。
仁淀ブルーの愛称で知られる仁淀川で最も下流にある沈下橋。 日高村といの町を結ぶ生活道で、交通量が比較的多く、待避所が4ヶ所設けられています。 橋の中央からは川面に立ったかのような絶景を楽しむことができま...
#景観(川)
#建築
-
48. 道の駅 土佐和紙工芸村「くらうど」高知中心部から車で約30分にある道の駅、土佐和紙工芸村「くらうど」。33.57357 133.36621
ホテル、入浴施設、直販所、レストラン等があり、旅の休憩所として最適。
豊かな自然の静けさのなか、カヌーや紙漉き、機織りなど様々な体験もすることができます。
高知中心部から車で約30分にある道の駅、土佐和紙工芸村「くらうど」。 ホテル、入浴施設、直販所、レストラン等があり、旅の休憩所として最適。 豊かな自然の静けさのなか、カヌーや紙漉き、機織りなど様々な体験...
#温泉
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#おみやげ
-
49. 雲の上のギャラリー建築家・隈研吾氏の設計により作られた、梼原町の木材がふんだんに使用された建築物。33.387394 132.94403
内部は、隈氏の設計で作られた梼原町にある建築物の解説パネルや、木で作られたギャラリーの模型などを展示しています。
雲の上の温泉・プール、雲の上の市場が隣接しています。
建築家・隈研吾氏の設計により作られた、梼原町の木材がふんだんに使用された建築物。 内部は、隈氏の設計で作られた梼原町にある建築物の解説パネルや、木で作られたギャラリーの模型などを展示しています。 雲の ...
#建築
#ミュージアム
-
賛助会員50. JR高知駅高知市中心部に位置するJR四国の主要駅。2008年に高架化されたホームを覆う大屋根「クジラドーム」は、流線型の美しいフォルムが印象的で、旅のはじまりを華やかに演出します。33.56762 133.54373
改札を入ると、アンパンマンの虹の大階段、階段を登るとアンパンマン列車ひろばがあります。
特急「南風」「しまんと」をはじめとする各種列車が発着し、高松・岡山方面とのアクセスも良好。駅前にはとさでん交通の路面電車乗り場や長距離バスターミナルが整い、市内外への移動がスムーズです。
館内にはみどりの窓口やコインロッカー、カフェ・お土産ショップも充実し、高知観光の拠点として便利にご利用いただけます。
駅前には観光案内所「とさてらす」がありま...
高知市中心部に位置するJR四国の主要駅。2008年に高架化されたホームを覆う大屋根「クジラドーム」は、流線型の美しいフォルムが印象的で、旅のはじまりを華やかに演出します。 改札を入ると、アンパンマンの虹の大 ...
#建築
#おみやげ
-
51. 仁淀川水質日本一の1級河川で奇跡の清流と呼ばれる仁淀川。抜群の透明度を誇る「仁淀川」ではカヌ ーやラフティングなどのアクティビティの他、釣り・キャンプ・川遊びなど、昔から水に親しまれており、その水辺利用率は常に全国トップクラスを維持しています。また、流域には水が青く澄んでいることから仁淀ブルーと呼ばれ、にこ淵や安居渓谷、中津渓谷などの見所が多くあります。33.470684 133.47449
水質日本一の1級河川で奇跡の清流と呼ばれる仁淀川。抜群の透明度を誇る「仁淀川」ではカヌ ーやラフティングなどのアクティビティの他、釣り・キャンプ・川遊びなど、昔から水に親しまれており、その水辺利用率 ...
#定番
#景観(川)
-
52. 琴ヶ浜東西約4kmに渡って続く琴ヶ浜は、白い砂浜と美しい松林が織りなす景観が「日本の白砂青松100選」に選定された海岸です。太平洋を一望できる開放的なロケーションで、昼は波打ち際を散策したり、夜は満天の星空と波の音を楽しんだりと、時間帯によって異なる魅力があります。33.517212 133.80458
月の名所としても有名で、中秋の名月の頃には「観月の宴」が開催されます。秋には「竹灯りの宵」が開かれ、砂浜に並ぶ無数の竹灯りが波の音や風に揺れる松林の音と相まって、幻想的な雰囲気を演出します。
東西約4kmに渡って続く琴ヶ浜は、白い砂浜と美しい松林が織りなす景観が「日本の白砂青松100選」に選定された海岸です。太平洋を一望できる開放的なロケーションで、昼は波打ち際を散策したり、夜は満天の星空と波の...
#景観(海)
#定番
#作品ゆかりの地
-
53. 高知県立 足摺海洋館SATOUMI足摺海洋館「SATOUMI」を拠点に、海も、山も、人も、すべてがつながる竜串エリア。32.79132 132.86201
新しい施設と既存の施設、そして自然のフィールドをひとつととらえた、かつてない海と自然のアドベンチャーミュージアムとして、「あらゆるいのちは海とつながり、海と生きている」ことを学び、遊び、楽しむことができます。
館内には、竜串湾に暮らす生き物を中心に約350 種15,000 点を展示。巨大な水槽や自然を再現した展示で、いきいきと生活する生き物たちに出会えます。
館内ガイドツアーやバックヤードツアーも実施しています。(要予約)
足摺海洋館「SATOUMI」を拠点に、海も、山も、人も、すべてがつながる竜串エリア。 新しい施設と既存の施設、そして自然のフィールドをひとつととらえた、かつてない海と自然のアドベンチャーミュージアムとして、「...
#定番
#水族館・動植物園
-
54. 海洋堂ホビー館四万十海洋堂ホビー館四万十は、平成21年度に廃校になった打井川小学校の体育館を改築してつくられています。過疎の地域に新たな人の集まりと賑わいを起こすという地域住民の思いがこめられています。海洋堂の門外不出、世界一のプラモデルコレクションから最新フィギュア、さらには有名造型師たちの恐竜から美少女まで、あらゆるホビーを大量展示する見た事も聞いた事もないミュージアムです。33.15288 133.04465
海洋堂ホビー館四万十は、平成21年度に廃校になった打井川小学校の体育館を改築してつくられています。過疎の地域に新たな人の集まりと賑わいを起こすという地域住民の思いがこめられています。海洋堂の門外不出、 ...
#ミュージアム
#ものづくり
-
55. 路面電車明治34(1904)年に運航を開始し、現在では日本最古となった高知の路面電車。33.559643 133.54222
走行距離は、南国市後免(ごめん)町駅からいの町伊野駅まで東西22.1km、高知駅前から桟橋通五丁目までの南北3.2kmの総延長25.3kmで、日本最長。
現在も地域住民の通勤、通学の足として利用され、路面電車が走るレトロな風景は、観光客にも人気です。
昔ながらの電車や超低床電車(LRV)のほか、ポルトガル・ノルウェー・オーストリアなど外国の街を実際に走っていた電車も走っています。
高知市のはりまや橋交差点は、線路が平面で交差する全国的にも珍しい場所で、「ダイヤモンドクロッシング」と呼ばれています。
明治34(1904)年に運航を開始し、現在では日本最古となった高知の路面電車。 走行距離は、南国市後免(ごめん)町駅からいの町伊野駅まで東西22.1km、高知駅前から桟橋通五丁目までの南北3.2kmの総延長25.3kmで、日本最 ...
#町並み
#乗り物
-
56. 佐川おもちゃ美術館植物学者・牧野富太郎博士の出身地であり、町内の至るところで四季折々の植物が楽しめる高知県佐川町。「佐川おもちゃ美術館」は遊びの中でその魅力を伝えます。33.50341 133.3171
高知県産木材をふんだんに使った館内は、一歩足を踏み入れるだけで木のぬくもりを全身で感じることができます。
佐川の野山を表現した遊びのトンネル「まきのさんのやま」や、牧野博士が愛したといわれる「バイカオウレン」などの花を集めて遊べる「まきのさんのはなばたけ」、化石も発掘できる⁉「木のたまごプール」などがあり、地域の魅力・文化に触れながら、多様なおもちゃと遊びが楽しめます。
また、赤いエプロンをつけた「おもちゃ学芸員」が来館者の皆様をおもてなし。遊...
植物学者・牧野富太郎博士の出身地であり、町内の至るところで四季折々の植物が楽しめる高知県佐川町。「佐川おもちゃ美術館」は遊びの中でその魅力を伝えます。 高知県産木材をふんだんに使った館内は、一歩足を ...
#ミュージアム
-
賛助会員57. 四万十の宿四万十川河口の近くにある温泉宿。32.944744 132.99362
天然温泉・薬湯・海水露天風呂が楽しめ、日帰り入浴も可能です。
四万十川河口の近くにある温泉宿。 天然温泉・薬湯・海水露天風呂が楽しめ、日帰り入浴も可能です。
#温泉
#ホテル
#旅館
-
58. 地球33番地東経33度33分33秒、北緯33度33分33秒という「3」が12個も並ぶ、世界でも珍しい場所「地球33番地」。33.56258 133.55666
緯度・経度の度、分、秒に同じ数字が12個並ぶ地点は21ヶ所ありますが、陸上にあるのは世界にわずか9ヶ所であり、市街地にあるのは地球33番地のみ。高知市を東流する「江ノ口川」の中にシンボルがたっています。南岸の弥生町には白いモニュメントもあります。
東経33度33分33秒、北緯33度33分33秒という「3」が12個も並ぶ、世界でも珍しい場所「地球33番地」。 緯度・経度の度、分、秒に同じ数字が12個並ぶ地点は21ヶ所ありますが、陸上にあるのは世界にわずか9ヶ所であり、市街地...
#銅像・記念碑
-
59. フォレストアドベンチャー・高知高知県と愛媛県の県境、四万十川源流の美しい水と標高1400mの四国カルストに守られてきた秘境の森にフォレストアドベンチャーがオープン。33.42953 132.99068
圧倒的な木々の高さと豊富な自然を利用したパーク、これこそフォレストアドベンチャーの真髄です。
高知県と愛媛県の県境、四万十川源流の美しい水と標高1400mの四国カルストに守られてきた秘境の森にフォレストアドベンチャーがオープン。 圧倒的な木々の高さと豊富な自然を利用したパーク、これこそフォレスト ...
#アミューズメント
#山あそび
-
60. 桑田山雪割桜桑田山雪割桜は、標高769mのばん蛇森(ばんだがもり)の中腹の桑田山地区(菊花園のとなり)で例年2月中旬~3月中旬にかけて見ごろをむかえます。鮮やかな桃色の花々が冬の終わりを告げます。33.434616 133.27965
山全体には約1000本の桜の木があります。
【見どころ】
鮮やかな桃色の雪割り桜と黄色の菜の花とのコントラストが美しく、一足早く春の訪れを感じられます。
桑田山雪割桜は、標高769mのばん蛇森(ばんだがもり)の中腹の桑田山地区(菊花園のとなり)で例年2月中旬~3月中旬にかけて見ごろをむかえます。鮮やかな桃色の花々が冬の終わりを告げます。 山全体には約1000本の桜...
#花・植物
-
61. 高知市立龍馬の生まれたまち記念館坂本龍馬の生誕地の上町にあり、家族や仲間に囲まれた龍馬の生い立ちや町の歴史を紹介した記念館。館内にはCGを使った体験コーナーや坂本家の離れをイメージした部屋などもあり、子どもから大人まで楽しく学ぶことができます。館内にはボランティアガイドも常駐しており、記念館内を無料で案内してもらえます。また、龍馬ゆかりの地を巡る史跡巡りツアー「龍馬の生まれたまち歩き~土佐っ歩~」も好評開催中。33.556454 133.52449
坂本龍馬の生誕地の上町にあり、家族や仲間に囲まれた龍馬の生い立ちや町の歴史を紹介した記念館。館内にはCGを使った体験コーナーや坂本家の離れをイメージした部屋などもあり、子どもから大人まで楽しく学ぶこと ...
#ミュージアム
-
62. 高知県立美術館世界的画家・シャガールの版画約1,200点から、高知にゆかりのある近現代アーティストの作品まで。高知県立美術館のコレクションは、国内外の約440名・41,000点以上におよぶ。企画展や常設のコレクション展を通じて、多彩な美術との出会いが待っている。さらに2013年には、高知生まれの国際的写真家・石元泰博の膨大な作品・資料を核とした石元泰博フォトセンターを開設。美術を軸としながらも、舞台芸術や映画のプログラムも展開する美術館です。33.56111 133.57347
世界的画家・シャガールの版画約1,200点から、高知にゆかりのある近現代アーティストの作品まで。高知県立美術館のコレクションは、国内外の約440名・41,000点以上におよぶ。企画展や常設のコレクション展を通じて、多 ...
#ミュージアム
-
賛助会員63. 日本サンゴセンター 宝石珊瑚資料館「35の杜」高知県沖はたくさんのサンゴが生息しており、高知県は宝石珊瑚の本場。33.510136 133.5758
宝石珊瑚のアクセサリーの販売や、サンゴでできた作品の展示のほか、アクセサリーづくりや宝石珊瑚を磨く体験もできます。
高知のお土産の販売もしているので、気軽に立ち寄れるスポットです。
高知県沖はたくさんのサンゴが生息しており、高知県は宝石珊瑚の本場。 宝石珊瑚のアクセサリーの販売や、サンゴでできた作品の展示のほか、アクセサリーづくりや宝石珊瑚を磨く体験もできます。 高知のお土産の ...
#おみやげ
#ミュージアム
-
64. 魚梁瀬森林鉄道かつて木材の運搬に活躍した森林鉄道が復元され、乗車・運転体験をすることができます。33.61515 134.1096
春には桜、秋には紅葉が楽しめます。
かつて木材の運搬に活躍した森林鉄道が復元され、乗車・運転体験をすることができます。 春には桜、秋には紅葉が楽しめます。
#文化財・史跡
#乗り物
-
65. 横山隆一記念まんが館高知市生まれのまんが家・横山隆一を記念して造られたまんが館。代表作「フクちゃん」の原画やユニークな収集品等を展示し、隆一のユーモア溢れる人柄や人生を紹介します。高さ9メートルの魚のオブジェ「魚々タワー」は圧巻。また、草創期のアニメやまんが関連書籍を無料で観覧できるまんがライブラリーもあります。33.558186 133.54727
高知市生まれのまんが家・横山隆一を記念して造られたまんが館。代表作「フクちゃん」の原画やユニークな収集品等を展示し、隆一のユーモア溢れる人柄や人生を紹介します。高さ9メートルの魚のオブジェ「魚々タワ...
#ミュージアム
-
賛助会員66. 西島園芸団地トロピカルナーセリーのハウスに一歩入れば、ブーゲンビレアをはじめ熱帯の花が咲き誇り、季節によっては実をつけています。33.5925 133.63953
花に囲まれ、スイカやメロン、フルーツをたっぷり使ったスイーツなどをお召し上がり下さい。
棚での栽培によるイチゴ狩り食べ放題は大人気です。
癒しのひとときをお過ごし下さい。
トロピカルナーセリーのハウスに一歩入れば、ブーゲンビレアをはじめ熱帯の花が咲き誇り、季節によっては実をつけています。 花に囲まれ、スイカやメロン、フルーツをたっぷり使ったスイーツなどをお召し上がり下 ...
#花・植物
#食の体験
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
賛助会員67. メルキュール高知土佐リゾート&スパ高台に位置し、太平洋を一望できるロケーション。高知県の観光名所「桂浜」「室戸岬」をイメージした露天風呂が自慢のリゾートホテルです。33.5227 133.78552
高台に位置し、太平洋を一望できるロケーション。高知県の観光名所「桂浜」「室戸岬」をイメージした露天風呂が自慢のリゾートホテルです。
#温泉
#ホテル
-
68. 火曜市藩政時代から残る水路の上に沿って開く高知市の火曜市。高知市上町は古くから住宅地だったこともあり、昔からの雰囲気が今も残り、古く懐かしい露店市の面影を伝えています。33.55664 133.51903
藩政時代から残る水路の上に沿って開く高知市の火曜市。高知市上町は古くから住宅地だったこともあり、昔からの雰囲気が今も残り、古く懐かしい露店市の面影を伝えています。
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
69. 竜宮神社参拝すると必ず大漁になると言い伝えがあり、航海の安全と豊漁を祈願する神社として知られています。臼碆は黒潮が日本で最初に接岸する場所で、荒波に削られてできたスケールの大きい断崖が広がります。県道27号線沿いにある鳥居をくぐり、木に囲まれた遊歩道を抜けた先、太平洋を見下ろす荒磯の上に建立されています。32.732197 132.96881
参拝すると必ず大漁になると言い伝えがあり、航海の安全と豊漁を祈願する神社として知られています。臼碆は黒潮が日本で最初に接岸する場所で、荒波に削られてできたスケールの大きい断崖が広がります。県道27号線 ...
#寺社
-
70. 和の森 わんぱーくこうちわんぱーくこうちは観覧車やメリーゴーランドなどの遊具で遊べるプレイランド、多くの動物たちがのんびりと生活し、モルモット達とも触れあえるアニマルランド、冒険をテーマに滝を中心に緑が多くある滝ゾーン、子どもたちに人気のアスレチックを設置したアスレチックゾーンなどがあります。33.542126 133.55753
自然がいっぱいの、どなたでも気軽にご利用いただける施設です。
※ふれあいコーナーは7.8.9月はお休みです。(暑さで動物が弱るため)
わんぱーくこうちは観覧車やメリーゴーランドなどの遊具で遊べるプレイランド、多くの動物たちがのんびりと生活し、モルモット達とも触れあえるアニマルランド、冒険をテーマに滝を中心に緑が多くある滝ゾーン、子...
#アミューズメント
#公園
#水族館・動植物園
-
71. 護国神社明治元年(1868年)戊辰戦争の戦死者を祀ったのが始まり。境内にある南海忠烈碑には維新志士85人の名前が刻まれており、龍馬や中岡慎太郎、吉村虎太郎を始め、岡田以蔵も合祀されています。33.544594 133.57112
明治元年(1868年)戊辰戦争の戦死者を祀ったのが始まり。境内にある南海忠烈碑には維新志士85人の名前が刻まれており、龍馬や中岡慎太郎、吉村虎太郎を始め、岡田以蔵も合祀されています。
#寺社
-
72. (休業中)海洋深層水体験交流センター シレストむろと【機械の不具合により臨時休業中です。令和8年4月の再開を予定しています】33.259174 134.18227
海洋深層水100パーセントの温かいプールで、室戸の美しい海を眺めながら様々なアクアエクササイズが楽しめるタラソテラピー施設です。他に露天風呂、フィンランドサウナ、外気浴ホットタブ、足湯など本格的な施設を完備。レストランも併設されています。
【機械の不具合により臨時休業中です。令和8年4月の再開を予定しています】 海洋深層水100パーセントの温かいプールで、室戸の美しい海を眺めながら様々なアクアエクササイズが楽しめるタラソテラピー施設です ...
#温泉
#スポーツ
-
73. ジョン万次郎資料館幕末、土佐清水市中浜の貧しい漁師の次男として生まれた万次郎は、14歳のときに仲間と漁に出て遭難。漂流の後アメリカの船に救助されたことからアメリカへ渡りました。そこで英語や航海術、造船技術など様々なことを学び、帰国後日本の近代化に尽力しました。32.781513 132.93259
資料館では、資料やジオラマから万次郎の波乱万丈の生涯を体感することができます。
幕末、土佐清水市中浜の貧しい漁師の次男として生まれた万次郎は、14歳のときに仲間と漁に出て遭難。漂流の後アメリカの船に救助されたことからアメリカへ渡りました。そこで英語や航海術、造船技術など様々なこと ...
#ミュージアム
-
74. 足摺岬紺碧の海が広がる太平洋に突き出た足摺半島の先端の岬。32.725792 133.01237
展望台からは270度以上の視界が広がり、地球の丸さが実感できます。
自然が織りなすダイナミックな景観があり、地球の雄大さを感じずにはいられません。
岬のシンボルとなっている灯台は、高さ18mと日本最大級の灯台で、大正3年(1914)に点灯されました。
岬に立つ灯台と海の大パノラマは絶景です。
紺碧の海が広がる太平洋に突き出た足摺半島の先端の岬。 展望台からは270度以上の視界が広がり、地球の丸さが実感できます。 自然が織りなすダイナミックな景観があり、地球の雄大さを感じずにはいられません。 ...
#定番
#景観(海)
-
75. 前浜掩体群高知龍馬空港南の田園地帯に、大きなかまぼこ形のコンクリート構造物が残されています。これは掩体と呼ばれ、第2次世界大戦中に敵の攻撃から飛行機を守るために作られたものです。現在は7基だけが残っており、一番大きいものは幅42m、奥行き22m、高さ10mを誇ります。5号掩体は公園として整備されています。33.542805 133.66222
高知龍馬空港南の田園地帯に、大きなかまぼこ形のコンクリート構造物が残されています。これは掩体と呼ばれ、第2次世界大戦中に敵の攻撃から飛行機を守るために作られたものです。現在は7基だけが残っており、一 ...
#文化財・史跡
-
76. 室戸ドルフィンセンターイルカとふれあうことのできる、非日常的な癒しの空間を体験してみませんか。33.26824 134.15964
ドルフィンタッチやトレーナー体験などのほか、イルカと一緒に泳ぐこともできます。
イルカとふれあうことのできる、非日常的な癒しの空間を体験してみませんか。 ドルフィンタッチやトレーナー体験などのほか、イルカと一緒に泳ぐこともできます。
#アミューズメント
-
77. 絵金蔵幕末土佐の絵師・金蔵、通称「絵金」の芝居絵屏風を展示する美術館。33.54179 133.72447
提灯を持って鑑賞する祭りの夜を模した展示や、収蔵庫に保管している芝居絵屏風をのぞき窓から鑑賞できる等、趣向を凝らした展示で絵金の生涯や祭礼文化をたどることができます。
幕末土佐の絵師・金蔵、通称「絵金」の芝居絵屏風を展示する美術館。 提灯を持って鑑賞する祭りの夜を模した展示や、収蔵庫に保管している芝居絵屏風をのぞき窓から鑑賞できる等、趣向を凝らした展示で絵金の生涯 ...
#ミュージアム
-
賛助会員78. 亀の井ホテル 高知土佐和紙発祥の里・いの町の高台に立地し、全室から仁淀川の美しい流れを眺めることができます。33.544827 133.41846
塩分が高く肌に心地よいお湯。露天風呂から望む列車(土讃線)が旅情をかきたてます。大浴場、露天風呂、寝湯など多彩な浴槽も自慢です。
土佐和紙発祥の里・いの町の高台に立地し、全室から仁淀川の美しい流れを眺めることができます。 塩分が高く肌に心地よいお湯。露天風呂から望む列車(土讃線)が旅情をかきたてます。大浴場、露天風呂、寝湯な ...
#温泉
#ホテル
-
79. ドラゴン広場高知県土佐市の高岡商店街にある「ドラゴン広場」は、地域の賑わいを取り戻すために平成25年(2013年)4月にオープンした複合施設です。直販所と飲食店が並び、地元食材を使った料理や土佐市の特産品を楽しめます。観光案内所も併設されているため、土佐市観光の拠点としても便利。地元の味と文化に触れられる、土佐市の新しい魅力発見スポットです。33.49654 133.4243
高知県土佐市の高岡商店街にある「ドラゴン広場」は、地域の賑わいを取り戻すために平成25年(2013年)4月にオープンした複合施設です。直販所と飲食店が並び、地元食材を使った料理や土佐市の特産品を楽しめます。 ...
#おみやげ
#市場・直売所
-
80. 高知ぽかぽか温泉多彩なお風呂やサウナが揃い、男女浴室は毎日入れ替え。家族で気軽に立ち寄れます。ゆったりとしたスペース、リラクゼーションサービスでリラックス。33.574757 133.55876
多彩なお風呂やサウナが揃い、男女浴室は毎日入れ替え。家族で気軽に立ち寄れます。ゆったりとしたスペース、リラクゼーションサービスでリラックス。
#温泉
-
81. ホエールウォッチング宇佐(7月~10月)春から夏。土佐市の海は、大人気のホエールウォッチングのシーズンです。宇佐のはるか沖合で会えるのは、巨大なニタリクジラや遊び好きで陽気なイルカたち。彼らと出会う感動は、日頃のストレスが一瞬で消えてしまうほど、パワフルでハートフル!33.450172 133.4515
クジラとイルカを探す、アドベンチャークルーズへ出かけてみませんか。
春から夏。土佐市の海は、大人気のホエールウォッチングのシーズンです。宇佐のはるか沖合で会えるのは、巨大なニタリクジラや遊び好きで陽気なイルカたち。彼らと出会う感動は、日頃のストレスが一瞬で消えてしま...
#アミューズメント
#海あそび
-
82. 土佐佐賀温泉 こぶしのさと2025年4月25日にリニューアルオープン!33.13737 133.12509
アルカリ性のとろみのある“美人の湯”に、豊富なメニューが揃うレストランが併設。
施設2階には、宿泊可能な客室もあります。
2025年4月25日にリニューアルオープン! アルカリ性のとろみのある“美人の湯”に、豊富なメニューが揃うレストランが併設。 施設2階には、宿泊可能な客室もあります。
#温泉
#レストラン・食堂
#ホテル
-
83. 岩間沈下橋観光ポスターやパンフレット、テレビCMなどで見かける機会の多い有名スポット。鏡のような川面に青い空と緑の山々が映し出された絶景を収めようと、写真撮影をする観光客の姿も多い。全長120m、普通車の通行可能。33.12835 132.81746
観光ポスターやパンフレット、テレビCMなどで見かける機会の多い有名スポット。鏡のような川面に青い空と緑の山々が映し出された絶景を収めようと、写真撮影をする観光客の姿も多い。全長120m、普通車の通行可能。
#景観(川)
#建築
-
84. 道の駅 よって西土佐清流四万十川沿いの道の駅。「てんねん」をコンセプトに四万十川が育んだ天然鮎や西土佐の山間米など、「よって西土佐」ならではの「地」のもの逸品が集まっています。33.173237 132.78935
2016年にオープンした高知県で23番目の道の駅です。
清流四万十川沿いの道の駅。「てんねん」をコンセプトに四万十川が育んだ天然鮎や西土佐の山間米など、「よって西土佐」ならではの「地」のもの逸品が集まっています。 2016年にオープンした高知県で23番目 ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
賛助会員85. 高知県立のいち動物公園檻や柵が少なく、動物たちの生息環境に近づけた展示が特徴の動物公園です。33.570877 133.70647
温帯の森、熱帯の森、アフリカ・オーストラリアゾーン、ジャングルミュージアム、こども動物園で構成された園内には、約110種類、1,000点の動物たちがのどかに暮らしています。
キリン・レッサーパンダ・ペンギンなどの人気動物のほか、存在感いっぱいのユニークな鳥ハシビロコウやとてもかわいいミナミコアリクイなど、見所満載です。
アメリカ生まれの旅行者向けサイト「トリップアドバイザー」の2019年の日本の動物園ランキングで1位、2020年の動物園・水族館ランキングで1位に選ばれました。
檻や柵が少なく、動物たちの生息環境に近づけた展示が特徴の動物公園です。 温帯の森、熱帯の森、アフリカ・オーストラリアゾーン、ジャングルミュージアム、こども動物園で構成された園内には、約110種類、1,000点 ...
#定番
#アミューズメント
#水族館・動植物園
-
86. 浅尾沈下橋周囲を山々に囲まれ、対岸にある鎌井田集落とのコントラストが美しい、全長約121mの沈下橋。33.567684 133.25583
周囲を山々に囲まれ、対岸にある鎌井田集落とのコントラストが美しい、全長約121mの沈下橋。
#定番
#景観(川)
#建築
#作品ゆかりの地
-
賛助会員87. 創造広場「アクトランド」「アクトランド」のアクト(ACT)とは、Art(芸術)・Culture(文化)・Technology(技術)の頭文字を並べたもので、芸術に親しみ、文化を高め、科学技術を発展させる、という想いのもと開設されました。33.568516 133.7001
施設内には、坂本龍馬の蝋人形館「龍馬歴史館」や、土佐の天才絵師・絵金らの作品を展示した「絵金派アートギャラリー」、自動車黎明期の技術が見られる「世界クラシックカー博物館」などの8つの展示館に加え、めずらしい遊具のある無料エリアを併設。
豊かな感性と創造性を育むための魅力に満ちた空間を遊びつくそう!
「アクトランド」のアクト(ACT)とは、Art(芸術)・Culture(文化)・Technology(技術)の頭文字を並べたもので、芸術に親しみ、文化を高め、科学技術を発展させる、という想いのもと開設されました。 施設内には、坂本...
#アミューズメント
-
賛助会員88. 千年の美湯 そうだ山温泉 和とろみのある泉質で、すべすべお肌になる「美人の湯」。33.4313 133.28008
自然に囲まれた和モダンな雰囲気の宿で、素敵な時間が過ごせます。
とろみのある泉質で、すべすべお肌になる「美人の湯」。 自然に囲まれた和モダンな雰囲気の宿で、素敵な時間が過ごせます。
#温泉
#旅館
-
89. 見残し海岸弘法大師が足を進められなかったほどの難所ゆえに名づけられた「見残し海岸」。ここは砂岩が長い歳月の波食と風食を受けて生まれた、壮大な海食台地が広がる場所です。徒歩では辿り着けないこの地を、かつては湾内の風よけを利用した漁師だけがひっそりと訪れていました。32.77172 132.86594
現在はグラスボートがその扉を開き、穏やかな見残し湾を渡って海底の世界へとあなたを誘います。
透明な船底越しに眺める国内最大級のシコロサンゴ群体は、2千万年の時を刻む天然記念物。刻々と変わる光と影のコントラストが、刻まれた時の深淵を感じさせるでしょう。
息をのむような大地の造形美を、海上からじっくりと堪能してください。
弘法大師が足を進められなかったほどの難所ゆえに名づけられた「見残し海岸」。ここは砂岩が長い歳月の波食と風食を受けて生まれた、壮大な海食台地が広がる場所です。徒歩では辿り着けないこの地を、かつては湾内...
#景観(海)
#ジオスポット
-
90. 佐川町立佐川地質館高知県佐川町の「佐川地質館」は、日本の地質学発祥の地の一つとされる佐川盆地に建つ地質・化石ミュージアムです。平成4年に開館し、ナウマン博士や小林貞一博士の研究成果とともに、動くティラノサウルス(3/5大)や世界各国の珍しい化石コレクションを展示。また、地質時代塔やプレート運動解説装置で地球46億年の歴史を体感できます。33.499695 133.30222
子どもから大人まで地球科学を楽しく学べる西南日本外帯の地質構造を代表する貴重な学習スポットです。
高知県佐川町の「佐川地質館」は、日本の地質学発祥の地の一つとされる佐川盆地に建つ地質・化石ミュージアムです。平成4年に開館し、ナウマン博士や小林貞一博士の研究成果とともに、動くティラノサウルス(3/5大 ...
#ミュージアム
-
91. 中津渓谷【紅葉の見ごろ】11月中旬33.56213 133.1276
国道33号より500mほど上がった所にあり、県立自然公園にも指定されている景勝地。中津明神山に降る雨が長い時間をかけて造りあげた壮大な水の森で、「紅葉の滝」「雨竜の滝」「龍宮淵」「石柱」など、水が作った傑作が随所に。入口から石柱まで約2.3kmに遊歩道が整備され、渓谷を間近に見ながら散策が楽しめます。渓谷入口には温泉宿泊施設「中津渓谷ゆの森」があり、ゆったり自然浴を楽しめます。
【紅葉の見ごろ】11月中旬 国道33号より500mほど上がった所にあり、県立自然公園にも指定されている景勝地。中津明神山に降る雨が長い時間をかけて造りあげた壮大な水の森で、「紅葉の滝」「雨竜の滝」「龍宮淵」 ...
#定番
#景観(川)
-
92. 佐川ナウマンカルストJR佐川駅から車ですぐの場所に広がるカルスト台地で、標高約160mの尾根から斜面中腹にかけて石灰岩が突出した独特の景観を持つスポット。33.492256 133.29674
日本の地質学の基礎を築いたドイツの地質学者・ナウマンがこの地を「地質のメッカ」として紹介したことに由来しており、佐川町の地質学的価値を象徴する地域が誇る名所です。
台地には巨大なナウマンゾウの親子オブジェが設置され、カルスト地形との不思議なコラボレーションが楽しめます。
9月中旬頃からは見事な彼岸花が自生し、白い石灰岩と赤い花のコントラストが美しい秋の絶景を演出します。
JR佐川駅から車ですぐの場所に広がるカルスト台地で、標高約160mの尾根から斜面中腹にかけて石灰岩が突出した独特の景観を持つスポット。 日本の地質学の基礎を築いたドイツの地質学者・ナウマンがこの地を「地質の ...
#ジオスポット
#作品ゆかりの地
-
93. 旧山内家下屋敷長屋展示館この長屋の立つ敷地は、幕末に家臣7人の屋敷地を召し上げて藩主であった山内容堂の下屋敷が設けられたところです。33.556023 133.53314
昭和53年、長屋(建物)は高知市に譲渡され、同54年、国の重要文化財に指定されました。同55年2月保存修理に着手、同56年9月に完成しました。
この種の本格的な武家長屋は全国的に少なく、貴重だといえます。
この長屋の立つ敷地は、幕末に家臣7人の屋敷地を召し上げて藩主であった山内容堂の下屋敷が設けられたところです。 昭和53年、長屋(建物)は高知市に譲渡され、同54年、国の重要文化財に指定されました。同55年2月 ...
#ミュージアム
#文化財・史跡
-
賛助会員94. 高知県立高知城歴史博物館土佐藩主山内家に伝わった土佐藩・高知県ゆかりの貴重な“本物”を見ることができる博物館。展望ロビーからパノラマでのぞむ高知城の眺めも必見!33.560467 133.53415
土佐藩主山内家に伝わった土佐藩・高知県ゆかりの貴重な“本物”を見ることができる博物館。展望ロビーからパノラマでのぞむ高知城の眺めも必見!
#ミュージアム
#定番
-
賛助会員95. 北川村温泉 ゆずの宿木の温もりが心地よい館内で、宿泊と日帰り温泉を楽しめます。33.49832 134.10051
木の温もりが心地よい館内で、宿泊と日帰り温泉を楽しめます。
#温泉
#ホテル
#旅館
-
96. 第31番札所 竹林寺神亀元年(724年)、聖武天皇の命により、僧行基が唐の五台山になぞらえ開創した土佐屈指の名刹。本尊は「日本三文殊」のひとつに数えられ、四国88ヶ所霊場第31番札所として参詣者が絶えることがありません。文殊堂や五重塔、国重要文化財指定の仏像17体、さらに国名勝指定庭園など見所も多いです。33.54662 133.57748
神亀元年(724年)、聖武天皇の命により、僧行基が唐の五台山になぞらえ開創した土佐屈指の名刹。本尊は「日本三文殊」のひとつに数えられ、四国88ヶ所霊場第31番札所として参詣者が絶えることがありません。文殊堂 ...
#花・植物
#寺社
#文化財・史跡
#作品ゆかりの地
-
97. 白山洞門足摺岬の海岸線にひっそりと佇む「白山洞門(はくさんどうもん)」は、高さ16m、幅17mを誇る日本最大級の花崗岩洞門です。32.723606 133.01347
長い年月をかけて海蝕によって形づくられたこの巨大な自然のアーチは、今なお波に削られ続けており、地質学的にも貴重な存在。遊歩道で気軽に訪れることができ、そのダイナミックな姿を間近で楽しめます。高知県の天然記念物にも指定されている、足摺を代表する絶景スポットです。
足摺岬の海岸線にひっそりと佇む「白山洞門(はくさんどうもん)」は、高さ16m、幅17mを誇る日本最大級の花崗岩洞門です。 長い年月をかけて海蝕によって形づくられたこの巨大な自然のアーチは、今なお波に削られ続 ...
#景観(海)
#定番
#ジオスポット
-
98. 四国自動車博物館1960年代から1980年代のレースカー、クラシックカーを中心に、国内外の希少な車(4輪・2輪)を展示。33.569416 133.70103
映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場したタイムマシンを再現した車、デロリアンも展示されています。
1960年代から1980年代のレースカー、クラシックカーを中心に、国内外の希少な車(4輪・2輪)を展示。 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場したタイムマシンを再現した車、デロリアンも展示されています。
#ミュージアム
-
99. 漣痕化石漣痕化石とは、海底に波などの影響によってできた模様が形となったものです。3500万年~4000万年前のものと推定され、市の天然記念物として指定されています。33.293743 134.11116
漣痕化石とは、海底に波などの影響によってできた模様が形となったものです。3500万年~4000万年前のものと推定され、市の天然記念物として指定されています。
#ジオスポット
-
100. 杉の大スギ国の特別天然記念物。推定樹齢3,000年、南北の2株が根元で合着し、夫婦スギの愛称で親しまれています。南大杉は根元の周りが20m、樹高60m。北大杉は根元の周りが16.5m、樹高56m。33.755642 133.66309
国の特別天然記念物。推定樹齢3,000年、南北の2株が根元で合着し、夫婦スギの愛称で親しまれています。南大杉は根元の周りが20m、樹高60m。北大杉は根元の周りが16.5m、樹高56m。
#花・植物
-
101. 木曜市県庁近くの市道に約70店が並び、高知市の街路市の中で日曜市に次ぐ規模を誇ります。1971年からこの場所で市が開かれ、街の中心部にありながら、椰子が並ぶ南国らしい風景。日曜市の雰囲気をコンパクトに感じることができるため、観光客も多く訪れます。33.55703 133.53227
県庁や市役所、企業などのビルが立ち並ぶ立地から、仕事の合間に昼食や食材を買い込む人の姿も多く見られます。
県庁近くの市道に約70店が並び、高知市の街路市の中で日曜市に次ぐ規模を誇ります。1971年からこの場所で市が開かれ、街の中心部にありながら、椰子が並ぶ南国らしい風景。日曜市の雰囲気をコンパクトに感じることが...
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
102. 猿田洞高知県日高村にある猿田洞は、安政5年(1858年)に付近の農民・虎之丞によって発見された全長約1420mの石灰洞です。発見当時は見物人で賑わい、入口付近には売店が並ぶほどの人気を博しました。『岩窟往来略図』及び『岩窟往来略図言』が印刷・販売され、大きな利益を得た者もいたと伝えられています。33.51533 133.35818
昭和35年(1960年)に村の文化財に指定され、洞内の探勝ができるよう整備されています。鍾乳石や石筍の状態が良いものは少ないですが、人の手があまり加えられていないため自然のままの地形が残り、探勝はスリル満点です。
洞内からは2万年前に生息した有蹄類の一種「赤鹿」の骨などが発見されており、現在もコウモリやカマドウマなどが生息しています ...
高知県日高村にある猿田洞は、安政5年(1858年)に付近の農民・虎之丞によって発見された全長約1420mの石灰洞です。発見当時は見物人で賑わい、入口付近には売店が並ぶほどの人気を博しました。『岩窟往来略図』及び『岩...
#ジオスポット
-
賛助会員103. 松葉川温泉四万十川の源流の一つ日野地川が流れる四万十町の山里にある温泉宿。33.31291 133.07156
トロトロした泉質が特徴で湯冷めしにくく効能の多さから万病に効く霊泉と言われています。
四万十川の源流の一つ日野地川が流れる四万十町の山里にある温泉宿。 トロトロした泉質が特徴で湯冷めしにくく効能の多さから万病に効く霊泉と言われています。
#温泉
#ホテル
#旅館
-
104. 池川茶園茶畑プリンが人気です♪33.62005 133.1644
仁淀川と茶畑を見ながらスイーツを楽しめます。
茶畑プリンが人気です♪ 仁淀川と茶畑を見ながらスイーツを楽しめます。
#景観(川)
#高知県産
#カフェ・スイーツ
-
賛助会員105. 癒しの湯宿 龍河温泉龍河洞に一番近い小さな温泉宿で、土佐の食材を中心とした会席料理と地酒をご堪能下さい。33.61738 133.72534
土日祝日は日帰り温泉も可能で、こんこんと湧き出るアルカリ泉の天然温泉で、お肌もスベスベほっこり。
のんびりゆったり、静かな癒しのひと時をお過ごしいただけます。
龍河洞に一番近い小さな温泉宿で、土佐の食材を中心とした会席料理と地酒をご堪能下さい。 土日祝日は日帰り温泉も可能で、こんこんと湧き出るアルカリ泉の天然温泉で、お肌もスベスベほっこり。 のんびりゆった ...
#温泉
#ホテル
#旅館
-
106. 竜串海域公園日本で最初に海中公園に指定された竜串海中公園は、サンゴや華やかな魚類とともに熱帯的な海中景観を形成しています。近くには、地質の博物館と呼ばれる竜串海岸、見残し海岸の奇岩や、海洋型の施設などがあります。32.78639 132.86954
日本で最初に海中公園に指定された竜串海中公園は、サンゴや華やかな魚類とともに熱帯的な海中景観を形成しています。近くには、地質の博物館と呼ばれる竜串海岸、見残し海岸の奇岩や、海洋型の施設などがあります。
#景観(海)
#公園
-
107. ゆとりすとパークおおとよさわやかな風が吹き渡る広大な敷地に、テントサイト33区画、ログハウス3棟、コテージ7棟があります。33.74855 133.68422
夜は、満天の星空が降り注いでくるかのような近さでみることができ、早朝には眼下に雲海を眺められることも。
キッズ遊具もリニューアルし、大人から子どもまで楽しむことができます。
さわやかな風が吹き渡る広大な敷地に、テントサイト33区画、ログハウス3棟、コテージ7棟があります。 夜は、満天の星空が降り注いでくるかのような近さでみることができ、早朝には眼下に雲海を眺められることも。 キ...
#アミューズメント
#公園
#キャンプ場
#景観(山)
#コテージ・グランピング
#キャンプ
-
108. 安芸駅ぢばさん市場「安芸駅ぢばさん市場」は、ごめん・なはり線安芸駅構内に併設された地元直送マルシェ&お土産ショップ。33.50433 133.90636
鮮度抜群の野菜や果物、朝獲れの鮮魚、名物「釜揚げちりめんじゃこ」に加え、安芸市発祥とされる芋ケンピや柚子みそ・ポン酢などの特産加工品もずらりと並びます。
店内工房「ぽっぽベーカリー」では、山型食パンやナスカレーパンといった焼きたてパンが大人気。さらに、安芸市の地酒や内原野焼の陶芸品、ごめん・なはり線オリジナルグッズまで、取り扱いアイテムは多彩そのものです。
市場周辺では大人用11台・子ども用3台の無料レンタサイクルを完備。
雨天時は貸出中止となりますが、晴れた日にはサイクリングでの散策も楽しめま ...
「安芸駅ぢばさん市場」は、ごめん・なはり線安芸駅構内に併設された地元直送マルシェ&お土産ショップ。 鮮度抜群の野菜や果物、朝獲れの鮮魚、名物「釜揚げちりめんじゃこ」に加え、安芸市発祥とされる芋ケン ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
109. 大堂お猿公園高知県で唯一の野猿の餌付け場で、約100匹のサルが生息しています。ウキウキしながら見に来てはいかがですか?32.76799 132.64658
高知県で唯一の野猿の餌付け場で、約100匹のサルが生息しています。ウキウキしながら見に来てはいかがですか?
#公園
-
110. 道の駅 すくも サニーサイドパーク国道321号線沿いにあり、市民の憩いの場、観光客の休憩場として利用されています。32.91625 132.71245
令和5年5月3日にリニューアルオープンをし、自然豊かなロケーションを活かしたアウトドアレジャーを楽しんでいただける道の駅として生まれ変わりました。
「幸運の夕日」と呼ばれるだるま夕日の鑑賞スポットとしても有名です。
国道321号線沿いにあり、市民の憩いの場、観光客の休憩場として利用されています。 令和5年5月3日にリニューアルオープンをし、自然豊かなロケーションを活かしたアウトドアレジャーを楽しんでいただける道の駅 ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#キャンプ
#おみやげ
#キャンプ場
-
111. 乗台寺の庭園竹林寺、青源寺とならんで、土佐の三大名園のひとつとして数えられる庭園。33.502758 133.2847
四季折々の美しい景色が見られ、春の新緑、夏の深い緑陰、秋の紅葉、冬の凛とした佇まいと、季節ごとに異なる表情を楽しめるのが魅力です。
寺院ならではの落ち着いた空気の中で、自然と向き合い、心を整える時間を過ごすことができます。
竹林寺、青源寺とならんで、土佐の三大名園のひとつとして数えられる庭園。 四季折々の美しい景色が見られ、春の新緑、夏の深い緑陰、秋の紅葉、冬の凛とした佇まいと、季節ごとに異なる表情を楽しめるのが魅力で ...
#寺社
-
112. 道の駅 キラメッセ室戸 鯨館室戸で栄えた古式捕鯨を、当時の様子を描いた絵図やアニメーションなどでわかりやすく紹介します。33.30644 134.1102
バーチャルリアリティの勢子船乗船体験が大人気です。
室戸で栄えた古式捕鯨を、当時の様子を描いた絵図やアニメーションなどでわかりやすく紹介します。 バーチャルリアリティの勢子船乗船体験が大人気です。
#ミュージアム
-
113. 長宗我部元親像 初陣の像長宗我部氏は岡豊城(現在の高知県南国市)を拠点とし、元親は1539(天文8)年に生まれました。少年時代は「姫若子」(ひめわこ)と呼ばれるほどおとなしかったと伝わっていますが、1560(永禄3)年5月の初陣で目覚ましい活躍をして勝利しました。33.493065 133.54628
直後に父・国親が死去した後を継いだ元親は戦い続け、土佐を統一し、その後1585(天正13)年に四国の大部分を制覇しました。
銅像は、初陣前夜に元親が陣を敷いた若宮八幡宮に、その姿を再現するものとして建てられました。2024年は銅像建立25周年となります。
長宗我部氏は岡豊城(現在の高知県南国市)を拠点とし、元親は1539(天文8)年に生まれました。少年時代は「姫若子」(ひめわこ)と呼ばれるほどおとなしかったと伝わっていますが、1560(永禄3)年5月の初陣で目 ...
#銅像・記念碑
-
114. オーベルジュ土佐山JR高知駅から車で約30分。高知市の山間にあるオーベルジュ土佐山。33.63425 133.4856
豊かな自然に心地よくまどろむ温泉、高知ならではのごちそうを味わえる “泊まれるレストラン”。
都会の喧騒を忘れ、そっと心を整えたい大人女子におすすめです。
JR高知駅から車で約30分。高知市の山間にあるオーベルジュ土佐山。 豊かな自然に心地よくまどろむ温泉、高知ならではのごちそうを味わえる “泊まれるレストラン”。 都会の喧騒を忘れ、そっと心を整えたい大人女子...
#温泉
#ホテル
-
115. 第37番札所 岩本寺聖武天皇の勅願にて行基が建立したと伝えられる福圓満寺が前身。仁井田明神の別当職(別当寺)でした。33.207966 133.13463
後に弘法大師がこの寺社を訪れて仁井田明神のご神体の本地仏を安置し、神仏習合の寺社として栄えました。
中世、寺社共に一時衰退してしまい、岩本寺に寺の法灯並びに別当職は継承されました。
明治の政策で寺社が分離され、五尊の本地仏と札所が岩本寺に統一されました。
聖武天皇の勅願にて行基が建立したと伝えられる福圓満寺が前身。仁井田明神の別当職(別当寺)でした。 後に弘法大師がこの寺社を訪れて仁井田明神のご神体の本地仏を安置し、神仏習合の寺社として栄えました。 ...
#寺社
-
116. 早瀬の一本橋一本橋は沈下橋の原型といわれ、流れ橋とも言います。長さ9メートル、幅60センチ、厚さ30センチほどの木の板3枚を橋桁の上に渡しただけのシンプルな橋。数十年前までは四万十川支流に数多く見られた一本橋も、津野町のこの橋だけとなりました。33.41027 133.02495
一本橋は沈下橋の原型といわれ、流れ橋とも言います。長さ9メートル、幅60センチ、厚さ30センチほどの木の板3枚を橋桁の上に渡しただけのシンプルな橋。数十年前までは四万十川支流に数多く見られた一本橋も、津野町...
#景観(川)
-
117. 咸陽島宿毛湾に浮かぶ2つの無人島から成る景勝地。対岸の大島からは約300m離れていますが、干潮時には道が現れて対岸まで歩いて渡る事が出来ます。32.913795 132.68408
11月中旬~2月中旬に見る事が出来る幸運の夕日と言われている「だるま夕日」のポイントとしても知られています。
宿毛湾に浮かぶ2つの無人島から成る景勝地。対岸の大島からは約300m離れていますが、干潮時には道が現れて対岸まで歩いて渡る事が出来ます。 11月中旬~2月中旬に見る事が出来る幸運の夕日と言われている「だるま夕 ...
#景観(海)
-
118. 吉良川の町並み太平洋を望む美しい港町である吉良川は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれており、江戸から昭和初期にかけて栄えた時代の面影が色濃く残っています。33.33104 134.10016
特徴的なのは、土佐漆喰の白い壁と、水害や火災から家を守るための水切り瓦やいぶし瓦が織りなす独特の景観です。かつて物資の運搬に使われた石畳の道も、当時の賑わいを伝えています。
古い町家や商店が立ち並ぶ吉良川を歩けば、まるでタイムスリップしたような感覚に。昔ながらの日本の風景と、そこに息づく人々の暮らしを感じることができます。
太平洋を望む美しい港町である吉良川は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれており、江戸から昭和初期にかけて栄えた時代の面影が色濃く残っています。 特徴的なのは、土佐漆喰の白い壁と、水害や火災から家 ...
#町並み
-
119. 三里沈下橋左岸下流側に広い河原があり、沈下橋から降りてゆっくりと見ることができます。訪れる人は少ないものの、夕日に映える風景は絶景。全長約146m、普通車の通行可能。33.01122 132.8729
左岸下流側に広い河原があり、沈下橋から降りてゆっくりと見ることができます。訪れる人は少ないものの、夕日に映える風景は絶景。全長約146m、普通車の通行可能。
#景観(川)
#建築
-
120. 岩崎弥太郎生家高知県安芸市の郊外にある岩崎彌太郎生家は、1795年頃に曽祖父が建てた藁葺き平屋建ての貴重な歴史建造物です。33.52628 133.89992
彌太郎の先祖は安芸国虎の家臣で、長宗我部氏や山内氏の時代を経て農業を営んでいました。生家には、現在の三菱マークの原型とされる「三階菱」の家紋が刻まれた鬼瓦や、彌太郎少年が日本列島を模して夢を託した石組の庭園が残されています。
歴史ファンや三菱財閥ゆかりのスポットを訪ねる観光客におすすめの場所です。
高知県安芸市の郊外にある岩崎彌太郎生家は、1795年頃に曽祖父が建てた藁葺き平屋建ての貴重な歴史建造物です。 彌太郎の先祖は安芸国虎の家臣で、長宗我部氏や山内氏の時代を経て農業を営んでいました。生家には ...
#文化財・史跡
-
121. 下津井のめがね橋森林鉄道の軌道橋として造られた橋で、湖畔に映る姿がめがねに見えることからこう呼ばれています。33.29745 132.94397
山に囲まれた静かな場所にたたずむ姿は、ノスタルジックな景色です。
森林鉄道の軌道橋として造られた橋で、湖畔に映る姿がめがねに見えることからこう呼ばれています。 山に囲まれた静かな場所にたたずむ姿は、ノスタルジックな景色です。
#建築
-
122. 高知市中心商店街東の端は「よさこい情報交流館」、西の端は「ひろめ市場」まで続くアーケード商店街。33.561 133.54263
ショッピングやグルメを楽しんだり、寄り道感覚で散策すれば「高知城」「高知城歴史博物館」までの道のりを楽しめます。
アーケード商店街は、東から西に向かって、「はりまや橋商店街」、「壱番街商店街」、「京町・新京橋商店街」、「帯屋町一丁目商店街」、「帯屋町二丁目商店街」、「大橋通り商店街」と続きます。
アーケード商店街の南に1本入った通りにある「おびさんロード」はアーケードはありませんが、レストランやミニシアターが並ぶ石畳の商店街です。
東の端は「よさこい情報交流館」、西の端は「ひろめ市場」まで続くアーケード商店街。 ショッピングやグルメを楽しんだり、寄り道感覚で散策すれば「高知城」「高知城歴史博物館」までの道のりを楽しめます。 ア...
#町並み
-
123. ペル猫注意の道路標識いの町と日高村の境界付近にある道路標識。133.40376 33.54326
猫をデザインした動物注意の道路標識は全国的にも非常に珍しいです。
【近くの観光スポット】
いの町紙の博物館、椙本神社、吉井源太翁生家、波川公園など
いの町と日高村の境界付近にある道路標識。 猫をデザインした動物注意の道路標識は全国的にも非常に珍しいです。 【近くの観光スポット】 いの町紙の博物館、椙本神社、吉井源太翁生家、波川公園など
#町並み
-
124. 道の駅 南国風良里高知自動車道・南国ICに近い道の駅。33.6112 133.64215
国道32号線沿いで高知県中東部の玄関口。
土産品店(アイスクリームコーナー有)、レストラン、農産物直売所があり、インフォメーション機能も充実。買い物、食事、休憩と幅広くご利用いただける総合施設です。
地元南国市を中心に高知の物産を幅広く品揃え、地産地消にこだわったお食事もお楽しみいただけます。
レストラン定休日(火曜)を利用した農家レストラン(まほろば畑)も大好評。
高知自動車道・南国ICに近い道の駅。 国道32号線沿いで高知県中東部の玄関口。 土産品店(アイスクリームコーナー有)、レストラン、農産物直売所があり、インフォメーション機能も充実。買い物、食事、休憩と幅広く ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
125. 御厨人窟と神明窟約1200年前の平安時代、青年時代の大師が悟りを開いたといわれる洞窟で、中には五所神社と呼ばれる社があります。空海と名前をつけたのもここから見える空と海に感銘を受けたからと言われています。「御厨人窟」の波音は環境省の「日本の音風景100選」に選ばれています。33.251396 134.18047
約1200年前の平安時代、青年時代の大師が悟りを開いたといわれる洞窟で、中には五所神社と呼ばれる社があります。空海と名前をつけたのもここから見える空と海に感銘を受けたからと言われています。「御厨人窟」の ...
#文化財・史跡
#寺社
-
126. まきのさんの道の駅・佐川日本を代表する植物分類学者・牧野富太郎博士の出身地、そして地質学上日本を代表する重要な地、高知県佐川町。33.50341 133.3171
「仁淀ブルー」として有名な仁淀川の支流が流れる自然あふれる山里、城下町の風情を感じさせる町並みが残る地に、2023年にオープン。
仁淀川流域の新鮮な野菜などの産直市や特産品を活かした地場産品・地酒を取り揃えた土産店はもちろん、地元食材を取り入れたバウムクーヘンを製造・販売するショップやレストランなどを備えた、「ごちそう」が一挙に集う道の駅です。
また、木のおもちゃにふれながら楽しく学べる体験型美術館「佐川おもちゃ美術館」を併設。
外には芝生広場や遊具公園もあり、1日楽しんでいただけます。
日本を代表する植物分類学者・牧野富太郎博士の出身地、そして地質学上日本を代表する重要な地、高知県佐川町。 「仁淀ブルー」として有名な仁淀川の支流が流れる自然あふれる山里、城下町の風情を感じさせる町並 ...
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
127. 高知県立文学館高知県立文学館は、高知城の東のふもとにあり、奥深い高知の文学の魅力を心ゆくまで堪能できる施設です。33.56187 133.5334
常設展示では、古典から現代文まで、多彩な高知の文学者・高知ゆかりの作家約40名を紹介しており、没後周年にあたる文学者や話題の文学者をローテーション方式で紹介する【変わる常設展示】が特徴で、来館のたびに新しい文学体験ができる仕組みになっています。また、「寺田寅彦記念室」「宮尾文学の世界」の特別室もあります。
高知県立文学館は、高知城の東のふもとにあり、奥深い高知の文学の魅力を心ゆくまで堪能できる施設です。 常設展示では、古典から現代文まで、多彩な高知の文学者・高知ゆかりの作家約40名を紹介しており、没後周 ...
#ミュージアム
-
128. 坂本龍馬誕生地日本の夜明け、幕末に海援隊長をつとめ、薩長同盟、大政奉還の立役者となった、坂本龍馬。高知市上町の生誕地には碑が立ち、龍馬の誕生日であり命日でもある11月15日には、毎年ここで龍馬誕生祭が行われています。33.557087 133.52586
日本の夜明け、幕末に海援隊長をつとめ、薩長同盟、大政奉還の立役者となった、坂本龍馬。高知市上町の生誕地には碑が立ち、龍馬の誕生日であり命日でもある11月15日には、毎年ここで龍馬誕生祭が行われています。
#文化財・史跡
#銅像・記念碑
-
129. 道の駅 めじかの里土佐清水「お魚の町土佐清水」と言われるように水産業が主産業の土佐清水市の魅力を最大限にお伝えすると共に、竜串地域、足摺地域と地域と地域を結ぶハブの役割を持っており「新鮮で美味しい」をモットーにした道の駅です。32.793407 132.88333
「お魚の町土佐清水」と言われるように水産業が主産業の土佐清水市の魅力を最大限にお伝えすると共に、竜串地域、足摺地域と地域と地域を結ぶハブの役割を持っており「新鮮で美味しい」をモットーにした道の駅です。
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
130. 金曜市高知市の愛宕商店街近く、JR土讃線の鉄道高架橋がそびえる通りに約30店が並びます。愛宕商店街と共に発展してきた、地元の住民にとって無くてはならない暮らしの市です。33.56717 133.53596
高知市の愛宕商店街近く、JR土讃線の鉄道高架橋がそびえる通りに約30店が並びます。愛宕商店街と共に発展してきた、地元の住民にとって無くてはならない暮らしの市です。
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
131. 馬路温泉緑いっぱいの馬路村で、安田川のせせらぎを聞きながら過ごす贅沢な時間。33.55668 134.04922
お部屋や浴室から安田川や馬路の山が眺められます。
温泉の泉質はナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉で、体があったまります。
緑いっぱいの馬路村で、安田川のせせらぎを聞きながら過ごす贅沢な時間。 お部屋や浴室から安田川や馬路の山が眺められます。 温泉の泉質はナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉で、体があったまります。
#温泉
#レストラン・食堂
#おみやげ
#ホテル
#旅館
-
132. アシズリテルメ ASHIZURI THERMAE足摺の豊かな大地より湧き出した天然のラドン温泉。32.72716 133.00658
お部屋や露天風呂から太平洋を一望でき、水平に沈む夕日や満天の星空を堪能できます。
足摺の豊かな大地より湧き出した天然のラドン温泉。 お部屋や露天風呂から太平洋を一望でき、水平に沈む夕日や満天の星空を堪能できます。
#温泉
#ホテル
-
133. 昭和レトロ お宝屋敷おおとよ30~40年代に迷い込んだかのような、なつかしい昭和の雑貨が集められた博物館。33.783558 133.69658
当時のお茶の間を再現し、「昭和レトロ」をコンセプトにした個人収集品を所狭しと展示しています。
ここは、なんとも言い難いノスタルジーを感じさせてくれる場所であり、なぜか不思議と落ち着く場所です。
30~40年代に迷い込んだかのような、なつかしい昭和の雑貨が集められた博物館。 当時のお茶の間を再現し、「昭和レトロ」をコンセプトにした個人収集品を所狭しと展示しています。 ここは、なんとも言い難いノスタル...
#ミュージアム
-
134. 四万十川源流点全長196kmと四国一の長さを誇り、日本最後の清流と呼ばれる四万十川。33.44268 133.07162
不入山の中腹に端を発し、苔むした倒木や岩肌の間を縫うように流れる清水は、大河の源流と呼ぶに相応しい。
全長196kmと四国一の長さを誇り、日本最後の清流と呼ばれる四万十川。 不入山の中腹に端を発し、苔むした倒木や岩肌の間を縫うように流れる清水は、大河の源流と呼ぶに相応しい。
#景観(川)
-
賛助会員135. 潮江天満宮菅原道真 太宰府左遷とともに土佐に流された、道真の長子高視が道真の遺品の観音像などを御神体として創建。33.55345 133.53488
楼門は市の文化財。
菅原道真 太宰府左遷とともに土佐に流された、道真の長子高視が道真の遺品の観音像などを御神体として創建。 楼門は市の文化財。
#寺社
-
136. 高田屋国登録有形文化財でもある高田屋(竹崎家住宅)は、明治10年頃に建てられ、樟脳業で栄えた商家です。33.423973 134.02184
蔵の入口は防犯のため家屋内部にあり、災害に備えて、蔵屋根の一部は二重構造になっています。
建築当初の蔵は、西蔵(道具蔵)・東蔵(米蔵)として利用されていました。現在、蔵はギャラリーとして利用され、竹崎家の調度品や工芸品等が展示されています。また、主屋は和風喫茶として開放されており、住民の方の憩いの場にもなっています。
国登録有形文化財でもある高田屋(竹崎家住宅)は、明治10年頃に建てられ、樟脳業で栄えた商家です。 蔵の入口は防犯のため家屋内部にあり、災害に備えて、蔵屋根の一部は二重構造になっています。 建築当初の蔵は...
#文化財・史跡
#町並み
#カフェ・スイーツ
-
137. 双名島中土佐町の久礼湾に浮かぶ「双名島(ふたなじま)」は、鬼が海に岩を運んで波を鎮めたという伝説が残る神秘の島。33.32974 133.24886
2つの島は弁天島と観音島で、いずれも漁師たちが海の守り神として信仰してきました。
堤防を歩いて渡れる距離にあり、島内では小道や階段を辿って、灯台や祠、海の絶景をめぐる気軽な散策が楽しめます。
天気のいい日には、透明な海に泳ぐ小魚や、のどかな漁港の風景も魅力。
歴史と自然、どちらも味わえる中土佐町の隠れた名所です。
中土佐町の久礼湾に浮かぶ「双名島(ふたなじま)」は、鬼が海に岩を運んで波を鎮めたという伝説が残る神秘の島。 2つの島は弁天島と観音島で、いずれも漁師たちが海の守り神として信仰してきました。 堤防を歩 ...
#景観(海)
-
賛助会員138. 夢の温泉物部川のほとりの温泉施設。33.62527 133.71944
日帰り温泉に宿泊も可能。グランピングでアウトドア体験も♪
物部川のほとりの温泉施設。 日帰り温泉に宿泊も可能。グランピングでアウトドア体験も♪
#温泉
#ホテル
#コテージ・グランピング
-
139. 三嶺「日本二百名山」のひとつ。剣山国定公園の連峰の中で四国一の展望を誇り、頂上からは石鎚山や剣山など四国山地の主峰を見渡せ、天候が良ければ太平洋、瀬戸内海までも眺望できます。頂上から西熊山を経て天狗塚までの尾根筋一帯は、国の天然記念物に指定されている「ミヤマクマザサとコメツツジの群落」と岩肌との調和が見事。33.839138 133.9886
「日本二百名山」のひとつ。剣山国定公園の連峰の中で四国一の展望を誇り、頂上からは石鎚山や剣山など四国山地の主峰を見渡せ、天候が良ければ太平洋、瀬戸内海までも眺望できます。頂上から西熊山を経て天狗塚ま...
#景観(山)
-
140. JAファーマーズマーケット とさのさととれたての野菜や果物、新鮮な魚、手作りのお惣菜、人気のおみやげなど、高知県産のおいしいものが勢ぞろい!33.56853 133.56152
同じ敷地内には、レストランやセレクトショップの複合施設「とさのさと AGRI COLLETTO」があります。
とれたての野菜や果物、新鮮な魚、手作りのお惣菜、人気のおみやげなど、高知県産のおいしいものが勢ぞろい! 同じ敷地内には、レストランやセレクトショップの複合施設「とさのさと AGRI COLLETTO」があります。
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
141. 道の駅木の香(木の香温泉)2024年11月にリニューアルオープンした、温泉と宿泊施設のある道の駅。33.779823 133.30766
天然温泉は露天風呂もあり、川のせせらぎを聞きながらゆっくりと過ごすことができます。
レストランでは、キジやアメゴなど地元のグルメを楽しむことができます。
2024年11月にリニューアルオープンした、温泉と宿泊施設のある道の駅。 天然温泉は露天風呂もあり、川のせせらぎを聞きながらゆっくりと過ごすことができます。 レストランでは、キジやアメゴなど地元のグルメを楽 ...
#温泉
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#おみやげ
#旅館
-
賛助会員142. 酒蔵 桂月館(大町桂月ミニ資料館)酒蔵を改造した明治の文豪・大町桂月のミニ資料室。見学には清酒がついています♪33.743565 133.54294
酒蔵を改造した明治の文豪・大町桂月のミニ資料室。見学には清酒がついています♪
#ミュージアム
#食の体験
#施設見学
#醸造所
-
143. 野良時計安芸市の田園風景に溶け込むように佇む「野良時計」は、明治時代中頃に地元の地主・畠中源馬氏が自らの手で製作した手づくりの時計台です。アメリカ製の八角形掛時計を手本に、何度も分解と組み立てを繰り返し、歯車や分銅に至るまで全て独力で仕上げたと伝えられています。33.515755 133.91148
当時、家に時計があるのはごく一部。畑で農作業をする人々にとって、この時計台は遠くからでも時間を知ることができる貴重な存在でした。以来、地域の暮らしを支える“野良(農作業)時計”として親しまれ、今もなお現役で時を刻み続けています。
安芸市の田園風景に溶け込むように佇む「野良時計」は、明治時代中頃に地元の地主・畠中源馬氏が自らの手で製作した手づくりの時計台です。アメリカ製の八角形掛時計を手本に、何度も分解と組み立てを繰り返し、歯...
#文化財・史跡
-
144. 瑞山神社武市半平太を祀る神社。境内には「花依清香愛 人以仁義栄 幽囚何可恥 只有赤心明」という彼の遺詠記念碑もあります。半平太の命日である5月11日には、ここで墓前祭が行われています。33.537125 133.60378
武市半平太を祀る神社。境内には「花依清香愛 人以仁義栄 幽囚何可恥 只有赤心明」という彼の遺詠記念碑もあります。半平太の命日である5月11日には、ここで墓前祭が行われています。
#寺社
-
145. 仁淀川河口(サーフィン)奇跡の清流「仁淀川」の河口。33.45949 133.48103
仁淀川河口大橋がかかり西側には土佐市の新居地区観光交流施設「南風(まぜ)」があります。サーフィンの後は南風2階のカフェで太平洋を眺めながらお食事はいかがでしょうか。
奇跡の清流「仁淀川」の河口。 仁淀川河口大橋がかかり西側には土佐市の新居地区観光交流施設「南風(まぜ)」があります。サーフィンの後は南風2階のカフェで太平洋を眺めながらお食事はいかがでしょうか。
#海あそび
#景観(海)
-
146. 坂本龍馬像(シェイクハンド)龍馬記念館前に立つ、右手を差し出した坂本龍馬の銅像。犬猿の敵対関係にあった坂本龍馬と後藤象二郎が大政奉還を前にすべての怨念を捨て、人々の幸せのために握手したと言われており、そこからシェイクハンド龍馬像の発想が生まれました。33.496555 133.57187
「シェイクハンド=握手」は、身分に関係なく同じ志を持つ者が協力することで平和で平等な国づくりを目指した龍馬の精神を表しています。
龍馬記念館前に立つ、右手を差し出した坂本龍馬の銅像。犬猿の敵対関係にあった坂本龍馬と後藤象二郎が大政奉還を前にすべての怨念を捨て、人々の幸せのために握手したと言われており、そこからシェイクハンド龍馬...
#銅像・記念碑
-
147. 香美市立やなせたかし記念館 詩とメルヘン絵本館<2025年3月29日(土)より、入館予約が必要です>33.64701 133.78452
詳しくは公式ホームページをご覧ください。
詩と絵と漫画が好きだから…やなせ氏の一途な思いから生まれた雑誌「詩とメルヘン」。その雑誌にまつわる作品を中心に、もう一つのやなせたかしワールドを紹介するギャラリー。年2~3回の企画展では、国内外の絵本作家等の原画展も開催しています。
<2025年3月29日(土)より、入館予約が必要です> 詳しくは公式ホームページをご覧ください。 詩と絵と漫画が好きだから…やなせ氏の一途な思いから生まれた雑誌「詩とメルヘン」。その雑誌にまつわる作品を中心...
#ミュージアム
-
148. 中津渓谷・ゆの森中津渓谷にある温泉宿。33.561382 133.13026
和室からは仁淀ブルーの中津川を眺められ、のんびりとくつろげます。
ツインルームのコテージには、仁淀川町産の杉や桧をふんだんに使用した内風呂もあり、贅沢なひとときを過ごせます。
アルカリ性硫黄鉱泉の天然温泉は、神経痛や切り傷などの効能あり。
景色を楽しみながら入浴できる露天風呂は、週替わりで男女が入れ替わります。
中津渓谷にある温泉宿。 和室からは仁淀ブルーの中津川を眺められ、のんびりとくつろげます。 ツインルームのコテージには、仁淀川町産の杉や桧をふんだんに使用した内風呂もあり、贅沢なひとときを過ごせます。 ...
#温泉
#ホテル
#コテージ・グランピング
-
149. 天神の大杉高知県香南市香我美町の天満宮境内にそびえる「天神の大杉」は、樹高約55m、幹周り約9.5m、推定樹齢800年の巨木です。1943年に国の天然記念物に指定され、四国に生育するスギの中でも特に貴重な存在として知られています。33.56235 133.75163
過去2度の火災に見舞われ、昭和46年(1971年)春には3日間も燃え続ける大火に遭いました。幹には今も修復の痕が残りますが、驚くことに樹勢は衰えず、むしろ近年の方が青々としているという報告もあります。
周辺のスギ・ヒノキ林を遥かに超える高さで、相当遠方からでもその姿を確認できます。かつて植物学者の中井猛之進博士が、小枝が細く垂れ下がる特徴から「コウチスギ」と変種命名したこともある、独特の樹形を持つ巨木です ...
高知県香南市香我美町の天満宮境内にそびえる「天神の大杉」は、樹高約55m、幹周り約9.5m、推定樹齢800年の巨木です。1943年に国の天然記念物に指定され、四国に生育するスギの中でも特に貴重な存在として知られていま ...
#花・植物
-
150. 万次郎足湯足摺岬の絶景を堪能できる足湯スポットが誕生。階段状に設計された足湯からは、どこに座っても目の前に雄大な太平洋と、日本最大級の花崗岩洞門「白山洞門」が広がります。32.724552 133.01408
約30人が利用できる足湯のほか、隣にはベンチも完備され、のんびりと海風を感じながら休憩も可能。白山洞門の目前まで海岸沿いを歩いて行くこともでき、観光にも癒しにもぴったりの立ち寄りスポットです。利用は無料、タオルは100円で販売中。
足摺岬の絶景を堪能できる足湯スポットが誕生。階段状に設計された足湯からは、どこに座っても目の前に雄大な太平洋と、日本最大級の花崗岩洞門「白山洞門」が広がります。 約30人が利用できる足湯のほか、隣には...
#温泉
-
151. 琵琶ヶ滝奈半利町の「南部」、室戸市に隣接する加領郷地区にあります。33.38388 134.04
琵琶ヶ滝は国道から少し入った場所にあるため、気軽に行くことができる観光スポットになっています。
名の由来は、「滝つぼが琵琶の形状に似ているから」や、「滝の音が琵琶の音色に聞こえたから」、「琵琶法師がその場所で亡くなった」など、さまざまな説があります。
滝の落差は約15mと、他の滝と比べて小ぶりですが、水量が豊富です。
琵琶ヶ滝を訪れるなら、水量が覆う夏場がオススメ♪滝に近づくにつれて、清涼感を味わうことができるので、夏の暑さを和らげてくれます。
奈半利町の「南部」、室戸市に隣接する加領郷地区にあります。 琵琶ヶ滝は国道から少し入った場所にあるため、気軽に行くことができる観光スポットになっています。 名の由来は、「滝つぼが琵琶の形状に似ているか ...
#景観(川)
-
152. 高知県立公園ヤ・シィパーク道の駅・鉄道駅に隣接した複合施設。太平洋に面しており、夏季には海水浴場が開設されます。33.535587 133.75108
他にも、太平洋を見ながらピクニックやバーベキューが楽しめるピクニックエリア、小さい子どもたちも楽しいパークエリア、砂浜のビーチボールエリアがあります。
毎年、7月中旬に開催される「マリンフェスティバルYASU」、8月15日に開催される「香南市手結盆踊り」、11月下旬の「秋まつり」、12月を通じて点灯される「海辺のイルミネーション」など、年間20以上のイベントが開催される人気スポットです。
道の駅・鉄道駅に隣接した複合施設。太平洋に面しており、夏季には海水浴場が開設されます。 他にも、太平洋を見ながらピクニックやバーベキューが楽しめるピクニックエリア、小さい子どもたちも楽しいパークエリ ...
#景観(海)
#公園
-
153. 長宗我部元親墓桂浜・浦戸方面へ向かう道沿い、バス停から北へ徒歩2分ほど。長浜・天甫寺山の静かな木立に囲まれて、「長宗我部元親の墓」がひっそりと佇んでいます。33.497177 133.553
戦国時代、土佐を統一し、四国の覇者となった名将・長宗我部元親(1539–1599)。初陣から華々しい活躍を見せ、やがて土佐一国の主から四国全域を平定するまでに至りましたが、豊臣秀吉の征討を受け、土佐一国に留まることとなります。
その後も秀吉に忠義を尽くし、小田原征伐や朝鮮出兵にも従軍。しかし、晩年には愛息・信親の戦死や家中の内紛など苦難も多く、京都で病に倒れ、61歳で没しました。遺言により火葬後、遺骨は故郷・土佐に戻され、この天甫寺山に葬られました。
歴史に名を ...
桂浜・浦戸方面へ向かう道沿い、バス停から北へ徒歩2分ほど。長浜・天甫寺山の静かな木立に囲まれて、「長宗我部元親の墓」がひっそりと佇んでいます。 戦国時代、土佐を統一し、四国の覇者となった名将・長宗我 ...
#文化財・史跡
-
154. アメガエリの滝土佐の名水40選。吉野川の支流の一つ、瀬戸川の上流部にある滝。両岸に緑豊な山々が続き、すばらしい渓谷美を誇ります。川全体が断層により落差30mの二段の滝となっています。33.724854 133.39935
土佐の名水40選。吉野川の支流の一つ、瀬戸川の上流部にある滝。両岸に緑豊な山々が続き、すばらしい渓谷美を誇ります。川全体が断層により落差30mの二段の滝となっています。
#景観(川)
-
155. 高知オーガニックマーケット有機をコンセプトに、無農薬の農産物や無添加の加工食品づくりに取り組む人たちが出店者となり、2008年に日本で初めて毎週開催されるオーガニックマーケットとしてスタート。家族でのんびりできる池公園内に開かれていることもあり、県外からも口コミでたくさんのファンが訪れています。33.525295 133.58818
有機をコンセプトに、無農薬の農産物や無添加の加工食品づくりに取り組む人たちが出店者となり、2008年に日本で初めて毎週開催されるオーガニックマーケットとしてスタート。家族でのんびりできる池公園内に開かれ ...
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
156. 土居廓中高知県安芸市に広がる「土居廓中(どいかちゅう)」は、江戸時代の武家文化と往時の暮らしを今に伝えます。33.51853 133.91139
廓中を歩くと、かつての武士たちが暮らした家々や、人々の営みが聞こえてくるかのような錯覚に陥るでしょう。
地区内には一般公開されている野村家住宅のような貴重な武家屋敷もあり、当時の建築様式や生活空間を間近に見学できます。
安芸市土居廓中伝統的建造物群保存地区は、単なる観光地ではなく、高知の歴史と文化が息づく特別な場所です。喧騒を離れて、じっくりと歴史と向き合い、心安らぐひとときを過ごしたい方には、ぜひ訪れていただきたい高知の隠れた名所と言えるでしょう。
高知県安芸市に広がる「土居廓中(どいかちゅう)」は、江戸時代の武家文化と往時の暮らしを今に伝えます。 廓中を歩くと、かつての武士たちが暮らした家々や、人々の営みが聞こえてくるかのような錯覚に陥るで ...
#文化財・史跡
#町並み
-
賛助会員157. 砂浜美術館4kmの海岸を美術館に見立てて作品を展示。33.035046 133.02702
「Tシャツアート展」や「潮風のキルト展」などを企画・開催しています。
4kmの海岸を美術館に見立てて作品を展示。 「Tシャツアート展」や「潮風のキルト展」などを企画・開催しています。
#景観(海)
-
158. 仁淀ブルースクエアJR西佐川駅にある交流スペース。33.512638 133.28651
仁淀川流域6市町村のパンフレットやイベント情報を提供、仁淀川流域の商品販売もしています。
観光する場所をゆっくり探せるテーブル席のほか、列車や線路を望めるカウンター席もあります。
JR西佐川駅にある交流スペース。 仁淀川流域6市町村のパンフレットやイベント情報を提供、仁淀川流域の商品販売もしています。 観光する場所をゆっくり探せるテーブル席のほか、列車や線路を望めるカウンター席も ...
#観光案内所
-
159. 横浪黒潮ライン高知県土佐市と須崎市を結ぶ横浪黒潮ラインは、横浪半島の稜線を走る全長18.8kmの快適なドライブウェイです。足摺岬と室戸岬のほぼ中間に位置し、リアス式海岸の美しい海岸線を眺めながら、内海の浦ノ内湾と太平洋の両方を展望できる絶景ルートです。33.43931 133.43951
横浪半島は標高255.4mの宇津賀山を最高峰に200m前後の山々が連なり、外海と隔てられた浦ノ内湾は入口から奥まで約12kmあります。湾口からの波が横に波紋を広げることから「横浪三里」と呼ばれ、リアス式海岸特有の入り組んだ枝湾の風景が車窓から楽しめます。
高知県土佐市と須崎市を結ぶ横浪黒潮ラインは、横浪半島の稜線を走る全長18.8kmの快適なドライブウェイです。足摺岬と室戸岬のほぼ中間に位置し、リアス式海岸の美しい海岸線を眺めながら、内海の浦ノ内湾と太平洋の...
#定番
#景観(海)
-
160. JR朝倉駅JR四国の朝倉駅は、アニメ映画『竜とそばかすの姫』で、主人公たちが下校時に通った駅のモデルとなった駅です。33.55145 133.48549
JR四国の朝倉駅は、アニメ映画『竜とそばかすの姫』で、主人公たちが下校時に通った駅のモデルとなった駅です。
#作品ゆかりの地
-
161. 寺田寅彦記念館物理学者で随筆家としても知られる寺田寅彦(てらだとらひこ、1878〜1935年)が幼年時代を過ごした邸宅を保存公開しています。33.563427 133.52849
第二次大戦の空襲で焼かれ旧寺田邸もはなれの勉強部屋を除いて焼失したのですが、「復元する会」により茶室と主屋が再建され、昭和59年、記念館として公開されました。
「天災は忘れた頃にやってくる」という有名な言葉を最初に唱えたのが寺田寅彦で、第五高等学校(現・熊本大学)で夏目漱石(なつめそうせき)に英語を習い、生涯親交を持ちました。小説『吾輩は猫である』に登場する「水島寒月(かんげつ)」は、寺田寅彦がモデルと言われています。
記念館の入り口の左側にある「寺田寅彦先生邸址」碑は牧野富...
物理学者で随筆家としても知られる寺田寅彦(てらだとらひこ、1878〜1935年)が幼年時代を過ごした邸宅を保存公開しています。 第二次大戦の空襲で焼かれ旧寺田邸もはなれの勉強部屋を除いて焼失したのですが、「 ...
#ミュージアム
#建築
#文化財・史跡
#銅像・記念碑
-
162. 瓶ヶ森西条市の「瓶ヶ森」は、頂上部が一面の笹原に覆われたなだらかな高原で、樅や栂の群生と白骨林が織り成す神秘的な景観が魅力です。33.792 133.19096
山頂には女山・男山の二峰がそびえ、石鎚山をはじめ四国の山々をぐるりと見渡せるパノラマビューが広がります。
瓶ヶ森駐車場から山頂までは約1時間の手軽な登山道で、初心者やファミリーにも人気。2017年末に整備された避難小屋とトイレ、近隣のキャンプ場も利用でき、四季折々の自然美を満喫する拠点として最適です。豊かな高原の風と広大な眺望を、ぜひ体感してください。
西条市の「瓶ヶ森」は、頂上部が一面の笹原に覆われたなだらかな高原で、樅や栂の群生と白骨林が織り成す神秘的な景観が魅力です。 山頂には女山・男山の二峰がそびえ、石鎚山をはじめ四国の山々をぐるりと見渡 ...
#景観(山)
-
163. 唐人駄場遺跡森の奥に静かにたたずむ唐人駄場遺跡は、およそ5,000~6,000年前の縄文時代早期から弥生時代にかけて形成された古代の暮らしの跡です。32.742928 132.98323
ここからは石器、土器片、黒曜石の矢じりに加え、謎に満ちた巨石のミステリーサークルも発見されています。大きさ6~7mもあるこれらの巨石をどう運び、どう配置したのか — 高度な技術なのか、巨人が関わっていたのか — 真相はいまだ解明していないというロマンに溢れたパワースポットです。
遊歩道もあり、安心して散策も可能。深い森と巨石が織り成すダイナミックな景観に身も心も癒されます。巨石に上って遠くに広がる太平洋を臨めば、その雄大さに圧倒されることでしょう。
森の奥に静かにたたずむ唐人駄場遺跡は、およそ5,000~6,000年前の縄文時代早期から弥生時代にかけて形成された古代の暮らしの跡です。 ここからは石器、土器片、黒曜石の矢じりに加え、謎に満ちた巨石のミステリー ...
#文化財・史跡
-
164. まちの駅ゆすはら(マルシェ・ユスハラ)梼原町の特産品販売と宿泊機能が一体となった“まちの駅 ゆすはら”は、訪れる誰もを梼原町の顔としてお迎えします。33.393753 132.9267
東側を覆うのは、伝統的な茅葺屋根に学んだ隈研吾氏デザインの茅(かや)ファサード。風を通し、熱を逃がす“自然の空調”が、町の気候に寄り添う快適な居心地を生み出します。
館内に一歩足を踏み入れれば、杉丸太の柱が林立し、まるで“まちの中の森”を巡るような緑陰の空間が広がります。
客室は、時間を忘れてゆったりと過ごせるよう細部まで計算されたスタイリッシュな設え。地元の恵みを手に取り、森の安らぎに包まれる──ここから、梼原町の魅力があなたの旅を豊かに彩ります。
梼原町の特産品販売と宿泊機能が一体となった“まちの駅 ゆすはら”は、訪れる誰もを梼原町の顔としてお迎えします。 東側を覆うのは、伝統的な茅葺屋根に学んだ隈研吾氏デザインの茅(かや)ファサード。風を通 ...
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
賛助会員165. 龍河洞博物館龍河洞の実物の石筍、世界の珍しい洞窟の写真、龍河洞の生い立ちのパノラマ、洞内から出土した土器、石器や、弥生時代の遺跡・出土品、洞内植物標本、地質関係資料などが展示されており、龍河洞のことをより深く知ることができます。33.603825 133.74507
龍河洞の実物の石筍、世界の珍しい洞窟の写真、龍河洞の生い立ちのパノラマ、洞内から出土した土器、石器や、弥生時代の遺跡・出土品、洞内植物標本、地質関係資料などが展示されており、龍河洞のことをより深く知...
#ミュージアム
-
166. 室戸世界ジオパークセンター室戸の変動する大地の風土に合わせた独特な文化や歴史、産業を紹介しており、室戸ユネスコ世界ジオパークの楽しみ方を知ることができる施設です。33.299206 134.18652
インフォメーションカウンターではグッズ販売や各種ツアーの案内も行っています。
室戸の変動する大地の風土に合わせた独特な文化や歴史、産業を紹介しており、室戸ユネスコ世界ジオパークの楽しみ方を知ることができる施設です。 インフォメーションカウンターではグッズ販売や各種ツアーの案内 ...
#ミュージアム
-
167. (休館中)海洋堂かっぱ館海洋堂かっぱ館には、「四万十川カッパ造形大賞」の全応募作品を収蔵。館内には常時500点以上のカッパ作品を展示しているほか、館外にもチェーンソーアートで作られたユニークなカッパが並びます。また、平成26年に2号館を増設し、体験コーナーなどが充実。側を流れる打井川では川遊びを楽しむことができます。四万十川の新たな河童伝説となる、創る楽しみと遊び心を詰め込んだ奇想天外なミュージアム。33.141922 133.05447
海洋堂かっぱ館には、「四万十川カッパ造形大賞」の全応募作品を収蔵。館内には常時500点以上のカッパ作品を展示しているほか、館外にもチェーンソーアートで作られたユニークなカッパが並びます。また、平成26年に ...
#ミュージアム
-
168. 室戸スカイライン山頂展望台展望台からは雄大な太平洋を望むことができます。壮大でロマンティックなロケーションです。室戸市に3箇所ある「恋人の聖地」のひとつ。33.26584 134.17838
展望台からは雄大な太平洋を望むことができます。壮大でロマンティックなロケーションです。室戸市に3箇所ある「恋人の聖地」のひとつ。
#景観(海)
-
169. 白木谷国際現代美術館白木谷の山里にある異色のミュージアム。県展無鑑査の洋画家で、中央画壇でも高い評価を得る武内光仁氏が愛情を注いで完成させた手造りの美術館で、屋外展示場へとつづく遊歩道は車いすでも通行でき、休憩所も完備。33.620663 133.59819
白木谷の山里にある異色のミュージアム。県展無鑑査の洋画家で、中央画壇でも高い評価を得る武内光仁氏が愛情を注いで完成させた手造りの美術館で、屋外展示場へとつづく遊歩道は車いすでも通行でき、休憩所も完備。
#ミュージアム
-
170. 高須の棚田NHK「龍馬伝」で岩崎弥太郎が五右衛門風呂の中で歌っていた民謡「土佐芝刈唄」発祥の地です。33.715458 133.53677
土佐芝刈りの里の看板の横にあるボタンを押すと、この民謡が流れます。
季節によって全く違う顔を見せる高須の棚田は一見の価値ありです。
展望台として木のベンチと机もあるので、ちょっとしたピクニックもいいですね♪
NHK「龍馬伝」で岩崎弥太郎が五右衛門風呂の中で歌っていた民謡「土佐芝刈唄」発祥の地です。 土佐芝刈りの里の看板の横にあるボタンを押すと、この民謡が流れます。 季節によって全く違う顔を見せる高須の棚田は ...
#景観(山)
-
171. 佐川町上町地区の町並み佐川町上町地区は、江戸時代土佐藩の筆頭家老深尾家の城下町で、主に商人が居を構えました。33.499126 133.28967
その佇まいは、現在にも受け継がれ、伝統的な商家住宅や酒蔵などが町並みを形成しています。
平成20年度には、歴史的風致維持向上計画の重点区域に認定されました。
佐川町上町地区は、江戸時代土佐藩の筆頭家老深尾家の城下町で、主に商人が居を構えました。 その佇まいは、現在にも受け継がれ、伝統的な商家住宅や酒蔵などが町並みを形成しています。 平成20年度には、歴史的風...
#町並み
-
172. 乱礁遊歩道室戸岬周辺2.6kmにわたり遊歩道がつけられています。アコウ、ハマユウなどの亜熱帯植物、岩礁に砕け散る荒波、空海ゆぁりの場所として悟りをひらいたとされる「御厨人窟」(みくろど)、行水の池、衆生の眼病を治したとされる目洗いの池、さらに悲しい伝説が残されているビシャゴ巌など、室戸の自然と歴史を遊歩道に沿って楽しんで下さい。33.245205 134.17636
室戸岬周辺2.6kmにわたり遊歩道がつけられています。アコウ、ハマユウなどの亜熱帯植物、岩礁に砕け散る荒波、空海ゆぁりの場所として悟りをひらいたとされる「御厨人窟」(みくろど)、行水の池、衆生の眼病を治し ...
#景観(海)
-
173. 道の駅 なぶら土佐佐賀幡多地域の東の玄関口に位置する道の駅、フードコート、農林水産直売所、情報発信スペースにより構成、フードコートでは、地元の食材を活かしたメニューや、カツオの藁焼きタタキの実演が見られるブースを設け、目で見て楽しみ食することができます。33.086967 133.10176
直売所でも地域でとれた新鮮な魚介類や野菜等を販売、日戻りカツオも提供しています。また、情報発信スペース等により黒潮町、幡多地域の観光イベント情報を発信しています。
「高知家の食卓」県民総選挙2016選抜店舗。
鰹の漁獲高日本一を誇る漁業が盛んな黒潮町。鰹を豪快に藁で焼いた鰹のタタキを豊富なメニューで贅沢に味わえる道の駅。この町のもう一つの特産品、太陽と風の力で製塩した天...
幡多地域の東の玄関口に位置する道の駅、フードコート、農林水産直売所、情報発信スペースにより構成、フードコートでは、地元の食材を活かしたメニューや、カツオの藁焼きタタキの実演が見られるブースを設け、目...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
174. 道の駅 四万十とおわ川と人の暮らしがもっとも近い四万十川中流域の「四万十町十和地区」の風景と自然素材にこだわった道の駅。33.224052 132.83568
産直ショップ「とおわ市場」には、おみやげ品やお酒はもちろん、旬の野菜や果物、お弁当なども揃っています。
敷地内の「四万十川ジップライン」は、対岸から道の駅まで四万十川の上を爽快に滑空できる人気のアクティビティです。
川と人の暮らしがもっとも近い四万十川中流域の「四万十町十和地区」の風景と自然素材にこだわった道の駅。 産直ショップ「とおわ市場」には、おみやげ品やお酒はもちろん、旬の野菜や果物、お弁当なども揃ってい ...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
175. 室戸岬灯台室戸岬のシンボルは、青い空と海のはざまに立つ白亜の灯台。明治32年以来、航海者たちの安全を照らす水先案内人として活躍しています。室戸岬の先端、標高151mにあり、レンズの大きさは直径2m60cmと日本最大級。毎年11月1日に近い日曜に行われる「灯台まつり」の日には、内部を一部一般開放しています。33.24693 134.17577
室戸岬のシンボルは、青い空と海のはざまに立つ白亜の灯台。明治32年以来、航海者たちの安全を照らす水先案内人として活躍しています。室戸岬の先端、標高151mにあり、レンズの大きさは直径2m60cmと日本最大級。毎年11 ...
#景観(海)
#建築
-
176. 若宮八幡宮永禄3年、長宗我部元親公は本山氏の長浜城攻略にあたり、当社の馬場先で一夜戦勝を祈願し初陣に臨んだところ、見事にこれを討ちやぶることができました。以来元親公は当社を出陣祈願の社と定め、社殿を出蜻蛉式建築に改めました。33.495026 133.54361
現在は、宗教法人若宮八幡宮として高知市港南地区の総氏神、また厄除け開運の神等として近郷近在の里人から広く信仰を集めています。
永禄3年、長宗我部元親公は本山氏の長浜城攻略にあたり、当社の馬場先で一夜戦勝を祈願し初陣に臨んだところ、見事にこれを討ちやぶることができました。以来元親公は当社を出陣祈願の社と定め、社殿を出蜻蛉式建 ...
#寺社
-
177. 高知よさこい情報交流館昭和29年に生まれた高知の「よさこい祭り」の歴史や魅力を紹介する『高知よさこい情報交流館』。33.5605 133.54462
外観はよさこい祭りには欠かせない地方車[じかたしゃ]をモチーフとしており、館内は歴史と知識のエリア「よさこいサークル」と進化と体験のエリア「よさこいスクエア」で構成。
迫力ある150インチの大型スクリーンで60年の歩みを上映する「よさこいシアター」、鳴子を手に衣装も身に着けて記念撮影ができる「よさこい体感コーナー」他、魅力いっぱいのコーナーを設けています。
昭和29年に生まれた高知の「よさこい祭り」の歴史や魅力を紹介する『高知よさこい情報交流館』。 外観はよさこい祭りには欠かせない地方車[じかたしゃ]をモチーフとしており、館内は歴史と知識のエリア「よさこい...
#ミュージアム
-
178. 土佐ぽかぽか温泉露天風呂やサウナはもちろん、岩盤浴やエステなど、女性に嬉しい設備も充実。営業は深夜までと、旅先の心強い味方。33.54106 133.51207
露天風呂やサウナはもちろん、岩盤浴やエステなど、女性に嬉しい設備も充実。営業は深夜までと、旅先の心強い味方。
#温泉
-
179. 観音岩柏島の手前、大堂海岸にそびえ立つ観音岩は、高さ約30メートルの花崗岩の巨岩です。断崖絶壁から海に向かって立つ姿が観音菩薩に似ていることから、この名が付けられました。32.766754 132.63998
昔から「沖を航行する船を照らした」という伝説が残る神聖な岩で、荒々しい海岸線に佇むその姿は、訪れる人に神秘的な印象を与えます。
県道沿いから大堂山展望台へ続く遊歩道に入ってすぐの場所から眺めることができ、気軽に立ち寄れるスポットです。また、町内のクルーズ体験では、海上からそびえ立つ観音岩の迫力ある姿を間近に楽しむことができます。陸と海、両方から異なる表情を見せる絶景ポイントです。
柏島の手前、大堂海岸にそびえ立つ観音岩は、高さ約30メートルの花崗岩の巨岩です。断崖絶壁から海に向かって立つ姿が観音菩薩に似ていることから、この名が付けられました。 昔から「沖を航行する船を照らした」と...
#景観(海)
-
180. 天然の湯 吾北むささび温泉鉄分豊富な含鉄ナトリウム塩化物泉が特徴の「吾北むささび温泉」は、あかね色の湯が肌のキメを整え、切り傷や神経痛、関節痛にも効果を発揮します。湯上がり後もしばらく身体がぽかぽかと温まり、その心地よさは地元の釣り人やトレッキング客にも愛されてきました。33.626816 133.30003
館内にはエアロバイクなどを備えたトレーニングルームも併設。仁淀川の支流・上八川川を一望する露天風呂では、透き通った清流を眼下に、心身ともにリフレッシュできます。自然の中で湯に浸かり、川のせせらぎと赤銅色の湯が織りなす贅沢なひとときをお楽しみください。
鉄分豊富な含鉄ナトリウム塩化物泉が特徴の「吾北むささび温泉」は、あかね色の湯が肌のキメを整え、切り傷や神経痛、関節痛にも効果を発揮します。湯上がり後もしばらく身体がぽかぽかと温まり、その心地よさは地...
#温泉
-
181. 道の駅 キラメッセ室戸 楽市新鮮野菜や果物、鮮魚など地元でとれた旬の海のもん、山のもんの、「安うて活きがえいもん」が毎日並ぶ直販所。33.30644 134.1102
皮が柔らかくホクホク感が特徴の「早掘りサツマイモ」や、糖度が高い「キラ坊スイカ」、サツマイモを使ったクリーム大福やお菓子が人気です。
加工場では、地元の素材を使ったオリジナルジェラートや、お弁当を販売しています。
目の前の海を眺めながら食べるジェラートは絶品です。
新鮮野菜や果物、鮮魚など地元でとれた旬の海のもん、山のもんの、「安うて活きがえいもん」が毎日並ぶ直販所。 皮が柔らかくホクホク感が特徴の「早掘りサツマイモ」や、糖度が高い「キラ坊スイカ」、サツマイモ ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
182. 星ヶ丘公園(ヒメノボタンの里)ヒメノボタンはノボタン科の多年草で、高知県の絶滅危惧種。公園を管理する地元の方々が毎年、種を採種して育てています。ヒメノボ タンは夏の終わりから秋にかけてが見頃です。その他にも、春にはエビネラン、夏はスイレンやオオオニバス、秋はオミナエシやリンドウ、冬はバイカオウレンなど一年中花が楽しめます。32.92311 132.84013
ヒメノボタンはノボタン科の多年草で、高知県の絶滅危惧種。公園を管理する地元の方々が毎年、種を採種して育てています。ヒメノボ タンは夏の終わりから秋にかけてが見頃です。その他にも、春にはエビネラン、夏 ...
#公園
#花・植物
-
183. 道の駅 やす地元の新鮮な野菜や果物、魚介類、グルメ、テイクアウト、お土産、観光情報までいろいろ揃っています。駐車場、トイレ、公衆電話は24時間利用可能です。33.534195 133.7537
地元の新鮮な野菜や果物、魚介類、グルメ、テイクアウト、お土産、観光情報までいろいろ揃っています。駐車場、トイレ、公衆電話は24時間利用可能です。
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
184. 菖蒲洞高知市土佐山の東端、鏡川上流の菖蒲にある鍾乳洞。33.63622 133.56409
東西の2室にわかれた洞内には、様々な鍾乳石や石筍が自然のまま残され、特に“帝王の間”と呼ばれる一角が変化に富んでいます。
洞窟性の動物・虫類も多数生息しています。
高知市土佐山の東端、鏡川上流の菖蒲にある鍾乳洞。 東西の2室にわかれた洞内には、様々な鍾乳石や石筍が自然のまま残され、特に“帝王の間”と呼ばれる一角が変化に富んでいます。 洞窟性の動物・虫類も多数生息 ...
#ジオスポット
#花・植物
-
185. 室戸岬亜熱帯性樹林及び海岸植物群落国の天然記念物として、58種類の植物が指定を受けています。33.250053 134.17717
代表的な植物:アコウ アオギリ ウバメガシ ナチシダ等
国の天然記念物として、58種類の植物が指定を受けています。 代表的な植物:アコウ アオギリ ウバメガシ ナチシダ等
#花・植物
-
186. 柏島ビーチ柏島にかかる2本の橋のうち、細い方の柏島橋を渡ってすぐ下に広がる遊泳可能エリアが、通称"柏島ビーチ"です。橋の上からでも海底が見えるほどの透明度で、海に入らなくても泳ぐ魚の姿を観察できる、高知屈指の絶景ビーチとして知られています。32.76703 132.6298
島と本土に挟まれた自然のままの地形を生かした海岸で、流れ込む川がないため驚くほど水が澄んでいます。この地形的な特徴が、柏島ビーチの類まれな透明度を生み出しています。
エメラルドグリーンの海では、浅瀬でもカラフルな熱帯魚やサンゴを間近で観察でき、シュノーケリングに最適。泳ぎが苦手な方でも、橋の上や浅瀬から海中世界を楽しめるのが魅力です。
柏島にかかる2本の橋のうち、細い方の柏島橋を渡ってすぐ下に広がる遊泳可能エリアが、通称"柏島ビーチ"です。橋の上からでも海底が見えるほどの透明度で、海に入らなくても泳ぐ魚の姿を観察できる、高知屈指の絶景...
#景観(海)
-
187. 長尾鶏センター(土佐のオナガドリ)南国市篠原を原産地とする、希少な土佐のオナガドリを見学できる施設。33.56731 133.63484
入館はガイド付きで、オナガドリと一緒に記念撮影もできます。
南国市篠原を原産地とする、希少な土佐のオナガドリを見学できる施設。 入館はガイド付きで、オナガドリと一緒に記念撮影もできます。
#ミュージアム
-
188. 大川筋武家屋敷資料館土佐藩の武士・手嶋家の住宅であった建物が、平成8年に高知市有形文化財に指定され復元。当時の武家の建築様式を残している城下では唯一の建造物です。33.565414 133.53528
書院造りの主屋と長屋門を忠実に復元しており、細部の金具や瓦なども必見です。
土佐藩の武士・手嶋家の住宅であった建物が、平成8年に高知市有形文化財に指定され復元。当時の武家の建築様式を残している城下では唯一の建造物です。 書院造りの主屋と長屋門を忠実に復元しており、細部の金具や...
#ミュージアム
#文化財・史跡
-
189. 琴平神社【南国市】32番札所、禅師峰寺[ぜんじぶじ]の東約2.5km、県道から少し北へ入った高台にある、海上守護・豊漁の神として崇敬される神社。33.53633 133.63737
祭神は大物主大神。天智天皇の時代(668~71)の創建と伝えられています。
32番札所、禅師峰寺[ぜんじぶじ]の東約2.5km、県道から少し北へ入った高台にある、海上守護・豊漁の神として崇敬される神社。 祭神は大物主大神。天智天皇の時代(668~71)の創建と伝えられています。
#寺社
-
190. 板垣退助像自由民権運動で知られる板垣退助は、1837(天保8)年に土佐藩中島町(現在の高知市本町)に生まれました。33.5608 133.53255
板垣らが設立した立志社を中心とした自由民権運動は全国に広がり、「自由は土佐の山間より出づ」と言われました。
明治15年4月6日、暴漢に刺された際に口にした「板垣死すとも自由は死せず」の言葉が有名で、自由民権運動はその後の憲法発布、国会開設へ繋がっていきました。
自由民権運動で知られる板垣退助は、1837(天保8)年に土佐藩中島町(現在の高知市本町)に生まれました。 板垣らが設立した立志社を中心とした自由民権運動は全国に広がり、「自由は土佐の山間より出づ」と言われ ...
#銅像・記念碑
-
191. 宿毛湾のだるま夕日11月初旬から2月中旬、黒潮の温かい水蒸気と冷たい大気の境目に光が反射し、夕日がだるまのように見える現象。ひと冬で20回ほどしか見ることができない貴重な風景。32.916977 132.6879
11月初旬から2月中旬、黒潮の温かい水蒸気と冷たい大気の境目に光が反射し、夕日がだるまのように見える現象。ひと冬で20回ほどしか見ることができない貴重な風景。
#景観(海)
-
192. 雲の上の温泉日本最後の清流四万十川の源流域に位置する源泉かけ流しの温泉。33.387726 132.94426
薬湯風呂は期間ごとに入れ替わるので、様々な薬湯が楽しめます。
同じ建物にプールもあります。
日本最後の清流四万十川の源流域に位置する源泉かけ流しの温泉。 薬湯風呂は期間ごとに入れ替わるので、様々な薬湯が楽しめます。 同じ建物にプールもあります。
#温泉
-
193. 坂本龍馬脱藩の道梼原町の中心部にある三嶋神社は、延喜19年(919年)に建立されたと伝えられています。この神社のすぐ横を「坂本龍馬脱藩の道」が通っており、龍馬は文久2年(1862年)3月下旬、沢村惣之丞と共にここから宮野々関、韮ヶ峠を経由して土佐藩を脱藩しました。33.3965 132.92786
梼原町の中心部にある三嶋神社は、延喜19年(919年)に建立されたと伝えられています。この神社のすぐ横を「坂本龍馬脱藩の道」が通っており、龍馬は文久2年(1862年)3月下旬、沢村惣之丞と共にここから宮野々関、韮 ...
#文化財・史跡
-
194. 高知市立自由民権記念館「自由は土佐の山間より」といわれるように、近代日本の歴史に大きな役割を果たした土佐の自由民権運動。33.543133 133.55026
日本最初の民主主義運動にかけた、土佐の先人たちの熱い思いが溢れています。
「自由は土佐の山間より」といわれるように、近代日本の歴史に大きな役割を果たした土佐の自由民権運動。 日本最初の民主主義運動にかけた、土佐の先人たちの熱い思いが溢れています。
#ミュージアム
-
195. 轟の滝落差82メートル、青く輝く3段の滝壷には玉織姫にまつわる平家伝説があり、桜、新緑、紅葉と四季を通じた景勝地として賑わいます。歌人・吉井勇も訪れた滝で、県指定文化財(名勝・天然記念物)でもあります。「日本の滝100選」にも選ばれた香美市のシンボルとも言うべき美しい滝です。33.712006 133.83412
紅葉のシーズンには茶屋の営業もあり、滝を彩る紅葉を見ながら手打ちそばやうどん、田舎ずしなどを味わうことができます。
落差82メートル、青く輝く3段の滝壷には玉織姫にまつわる平家伝説があり、桜、新緑、紅葉と四季を通じた景勝地として賑わいます。歌人・吉井勇も訪れた滝で、県指定文化財(名勝・天然記念物)でもあります。「日本...
#景観(川)
-
196. 掛川神社高知城の東側にある掛川神社は、江戸時代の1644年に土佐藩主・山内忠義が建てた神社です。城の鬼門(北東の方角)を守る役割があり、代々の藩主から大切にされてきました。33.578903 133.5577
この神社の最大の特徴は、境内に徳川家康を祀る東照神社が合祀されていること。そのため、高知県内で唯一、徳川家の家紋「三つ葉葵」を社殿や手水鉢に掲げることが許された特別な神社です。
また、歴代藩主が奉納した刀や銅鉾など、国の重要文化財3点を所蔵しています(現在は東京国立博物館に保管)。
土佐藩と徳川家のつながりを感じられる、歴史好きにおすすめのスポットです。
高知城の東側にある掛川神社は、江戸時代の1644年に土佐藩主・山内忠義が建てた神社です。城の鬼門(北東の方角)を守る役割があり、代々の藩主から大切にされてきました。 この神社の最大の特徴は、境内に徳川家康...
#寺社
-
197. 道の駅 美良布(韮生の里)「美良布地区集落活動センター」と、地元野菜などが購入でき、食事もできる「韮生の里美良布直販店」があります。33.648125 133.78255
周辺にはアンパンマンミュージアムのほか、アンパンマン遊具のある広場や、スポーツ施設「健康センターセレネ」、裏山は遊歩道散策や山野草観察ができる「香北の自然公園」になっており、子どもから大人まで楽しめます。
「美良布地区集落活動センター」と、地元野菜などが購入でき、食事もできる「韮生の里美良布直販店」があります。 周辺にはアンパンマンミュージアムのほか、アンパンマン遊具のある広場や、スポーツ施設「健康セ ...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
198. 白木谷の梅林早春を迎えると、約400本の紅梅・白梅がほころび、白木谷一帯は芳しい梅の香りに包まれます。(シーズン中は近隣道路に駐車可)33.621574 133.60413
早春を迎えると、約400本の紅梅・白梅がほころび、白木谷一帯は芳しい梅の香りに包まれます。(シーズン中は近隣道路に駐車可)
#花・植物
-
199. ひょうたん桜樹齢500年、標高21m、根回り6mのエドヒガン(ウバヒガン)の巨木。33.591236 133.16953
ツボミがひょうたんの形をしていることからいつしか呼ばれるようになりました。
土地の始祖大崎玄蕃がここに祇園神社を祀り、今もその祀があることから地元の人たちはこの桜を「祇園さま」と呼び大切に守り続けています。
樹齢500年、標高21m、根回り6mのエドヒガン(ウバヒガン)の巨木。 ツボミがひょうたんの形をしていることからいつしか呼ばれるようになりました。 土地の始祖大崎玄蕃がここに祇園神社を祀り、今もその祀があること...
#花・植物
-
200. 第36番札所 青龍寺弘法大師が恩師を偲んで開基したと伝えられています。本尊は波切不動明王で漁民の信仰が厚く、本堂から約500m南方(海側)には奥の院があり、森厳な行場として信仰を集めています。33.426 133.4521
弘法大師が、唐から日本に帰国する際、真言密教の奥義を授けてもらった青龍寺の恵果和尚の恩に報いるため、「約束の地に飛んで行け」という願いをこめ、東の空に独鈷を投げました。
帰国後、この地の老松に独鈷が刺さっているのを見つけ、建てたとされています。
弘法大師が恩師を偲んで開基したと伝えられています。本尊は波切不動明王で漁民の信仰が厚く、本堂から約500m南方(海側)には奥の院があり、森厳な行場として信仰を集めています。 弘法大師が、唐から日本に帰国す...
#寺社
-
201. 雨森芍薬観光農園1・5ヘクタールほどの敷地に約180種、5万本のシャクヤクが咲き誇ります。一重咲きや八重咲きなどさまざまな形、濃いピンク、淡いピンク、黄色のものなど色とりどりのシャクヤクを楽しむことができます。33.48523 133.48647
1・5ヘクタールほどの敷地に約180種、5万本のシャクヤクが咲き誇ります。一重咲きや八重咲きなどさまざまな形、濃いピンク、淡いピンク、黄色のものなど色とりどりのシャクヤクを楽しむことができます。
#花・植物
-
202. わんぱーくこうちアニマルランドライオン、トラ、チンパンジーなど世界の動物とオオイタサンショウウオ、ムササビ、タヌキなどの高知の動物たち約90種類を飼育。毎日開催の動物たちの「エサの時間」や日・祝日開催の「ワンポイントガイド」などイベント盛りだくさん。ふれあいコーナーではシバヤギやモルモット、世界最小のアヒル、コールダックがあなたを待っています。33.542133 133.5572
ライオン、トラ、チンパンジーなど世界の動物とオオイタサンショウウオ、ムササビ、タヌキなどの高知の動物たち約90種類を飼育。毎日開催の動物たちの「エサの時間」や日・祝日開催の「ワンポイントガイド」などイ ...
#アミューズメント
#水族館・動植物園
-
203. べふ峡剣山国定公園の物部川源流域にある渓谷で、四季を通して変化に富んだ風景が楽しめます。33.773525 134.03006
紅葉の名所として有名で、山一面が紅葉に染まる秋の美しさは格別。
周辺には整備された遊歩道が続いており散策が楽しめます。
剣山国定公園の物部川源流域にある渓谷で、四季を通して変化に富んだ風景が楽しめます。 紅葉の名所として有名で、山一面が紅葉に染まる秋の美しさは格別。 周辺には整備された遊歩道が続いており散策が楽しめま ...
#景観(山)
#景観(川)
#花・植物
-
204. 馬路村ふるさとセンターまかいちょって家馬路村の観光案内所であり、ゆず製品や魚梁瀬杉の木工芸品などを数多く販売しています。33.549717 134.04941
むらの案内人クラブの受付も行っており、事前予約していただくと村のガイド人が隅々まで案内してくれます。
また、2階には旧魚梁瀬森林鉄道の資料を展示しており、当時の写真やビデオとともに村の歴史を学ぶことができます。
馬路村の観光案内所であり、ゆず製品や魚梁瀬杉の木工芸品などを数多く販売しています。 むらの案内人クラブの受付も行っており、事前予約していただくと村のガイド人が隅々まで案内してくれます。 また、2階には ...
#観光案内所
#おみやげ
#市場・直売所
-
205. 土佐清水市立竜串貝類展示館 海のギャラリー国の有形文化財に登録され、日本建築学会およびDOCOMOMOjapanより後世に残したい文化遺産として建築百選にも認定された名建築。1級建築家・林雅子氏による設計。32.788567 132.86568
館内には、土佐清水市の洋画家・黒原和男氏が収集した学術的価値の高い貝を含む世界の珍しい貝を多数展示しています。
国の有形文化財に登録され、日本建築学会およびDOCOMOMOjapanより後世に残したい文化遺産として建築百選にも認定された名建築。1級建築家・林雅子氏による設計。 館内には、土佐清水市の洋画家・黒原和男氏が収集した...
#ミュージアム
-
206. 坂本龍馬首切り地蔵(発生寺)高知県須崎市の発生寺は、幕末に勤王の志厚い智隆和尚が住職を務めた寺院です。同寺は近隣の郷士や庄屋たちの密会の場所として使われ、幕末維新の志士たちが集った歴史を持ちます。33.39212 133.28941
坂本龍馬が2度目に訪れた際、志士たちと熱論を交わすうち、境内に安置されていた石仏地蔵を木刀で一刀のもとに打ち落としたという逸話が残されています。
その地蔵供養のため、龍馬は城山から松の木を取ってきて植えたと伝えられています。松が枯れるたびに有志が植え替えを続け、現在の松は4代目。初代から数えて160年以上、龍馬の供養の心が受け継がれています。
松のかたわらには、発生寺を志士たちの拠点とした智隆和尚の墓もあります。勤王の志を持ち、時代の ...
高知県須崎市の発生寺は、幕末に勤王の志厚い智隆和尚が住職を務めた寺院です。同寺は近隣の郷士や庄屋たちの密会の場所として使われ、幕末維新の志士たちが集った歴史を持ちます。 坂本龍馬が2度目に訪れた際、志 ...
#寺社
-
207. 宿毛リゾート椰子の湯全室オーシャンビューの宿泊施設。32.91601 132.68974
宿毛の海を眺めながら楽しめる温泉は日帰り入浴も可能。
宿毛のおいしい魚が楽しめるレストランもあります。
全室オーシャンビューの宿泊施設。 宿毛の海を眺めながら楽しめる温泉は日帰り入浴も可能。 宿毛のおいしい魚が楽しめるレストランもあります。
#温泉
#高知県産
#レストラン・食堂
#ホテル
-
208. 手結の夫婦岩全国各地にある夫婦岩の中でも、2つの岩がほぼ同じ大きさの「男女同権型」は珍しいと言われています。潮時、角度により風情が異なるので、浜に降りて、じっくり鑑賞してみてください。33.52088 133.75397
全国各地にある夫婦岩の中でも、2つの岩がほぼ同じ大きさの「男女同権型」は珍しいと言われています。潮時、角度により風情が異なるので、浜に降りて、じっくり鑑賞してみてください。
#景観(海)
-
209. 白岩岬公園沖の島の母島集落と弘瀬集落の中間に位置し、公園内の展望台からは視界270度の大パノラマと太平洋が眼下に広がり、星空の眺めは圧巻。32.72829 132.53894
キャンプ場としても整備されています。
沖の島の母島集落と弘瀬集落の中間に位置し、公園内の展望台からは視界270度の大パノラマと太平洋が眼下に広がり、星空の眺めは圧巻。 キャンプ場としても整備されています。
#景観(海)
#公園
#キャンプ
#キャンプ場
-
210. 手結港可動橋約6分かけてゆっくりと開閉する、長さ約32メートルの可動橋。この橋は、土佐藩家老の野中兼山によって作られた手結港の入口に架けられています。港に出入りする船の邪魔にならないように、殆ど橋は空高くそそり立っており、持ち上がった橋の下からの眺めは壮観。この橋を渡れるのは、1日のうち約7時間だけです。33.52848 133.75629
約6分かけてゆっくりと開閉する、長さ約32メートルの可動橋。この橋は、土佐藩家老の野中兼山によって作られた手結港の入口に架けられています。港に出入りする船の邪魔にならないように、殆ど橋は空高くそそり立っ...
#建築
#景観(海)
-
211. 山姥の滝滝の高さは30m。名前の由来は、滝の中間に祀られた山姥様によります。33.64503 133.50452
滝の高さは30m。名前の由来は、滝の中間に祀られた山姥様によります。
#景観(川)
-
212. モンベルアウトドアヴィレッジ本山 土佐れいほくの湯日帰り利用が可能な温泉施設で、広々とした大浴場・露天風呂・サウナがあり、吉野川でのラフティングやカヌーで疲れた体をゆっくりと癒すのに最適です。33.759007 133.59447
隣にはモンベル直営の複合施設もあり、ラフティングやカヌーといったウォーターアクティビティの拠点としても利用されています。施設内には宿泊施設・レストラン・モンベルショップも併設されています。
日帰り利用が可能な温泉施設で、広々とした大浴場・露天風呂・サウナがあり、吉野川でのラフティングやカヌーで疲れた体をゆっくりと癒すのに最適です。 隣にはモンベル直営の複合施設もあり、ラフティングやカヌ ...
#温泉
-
213. 道の駅 土佐さめうら“土佐あかうしの里”として知られる土佐町の国道439号沿いにある道の駅。嶺北エリアの観光案内拠点として、周辺の見どころやルート情報を提供しているほか、快適なドライブの休憩所としてトイレやシャワー設備も整っています。33.74259 133.54424
館内では、地元の特産品や民工芸品の展示・販売があり、旅のおみやげ探しにもぴったり。さらに3月から11月にかけては、名物「土佐あかうし」を楽しめる手ぶらでBBQテラスを営業中!気軽に立ち寄ってジューシーな牛串を味わうこともできます。
高原の風を感じながら、土佐の自然とグルメを満喫できるスポットです。
“土佐あかうしの里”として知られる土佐町の国道439号沿いにある道の駅。嶺北エリアの観光案内拠点として、周辺の見どころやルート情報を提供しているほか、快適なドライブの休憩所としてトイレやシャワー設備も整...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#おみやげ
-
214. 武市半平太道場跡武市半平太は嘉永2年(1849年)、21歳の時からこの場所に居住。安政元年(1854年)に道場を開き、多くの門人を養成しました。坂本龍馬もここをよく出入りしたといい、この道場がのちの土佐勤王党の母体となりました。33.560284 133.54788
武市半平太は嘉永2年(1849年)、21歳の時からこの場所に居住。安政元年(1854年)に道場を開き、多くの門人を養成しました。坂本龍馬もここをよく出入りしたといい、この道場がのちの土佐勤王党の母体となりました。
#文化財・史跡
-
215. 宇佐しおかぜ公園高知県土佐市の宇佐しおかぜ公園は、高知市内や高知龍馬空港から最も近いホエールウォッチングの出航地として知られる海浜公園です。入口では2頭の大きな親子クジラのモニュメントが訪れる人々を出迎えます。33.449852 133.45282
高知県内ではさまざまな場所からホエールウォッチングの船が出航していますが、宇佐しおかぜ公園は高知の玄関口から最も近く、気軽にクジラとの出会いを体験できるスポットです。夏には花火大会の会場としても賑わいます。
高知県土佐市の宇佐しおかぜ公園は、高知市内や高知龍馬空港から最も近いホエールウォッチングの出航地として知られる海浜公園です。入口では2頭の大きな親子クジラのモニュメントが訪れる人々を出迎えます。 高知...
#公園
#景観(海)
-
216. 佐川文庫庫舎(旧青山文庫)明治初年の鹿鳴館時代の雰囲気を現在に伝える県下最古の木造洋館。33.4988 133.28804
明治19年(1886)須崎警察署、佐川分署として上町西方の山側に建築。
昭和5年に現状のまま西町に移設され、川田文庫・青山文庫として活用されました。
昭和53年、佐川町総合文化センター敷地内に民具館として移築され、その後平成22年に当初の場所に移築されました。
敷地内に広井勇の銅像があります。
明治初年の鹿鳴館時代の雰囲気を現在に伝える県下最古の木造洋館。 明治19年(1886)須崎警察署、佐川分署として上町西方の山側に建築。 昭和5年に現状のまま西町に移設され、川田文庫・青山文庫として活用されました...
#建築
-
217. 牧野富太郎ふるさと館佐川町出身の植物学者・牧野富太郎博士の生家跡に建つ資料館。33.499588 133.28671
博士の遺品や直筆の手紙、原稿等が展示されています。
少年時代の博士の部屋をイメージした展示も行われています。
佐川町出身の植物学者・牧野富太郎博士の生家跡に建つ資料館。 博士の遺品や直筆の手紙、原稿等が展示されています。 少年時代の博士の部屋をイメージした展示も行われています。
#ミュージアム
#文化財・史跡
-
218. 土佐の高知のくだもの畑香南市香我美町の山北みかんは、甘くておいしいと評判のブランドです。33.583492 133.7623
毎年10月~12月中旬には、みかん狩りができ、食べ放題!
平坦な場所に低い木を植えていますので、車いすや小さなお子様もお楽しみいただけます。
4月下旬ごろには、藤の花が見ごろを迎えます。
香南市香我美町の山北みかんは、甘くておいしいと評判のブランドです。 毎年10月~12月中旬には、みかん狩りができ、食べ放題! 平坦な場所に低い木を植えていますので、車いすや小さなお子様もお楽しみいただけま ...
#花・植物
#食の体験
-
219. 久喜沈下橋高知県に現存する沈下橋の中で最も古く、昭和10年に架けられました。2004年3月に国の登録有形文化財に指定。仁淀川流域でも珍しいアーチ形の沈下橋です。33.568333 133.15987
高知県に現存する沈下橋の中で最も古く、昭和10年に架けられました。2004年3月に国の登録有形文化財に指定。仁淀川流域でも珍しいアーチ形の沈下橋です。
#景観(川)
#建築
-
220. 第24番札所 最御崎寺(東寺)807年(大同2年)嵯峨天皇の勅願により弘法大師空海が創建した。本尊は空海の自刻の虚空蔵菩薩(秘仏)寺宝に国指定重要文化財の「木造薬師如来坐像」、「木造月光菩薩立像」、「石造如意輪観音半跏像」等33.24993 134.17555
807年(大同2年)嵯峨天皇の勅願により弘法大師空海が創建した。本尊は空海の自刻の虚空蔵菩薩(秘仏)寺宝に国指定重要文化財の「木造薬師如来坐像」、「木造月光菩薩立像」、「石造如意輪観音半跏像」等
#寺社
-
221. 坂本家墓所山手町の丹中山にある坂本家の墓所。坂本龍馬の父・八平直足、母・幸、2番目の姉の栄、3番目の姉の乙女ら21人が眠っています。母である幸は、弘化2年(1846年)龍馬が12歳の時、父である八平直足は安政2年(1855年)龍馬が21歳の時に亡くなっているため、龍馬も一族とともにこの墓地への坂道を上って来たと思われます。33.560143 133.51456
山手町の丹中山にある坂本家の墓所。坂本龍馬の父・八平直足、母・幸、2番目の姉の栄、3番目の姉の乙女ら21人が眠っています。母である幸は、弘化2年(1846年)龍馬が12歳の時、父である八平直足は安政2年(1855年)龍 ...
#文化財・史跡
-
222. 第26番札所 金剛頂寺(西寺)四国八十八ヶ所霊場第26番札所の金剛頂寺は、大同二年(807年)に勅願寺として建立され、平安時代の代表する宗教家の空海が開祖となります。33.30718 134.12285
当時は密教道場として栄え、室戸三山において通称「西寺」と呼ばれ、またかって室戸が捕鯨地区であったことより鯨の供養塔があることから「鯨寺」ともいわれています。境内の正倉院様式の霊宝殿には金銅旅壇具を始め古来よりの文化財を数多く収蔵されています。
四国八十八ヶ所霊場第26番札所の金剛頂寺は、大同二年(807年)に勅願寺として建立され、平安時代の代表する宗教家の空海が開祖となります。 当時は密教道場として栄え、室戸三山において通称「西寺」と呼ばれ、またか...
#寺社
-
223. ゆすはら座ゆすはら座は、1948年に梼原町北町で誕生し、1995年に東町へ移築復元された木造劇場です。33.391655 132.9275
大正期の和洋折衷様式を生かしたモダンな外観に、花道付きの本格舞台、桟敷席が配された2階空間、そして美しい木目を見せる天井と、高知県下で唯一の木造芝居小屋として、これまでに歌舞伎から映画上映まで多彩な演目を演出してきました。
住民の娯楽殿堂「梼原公民館」として親しまれ、今も昔も、心を揺さぶる舞台の息吹が息づいています。
ゆすはら座は、1948年に梼原町北町で誕生し、1995年に東町へ移築復元された木造劇場です。 大正期の和洋折衷様式を生かしたモダンな外観に、花道付きの本格舞台、桟敷席が配された2階空間、そして美しい木目を見せ ...
#建築
#文化財・史跡
-
224. 瑞山記念館「瑞山記念館」は、幕末の志士・武市半平太(瑞山)の生涯と土佐勤王党の活動をわかりやすく紹介する資料館。33.53777 133.60373
入口の協力金箱に志を込めて入館すると、時代背景や半平太の人となりを彩る豊富な展示パネルと、ここでしか見られない半平太筆の美人画掛軸(複製)に出会えます。
年譜コーナーでは土佐藩・日本・世界の動きを同期して学び、勤王党志士たちの出身地分布図から当時の地域性や身分構造も理解可能。歴史好きはもちろん、幕末マニアも満足度◎の穴場スポットです。
「瑞山記念館」は、幕末の志士・武市半平太(瑞山)の生涯と土佐勤王党の活動をわかりやすく紹介する資料館。 入口の協力金箱に志を込めて入館すると、時代背景や半平太の人となりを彩る豊富な展示パネルと、ここ ...
#ミュージアム
-
賛助会員225. 道の駅 かわうその里すさき2Fレストランでは高知県唯一のご当地ラーメン「鍋焼きラーメン」や地元の高級養殖魚「カンパチ」を使った丼ぶりなどを提供しています。33.38766 133.27467
1Fは土産売り場となっており、高知の銘菓や地酒など豊富に取り揃えております。
また、カツオのタタキを実演販売する魚屋などもあります。
2Fレストランでは高知県唯一のご当地ラーメン「鍋焼きラーメン」や地元の高級養殖魚「カンパチ」を使った丼ぶりなどを提供しています。 1Fは土産売り場となっており、高知の銘菓や地酒など豊富に取り揃えておりま...
#道の駅・休憩所
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
226. 柏島白浜柏島の白い砂浜が美しい「柏島白浜」は、エメラルドグリーンの海と抜群の透明度を誇る天然ビーチです。夏には多くの海水浴客やキャンプ客で賑わい、家族連れにも人気の海岸となっています。32.76776 132.63245
柏島ならではの驚異的な透明度で、浅瀬でもカラフルな熱帯魚やサンゴを観察できます。シュノーケリング初心者でも泳げるスポットです。
柏島の白い砂浜が美しい「柏島白浜」は、エメラルドグリーンの海と抜群の透明度を誇る天然ビーチです。夏には多くの海水浴客やキャンプ客で賑わい、家族連れにも人気の海岸となっています。 柏島ならではの驚異的 ...
#景観(海)
-
227. 高知龍馬空港総合案内所空の玄関、高知龍馬空港1階到着ロビーにある案内所です。33.547333 133.67427
県外、県内、外国のお客様からの観光案内、落とし物、各地へのアクセス情報、館内施設等の様々なお問合せに対応しています。
また、龍馬パスポート(青パスポートのみ)の交付や、牧野植物園、竹林寺、桂浜などの主要な観光地を巡る「MY遊バス」の乗車券販売もしています。
各観光施設のパンフレット、イベント情報等も取り揃えています。
空の玄関、高知龍馬空港1階到着ロビーにある案内所です。 県外、県内、外国のお客様からの観光案内、落とし物、各地へのアクセス情報、館内施設等の様々なお問合せに対応しています。 また、龍馬パスポート(青 ...
#観光案内所
-
228. 高知県立甫喜ヶ峰森林公園高知県内唯一の森林公園で、広さは102ha。頂上からは太平洋を一望できます。季節ごとに、山野草などの草花の観察、山歩き、キャンプなどを楽しむことができます。33.672676 133.6877
高知県内唯一の森林公園で、広さは102ha。頂上からは太平洋を一望できます。季節ごとに、山野草などの草花の観察、山歩き、キャンプなどを楽しむことができます。
#公園
#花・植物
#キャンプ場
#キャンプ
-
229. 香美市いんふぉめーしょん『香美市いんふぉめーしょん』では香美市の観光情報はもちろん、お隣の南国市や香南市といった物部川エリアや高知市内など、高知県の楽しい情報が盛りだくさん!33.60703 133.6849
パンフレットやイベント情報もたくさんご用意しております。
『香美市いんふぉめーしょん』では香美市の観光情報はもちろん、お隣の南国市や香南市といった物部川エリアや高知市内など、高知県の楽しい情報が盛りだくさん! パンフレットやイベント情報もたくさんご用意して ...
#観光案内所
-
230. 道の駅 東洋町観光客や地元の住民でにぎわう直売所です。33.54317 134.2951
地元の新鮮な鮮魚や野菜を購入したり、レストランでの食事もできます。
阿佐海岸鉄道のDMVや徳島南部バス、高知東部交通の乗り場も隣接しています。
高知の東の入り口として、高知県東部をメインに様々な自治体のパンフレットを用意しています。
観光客や地元の住民でにぎわう直売所です。 地元の新鮮な鮮魚や野菜を購入したり、レストランでの食事もできます。 阿佐海岸鉄道のDMVや徳島南部バス、高知東部交通の乗り場も隣接しています。 高知の東の入り口 ...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
賛助会員231. 中岡慎太郎館坂本龍馬と共に薩長同盟締結に尽力し、維新の礎を築いた北川村出身の中岡慎太郎。33.456837 134.05646
彼の生涯をパネルやドラマ仕立ての映像等で知ることができる歴史資料館です。
慎太郎ゆかりの品々など、貴重な史料も展示。記念撮影用の慎太郎裃も人気です。
坂本龍馬と共に薩長同盟締結に尽力し、維新の礎を築いた北川村出身の中岡慎太郎。 彼の生涯をパネルやドラマ仕立ての映像等で知ることができる歴史資料館です。 慎太郎ゆかりの品々など、貴重な史料も展示。記念 ...
#ミュージアム
-
232. 開成門慶応2年(1866年)、土佐藩が殖産興業・富国強兵の目的で開成館を現在の高知市九反田に創設。その後、明治3年には寅賓館と改称され、外来客の接待をするために使われました。翌年には維新三傑の西郷隆盛・木戸孝允・大久保利通を迎え、薩長土首脳会議が行われています。その表門は三度の移築を経てなお昔のままに保存されています。昭和32年、県の有形文化財に指定。33.563667 133.5254
慶応2年(1866年)、土佐藩が殖産興業・富国強兵の目的で開成館を現在の高知市九反田に創設。その後、明治3年には寅賓館と改称され、外来客の接待をするために使われました。翌年には維新三傑の西郷隆盛・木戸孝允・...
#文化財・史跡
-
233. 夫婦岩(室戸市)国道55号線沿い、室戸岬町と佐喜浜町の境にある鹿岡鼻にあり、海中からまっすぐに立つ二つの岩柱。夫婦岩は全国各地にありますが、室戸の夫婦岩は規模が大きいです。長年に及ぶ風と波の浸食によりできた紋様が美しいです。現在は危険防止のため、近くへは立入禁止になっています。33.353165 134.2028
国道55号線沿い、室戸岬町と佐喜浜町の境にある鹿岡鼻にあり、海中からまっすぐに立つ二つの岩柱。夫婦岩は全国各地にありますが、室戸の夫婦岩は規模が大きいです。長年に及ぶ風と波の浸食によりできた紋様が美し ...
#景観(海)
-
234. 山嶽社明治時代にこの地域の自由民権運動の拠点だった場所。板垣退助の秘書、和田三郎の生家でもあります。33.63833 133.55573
自由民権運動の影響を受けた医師・和田波冶・千秋父子が自宅を提供し寺子屋をつくったのが始まりで、後に門下生の高橋簡吉が遺志を継ぎ、民権結社山嶽社を結成しました。
現在の建物は平成3年に復元されたもので、平成16年に高知市史跡に指定されました。
明治時代にこの地域の自由民権運動の拠点だった場所。板垣退助の秘書、和田三郎の生家でもあります。 自由民権運動の影響を受けた医師・和田波冶・千秋父子が自宅を提供し寺子屋をつくったのが始まりで、後に門下 ...
#文化財・史跡
-
235. 第34番札所 種間寺577年敏達天皇の時代、百済から招かれた仏師たちがその帰途に土佐沖で暴風雨に遭ってこの地に流れ着き、会場の安全を祈願して薬師如来を刻み祀ったことに始まると言われます。33.491756 133.4876
その後、弘法大師が訪れてお堂を整え、唐から持ち帰った五穀(米、麦、粟、きび、豆)の種を蒔いたことから種間寺という名がついたと伝えられています。
577年敏達天皇の時代、百済から招かれた仏師たちがその帰途に土佐沖で暴風雨に遭ってこの地に流れ着き、会場の安全を祈願して薬師如来を刻み祀ったことに始まると言われます。 その後、弘法大師が訪れてお堂を整え ...
#寺社
-
236. 月光桜大月町役場にほど近い長沢地区の丘陵に立つ1本の桜、「月光桜」。植物学者牧野富太郎博士が生前に研究し「アシズリザクラ」という名前で新種として登録しようとしていたといわれ、「満月に満開になる」という言い伝えのある幻の山桜です。その花は開花すると花びら全体が白く、輝くような光沢を発するのが特徴。花の見ごろは3月下旬から4月上旬で、花の見ごろの時期にはライトアップされ「月光桜」のイメージ通りの幻想的な姿を目にすることができます。また、その時期には各種イベントを開催しており、お花見の気分を盛り上げてくれます。32.839382 132.6995
花の美しさはもちろん、幹径が1mもある巨樹から四方に広がる枝ぶりからなる見事な樹形は見るものを引き...
大月町役場にほど近い長沢地区の丘陵に立つ1本の桜、「月光桜」。植物学者牧野富太郎博士が生前に研究し「アシズリザクラ」という名前で新種として登録しようとしていたといわれ、「満月に満開になる」という言い ...
#花・植物
-
237. 武市瑞山(半平太)殉節地・南会所跡山内容堂は吉田東洋の暗殺を勤王党の仕業とにらみ、文久三年(1863年)9月、土佐勤王党首領武市半平太らを南会所と山田町の獄舎に入牢させました。長い取り調べの中で田内衛吉の服毒自殺、島村衛吉の拷問死などがあり、半平太は慶応元年(1865年)5月11日に南会所で切腹しました。33.559853 133.5355
山内容堂は吉田東洋の暗殺を勤王党の仕業とにらみ、文久三年(1863年)9月、土佐勤王党首領武市半平太らを南会所と山田町の獄舎に入牢させました。長い取り調べの中で田内衛吉の服毒自殺、島村衛吉の拷問死などがあ ...
#文化財・史跡
-
238. 道の駅 なかとさ黒潮あらう太平洋と清流四万十川源流域を併せ持つ中土佐町。33.322186 133.23534
高知の魅力がギュッと詰まった町には豊かな自然がもたらす魅力あふれる食材がいっぱい。
そんな町に平成29年7月に誕生した「道の駅なかとさ」には、地元の農家で大切に育てられた旬の野菜やお米、目の前の海で漁師が獲った新鮮な海の幸をはじめ、ここでしか味わうことのできない海山川のグルメが勢ぞろいしています。
直売所にレストラン、パン屋、軽食コーナーからお土産まで、漁師町のおいしい魅力がたっぷり詰まった自慢の道の駅にぜひお立ち寄りください。
黒潮あらう太平洋と清流四万十川源流域を併せ持つ中土佐町。 高知の魅力がギュッと詰まった町には豊かな自然がもたらす魅力あふれる食材がいっぱい。 そんな町に平成29年7月に誕生した「道の駅なかとさ」には、地 ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
239. 道の駅 四万十大正周辺の観光情報を発信する「情報館」や、地場産品やアユ、うなぎ、山菜を使用した食のメニューを提供する物産販売施設「であいの里」があります。33.182743 132.97125
施設の裏には四万十川が流れ、眺めることができます。
周辺の観光情報を発信する「情報館」や、地場産品やアユ、うなぎ、山菜を使用した食のメニューを提供する物産販売施設「であいの里」があります。 施設の裏には四万十川が流れ、眺めることができます。
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
240. 第33番札所 雪蹊寺臨済宗の寺。平安初期、弘法大師空海の開創の折は、真言宗の寺で高福寺と称したが、長宗我部元親が臨済宗に改宗しました。33.50083 133.5431
雪蹊は、元親の法号。
運慶作本尊の薬師如来及び両脇侍像と、寺宝の十二神将像、毘沙門天及び脇侍像は国の重要文化財。特に毘沙門天3尊は運慶の長男の作として著名です。
臨済宗の寺。平安初期、弘法大師空海の開創の折は、真言宗の寺で高福寺と称したが、長宗我部元親が臨済宗に改宗しました。 雪蹊は、元親の法号。 運慶作本尊の薬師如来及び両脇侍像と、寺宝の十二神将像、毘沙門天...
#寺社
-
241. 大引割・小引割天狗の森と鳥形山のほぼ中間点にあり、白木谷層群(古生代二畳記)に属する赤色及び赤褐色のチャート(硅石)にできた2本の亀裂。長さ60~70m、深さ20~40mにも達するその亀裂は、有史以前の大地震によってできたという説が有力で、このような亀裂が埋没せずに残っているのは学術上貴重なものとして、国の天然記念物に指定されています。33.47602 133.04527
天狗の森と鳥形山のほぼ中間点にあり、白木谷層群(古生代二畳記)に属する赤色及び赤褐色のチャート(硅石)にできた2本の亀裂。長さ60~70m、深さ20~40mにも達するその亀裂は、有史以前の大地震によ ...
#ジオスポット
-
242. 大堂海岸展望台高知県大月町の大堂海岸一帯は、足摺宇和海国立公園に指定された自然豊かなエリアです。船が宙に浮いて見える透明度抜群の海だけでなく、周辺には魅力的な観光スポットが点在し、海岸沿いの遊歩道でハイキングも楽しめる、一日中満喫できる観光地となっています。32.774113 132.64441
大堂山展望台からは、太平洋の大パノラマと柏島の美しい海岸線を一望できます。エメラルドグリーンの海に浮かぶ船の幻想的な光景は、写真愛好家にも人気の絶景ポイントです。
観音岩は、自然が造り出した神秘的な奇岩で、長い年月をかけて波に削られた独特の造形美が魅力です。
海岸沿いに整備された遊歩道では、潮風を感じながら気軽にハイキングを楽しめます。透き通る海を眺めな...
高知県大月町の大堂海岸一帯は、足摺宇和海国立公園に指定された自然豊かなエリアです。船が宙に浮いて見える透明度抜群の海だけでなく、周辺には魅力的な観光スポットが点在し、海岸沿いの遊歩道でハイキングも楽...
#景観(海)
-
243. 宇佐土曜市(土佐市)33.450485 133.44295
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
244. 朝倉神社JR朝倉駅から北西に徒歩約15分、赤鬼山のふもとに佇む朝倉神社は、古代の『土佐国風土記』にも記される由緒ある神社。平安時代の法典『延喜式』にもその名が見え、長く土佐の人々に親しまれてきました。33.55351 133.48166
現在の本殿は、江戸時代初期・1657年に土佐藩2代藩主 山内忠義によって再建されたもの。正面の唐破風(からはふ)や屋根の千木・勝男木(かつおぎ)など、格式高い神社建築の意匠を今に伝えています。
外観からは当時の建築様式や装飾の美しさを垣間見ることができます。境内は静かで落ち着いた雰囲気に包まれ、歴史に思いを馳せながらゆっくり散策できます。
JR朝倉駅から北西に徒歩約15分、赤鬼山のふもとに佇む朝倉神社は、古代の『土佐国風土記』にも記される由緒ある神社。平安時代の法典『延喜式』にもその名が見え、長く土佐の人々に親しまれてきました。 現在の本 ...
#寺社
-
245. 高知公園山内一豊(やまうちかつとよ)が築城した高知城を中心に形成された歴史公園。33.561287 133.5314
城跡全域が国の史跡で、山内一豊や妻千代、板垣退助の像なども立っています。
季節を花木で感じられ、いつもどこかで鳥がさえずる、街中のオアシス。高知市街を一望できます。
[梅のシーズン] 2月中旬~3月初旬
[桜のシーズン] 3月下旬~4月上旬
[紅葉のシーズン] 11月下旬~12月中旬
山内一豊(やまうちかつとよ)が築城した高知城を中心に形成された歴史公園。 城跡全域が国の史跡で、山内一豊や妻千代、板垣退助の像なども立っています。 季節を花木で感じられ、いつもどこかで鳥がさえずる、 ...
#花・植物
#公園
-
246. 安徳天皇陵墓参考地源平の戦いに敗れ、従臣たちと四国の各地を潜幸(せんこう)した幼帝・安徳天皇。最終的に越知町横倉山に辿り着き、同地で暮らすも23歳で崩御されたと伝えられています。33.535915 133.20148
全国にある陵墓の参考地として宮内庁から指定されている5ヶ所の内の一つで、安徳天皇が従臣たちと蹴鞠をして遊ばれた所とされ、“鞠ケ奈呂陵墓参考地”とも言われています。
横倉山の奥で静かに佇む陵墓参考地は、どこか厳かな雰囲気。111段の広い立派な石段を上り詰めた所にあり、御影石の二重の玉垣によって取り囲まれています。
また、西隣の平坦地は安徳天皇が乗馬の練習をされたと伝えられ、“御馬場跡”と呼ばれています。
源平の戦いに敗れ、従臣たちと四国の各地を潜幸(せんこう)した幼帝・安徳天皇。最終的に越知町横倉山に辿り着き、同地で暮らすも23歳で崩御されたと伝えられています。 全国にある陵墓の参考地として宮内庁から ...
#文化財・史跡
-
247. 古今集の庭・紀貫之邸跡土佐日記の作者、古今和歌集の撰者として知られる紀貫之が、国司として赴任したことにちなんだ場所。古今和歌集の和歌32首にちなんだ草木と曲水の流れが配され、平安朝を思わせます。紀貫之邸跡も隣接しています。33.603443 133.6471
土佐日記の作者、古今和歌集の撰者として知られる紀貫之が、国司として赴任したことにちなんだ場所。古今和歌集の和歌32首にちなんだ草木と曲水の流れが配され、平安朝を思わせます。紀貫之邸跡も隣接しています。
#文化財・史跡
-
248. ゆういんぐ四万十「ゆういんぐ四万十」は、四万十川流域の厳選食材と地元産品を一堂に集めた体験型マーケット&レストラン。店内レストランでは、香り高い仁井田米ご飯に、大麦・小麦飼料で育てられたきめ細かな肉質の四万十ポークをたっぷりかけ放題の定食としてご提供。33.22959 133.14719
朝は7:00~10:00の朝食バイキングで、地元野菜を使った惣菜とふっくら炊き上げた仁井田米おにぎりは絶品。
売り場スペースでは、無農薬・有機肥料の仁井田米をはじめ、さつまいも・人参・玉ねぎ・季節の果実など四万十町産の新鮮野菜&果物を毎日入荷。カステラやミレービスケット、芋けんぴなど銘菓・地酒のほか、工場直送の宗田節や山型食パンまで、多彩なお土産選びも楽しめます。四万十...
「ゆういんぐ四万十」は、四万十川流域の厳選食材と地元産品を一堂に集めた体験型マーケット&レストラン。店内レストランでは、香り高い仁井田米ご飯に、大麦・小麦飼料で育てられたきめ細かな肉質の四万十ポーク...
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
#レストラン・食堂
#道の駅・休憩所
-
249. 龍馬郵便局郵便局入口前には大きな龍馬像が立ち、ポストの上には龍馬と一緒に「地球」と「桂浜の波」の像がのっています。33.556187 133.52596
局内には龍馬関連の資料が展示され、この郵便局から郵便物を発送すると、生誕の地と龍馬の図柄が入った消印を押してもらえます。
郵便局入口前には大きな龍馬像が立ち、ポストの上には龍馬と一緒に「地球」と「桂浜の波」の像がのっています。 局内には龍馬関連の資料が展示され、この郵便局から郵便物を発送すると、生誕の地と龍馬の図柄が入 ...
#銅像・記念碑
-
250. 龍王の滝日本の滝百選。33.76726 133.76129
龍王の滝は、梶ヶ森の七合目にあり滝壷近くに龍神さまが祀られていることから命名されました。
この滝の落差は20m、水量豊富でアメゴや山椒魚などが生息し、名僧空海が若年の頃修業したところ。梶ヶ森への登山客の休息場所。
日本の滝百選。 龍王の滝は、梶ヶ森の七合目にあり滝壷近くに龍神さまが祀られていることから命名されました。 この滝の落差は20m、水量豊富でアメゴや山椒魚などが生息し、名僧空海が若年の頃修業したところ。梶ヶ ...
#景観(川)
-
251. 入野海岸・入野松原海水浴やサーフィンも楽しめる海岸。33.027176 133.0185
砂浜美術館として、Tシャツアート展なども開催されます。
月の名所でもあり、月見ヶ浜とも呼ばれます。
条件がそろえば、「水鏡」という現象が起き、高知の「ウユニ塩湖」と呼ばれる景色が見られます。
入野松原は、入野海岸の背後の松林(クロマツ林)で、長宗我部時代の防風の植林に始まるといいます。
海水浴やサーフィンも楽しめる海岸。 砂浜美術館として、Tシャツアート展なども開催されます。 月の名所でもあり、月見ヶ浜とも呼ばれます。 条件がそろえば、「水鏡」という現象が起き、高知の「ウユニ塩湖」と ...
#景観(海)
#定番
-
252. 高知県立歴史民俗資料館高知県の歴史系総合博物館です。33.596066 133.62349
2階には長宗我部展示室を設け、長宗我部氏関連資料を展示。常設の総合展示室も資料を入れ替えて土佐の歴史・文化・くらしを紹介しています。
館の立地する岡豊山は戦国時代の長宗我部氏の居城跡「国史跡岡豊城跡」で、一角に山村民家を移築している「岡豊山歴史公園」です。
散策しながら城跡や民家の学習、また桜をはじめ四季折々の草花を楽しむこともできます。
高知県の歴史系総合博物館です。 2階には長宗我部展示室を設け、長宗我部氏関連資料を展示。常設の総合展示室も資料を入れ替えて土佐の歴史・文化・くらしを紹介しています。 館の立地する岡豊山は戦国時代の長 ...
#ミュージアム
-
253. カルストテラスまるで白い羊の群のようなカレンフェルト、草原の中にできた窪地ドリーネなど独特の地形を持つ四国カルスト。この形成の仕組みや、天狗高原や周辺の山々、そこに咲く高山植物・花木や生き物などについての展示が行われています。33.476803 133.00351
ソフトクリームが食べられるカフェや電動自転車の貸し出しもあります。
良く晴れた日には、テラスから室戸岬や足摺半島を見ることもできます。
まるで白い羊の群のようなカレンフェルト、草原の中にできた窪地ドリーネなど独特の地形を持つ四国カルスト。この形成の仕組みや、天狗高原や周辺の山々、そこに咲く高山植物・花木や生き物などについての展示が行...
#ミュージアム
-
254. 道の駅 633美の里仁淀ブルーで有名な「にこ淵」に最も近い場所にある道の駅。33.64372 133.32837
国道194号と、国道439号が交わる位置にあるため二つの数字を足した「633」が名前の由来となっています。
食堂やお菓子屋があるので休憩には最適。地元の農産物の販売も行われています。
仁淀ブルーで有名な「にこ淵」に最も近い場所にある道の駅。 国道194号と、国道439号が交わる位置にあるため二つの数字を足した「633」が名前の由来となっています。 食堂やお菓子屋があるので休憩には最適。地元の農 ...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
255. 弁天座香南市赤岡町にある芝居小屋。ここでは、絵師・金蔵の芝居絵屏風の世界が「絵金歌舞伎」として演じられています。明治期に住民が建て1970年に閉館していたものを、文化活動拠点として2007年に復活。花道もあり、枡席や桟敷席などを構えた本格的な造りとなっています。33.541847 133.72478
香南市赤岡町にある芝居小屋。ここでは、絵師・金蔵の芝居絵屏風の世界が「絵金歌舞伎」として演じられています。明治期に住民が建て1970年に閉館していたものを、文化活動拠点として2007年に復活。花道もあり、枡席 ...
#建築
-
256. 道の駅大杉大歩危・小歩危に向かう国道32号線沿い、日本一の大スギと美空ひばり遺影碑・歌碑への登り口に道の駅「大杉」があります。33.750896 133.66336
町内外の観光情報の発信地であり、大豊名物「立川(たぢかわ)そば」の他、特産物である「碁石茶」「柚子」加工品、「銀不老豆」を使用した銀不老ロールや銀不老大福等各種お土産も販売しております。
大歩危・小歩危に向かう国道32号線沿い、日本一の大スギと美空ひばり遺影碑・歌碑への登り口に道の駅「大杉」があります。 町内外の観光情報の発信地であり、大豊名物「立川(たぢかわ)そば」の他、特産物である「...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
257. 第30番札所 善楽寺高知市内に入り最初の札所となる善楽寺は、階段も少なく高知ICから近いということもあり、お遍路さんのみならず多くの方々がお参りみえます。33.59194 133.57745
善楽寺は1637年土佐一宮神社の別当寺として建立されましたが、明治の廃仏毀釈により廃寺。昭和4年に念願の復興を果たしました。
新風薫る境内には本尊阿弥陀如来をはじめ、首から上にご利益がある梅見地蔵や子安地蔵が、昔と変らずお参りの方々を見護っておられます。
高知市内に入り最初の札所となる善楽寺は、階段も少なく高知ICから近いということもあり、お遍路さんのみならず多くの方々がお参りみえます。 善楽寺は1637年土佐一宮神社の別当寺として建立されましたが、明治の廃 ...
#寺社
-
258. すさきまちかどギャラリー 旧三浦邸高知県須崎市の古商家・三浦家の元邸宅を利用した市民ギャラリー。33.389927 133.28955
観光案内所と地域の憩いの場を兼ねた総合交流施設です(平成22年2月12日から運営)。
大正時代中期に建てられた、高知を代表する商家建築と評される貴重な建造物を、無料で見学することができます。
周辺地域の案内のほか、市街地散策に便利なミニサイクルの貸出し、まち歩きガイドツアー、須崎の伝統文化「わら馬」づくり体験プログラムを実施しています。(いずれも要予約)
高知県須崎市の古商家・三浦家の元邸宅を利用した市民ギャラリー。 観光案内所と地域の憩いの場を兼ねた総合交流施設です(平成22年2月12日から運営)。 大正時代中期に建てられた、高知を代表する商家建築と評される ...
#文化財・史跡
#観光案内所
-
賛助会員259. 山内神社高知城下に鎮座する山内神社は、土佐藩を築いた山内一豊公と千代夫人、そして歴代藩主十六代を祀る由緒ある神社です。江戸時代から現代まで200年以上の歴史を持ち、幕末の英雄・山内容堂公ゆかりの地としても知られています。33.555546 133.53183
1806年、高知城内に創建された藤並神社を起源とし、明治維新の功績を顕彰するため昭和9年に別格官幣社山内神社として新たに創建されました。戦後の再建を経て、昭和45年に藤並神社と合併し、現在の姿となっています。
境内には山内容堂公の銅像が建立されており、土佐藩の栄光と明治維新への貢献を今に伝えています。高知城観光と合わせて訪れたい、歴史ファン必見のパワースポットです。
高知城下に鎮座する山内神社は、土佐藩を築いた山内一豊公と千代夫人、そして歴代藩主十六代を祀る由緒ある神社です。江戸時代から現代まで200年以上の歴史を持ち、幕末の英雄・山内容堂公ゆかりの地としても知られ...
#寺社
-
260. 中岡慎太郎生家坂本龍馬とともに京都近江屋で暗殺された慎太郎は、大庄屋の子として生まれ、のち間崎滄浪の塾で学び、土佐勤王党に参加。文久3年(1863年)に脱藩して討幕運動に奔走。龍馬とともに薩長連合を実現させたり、陸援隊を組織したりするなどの活躍をしました。33.45719 134.05629
昭和42年に発見された中岡家の見取り図をもとにして生家が復元されており、近くの松林寺境内内に遺髪が埋葬されているほか、すぐそばには北川村立中岡慎太郎館もあります。
坂本龍馬とともに京都近江屋で暗殺された慎太郎は、大庄屋の子として生まれ、のち間崎滄浪の塾で学び、土佐勤王党に参加。文久3年(1863年)に脱藩して討幕運動に奔走。龍馬とともに薩長連合を実現させたり、陸援隊 ...
#文化財・史跡
-
261. 旧浜口家住宅江戸中期より佐川で酒造業を営んだ浜口家の住宅。平成25年に改築され、観光客を迎える施設として整備されました。カフェも併設、お土産販売や休憩所としても利用できます。33.498848 133.28827
江戸中期より佐川で酒造業を営んだ浜口家の住宅。平成25年に改築され、観光客を迎える施設として整備されました。カフェも併設、お土産販売や休憩所としても利用できます。
#建築
#道の駅・休憩所
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
262. 大岐海岸中村から土佐清水に向かう国道321号線沿いにあり、真っ白な砂浜と緑の林が1.6kmに渡りゆるやかな曲線を描く美しい海岸。最近はサーフポイントとしての人気も高く、県内外から多くのサーファーが訪れます。32.820847 132.94844
中村から土佐清水に向かう国道321号線沿いにあり、真っ白な砂浜と緑の林が1.6kmに渡りゆるやかな曲線を描く美しい海岸。最近はサーフポイントとしての人気も高く、県内外から多くのサーファーが訪れます。
#景観(海)
-
263. 廓中ふるさと館のどかな田園風景の中に、笑顔を大切にした活気のあるこの店は、都市と農村のふれあいの場。安芸市のご当地グルメ・釜あげちりめん丼に大きなかき揚げを乗せた、かき揚げちりめん丼はサクサクでボリューム満点。店内入口には地場産品市コーナーがあり、安芸市の名産品なすを使ったアイスも味わえます。33.518036 133.91364
のどかな田園風景の中に、笑顔を大切にした活気のあるこの店は、都市と農村のふれあいの場。安芸市のご当地グルメ・釜あげちりめん丼に大きなかき揚げを乗せた、かき揚げちりめん丼はサクサクでボリューム満点。店...
#市場・直売所
#高知県産
#和食
-
264. 平石の乳イチョウ国の天然記念物、平石の乳イチョウ。33.71538 133.4883
推定樹齢800年、あるいは1000年とも言われます。
幹から大小50余りの気根(乳柱)が垂れ下がる姿は、神秘的で圧巻。
国の天然記念物、平石の乳イチョウ。 推定樹齢800年、あるいは1000年とも言われます。 幹から大小50余りの気根(乳柱)が垂れ下がる姿は、神秘的で圧巻。
#花・植物
-
265. 岡豊城跡戦国時代、土佐を統一し、四国制覇を試みた長宗我部元親の居城であり、平成20年に国指定史跡となりました。33.59493 133.62242
山頂の詰を中心とした主郭部分は発掘調査に基づいて公園整備されています。
中腹には県立歴史民俗資料館があり、常設展示で長宗我部展示室も設けられています。
戦国時代、土佐を統一し、四国制覇を試みた長宗我部元親の居城であり、平成20年に国指定史跡となりました。 山頂の詰を中心とした主郭部分は発掘調査に基づいて公園整備されています。 中腹には県立歴史民俗資料館...
#文化財・史跡
-
266. 道の駅 大山安芸市の東端、大山岬にある道の駅。2024年2月10日にリニューアルオープンし、レストランを新設。なす、ちりめん、ゆずなど、安芸の特産品たっぷりのメニューが揃っており、太平洋を眺めながら食事ができます。33.470123 133.94403
なすやピーマンなどJA土佐あき安芸集出荷場直送の新鮮な野菜やお土産も購入できます。
大山岬は、2011年11月に「恋人の聖地」に認定され、特産品である内原野焼で製作された特製ベンチに座って「だるま夕日」が見られたら、願い事が叶うと言われています。
安芸市の東端、大山岬にある道の駅。2024年2月10日にリニューアルオープンし、レストランを新設。なす、ちりめん、ゆずなど、安芸の特産品たっぷりのメニューが揃っており、太平洋を眺めながら食事ができます。 なす ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
267. はりまや橋・葉山庭園よさこい公園「よさこい節」の純信お馬の道行で有名。江戸時代初期、土佐藩の御用商人の播磨屋宗徳と櫃屋道清が両家を往来するために設けた私設の仮橋が最初と言われています。現在は周辺がはりまや橋公園として整備されています。33.56004 133.54214
「よさこい節」の純信お馬の道行で有名。江戸時代初期、土佐藩の御用商人の播磨屋宗徳と櫃屋道清が両家を往来するために設けた私設の仮橋が最初と言われています。現在は周辺がはりまや橋公園として整備されていま...
#公園
-
268. 樽の滝鏡ダム湖の奥、鏡川の支流穴川川の源流にあたる「樽の滝」は、高さ65mの2段の滝からなり、春の山桜や新緑、秋の紅葉が美しいスポット。大雨が降ると樽を転がすような音がすることからこの名がつきました。滝壺に龍が棲んでいた伝説から龍神宮が祀られています。33.645588 133.46643
鏡ダム湖の奥、鏡川の支流穴川川の源流にあたる「樽の滝」は、高さ65mの2段の滝からなり、春の山桜や新緑、秋の紅葉が美しいスポット。大雨が降ると樽を転がすような音がすることからこの名がつきました。滝壺に龍 ...
#景観(川)
-
269. 郷麓温泉津野町内唯一の温泉は、源泉かけ流しのアルカリイオウ単純泉のやさしいお湯。館内の一番眺めが良い場所にある浴室からは、四万十川支流の北川川を望めます。33.377968 133.01222
津野町内唯一の温泉は、源泉かけ流しのアルカリイオウ単純泉のやさしいお湯。館内の一番眺めが良い場所にある浴室からは、四万十川支流の北川川を望めます。
#温泉
-
270. 三樽権現の滝落差約7mの小さな滝で、流れる姿は静かな癒しを感じます。33.713276 133.47894
エメラルドグリーンの滝壺は、星型に見えるとも。
ゆっくり滝の音を聞きながら、マイナスイオンを浴びられる穴場スポットです。
落差約7mの小さな滝で、流れる姿は静かな癒しを感じます。 エメラルドグリーンの滝壺は、星型に見えるとも。 ゆっくり滝の音を聞きながら、マイナスイオンを浴びられる穴場スポットです。
#景観(川)
-
271. なはりの郷奈半利町を活気ある町にしようと立ち上げた、集落活動センターです。33.42479 134.02153
住民の方々の憩いの場でもあり、観光パンフレットも置いていますので、奈半利町へ観光に来ていただいた方のための「観光案内所」の一面もあります。
また、事前予約が必要とはなりますが、街並みの案内ガイドもあります。
奈半利町を活気ある町にしようと立ち上げた、集落活動センターです。 住民の方々の憩いの場でもあり、観光パンフレットも置いていますので、奈半利町へ観光に来ていただいた方のための「観光案内所」の一面もあり ...
#観光案内所
-
272. 県立 月見山こどもの森(キャンプ場/フィールドアスレチック)20.7haの敷地に広がる自然林の中に、休憩所、野鳥観察小屋、キャンプ場、アスレチックコースなどが配置され、健康づくりをしながら森林浴が楽しめます。33.53948 133.74396
「国際児童年」を記念して町の南端にある標高68mの月見山を整備。1980(昭和55)年に開園しました。
月見山こどもの森ハウスでは、ものづくりなどの体験学習も行っています。
20.7haの敷地に広がる自然林の中に、休憩所、野鳥観察小屋、キャンプ場、アスレチックコースなどが配置され、健康づくりをしながら森林浴が楽しめます。 「国際児童年」を記念して町の南端にある標高68mの月見山を整 ...
#公園
#キャンプ
#体験学習
#キャンプ場
-
273. 大山岬2011年11月に「恋人の聖地」に認定され、リング型のモニュメントが撮影スポットになっています。33.463333 133.94202
海岸段丘が垂直に迫り、先端は海食によって巨大な洞くつや奇岩が連続した貴重な地形の岬。
特産品である内原野焼で製作された特製ベンチから「だるま夕日」が見られたら願い事が叶うと言われています。
すぐ近くに道の駅大山があります。
2011年11月に「恋人の聖地」に認定され、リング型のモニュメントが撮影スポットになっています。 海岸段丘が垂直に迫り、先端は海食によって巨大な洞くつや奇岩が連続した貴重な地形の岬。 特産品である内原野焼で ...
#景観(海)
-
274. 和霊神社文久2年(1862年)3月23日、脱藩の決意を固めた坂本龍馬は、酒をもって和霊神社に詣で、武運長久を祈願したと伝承されています。昭和60年3月24日に龍馬生誕150年記念行事としてここで脱藩祭が行われて以来、毎年3月24日、恒例の行事として脱藩祭が行われています。33.536415 133.51085
文久2年(1862年)3月23日、脱藩の決意を固めた坂本龍馬は、酒をもって和霊神社に詣で、武運長久を祈願したと伝承されています。昭和60年3月24日に龍馬生誕150年記念行事としてここで脱藩祭が行われて以来、毎年3月24日 ...
#寺社
-
275. 中半家沈下橋JRの鉄橋と抜水橋(半家大橋)、沈下橋という3つの橋が並行に架かる珍しい風景。フォトスポットとしても人気。全長約126m、普通車の通行不可(二輪車以下は通行可能)。33.207478 132.79329
JRの鉄橋と抜水橋(半家大橋)、沈下橋という3つの橋が並行に架かる珍しい風景。フォトスポットとしても人気。全長約126m、普通車の通行不可(二輪車以下は通行可能)。
#景観(川)
#建築
-
276. 土佐の元気市・輝るぽーと安田地元の農家さんが毎朝持ってきた新鮮野菜や田舎寿司、お弁当、お惣菜、日用雑貨、安田朗グッズ、特産品など、何でも揃うお店です。33.436512 133.98064
名物の大判焼きや、ソフトクリームも販売。
県東部に来た際には外せない立ち寄りポイントです。
地元の農家さんが毎朝持ってきた新鮮野菜や田舎寿司、お弁当、お惣菜、日用雑貨、安田朗グッズ、特産品など、何でも揃うお店です。 名物の大判焼きや、ソフトクリームも販売。 県東部に来た際には外せない立ち寄り ...
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
277. 土佐魚菜市場須崎で採れた魚や野菜から作った、天ぷら・ちくわ・かまぼこなどの加工・販売をしています。33.38467 133.27278
新鮮な野菜や練り物をお得に購入できる産直市もあります。
須崎で採れた魚や野菜から作った、天ぷら・ちくわ・かまぼこなどの加工・販売をしています。 新鮮な野菜や練り物をお得に購入できる産直市もあります。
#市場・直売所
#おみやげ
-
278. 安居渓谷 みかえりの滝安居渓谷最初の見どころですが、初めて行く人は知らないうちに通り過ぎてしまいそう。水量豊かな頃の滝の眺めはとりわけ素晴しく、立ち去る前にもう一度振り返って見たい滝なのでこのように呼ばれるようになったと言われています。33.66755 133.19263
安居渓谷最初の見どころですが、初めて行く人は知らないうちに通り過ぎてしまいそう。水量豊かな頃の滝の眺めはとりわけ素晴しく、立ち去る前にもう一度振り返って見たい滝なのでこのように呼ばれるようになったと...
#景観(川)
-
279. 道の駅 あぐり窪川四万十中央ICを降りてすぐにある「道の駅あぐり窪川」は、海洋堂ホビー館四万十など周辺文化施設を結ぶ東の玄関口です。33.231236 133.14919
自社工場製のボリューム満点「具だくさん豚まん」や、朝採れ牛乳でつくるオリジナルアイス、自家製米粉パンなど、ここでしか味わえない地元食材をふんだんに使った逸品がズラリ。
お土産コーナーでは四万十ポークや仁井田米を使った川のり、ミレービスケット、地酒などバラエティ豊かな特産品を取り揃え、県外発送も可能です。
ドライブの合間に立ち寄れば、四万十の“食”と“遊び”がぎゅっと詰まった一日をお楽しみいただけます。
四万十中央ICを降りてすぐにある「道の駅あぐり窪川」は、海洋堂ホビー館四万十など周辺文化施設を結ぶ東の玄関口です。 自社工場製のボリューム満点「具だくさん豚まん」や、朝採れ牛乳でつくるオリジナルアイス...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
280. 朝倉城跡土佐戦国の七守護のひとり本山氏の居城跡。長宗我部氏との抗争の中、本山に撤退する折に、本山氏自ら城を焼いて以来廃城となりました。城跡の標高103m。二ノ段・三ノ段等、中世山城の典型的な遺構が残っています。33.547073 133.48056
土佐戦国の七守護のひとり本山氏の居城跡。長宗我部氏との抗争の中、本山に撤退する折に、本山氏自ら城を焼いて以来廃城となりました。城跡の標高103m。二ノ段・三ノ段等、中世山城の典型的な遺構が残っています。
#文化財・史跡
-
281. 平家の滝的渕川の上流にある「平家の滝」は高さ30メートルで、二段に分かれた滝の一段目に深い滝壺があります。源平の戦に敗れた平家の落人が、対岸の高キビを源氏の追っ手と見間違え「もはや、これまで」と滝壺に身を投げたと伝えられています。その霊を慰め祟りを鎮めるため、貴船大明神が祀られています。33.6246 133.42278
的渕川の上流にある「平家の滝」は高さ30メートルで、二段に分かれた滝の一段目に深い滝壺があります。源平の戦に敗れた平家の落人が、対岸の高キビを源氏の追っ手と見間違え「もはや、これまで」と滝壺に身を投げ ...
#景観(川)
-
282. 青源寺青源寺は、山内家筆頭家老深尾家の菩提寺。庭園は「土佐三大名園」の一つで、禅的風格を備えた池泉式借景庭園。県指定の名勝。33.49724 133.28809
青源寺は、山内家筆頭家老深尾家の菩提寺。庭園は「土佐三大名園」の一つで、禅的風格を備えた池泉式借景庭園。県指定の名勝。
#寺社
-
283. 中岡慎太郎像上展望台室戸岬の中岡慎太郎像の上にある展望台。展望台からは、果てしなく広がる太平洋と隆起したダイナミックな大地を望むことができる穴場絶景スポット。恋人の聖地の1つ。33.24611 134.17648
室戸岬の中岡慎太郎像の上にある展望台。展望台からは、果てしなく広がる太平洋と隆起したダイナミックな大地を望むことができる穴場絶景スポット。恋人の聖地の1つ。
#景観(海)
-
284. 紙博直販所しょうがまんじゅうは、いの町産の生姜を砂糖煮して生地に練りこんだお饅頭です。33.547325 133.42311
あっさりとした素朴な味で博物館を訪れる方や直販所を利用する方にも人気の味です。
しょうがまんじゅうは、いの町産の生姜を砂糖煮して生地に練りこんだお饅頭です。 あっさりとした素朴な味で博物館を訪れる方や直販所を利用する方にも人気の味です。
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
285. 爪彫り薬師天平年中(729~49)聖武天皇の勅願により行基が開山し、後に空海が四国霊場28番札所定めた大日寺の奥の院・爪彫薬師堂。33.577576 133.70541
爪彫り薬師は空海が彫ったと伝えられ、耳・眼・口・鼻の病に霊験があると言われています。
天平年中(729~49)聖武天皇の勅願により行基が開山し、後に空海が四国霊場28番札所定めた大日寺の奥の院・爪彫薬師堂。 爪彫り薬師は空海が彫ったと伝えられ、耳・眼・口・鼻の病に霊験があると言われています。
#文化財・史跡
-
286. 龍王公園タコの形をした滑り台やブランコなどの遊具、休憩所などのほか公園に隣接してフィールドアスレチックができる児童遊園があります。33.4639 133.28304
タコの形をした滑り台やブランコなどの遊具、休憩所などのほか公園に隣接してフィールドアスレチックができる児童遊園があります。
#公園
-
287. 妙見山少年だった弥太郎が、安政元年(1854年)に江戸遊学に出かける際に登り、頂上にある星神社の社に「吾れ志を得ずんば、再び帰りてこの山に登らじ」と落書きをし、立身出世を祈願した逸話が残っています。弥太郎の商いの始まりである楠や、安芸平野の武家屋敷群の生垣に使われている土用竹など、地元の風土と密着した植生が随所に見られます。登り始めと星神社に、ふもとの井ノ口小学校の児童が設置した案内板が設置されています。33.529305 133.88542
少年だった弥太郎が、安政元年(1854年)に江戸遊学に出かける際に登り、頂上にある星神社の社に「吾れ志を得ずんば、再び帰りてこの山に登らじ」と落書きをし、立身出世を祈願した逸話が残っています。弥太郎の商 ...
#景観(山)
-
288. 山内一豊の像山内一豊は土佐藩の初代藩主となった戦国武将です。33.56104 133.53352
戦国時代の尾張藩(現在の愛知県)で生まれ、織田信長、豊臣秀吉と仕えた後に、関ケ原の戦での功から土佐国(現在の高知県)を徳川家康から拝領しました。
その生涯が司馬遼太郎の小説『功名が辻』(こうみょうがつじ)で描かれ、NHK大河ドラマにもなりました(2006年)。
銅像は、坂本龍馬像(桂浜)や中岡慎太郎像(室戸岬)を作った本山白雲によるものです。
山内一豊は土佐藩の初代藩主となった戦国武将です。 戦国時代の尾張藩(現在の愛知県)で生まれ、織田信長、豊臣秀吉と仕えた後に、関ケ原の戦での功から土佐国(現在の高知県)を徳川家康から拝領しました。 そ ...
#銅像・記念碑
-
賛助会員289. 宿毛駅観光案内センター(宿毛市観光協会)土佐くろしお鉄道・宿毛駅1Fにある観光案内施設です。観光案内、特産品の販売、高速バスチケットの販売、周辺観光に便利な電動自転車、ロードバイクのレンタルなどを行っています。32.932552 132.71329
土佐くろしお鉄道・宿毛駅1Fにある観光案内施設です。観光案内、特産品の販売、高速バスチケットの販売、周辺観光に便利な電動自転車、ロードバイクのレンタルなどを行っています。
#観光案内所
-
賛助会員290. 室戸市観光協会室戸市の観光情報を一堂に集めた総合観光案内所です。33.24604 134.1773
案内カウンターでは、手荷物を預かるサービスや室戸ユネスコ世界ジオパークを地元ガイドのガイド案内、シェアサイクルなど様々な体験ができます。
室戸市内や東部地域のパンフレットをご用意しています。(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットも多数ご用意しています。)
室戸市の観光情報を一堂に集めた総合観光案内所です。 案内カウンターでは、手荷物を預かるサービスや室戸ユネスコ世界ジオパークを地元ガイドのガイド案内、シェアサイクルなど様々な体験ができます。 室戸市内 ...
#観光案内所
-
291. 小鎌田の浜目の前には双名島が広がり、のどかな雰囲気の浜。秋から冬は水平線から昇る朝日を見ることができます。33.333122 133.23863
目の前には双名島が広がり、のどかな雰囲気の浜。秋から冬は水平線から昇る朝日を見ることができます。
#景観(海)
#キャンプ
#キャンプ場
-
292. 香美市立吉井勇記念館「命短し 恋せよ乙女」で有名なゴンドラの唄で知られる歌人・吉井勇(よしいいさむ)が不遇の時代に移り住み、癒された猪野々地区。そこに建つ記念館では、彼の生涯や猪野々での生活を映像や作品、遺品等で紹介しています。33.706043 133.8563
敷地内には、国の登録有形文化財にも指定されている渓鬼荘(けいきそう)が移築されており、勇が滞在した当時の様子をうかがうことができます。
「命短し 恋せよ乙女」で有名なゴンドラの唄で知られる歌人・吉井勇(よしいいさむ)が不遇の時代に移り住み、癒された猪野々地区。そこに建つ記念館では、彼の生涯や猪野々での生活を映像や作品、遺品等で紹介し...
#ミュージアム
-
293. 廣井勇像日本初のコンクリート製外洋防波堤を建設した、日本近代土木工学の第一人者です。33.49886 133.28806
幕末に土佐藩(現在の高知県)の佐川町に生まれ、植物学者・牧野富太郎とともに、藩校「名教館(めいこうかん)」で学びました。
明治維新前後の混乱に苦労して学び、札幌農学校北海道で学んだ後にアメリカやドイツに留学、河川や橋梁の工事に従事しました。帰国して間もなく小樽港の建設に携わり、北防波堤を建設しました。当時はお雇い欧米人でも成功が難しい土木事業でしたが、廣井勇の作った防波堤は100年経った今も壊れることなく当時のまま使われており、2000年には公益社団法人土木学会から「土木学会選奨土木遺産」に選ばれました。
その後、東京帝国大 ...
日本初のコンクリート製外洋防波堤を建設した、日本近代土木工学の第一人者です。 幕末に土佐藩(現在の高知県)の佐川町に生まれ、植物学者・牧野富太郎とともに、藩校「名教館(めいこうかん)」で学びました。 ...
#銅像・記念碑
-
294. 名教館券の文化財にも指定されている藩政時代の建物「名教館」。かつて、家臣の子どもたちに教育を学ばせたいと考えた佐川の領主・深尾氏によって開かれた塾でした。ここで学んだ者は多く、明治維新では、多くの勤王の志士を輩出。また、佐川町出身の植物学者・牧野富太郎博士らもこの名教館で学んでいます。33.499107 133.28828
「名教館」の玄関部分が当時のまま現存しており、現在は館全体も復元されています。
券の文化財にも指定されている藩政時代の建物「名教館」。かつて、家臣の子どもたちに教育を学ばせたいと考えた佐川の領主・深尾氏によって開かれた塾でした。ここで学んだ者は多く、明治維新では、多くの勤王の志...
#ミュージアム
-
295. 半家沈下橋四万十川ウルトラマラソンに代表される撮影スポットの一つ。右岸側に岩盤が見られる急流に架かり、瀬音や白い水しぶきを楽しめます。全長約125m、普通車の通行可能。33.213 132.80539
四万十川ウルトラマラソンに代表される撮影スポットの一つ。右岸側に岩盤が見られる急流に架かり、瀬音や白い水しぶきを楽しめます。全長約125m、普通車の通行可能。
#景観(川)
#建築
-
296. 山内容堂像「幕末の四賢侯」に数えられる土佐藩主・山内容堂の銅像は、山内家の藩主を代々祀った山内神社境内にあります。最後の将軍・徳川慶喜に大政奉還を進言した容堂が、歴史的な大偉業の実現を慶んで、ギヤマンの杯を片手にあぐらをかいている様子を再現しています。酒と詩歌におぼれる悠々自適な生活を好んだ人物として知られる容堂を偲んだ座像です。33.55545 133.53185
※ギヤマン…江戸時代から明治初期に使われていた外来語で、ガラス製品を指します
「幕末の四賢侯」に数えられる土佐藩主・山内容堂の銅像は、山内家の藩主を代々祀った山内神社境内にあります。最後の将軍・徳川慶喜に大政奉還を進言した容堂が、歴史的な大偉業の実現を慶んで、ギヤマンの杯を片...
#銅像・記念碑
-
297. 浦戸城跡高知県指定史跡の浦戸城跡は、長宗我部元親が戦国時代に本山氏から切り取った城。元親は豊臣秀吉に降った後、岡豊城から浦戸城に本拠を移しました。33.49695 133.57196
関ヶ原の戦い後、山内氏が入国してくると、長宗我部遺臣が浦戸城に立て籠もり抵抗しました。その時討ち取られた273名の霊を導くため、近くに六体地蔵が建立されています。
高知県指定史跡の浦戸城跡は、長宗我部元親が戦国時代に本山氏から切り取った城。元親は豊臣秀吉に降った後、岡豊城から浦戸城に本拠を移しました。 関ヶ原の戦い後、山内氏が入国してくると、長宗我部遺臣が浦戸 ...
#文化財・史跡
-
298. 不動の滝(北川村)小島地区にある不動の滝は3つの滝からなる名瀑。33.50141 134.11334
入り口となる水谷口から滝の轟音が聞こえ、遊歩道は三の滝、二の滝、一の滝へと続く。お不動様が祭られていて、滝壷の側面には磨崖仏(まがいぶつ)が彫られています。水量が豊富でどんなかんばつでも一度も枯れたことがなく、近郷の集落からかんばつ期にこの「お不動様」へ雨乞いに訪れると、3日以内には必ず雨が降ると言い伝えられています。
小島地区にある不動の滝は3つの滝からなる名瀑。 入り口となる水谷口から滝の轟音が聞こえ、遊歩道は三の滝、二の滝、一の滝へと続く。お不動様が祭られていて、滝壷の側面には磨崖仏(まがいぶつ)が彫られていま...
#景観(川)
-
299. 水辺の駅あいの里仁淀川仁淀川の景色を眺めながら、地元食材を使った食事が楽しめます。33.564022 133.33255
地元でとれた野菜などの販売もされています。
仁淀川の景色を眺めながら、地元食材を使った食事が楽しめます。 地元でとれた野菜などの販売もされています。
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#おみやげ
-
300. 芸西メランジュ世界的に珍しい混在岩の地層が露出しており、1億3000万年前から、7500万年前までの地層や岩石が観察できます。33.515965 133.7705
世界的に珍しい混在岩の地層が露出しており、1億3000万年前から、7500万年前までの地層や岩石が観察できます。
#ジオスポット
-
301. 久礼八幡宮久礼八幡宮は漁師や農家が大漁や豊作の祈願に来る神社として知られ、勝負の神様ということで試合や受験の前に祈願に訪れる方も。33.3273 133.23021
毎年、旧暦の8月14日から15日にかけて、高知県の3大祭りの一つ「久礼八幡宮秋季大祭」が開かれます。
久礼八幡宮は漁師や農家が大漁や豊作の祈願に来る神社として知られ、勝負の神様ということで試合や受験の前に祈願に訪れる方も。 毎年、旧暦の8月14日から15日にかけて、高知県の3大祭りの一つ「久礼八幡宮秋季大 ...
#寺社
-
302. 蟠蛇森標高769m。頂上の展望台からの眺望が特に素晴らしく、また途中の七曲がりの道から刻々表情を変える太平洋も絶景です。33.440994 133.26161
標高769m。頂上の展望台からの眺望が特に素晴らしく、また途中の七曲がりの道から刻々表情を変える太平洋も絶景です。
#景観(山)
-
303. 六條八幡宮(あじさい神社)県内有数のあじさいの名所として「あじさい神社」の愛称で親しまれている六條八幡宮。33.49822 133.4904
参道や境内周辺には様々な品種、約1,500株のあじさいが彩り、参拝者を出迎えてくれます。
6月には神社周辺の‶あじさい街道"で、ウォーキングを楽しむ「あじさい祭り」が催されます。
県内有数のあじさいの名所として「あじさい神社」の愛称で親しまれている六條八幡宮。 参道や境内周辺には様々な品種、約1,500株のあじさいが彩り、参拝者を出迎えてくれます。 6月には神社周辺の‶あじさい街道" ...
#寺社
#花・植物
-
304. 安芸市立歴史民俗資料館戦国の武将、安芸国虎の居城であった安芸城跡にあり、江戸時代、土佐藩家老であった五藤家に伝わる武具・甲冑や美術工芸品などを中心に、弘田龍太郎や岩崎弥太郎など安芸市出身の人物なども紹介しています。33.519176 133.91324
戦国の武将、安芸国虎の居城であった安芸城跡にあり、江戸時代、土佐藩家老であった五藤家に伝わる武具・甲冑や美術工芸品などを中心に、弘田龍太郎や岩崎弥太郎など安芸市出身の人物なども紹介しています。
#ミュージアム
-
305. 地のもん市場 ハレタ高知県の「地のもん市場ハレタ」は、地元の新鮮な食材と出来立てグルメが揃う人気スポットです。併設の「ごはん家ハレタ」では、店内で販売している冷凍フライを15時以降に揚げたてで提供する無料サービスが好評。精米工場直営の新鮮なお米、県内18蔵の土佐酒、旬の果物と野菜、花と苗まで幅広く取り揃えています。「惣菜工房ハレタ」の手作り弁当やおかず、人気の餃子も見逃せません。試食コーナーも充実しており、気軽に高知の味を体験できます。駐車場70台完備で、お買い物にも便利。高知観光のお土産探しや、地元グルメを堪能したい方におすすめの施設です。33.50323 133.42693
高知県の「地のもん市場ハレタ」は、地元の新鮮な食材と出来立てグルメが揃う人気スポットです。併設の「ごはん家ハレタ」では、店内で販売している冷凍フライを15時以降に揚げたてで提供する無料サービスが好評。 ...
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
306. 五色ノ浜の横浪メランジュ横浪半島の五色ノ浜の海岸では、フィリピン海プレートが沈み込む際に、その堆積層(玄武岩・チャート・遠洋性粘土等)が陸側に剥ぎ取られ、押しつけられる「付加作用」により、混じり合った地層(メランジュ)となって分布している様子を広い範囲で観察できます。33.424816 133.45717
プレートテクトニクス理論が世界に先駆けて陸上で実証された場所として重要と言われています。
横浪半島の五色ノ浜の海岸では、フィリピン海プレートが沈み込む際に、その堆積層(玄武岩・チャート・遠洋性粘土等)が陸側に剥ぎ取られ、押しつけられる「付加作用」により、混じり合った地層(メランジュ)とな...
#ジオスポット
-
307. 高瀬沈下橋全長約232mと四万十川で3番目に長い沈下橋。川幅も広く、清流がゆっくりと流れるのどかな風景が心を癒します。初夏のホタル観賞、夏場のキャンプなどで賑わいます。普通車の通行可能。33.036217 132.84488
全長約232mと四万十川で3番目に長い沈下橋。川幅も広く、清流がゆっくりと流れるのどかな風景が心を癒します。初夏のホタル観賞、夏場のキャンプなどで賑わいます。普通車の通行可能。
#景観(川)
#建築
-
308. 中越家のしだれ桜推定樹齢200年・樹高15m・根周り4.5m。町指定天然記念物。33.53067 133.054
町文化財指定旧庄屋の中越家はかつては佐川領主深尾公の休憩の地とされていました。
土佐三大祭りの一つ「秋葉の練り」もこの庭先で行われ、由緒ある庄屋跡地のしだれ桜として県内外から花見客やカメラマンが訪れます。
推定樹齢200年・樹高15m・根周り4.5m。町指定天然記念物。 町文化財指定旧庄屋の中越家はかつては佐川領主深尾公の休憩の地とされていました。 土佐三大祭りの一つ「秋葉の練り」もこの庭先で行われ、由緒ある庄屋...
#花・植物
-
309. こうち観光ナビ・ツーリストセンター高知駅前すぐ、「こうち観光ナビ・ツーリストセンター」は、高知県内34すべての市町村の観光情報を集めた広域観光案内所。英語対応スタッフも常駐しているので、海外からのお客様も安心です。33.5601 133.53662
県内の観光スポット案内はもちろん、手荷物預かり(有料)、龍馬パスポート(青)の発行、「MY遊バス」のチケット販売など、観光に便利なサービスが充実。パンフレットは日本語に加え、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語もご用意しており、郵送サービスも行っています。
観光の計画を立てるのにぴったりのスポットです。
高知駅前すぐ、「こうち観光ナビ・ツーリストセンター」は、高知県内34すべての市町村の観光情報を集めた広域観光案内所。英語対応スタッフも常駐しているので、海外からのお客様も安心です。 県内の観光スポット...
#観光案内所
-
310. 秦山公園(子どもの広場・ふれあい広場)美しい森の緑に囲まれた秦山公園は、夢いっぱいの遊具が沢山あることで人気。ゲートボール場をはじめ憩いの広場や、ローラー滑り台がついた小学生向けの「大きな森の物語」、幼児向けの「どんぐりの森」、ふわふわドームなどがあります。また、土佐山田スタジアムなどの施設が併設され、運動施設を中心に散策、休憩、レクリエーション等、子どもから老年齢層まで楽しめる場所です。33.61268 133.67863
美しい森の緑に囲まれた秦山公園は、夢いっぱいの遊具が沢山あることで人気。ゲートボール場をはじめ憩いの広場や、ローラー滑り台がついた小学生向けの「大きな森の物語」、幼児向けの「どんぐりの森」、ふわふわ...
#公園
-
311. 美空ひばり遺影碑・歌碑杉の大スギのすぐそばに故美空ひばりさんの遺影碑・歌碑があります。この遺影碑・歌碑は美空ひばりさんゆかりの地として、平成5年5月にファンやプロダクション、レコード会社など数多くの関係者の全面的なご協力を得て建立されました。遺影碑からはボタンスイッチで「川の流れのように」「龍馬残影」「悲しき口笛」の3曲が流れてきます。33.755615 133.66292
杉の大スギのすぐそばに故美空ひばりさんの遺影碑・歌碑があります。この遺影碑・歌碑は美空ひばりさんゆかりの地として、平成5年5月にファンやプロダクション、レコード会社など数多くの関係者の全面的なご協力...
#銅像・記念碑
-
312. 吉田東洋記念之地文久2年(1862年)4月8日、帯屋町の自宅付近で、東洋の公武合体論に反対する土佐勤王党員の那須信吾、大石団蔵、安岡嘉助によって暗殺されました。城中で藩主に『日本外史』の最終講義した帰り道だったといいます。33.560814 133.53773
文久2年(1862年)4月8日、帯屋町の自宅付近で、東洋の公武合体論に反対する土佐勤王党員の那須信吾、大石団蔵、安岡嘉助によって暗殺されました。城中で藩主に『日本外史』の最終講義した帰り道だったといいます。
#文化財・史跡
#銅像・記念碑
-
313. 武市半平太(瑞山)像幕末の土佐藩で、土佐勤王党を組織した武市半平太の銅像。瑞山(ずいざん)は号です。33.407333 133.38802
太平洋を見渡しながら東西19kmほど続く絶景ドライブコース「横浪黒潮ライン」の中ほどに銅像があります。
銅像の裏側には「土佐勤王党血盟者と同志人名」を刻んだ石版があり、坂本龍馬たちの名前が載っています。
武市瑞山の銅像は1979(昭和54)年に建立されましたが、今あるのは1985(昭和60)年に再建された2代目の銅像です。高さは初代の6メートルから2代目は3メートルほどになりました。制作者は原寛山(はらかんざん)。
初代銅像が持っていた刀が高知市仁井田の武市半平太旧宅近くの瑞山神社に展示されています。
幕末の土佐藩で、土佐勤王党を組織した武市半平太の銅像。瑞山(ずいざん)は号です。 太平洋を見渡しながら東西19kmほど続く絶景ドライブコース「横浪黒潮ライン」の中ほどに銅像があります。 銅像の裏側には「 ...
#銅像・記念碑
-
314. 山田邸の庭園(昭和天皇の歌碑)江戸時代から続いた土佐捕鯨の網元、その後マグロの遠洋漁業でも栄えた旧家。33.26049 134.16849
海岸の巨大な岩場をそのまま利用した庭は太平洋の荒々しさを残しており、近くの保育園児が遠足に来るほど広い立派な庭園。
かつて皇室関係者も宿泊した由緒正しい邸宅。
昭和25年に昭和天皇陛下が山田家にお泊まりの際、詠まれた歌の碑もあります。
江戸時代から続いた土佐捕鯨の網元、その後マグロの遠洋漁業でも栄えた旧家。 海岸の巨大な岩場をそのまま利用した庭は太平洋の荒々しさを残しており、近くの保育園児が遠足に来るほど広い立派な庭園。 かつて皇 ...
#銅像・記念碑
-
315. 維新の門(群像)1862(文久2)年の春、坂本龍馬は盟友・澤村惣之丞(さわむらそうのじょう)とともに梼原町の韮ヶ峠(にらがとうげ)を越えて脱藩、幕末の日本を駆け抜けた龍馬の活躍は始まりました。33.3912 132.92416
那須信吾・俊平父子ら梼原町にゆかりのある六志士に、龍馬と惣之丞をあわせた8人の銅像が建てられ、「維新の門」と名付けられました。
明治維新の1868年、この8人の志士たちは皆壮絶な死を遂げました。
1862(文久2)年の春、坂本龍馬は盟友・澤村惣之丞(さわむらそうのじょう)とともに梼原町の韮ヶ峠(にらがとうげ)を越えて脱藩、幕末の日本を駆け抜けた龍馬の活躍は始まりました。 那須信吾・俊平父子ら梼原町に...
#銅像・記念碑
-
316. 鏡川「鏡川」は、平成の名水百選に選ばれた高知市を代表する美しい川です。透明度が高く、水面に映し出される光景はまさに「鏡」のようです。33.554222 133.53293
アニメ映画『竜とそばかすの姫』では、主人公すずの通学シーンで何度も出てくる川のモデルとなりました。すずが歌ったり、同級生と過ごしたり、いろんなシーンで、いろんな絵で描かれています。
「鏡川」は、平成の名水百選に選ばれた高知市を代表する美しい川です。透明度が高く、水面に映し出される光景はまさに「鏡」のようです。 アニメ映画『竜とそばかすの姫』では、主人公すずの通学シーンで何度も ...
#景観(川)
-
317. 奈半利駅物産館 いちじく高知県ごめんなはり線の奈半利駅1Fにある販売店です。奈半利町の無添加なはり味噌、どぶろく、特産品でもあるいちじくジャムなどご当地商品をメインに、ひがし高知のセレクトされた土産もの、地酒、菓子など商品をたくさん取り揃えています。33.424793 134.01814
店舗の2Fはイートインスペースになっているので、店舗で1杯ずつ豆から挽いたコーヒーやイチジクソフトなどと一緒に、ごゆっくりおくつろぎいただけます。
高知県ごめんなはり線の奈半利駅1Fにある販売店です。奈半利町の無添加なはり味噌、どぶろく、特産品でもあるいちじくジャムなどご当地商品をメインに、ひがし高知のセレクトされた土産もの、地酒、菓子など商品を ...
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
318. 明星来影寺平安時代の宗教家である弘法大師空海の著書「三教指帰」に”室戸崎にて勤念す”と記され、青年時代難行苦行の末に悟りを開かれたのが、現在の高知県室戸市です。昭和59年に室戸阿南海岸国定公園を目の前に控えた絶景の地を明星来影の丘”と定め、日本最大の弘法大師立像を建立、そして明星来影寺と名付けられました。お像は室戸青年大師と称されています。目前には壮大な空と海が一面に広がっています。33.254025 134.18079
平安時代の宗教家である弘法大師空海の著書「三教指帰」に”室戸崎にて勤念す”と記され、青年時代難行苦行の末に悟りを開かれたのが、現在の高知県室戸市です。昭和59年に室戸阿南海岸国定公園を目の前に控えた絶 ...
#寺社
-
319. かわうそ自然公園キャンプやピクニック、新荘川での川遊びも楽しめます。33.446 133.20433
津野町役場の前にあります。
キャンプやピクニック、新荘川での川遊びも楽しめます。 津野町役場の前にあります。
#公園
-
320. 城西館から最も近い“隠れた”お花見スポット♪【上町鏡川沿い】0.0 0.0
城西館から最も近い、南へ数十メートルの鏡川に沿った桜並木です。
時期が来ると川沿い一面がピンク色に染まります。
【上町鏡川沿い】 城西館から最も近い、南へ数十メートルの鏡川に沿った桜並木です。 時期が来ると川沿い一面がピンク色に染まります。
#花・植物
-
321. 久礼の港と漁師町の景観中近世に繁栄した港を核として形成された市街地が、鰹漁とともに発展した漁師町や漁港と相まって形成される独特の文化的景観。2011年2月に漁師町としては、全国で初めて国の文化財(重要文化的景観)として選定されました。海運による交易が多様な文化をもたらした久礼の町並みには、家屋が密集し庶民的な漁師町の暮らしを見ることができます。33.330585 133.23294
中近世に繁栄した港を核として形成された市街地が、鰹漁とともに発展した漁師町や漁港と相まって形成される独特の文化的景観。2011年2月に漁師町としては、全国で初めて国の文化財(重要文化的景観)として選定され ...
#景観(海)
#町並み
-
322. 土佐興津坂展望台この展望台には、四万十町産木材をふんだんに使用した東屋や木製の安全柵が整備されています。「初日の出」や、夏には興津地区の花火が望めることができるそうです。また、「高知フォトスポット100景」にも選定されていて、心地よい浜風や木のぬくもりを感じながら、素晴らしい眺望をお楽しみください。33.18434 133.19316
この展望台には、四万十町産木材をふんだんに使用した東屋や木製の安全柵が整備されています。「初日の出」や、夏には興津地区の花火が望めることができるそうです。また、「高知フォトスポット100景」にも選定され...
#景観(山)
-
323. 毘沙門の滝【土佐山田町】三滝神社の滝ともいわれているように三つの滝があり、高さは、上の滝が約9m、中の滝が11m、下の滝が約15mあります。上の滝には、直径、深さとも約2mの見事な甌穴ができています。付近の山は、奇岩怪石が重なりまわりの杉、檜、樫、つつじ等が美しいです。33.66544 133.65634
三滝神社の滝ともいわれているように三つの滝があり、高さは、上の滝が約9m、中の滝が11m、下の滝が約15mあります。上の滝には、直径、深さとも約2mの見事な甌穴ができています。付近の山は、奇岩怪石が重なりまわり ...
#景観(川)
-
324. 日ノ御子川香北町の中心地、美良布を流れる日ノ御子川は、北方の河野山塊を源とする清流。周辺にはキャンプ場が整備され、気軽に宿泊やバーベキューを楽しめます。また、日ノ御子川に沿って走る河野林道(約6km)は、渓谷の四季の変化を存分に楽しめます。33.6596 133.77867
香北町の中心地、美良布を流れる日ノ御子川は、北方の河野山塊を源とする清流。周辺にはキャンプ場が整備され、気軽に宿泊やバーベキューを楽しめます。また、日ノ御子川に沿って走る河野林道(約6km)は、渓谷の四...
#景観(川)
-
325. 勝間沈下橋四万十川で唯一、橋脚が3本で作られた沈下橋。川幅が広く、流れも穏やか。右岸側は河原でキャンプ地にも向いています。2003年には、釣りバカ日誌14のロケ地となり、釣りファンにも有名なスポット。全長約171m、普通車の通行可能。33.054844 132.81717
四万十川で唯一、橋脚が3本で作られた沈下橋。川幅が広く、流れも穏やか。右岸側は河原でキャンプ地にも向いています。2003年には、釣りバカ日誌14のロケ地となり、釣りファンにも有名なスポット。全長約171m、普通 ...
#景観(川)
#建築
-
326. 第35番札所 清瀧寺723年(養老7年)行基が自刻の薬師如来を安置して建立したのが起こり。後に空海が四国霊場に定めます。本尊の薬師如来立像は国指定の重要文化財。寺宝に、県指定文化財の銅造鏡像4面があります。(真言宗豊山派 山号:醫王山)33.512535 133.40947
弘法大師空海がご修行のおり、満願の日に金剛杖で壇前を突くと清水が瀧のように湧き出して鏡のような池になったことから、醫王山鏡池院清瀧寺と名づけたと伝わります。
境内には、大きな薬師如来立像があり、台座の中の「戒壇めぐり」をすると厄除けのご利益があるといわれています。
723年(養老7年)行基が自刻の薬師如来を安置して建立したのが起こり。後に空海が四国霊場に定めます。本尊の薬師如来立像は国指定の重要文化財。寺宝に、県指定文化財の銅造鏡像4面があります。(真言宗豊山派 山 ...
#寺社
-
327. 牧野富太郎像牧野富太郎は幕末の土佐藩(現在の高知県佐川町)に生まれ、日本の植物分類学を独力で切り拓いて第一人者にまでなりました。幼少から植物に親しみ、小学校を中退してから95年の生涯を終えるまで、独学による植物研究に人生を捧げました。日本全国で採集調査を行い、植物標本40万枚、命名した植物は2,500余、蔵書は45,000冊に達しました。33.54727 133.5792
その業績を顕彰して、博士逝去の翌年、高知市の五台山に開園した植物園内に銅像が建てられました。
2023(令和5)年には牧野富太郎をモデルにしたドラマ『らんまん』(NHK連続テレビ小説)が放送されました。
牧野富太郎は幕末の土佐藩(現在の高知県佐川町)に生まれ、日本の植物分類学を独力で切り拓いて第一人者にまでなりました。幼少から植物に親しみ、小学校を中退してから95年の生涯を終えるまで、独学による植物研 ...
#銅像・記念碑
-
賛助会員328. いの町観光協会JR伊野駅から徒歩5分、とさ電伊野駅から徒歩30秒の場所にあります。33.548252 133.42792
仁淀川観光の玄関口として、観光情報の発信や案内、レンタサイクルなどを行っております。
JR伊野駅から徒歩5分、とさ電伊野駅から徒歩30秒の場所にあります。 仁淀川観光の玄関口として、観光情報の発信や案内、レンタサイクルなどを行っております。
#観光案内所
-
329. 大川上美良布神社慶応元年(1865年)に着工、明治2年(1869年)に完成。各所に見事な彫刻が施されており、“土佐の日光”の別称があります。33.649963 133.78397
社殿は県指定文化財になっており、社殿の規模は大きく木割も堂々として落ち着きを感じさせます。
県の無形民俗文化財に指定されている秋祭り(毎年11月3日)は特に盛大で、古式にのっとった神輿のおなばれ行列が町内を練り歩き、大勢の人出で賑わいます。クライマックスの練り込みは見ものです。
やなせたかしさん奉納の絵馬や32人の漫画家の天井絵は、祭りやガイドツアーで拝観可能。
社務所が開いているときには、やなせたかしさんデザインの幸運十二支お守りも購入できます。
慶応元年(1865年)に着工、明治2年(1869年)に完成。各所に見事な彫刻が施されており、“土佐の日光”の別称があります。 社殿は県指定文化財になっており、社殿の規模は大きく木割も堂々として落ち着きを感じさせ ...
#寺社
-
330. 藩校致道館跡致道館(文武館)は文久2年(1862年)吉田東洋が開校した藩校。表門が武道館正門として当時の姿を残しています。それまでの儒学中心の教育方針を改め文武両道を重んじ、幕末の西洋式軍備に対応した人材育成を担いました。戊辰戦争時、土佐藩兵迅衝隊は致道館に集合、東門から出軍しました。県重要文化財に指定されています。33.56105 133.52888
致道館(文武館)は文久2年(1862年)吉田東洋が開校した藩校。表門が武道館正門として当時の姿を残しています。それまでの儒学中心の教育方針を改め文武両道を重んじ、幕末の西洋式軍備に対応した人材育成を担いま ...
#文化財・史跡
-
331. 足摺宇和海国立公園竜串ビジターセンターうみのわ竜串湾、桜浜を臨む絶好のロケーションにある足摺宇和海国立公園のビジターセンター。32.79109 132.8633
国立公園内の観光情報や自然解説を行っており、土佐清水ジオパークの拠点施設も兼ねています。フリーWi-Fi、キッズコーナー、授乳室、シャワーなどが完備されており休憩にもご利用いただけます。館内では無料の体験プログラムのほか、有料のガイド付きプログラムを実施。オリジナルグッズの販売も行っています。
地域をよく知るスタッフが、旬の情報やこの土地ならでの自然体験をご紹介します。
竜串湾、桜浜を臨む絶好のロケーションにある足摺宇和海国立公園のビジターセンター。 国立公園内の観光情報や自然解説を行っており、土佐清水ジオパークの拠点施設も兼ねています。フリーWi-Fi、キッズコーナー、 ...
#観光案内所
-
332. 口屋内沈下橋支流の中で最も透明度が高いといわれている黒尊川との合流地点にあり、口屋内と呼ばれる集落内に架かる沈下橋。丸みを帯びた独特な橋桁の形がユニーク。全長約241m、車両の通行不可。33.097088 132.80167
支流の中で最も透明度が高いといわれている黒尊川との合流地点にあり、口屋内と呼ばれる集落内に架かる沈下橋。丸みを帯びた独特な橋桁の形がユニーク。全長約241m、車両の通行不可。
#景観(川)
#建築
-
333. 天神のオオクスノキ高知市の中心部、鏡川沿いに立つ「天神町のオオクスノキ」は、市街地にありながら見事な樹冠を広げる、目を引く存在です。東西約15m、南北約18mに及ぶ枝ぶりは、周囲を遮るものがなく、四方に堂々と広がっています。33.55434 133.53734
このクスノキは、高知県内では須崎市の「大谷のクスノキ」(国指定天然記念物)に次ぐ規模で、市の天然記念物にも指定されています。巨樹の代表種といわれるクスノキの中でも、これほど美しい樹形を市街地で見られるのは貴重です。
街歩きで立ち寄れる自然スポット。樹下に立つと、まるで緑の天蓋に包まれるような感覚が味わえます。
高知市の中心部、鏡川沿いに立つ「天神町のオオクスノキ」は、市街地にありながら見事な樹冠を広げる、目を引く存在です。東西約15m、南北約18mに及ぶ枝ぶりは、周囲を遮るものがなく、四方に堂々と広がっています。...
#花・植物
-
334. あけぼの街道 なの市長岡地域の新鮮な野菜や果物を販売している直販所。33.5888 133.6515
ながおか温泉のすぐ近くです。
地元でとれた野菜や果物のほか、地元食材を使用したお弁当類も好評です。
長岡地域の新鮮な野菜や果物を販売している直販所。 ながおか温泉のすぐ近くです。 地元でとれた野菜や果物のほか、地元食材を使用したお弁当類も好評です。
#市場・直売所
#高知県産
-
335. 梼原町総合庁舎2006年に誕生した梼原町総合庁舎は、「防災の拠点機能」と「住民の利便性」を両立させつつ、地元資源への敬意を込めた建築です。33.39196 132.92696
四万十川源流の豊かな森に育まれた梼原産杉材をふんだんに用い、館内全域に温かな木のぬくもりが漂います。
1階ホールには町伝統の茶堂を設え、町民や観光客をやさしく迎え入れる空間に。地域の歴史と風土がひとつになるこの“森の庁舎”は、防災拠点としての安心と、日常の交流を織り交ぜ、誰もが親しみ感じる場として愛され続けています。
2006年に誕生した梼原町総合庁舎は、「防災の拠点機能」と「住民の利便性」を両立させつつ、地元資源への敬意を込めた建築です。 四万十川源流の豊かな森に育まれた梼原産杉材をふんだんに用い、館内全域に温かな ...
#建築
-
336. 山内一豊の妻の銅像土佐藩の初代藩主山内一豊の妻・千代は夫の出世を支えたエピソードが有名です。33.56108 133.53249
豊臣秀吉に仕えていた時期に、高額の駿馬を買えずにいる一豊に嫁入りの持参金十両を差し出します。
織田信長が行った「馬揃え」(軍馬を集めてその優劣などを検分すること)の時に、一豊の立派な馬が信長の目を引き、一目置かれるようになりました。
関ヶ原の戦いの時も、石田三成から西軍への加勢を促す書状が一豊に届きますが、千代は「未開封のまま家康に渡すように」と助言しました。その通りに一豊は家康に届けたことで、「一豊は二心が無い」と家康からの信頼を得たと言われています。
土佐藩の初代藩主山内一豊の妻・千代は夫の出世を支えたエピソードが有名です。 豊臣秀吉に仕えていた時期に、高額の駿馬を買えずにいる一豊に嫁入りの持参金十両を差し出します。 織田信長が行った「馬揃え」(...
#銅像・記念碑
-
337. 片岡沈下橋現存する仁淀川の沈下橋では、河口に二番目に近い。県道301号線として、現在も生活道として利用されており、付近では火振り漁も行われています。33.57099 133.2851
現存する仁淀川の沈下橋では、河口に二番目に近い。県道301号線として、現在も生活道として利用されており、付近では火振り漁も行われています。
#景観(川)
#建築
-
338. ふるさと海岸(久礼外港)久礼八幡宮の正面に広がる太平洋に面した港と海岸の景観が楽しめます。久礼湾・双名島の眺めが人気で、気象条件が合うと「だるま朝日」や「海霧」が見られるので、写真スポットとしても人気です。33.32869 133.23235
久礼八幡宮の正面に広がる太平洋に面した港と海岸の景観が楽しめます。久礼湾・双名島の眺めが人気で、気象条件が合うと「だるま朝日」や「海霧」が見られるので、写真スポットとしても人気です。
#景観(海)
-
339. 村の駅ひだか高知市から車で約30分ほどの場所にある村の駅です。日高村特産のトマトなど村内産の新鮮な野菜、芋ケンピやトマトソースなどの加工食品などを販売しています。とまとおでんも人気です。また、店内には飲食店(2店舗)や国宝の一つ「金銅荘環頭大刀」のレプリカの展示もしています。33.531364 133.3549
高知市から車で約30分ほどの場所にある村の駅です。日高村特産のトマトなど村内産の新鮮な野菜、芋ケンピやトマトソースなどの加工食品などを販売しています。とまとおでんも人気です。また、店内には飲食店(2店舗...
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
340. 道の駅 ゆすはら太郎川公園全体が道の駅となっている複合型施設。33.38833 132.94496
レストラン、露天風呂も完備した温泉、木造の室内型温水プール、木の香りただようギャラリー、地元産の商品が数多く並ぶ市場をはじめ、キャンプ場に自然学習館まで整っています。
太郎川公園全体が道の駅となっている複合型施設。 レストラン、露天風呂も完備した温泉、木造の室内型温水プール、木の香りただようギャラリー、地元産の商品が数多く並ぶ市場をはじめ、キャンプ場に自然学習館ま ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
341. 四万十民俗館旧大野見村の歴史、伝統的な漁具、農具、鍛冶屋等の道具を展示しています。33.33664 133.13968
昭和9年に建てられた米貯蔵庫を改築した建物は、今では珍しい二重構造の屋根を持っています。
旧大野見村の歴史、伝統的な漁具、農具、鍛冶屋等の道具を展示しています。 昭和9年に建てられた米貯蔵庫を改築した建物は、今では珍しい二重構造の屋根を持っています。
#ミュージアム
-
342. 御田八幡宮室戸市吉良川町の中心に鎮座する御田八幡宮は、鎌倉時代から続く古式神事「御田祭」で知られる神社です。境内には高知県指定天然記念物ボウランが自生し、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された白壁の町並みと共に、吉良川の歴史と信仰を今に伝えています。33.33222 134.10086
室戸市吉良川町の中心に鎮座する御田八幡宮は、鎌倉時代から続く古式神事「御田祭」で知られる神社です。境内には高知県指定天然記念物ボウランが自生し、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された白壁の町並み...
#寺社
-
343. 大堂山展望台高知県大月町の大堂山山頂に位置する大堂山展望台は、柏島と大堂海岸を眺める町屈指の絶景ポイントです。周辺の山々よりも高い標高から360°のパノラマビューが楽しめ、柏島を訪れる際には必見の観光スポットとなっています。32.77219 132.64381
展望台からは、東に白い岩肌の断崖絶壁が続く大堂海岸、西に宿毛市の離島である沖の島や鵜来島、そして豊後水道の雄大な海景が広がります。南には果てしなく続く太平洋の水平線が望め、その360°に広がる絶景は訪れる人々を魅了してやみません。
柏島からの帰り道に立ち寄るべきスポットです。
展望台から観音岩までは遊歩道が整備されており、断崖絶壁の迫力ある景観を眺めながらハイキングを楽しめます。
高知県大月町の大堂山山頂に位置する大堂山展望台は、柏島と大堂海岸を眺める町屈指の絶景ポイントです。周辺の山々よりも高い標高から360°のパノラマビューが楽しめ、柏島を訪れる際には必見の観光スポットとなっ ...
#景観(海)
-
344. 朝倉古墳朝倉神社の背後、神奈備(かんなび)型の山容をもつ赤鬼山の東斜面に位置するのが、県指定史跡「朝倉古墳」です。明治初期の開墾作業で発見され、須恵器(すえき)や鉄鏃(てつぞく)、馬具などが出土したと伝えられ、高知平野を支配していた人の古墳と言われています。33.553207 133.47786
現在では、横穴式石室が露出しており、玄室と羨道(せんどう)をあわせた全長は約10.3mと推定されています。特に玄室部分は長さ5.4m、幅2.6mの巨石で構成され、美しく積み上げられた石室は保存状態も良好です。
この古墳は、南国市の「小蓮古墳」「明見1号古墳」と並び、“土佐三大古墳”のひとつとして知られ、歴史や考古学に関心のある方におすすめのスポットです。
朝倉神社の背後、神奈備(かんなび)型の山容をもつ赤鬼山の東斜面に位置するのが、県指定史跡「朝倉古墳」です。明治初期の開墾作業で発見され、須恵器(すえき)や鉄鏃(てつぞく)、馬具などが出土したと伝えら...
#文化財・史跡
-
345. 第25番札所 津照寺(津寺)室津港を見下ろす小高い山に佇む第25番札所「津照寺」。急勾配の石段と竜宮城を思わせる朱色の鐘楼門、本堂からの太平洋の眺望が印象的な霊場です。海を守る「楫取地蔵」(かじとりじぞう)の伝説が今も息づく、四国霊場屈指の絶景スポットです。33.28822 134.14842
室津港を見下ろす小高い山に佇む第25番札所「津照寺」。急勾配の石段と竜宮城を思わせる朱色の鐘楼門、本堂からの太平洋の眺望が印象的な霊場です。海を守る「楫取地蔵」(かじとりじぞう)の伝説が今も息づく、四 ...
#寺社
-
346. 南国市観光協会土佐のまほろばと呼ばれる南国市の楽しい観光情報を発信しています。「なんごく」と誤読されることが多いですが、本来の読み方は「なんこく」です。33.575638 133.6415
土佐のまほろばと呼ばれる南国市の楽しい観光情報を発信しています。「なんごく」と誤読されることが多いですが、本来の読み方は「なんこく」です。
#観光案内所
-
347. なかとさ美術館日本洋画界の先駆者・山本芳翠の滞欧作「洋美人」、黒田清輝の羽子板絵「舞妓図」などの貴重な収蔵品があり、年4期に分けた企画展示で見ることができます。33.32693 133.22762
海の見えるカフェスペースで静かに過ごすのもおすすめです。
黒潮本陣・黒潮工房が同じ丘にあるので、かつおや温泉を一緒に楽しんでいくこともできますよ♪
日本洋画界の先駆者・山本芳翠の滞欧作「洋美人」、黒田清輝の羽子板絵「舞妓図」などの貴重な収蔵品があり、年4期に分けた企画展示で見ることができます。 海の見えるカフェスペースで静かに過ごすのもおすすめ ...
#ミュージアム
-
348. 永瀬ダム物部川水系物部川にある重力式コンクリートダム。堤高87m、堤頂長207m。ダム湖は奥物部湖という名で親しまれ、夏にはダム建設犠牲者の慰霊などを目的に始まった湖水祭が開催されている。33.705807 133.865
物部川水系物部川にある重力式コンクリートダム。堤高87m、堤頂長207m。ダム湖は奥物部湖という名で親しまれ、夏にはダム建設犠牲者の慰霊などを目的に始まった湖水祭が開催されている。
#建築
-
349. 別府農林漁業体験実習館農林漁業体験実習館では、豆腐・こんにゃく作り、そば打ちなど、山里の味作り体験ができます。また、館内には、平家落人伝説の残る物部の人々の農耕用具や狩猟用具、生活雑貨などの歴史民俗資料を多数展示しているスペースがあり、国の重要無形文化財に指定されている「いざなぎ流祈祷」の祭壇を再現したものも見ることができます。33.76458 134.035
天然ニガリを使った「豆腐づくり」、そば粉100%使用の「手打ちそば」、ゆずの効いた「田舎寿司づくり」は一年中受け付けているほか、11~4月の期間は「こんにゃくづくり」、4~5月はイタドリやフキ、ウドなどの「山菜料理」の体験もできます。(体験実習は予約制。)
農林漁業体験実習館では、豆腐・こんにゃく作り、そば打ちなど、山里の味作り体験ができます。また、館内には、平家落人伝説の残る物部の人々の農耕用具や狩猟用具、生活雑貨などの歴史民俗資料を多数展示している...
#ミュージアム
#食の体験
-
賛助会員350. 天然の湯 ながおか温泉露天風呂や泡風呂など数種類の温泉があります。33.590096 133.65083
温水プール、トレーニングルーム、レストランもあり、ゆっくりと過ごすことができる施設です。
露天風呂や泡風呂など数種類の温泉があります。 温水プール、トレーニングルーム、レストランもあり、ゆっくりと過ごすことができる施設です。
#温泉
-
賛助会員351. 須崎市観光協会須崎市の総合観光案内所です。33.392376 133.29266
須崎市の飲食店や観光地の情報はもちろん、ツアーや体験イベントの案内等も行っております。
須崎市の総合観光案内所です。 須崎市の飲食店や観光地の情報はもちろん、ツアーや体験イベントの案内等も行っております。
#観光案内所
-
352. 四万十川学遊館 あきついお世界のトンボ標本約1,000種をメインとする「とんぼ館」と、アカメなど四万十川産魚種をメインに日本や世界の淡水・汽水魚約300種を飼育展示する「さかな館」からなる、自然博物館です。32.98932 132.91542
世界のトンボ標本約1,000種をメインとする「とんぼ館」と、アカメなど四万十川産魚種をメインに日本や世界の淡水・汽水魚約300種を飼育展示する「さかな館」からなる、自然博物館です。
#ミュージアム
-
353. 南国SA(上り)施設内には高知県の豊かな食の魅力を凝縮したレストランやフードコート、お土産コーナーが充実。カツオのたたき定食や土佐赤牛を使った料理など、ご当地グルメを堪能できるのはもちろん、芋けんぴやミレービスケットなどの高知ならではのお土産も豊富に取り揃えています。33.60245 133.61455
高速道路の料金や道案内・サービスエリア情報などもリモートインフォメーションで24時間稼働中。(オペレーターの対応は9:00~17:00)
施設内には高知県の豊かな食の魅力を凝縮したレストランやフードコート、お土産コーナーが充実。カツオのたたき定食や土佐赤牛を使った料理など、ご当地グルメを堪能できるのはもちろん、芋けんぴやミレービスケッ...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#おみやげ
-
354. 道の駅ビオスおおがた情報館高知市方面から土佐西南大規模公園への入口となる浮鞭地区にある、公園施設や観光情報の案内施設。33.03464 133.02695
観光・道路案内、入野松原キャンプ場の受付(NPO砂浜美術館)、浮津キャンプ場の受付((一社)黒潮町観光ネットワーク)、写真展などの企画、その他公園施設の利用案内を行っています。
館内にはミンククジラの標本展示や休憩スペースがあり、多数のチラシやパンフレットも設置しています。
隣には黒潮町が地域の物産などを販売する「物産館」も併設されています。
高知市方面から土佐西南大規模公園への入口となる浮鞭地区にある、公園施設や観光情報の案内施設。 観光・道路案内、入野松原キャンプ場の受付(NPO砂浜美術館)、浮津キャンプ場の受付((一社)黒潮町観光ネット ...
#観光案内所
-
355. 稲叢山標高1506mの稲叢山は、いの町と土佐町の境に位置する平家落人伝説と安徳天皇伝説が残る霊山です。春には頂上付近に自生するシャクナゲとアケボノツツジが咲き誇り、登山道を彩ります。四国山地の雄大な眺望と、眼下に広がる稲村ダムの景観も見どころ。登山経験者向けの本格的な山岳体験が楽しめます。33.74739 133.3583
標高1506mの稲叢山は、いの町と土佐町の境に位置する平家落人伝説と安徳天皇伝説が残る霊山です。春には頂上付近に自生するシャクナゲとアケボノツツジが咲き誇り、登山道を彩ります。四国山地の雄大な眺望と、眼下 ...
#景観(山)
-
356. 白猪谷渓谷吉野川の最源流部にある渓谷。石鎚山脈の中腹にある四国の秘境で、水晶のように透明度の高い水が流れています。33.752274 133.19794
初夏には新緑や青もみじ、秋には紅葉など、四季を通して様々な景色を楽しむことができます。
渓流に沿って遊歩道が整備され、女性や小さな子供でも気軽に無理なくハイキングが楽しむことができます。UFOラインとも非常に近く、終点からおよそ15分ほどで渓谷の入り口(白猪谷オートキャンプ場)まで行くことが可能です。
吉野川の最源流部にある渓谷。石鎚山脈の中腹にある四国の秘境で、水晶のように透明度の高い水が流れています。 初夏には新緑や青もみじ、秋には紅葉など、四季を通して様々な景色を楽しむことができます。 渓流に ...
#景観(川)
-
357. 赤野休憩所地中海風の建物が目をひく休憩所。33.51366 133.83592
屋根の上には、安芸市の特産品「ナス」のオブジェが!
太平洋を一望できる絶景スポットで、夕日もきれいです。
地中海風の建物が目をひく休憩所。 屋根の上には、安芸市の特産品「ナス」のオブジェが! 太平洋を一望できる絶景スポットで、夕日もきれいです。
#景観(海)
#道の駅・休憩所
-
358. 田中良助旧邸資料館田中邸は坂本家の領地の管理を引き受けており、坂本龍馬がよく足を運んだ場所の一つ。良助と兎狩りや碁や将棋を楽しみ、邸宅の横にあった池では、子どもたちとよく水遊びをしたとも伝えられています。33.597862 133.49544
田中邸は坂本家の領地の管理を引き受けており、坂本龍馬がよく足を運んだ場所の一つ。良助と兎狩りや碁や将棋を楽しみ、邸宅の横にあった池では、子どもたちとよく水遊びをしたとも伝えられています。
#ミュージアム
#文化財・史跡
-
359. 八京の一本桜舗装されていない山道を進むと、急に視界が開け、その先に一本の桜が目に飛び込んできます。33.62762 133.6102
周囲にはツツジやひょうたん桜等も植えられており、知る人ぞ知るフォトスポット。
舗装されていない山道を進むと、急に視界が開け、その先に一本の桜が目に飛び込んできます。 周囲にはツツジやひょうたん桜等も植えられており、知る人ぞ知るフォトスポット。
#花・植物
#景観(山)
#作品ゆかりの地
-
360. 佐川町立青山文庫幕末維新の生き証人であった、佐川町出身の元宮内大臣田中光顕(みつあき)が収集した志士たちの書や画などの遺筆コレクションをはじめ、近世・近代の歴史資料を多数収蔵。坂本竜馬・中岡慎太郎・武市瑞山らの維新関係資料や、江戸時代に佐川の領主であった土佐藩筆頭家老深尾家の資料などを展示。定期的に展示替えを行っているので、展示の詳細はホームページでご確認下さい。33.49788 133.28876
幕末維新の生き証人であった、佐川町出身の元宮内大臣田中光顕(みつあき)が収集した志士たちの書や画などの遺筆コレクションをはじめ、近世・近代の歴史資料を多数収蔵。坂本竜馬・中岡慎太郎・武市瑞山らの維新...
#ミュージアム
-
361. 春の里旬の農産物のほか、花や野菜苗、弁当、菓子、手芸品など、幅広い品揃えです。33.503162 133.49269
併設のAコープ店では、日用品、鮮魚、精肉、飲料等も販売されているので、買い物に便利です。
旬の農産物のほか、花や野菜苗、弁当、菓子、手芸品など、幅広い品揃えです。 併設のAコープ店では、日用品、鮮魚、精肉、飲料等も販売されているので、買い物に便利です。
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
362. 六体地蔵関ヶ原の戦いの後、幕府により浦戸城の新領主・山内氏への明け渡しが求められました。その際、旧主のために一領具足が明け渡しに抵抗したのが浦戸一揆です。昭和14年12月、野市町(現香南市)の住職が、浦戸一揆で討ち取られた273名の一領具足を供養するために広く浄財を募り建立されました。33.495434 133.57008
関ヶ原の戦いの後、幕府により浦戸城の新領主・山内氏への明け渡しが求められました。その際、旧主のために一領具足が明け渡しに抵抗したのが浦戸一揆です。昭和14年12月、野市町(現香南市)の住職が、浦戸一揆で ...
#文化財・史跡
-
363. 東山森林公園国道55号線沿いにある、伊尾木洞の奥にある標高360mの山林を整備した自然公園。33.49052 133.94493
展望台からは、安芸市街や太平洋が見渡せ、つつじや桜、もみじなどが植えられて、四季折々に楽しめます。
国道55号線沿いにある、伊尾木洞の奥にある標高360mの山林を整備した自然公園。 展望台からは、安芸市街や太平洋が見渡せ、つつじや桜、もみじなどが植えられて、四季折々に楽しめます。
#景観(山)
#公園
-
364. 酒蔵ホール 葉山の蔵酒造会社の酒蔵だったものを文化施設に改造。瓦屋根や漆喰、大きな梁や酒樽など、酒蔵のイメージが残ります。地元の人達のサークル活動や、町内外からコーラス、ピアノ発表会などの会場としても利用されています。館内には酒造りの道具なども展示されており、季節によっては企画展なども開催されます。33.44451 133.20816
酒造会社の酒蔵だったものを文化施設に改造。瓦屋根や漆喰、大きな梁や酒樽など、酒蔵のイメージが残ります。地元の人達のサークル活動や、町内外からコーラス、ピアノ発表会などの会場としても利用されています。...
#建築
-
365. JR伊野駅JR四国の伊野駅は、改札口や駅前の交差点などが、アニメ映画『竜とそばかすの姫』の重要なスポットのモデルとなった駅です。33.54753 133.43018
JR四国の伊野駅は、改札口や駅前の交差点などが、アニメ映画『竜とそばかすの姫』の重要なスポットのモデルとなった駅です。
#作品ゆかりの地
-
366. 四万十市郷土博物館山内一豊の弟、康豊の居城であった中村城跡に建つ城の形をした博物館で、天守閣(展望台)からは、四万十川、東山を望み、市街地を一望することができます。32.986584 132.9398
館内には、土佐一條家、中村山内家、幕末の志士・坂本龍馬らと親交があった樋口真吉、明治を代表する中村出身の社会主義者・幸徳秋水の遺品などを展示しています。
山内一豊の弟、康豊の居城であった中村城跡に建つ城の形をした博物館で、天守閣(展望台)からは、四万十川、東山を望み、市街地を一望することができます。 館内には、土佐一條家、中村山内家、幕末の志士・坂本 ...
#ミュージアム
-
367. 浄貞寺高知県安芸市に佇む浄貞寺は、戦国時代に土佐国東部で最大の勢力を誇った安芸氏の菩提寺として知られる由緒ある寺院です。文明年間(1469年~1487年)に安芸元親(國虎の父)が創建し、500年以上の歴史を刻んでいます。33.508472 133.89507
安芸氏は戦国時代、土佐七雄の一つとして繁栄した名族です。境内には安芸氏歴代の墓や大氏の先祖を祀る安藝神社があり、当時の栄華を今に伝えています。
江戸時代に再建された浄貞寺山門は「元親山門」「浄貞寺門」の法号で呼ばれ、元親の名を冠した貴重な建造物として知られています。また、山門には橘の紋章が刻まれた瓦や「元親」の文字が残されています。
昭和28年(1953年)に高知県保護有形文化財に指定され、昭和39年(1964年)には保存 ...
高知県安芸市に佇む浄貞寺は、戦国時代に土佐国東部で最大の勢力を誇った安芸氏の菩提寺として知られる由緒ある寺院です。文明年間(1469年~1487年)に安芸元親(國虎の父)が創建し、500年以上の歴史を刻んでいます。 安 ...
#寺社
-
368. 樽の滝(須崎市)ニホンカワウソが最後に発見された川として有名な新荘川の支流にあり、高さ37mの崖の上からダイナミックに流れ落ちる名瀑。滝壺周辺の岩肌がくぼんでおり、裏側から滝を眺めることができる裏見の滝としても知られています。一帯は須崎湾県立自然公園に指定されています。33.408768 133.22118
ニホンカワウソが最後に発見された川として有名な新荘川の支流にあり、高さ37mの崖の上からダイナミックに流れ落ちる名瀑。滝壺周辺の岩肌がくぼんでおり、裏側から滝を眺めることができる裏見の滝としても知られて...
#景観(川)
-
369. 仁淀ブルー観光協議会高知県仁淀川流域6市町村(土佐市・いの町・日高村・佐川町・越知町・仁淀川町)の、自然や歴史文化、伝統産業など、それぞれの観光素材を組み合わせた広域的な着地型旅行商品の組み立てや企画などを行っていて、「仁淀川」を中心にした山から海までの流域6市町村の魅力の発信をしています♪33.512596 133.28656
JR四国・西佐川駅の駅舎の中にあります。
高知県仁淀川流域6市町村(土佐市・いの町・日高村・佐川町・越知町・仁淀川町)の、自然や歴史文化、伝統産業など、それぞれの観光素材を組み合わせた広域的な着地型旅行商品の組み立てや企画などを行っていて、 ...
#観光案内所
-
370. 四万十町立美術館平成12年に図書館の中に併設され開館。四万十町出身・町のゆかりのある芸術家の作品を中心に展覧会を行っている。また、毎年、住民参加型の展覧会「アンデパンダン展」や小中学生を対象とした「読書感想画」などの展覧会を行い、地域に根ざした美術館をテーマとして、四万十町の文化の発展に寄与することを目標としています。33.20872 133.13339
所蔵作品:中澤竹太郎・今西中通 他
平成12年に図書館の中に併設され開館。四万十町出身・町のゆかりのある芸術家の作品を中心に展覧会を行っている。また、毎年、住民参加型の展覧会「アンデパンダン展」や小中学生を対象とした「読書感想画」などの ...
#ミュージアム
-
371. 入田ヤナギ林(四万十川菜の花の森)川沿いにつづく約2kmのヤナギの自然林、その足元には菜の花の絨毯が一面に広がり、優しい春の息吹を感じる事が出来ます。32.99589 132.92023
川沿いにつづく約2kmのヤナギの自然林、その足元には菜の花の絨毯が一面に広がり、優しい春の息吹を感じる事が出来ます。
#花・植物
-
372. 第32番札所 禅師峰寺大同年間(806年頃)僧空海が開いたもので、真言宗豊山派に属します。国の重要文化財の金剛力士像(木造)2体があります。33.52669 133.61148
本尊の空海自作の十一面観音像は船魂観音と呼ばれ、人々が海上安全を祈ったと言われています。
境内からは太平洋の美しい景色を眺めることができます。
大同年間(806年頃)僧空海が開いたもので、真言宗豊山派に属します。国の重要文化財の金剛力士像(木造)2体があります。 本尊の空海自作の十一面観音像は船魂観音と呼ばれ、人々が海上安全を祈ったと言われていま...
#寺社
-
373. 久保谷セラピーロード先人から受け継がれている水路に沿って散策できる、全長3kmの遊歩道。33.31549 132.97295
新林の緑を映した水の流れがゆっくりと動く様を見ながら、小鳥のさえずり、水の流れる音といった心地よい音色を聞くことにより、リラックスできるセラピーロードです。
先人から受け継がれている水路に沿って散策できる、全長3kmの遊歩道。 新林の緑を映した水の流れがゆっくりと動く様を見ながら、小鳥のさえずり、水の流れる音といった心地よい音色を聞くことにより、リラックス ...
#花・植物
-
374. 道の駅 布施ヶ坂国道197号線沿いの道の駅。33.42697 133.09955
店内には津野町ならではの特産品が販売しています。
併設された食堂では、種類豊富でボリューム満点の定食や地元の特産品を使用した「里芋担々麺」・「レモングラスの塩ラーメン」・「ししカツみそラーメン」などここでしか食べることができないメニューをお楽しみいただけます。
また、手づくりアイスやシャーベットも人気で「文旦・しょうが・かぼちゃ・よもぎ」など季節によって種類が変わりますので、ぜひ食べてみてください。
国道197号線沿いの道の駅。 店内には津野町ならではの特産品が販売しています。 併設された食堂では、種類豊富でボリューム満点の定食や地元の特産品を使用した「里芋担々麺」・「レモングラスの塩ラーメン」・「し ...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
375. 万次郎少年像大波を背後にした中濱萬次郎少年と仲間たちの群像(鉄筋コンクリート製)です。漁に出た船が足摺岬の沖合で突然の強風に襲われ、漂着した南海の孤島 鳥島で米国の捕鯨船に救助を求めている様子です。143日間の無人島生活に耐え抜いた5人が描かれています。その後、少年だった萬次郎はアメリカで成長し、幕末維新の日本に大きく貢献することになります。32.78315 132.93242
大波を背後にした中濱萬次郎少年と仲間たちの群像(鉄筋コンクリート製)です。漁に出た船が足摺岬の沖合で突然の強風に襲われ、漂着した南海の孤島 鳥島で米国の捕鯨船に救助を求めている様子です。143日間の無人 ...
#銅像・記念碑
-
376. 土曜市(南国市)昭和44年から始まった南国市の土曜市は、高知市の日曜市に次ぐ歴史を誇ります。33.572166 133.64607
新鮮な野菜や果物、海産物、手作り加工品などが並び、地元の人や観光客でにぎわいます。
昭和44年から始まった南国市の土曜市は、高知市の日曜市に次ぐ歴史を誇ります。 新鮮な野菜や果物、海産物、手作り加工品などが並び、地元の人や観光客でにぎわいます。
#市場・直売所
#高知県産
-
377. 舞川大蛇フジ香南市北部に位置する香我美町舞川地区、樹齢200年をこえる大蛇フジ。5月のシーズンに杉に絡みつき咲き誇る姿は大蛇そのもの。33.64296 133.8603
香南市北部に位置する香我美町舞川地区、樹齢200年をこえる大蛇フジ。5月のシーズンに杉に絡みつき咲き誇る姿は大蛇そのもの。
#花・植物
-
378. 伊尾木洞観光案内所伊尾木洞駐車場内にある観光案内所は、伊尾木洞散策の拠点施設です。洞窟の見どころや注意事項が分かる情報を入手できるほか、建物周辺ではフリーWi-Fiが利用可能。散策の様子をSNSでシェアするのにも便利です。特に人気なのが長靴の無料レンタルサービス。洞窟内は足元が濡れているため、長靴があれば安心して探検を楽しめます。夏場はヘビ対策としてもおすすめです。使用後は洗い場で泥をよく落としてご返却ください。ただし、洞窟内が増水している時は危険ですので、長靴着用時でも入洞はお控えください。快適で安全な伊尾木洞探検をサポートする、必ず立ち寄りたいスポットです。33.49025 133.93231
伊尾木洞駐車場内にある観光案内所は、伊尾木洞散策の拠点施設です。洞窟の見どころや注意事項が分かる情報を入手できるほか、建物周辺ではフリーWi-Fiが利用可能。散策の様子をSNSでシェアするのにも便利です。特に ...
#観光案内所
-
379. 日蓮宗 要法寺高知市・筆山のふもとにある「要法寺(ようぼうじ)」は、日蓮宗の歴史ある寺院。戦国武将・山内一豊の菩提寺として知られ、彼の転封とともに愛知・静岡・高知と移転を重ね、現在地には元禄元年(1688年)に移築されました。33.55323 133.53711
寺内には、日蓮聖人が直筆で記した貴重なお曼荼羅(まんだら)をはじめ、名僧たちが遺した多くの寺宝が伝えられています。四国で唯一とされる遺墨も残ることから、歴史ファンにとっても見逃せないスポットです。
静かな筆山の麓にたたずむ境内は、観光の合間に心落ち着くひとときを過ごすのにもおすすめです。
高知市・筆山のふもとにある「要法寺(ようぼうじ)」は、日蓮宗の歴史ある寺院。戦国武将・山内一豊の菩提寺として知られ、彼の転封とともに愛知・静岡・高知と移転を重ね、現在地には元禄元年(1688年)に移築さ ...
#寺社
-
380. 幡多・マーケット「海辺の日曜市」33.01552 133.00398
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
381. いの大国さま 椙本神社ご祭神は大国主命、素盞鳴命、奇稲田姫の三柱。ご神徳は、福徳開運、商業繁栄など多岐にわたる。33.550594 133.42105
春と秋に大祭があり、土佐の三大祭の一つとして知られる。
古くから伝えられている福俵を手に、福をいただきその年の幸せを祈願する。秋の大祭では「おなばれ」や獅子舞などが繰り広げられる。鎌倉時代に作られた国指定重要文化財「八角形漆塗御輿」のレプリカも披露される。
ご祭神は大国主命、素盞鳴命、奇稲田姫の三柱。ご神徳は、福徳開運、商業繁栄など多岐にわたる。 春と秋に大祭があり、土佐の三大祭の一つとして知られる。 古くから伝えられている福俵を手に、福をいただきその年 ...
#寺社
-
382. 琴ケ浜かっぱ市旬の野菜や果物、地元でつくられたお惣菜などが集まるお店。33.51875 133.80022
地元のさとうきびを使って、江戸時代から伝わる製法で作られる「白玉糖(黒糖)」を使ったお菓子などもあります。
旬の野菜や果物、地元でつくられたお惣菜などが集まるお店。 地元のさとうきびを使って、江戸時代から伝わる製法で作られる「白玉糖(黒糖)」を使ったお菓子などもあります。
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
383. 岩戸の砂留砂留は、河川の保全と水流調節を目的に行う砂防堤の一種で、当地では古くから山間の谷川などに砂留工事が行われました。岩戸の砂留は、天保8年(1837)土佐藩の直営工事である群寄せという方法で行ったという記録があり、今なお現存する貴重な歴史的遺構です。33.46776 133.38295
砂留は、河川の保全と水流調節を目的に行う砂防堤の一種で、当地では古くから山間の谷川などに砂留工事が行われました。岩戸の砂留は、天保8年(1837)土佐藩の直営工事である群寄せという方法で行ったという記録が ...
#文化財・史跡
-
384. 風車の駅 津野町ふるさとセンター大きな風車の羽が目印の「風車の駅」は、ドライブの休憩にぴったり。33.44331 133.19714
店内には津野町ならではの特産品や手づくり雑貨、地元の人が丹精込めて作った新鮮な野菜や果物を販売しています。
安くておいしいものを探しにぜひおいてください。
大きな風車の羽が目印の「風車の駅」は、ドライブの休憩にぴったり。 店内には津野町ならではの特産品や手づくり雑貨、地元の人が丹精込めて作った新鮮な野菜や果物を販売しています。 安くておいしいものを探し ...
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#おみやげ
-
385. 大北川渓谷【紅葉の見ごろ】11月上旬~中旬33.807697 133.44688
紅葉シーズンになると、渓谷全体が赤や黄色に色付き、おすすめです。
【紅葉の見ごろ】11月上旬~中旬 紅葉シーズンになると、渓谷全体が赤や黄色に色付き、おすすめです。
#景観(川)
-
386. 神在居の千枚田棚田が多いことで知られる高知県でも、圧巻のスケールを誇る神在居の千枚田。作家・司馬遼太郎がここを訪れた際、「万里の長城にも負けない遺産」と評したほどの美しく無数に広がる棚田は一見の価値があります。33.38926 132.95529
棚田が多いことで知られる高知県でも、圧巻のスケールを誇る神在居の千枚田。作家・司馬遼太郎がここを訪れた際、「万里の長城にも負けない遺産」と評したほどの美しく無数に広がる棚田は一見の価値があります。
#景観(山)
-
387. 井ノ岬海岸磯釣りで名高い海岸。水深があり、大きい磯物をあげることができます。33.023502 133.09265
磯釣りで名高い海岸。水深があり、大きい磯物をあげることができます。
#景観(海)
-
388. 浜田の泊り屋国指定重要有形民俗文化財。32.971535 132.79465
幕末頃の建築物で、桁行二間、梁間二間、木造高床式平家建で屋根は入母屋造り棧瓦ぶき、柱は栗の自然木を使い、風格のある建物です。
泊り屋は、江戸時代から明治、大正時代にかけて若衆組(わかしゅうぐみ)の拠点となった建物。
当時の若者の風習を知るうえで貴重な遺産となっています。
宿毛市には4つの泊り屋が残っています。
国指定重要有形民俗文化財。 幕末頃の建築物で、桁行二間、梁間二間、木造高床式平家建で屋根は入母屋造り棧瓦ぶき、柱は栗の自然木を使い、風格のある建物です。 泊り屋は、江戸時代から明治、大正時代にかけて ...
#文化財・史跡
-
389. 安芸観光情報センター ~彌太郎こころざし社中~2020年3月28日、三菱グループ創業150周年に合わせて、安芸市出身である岩崎彌太郎の一生涯を追体験できる全長約13mのVRシアターや、船とコンパスをイメージしたタッチパネル式情報収集機器を新たに設置。33.50236 133.90788
また、安芸市を中心に高知県東部地域(芸西村、安田町、北川村、馬路村、田野町、奈半利町、室戸市、東洋町)の観光情報発信や特産品の販売、無料レンタサイクルも行っています。
2020年3月28日、三菱グループ創業150周年に合わせて、安芸市出身である岩崎彌太郎の一生涯を追体験できる全長約13mのVRシアターや、船とコンパスをイメージしたタッチパネル式情報収集機器を新たに設置。 また、安芸市 ...
#観光案内所
-
390. 豊永郷民俗資料館私達の先祖が使用した農耕用具、山林用具等の民具は、貴重な先人の汗と知恵が滲み出る生活遺産であるとともに、貴い文化遺産でもあります。33.792664 133.76956
当資料館に収蔵されている 10,000点あまりの中から、2,595点が昭和57年4月21日付で、土佐豊永郷及び周辺地域の山村生産用具として国の重要有形民俗文化財に指定されています。
2017年GOOD DESIGN AWARD 受賞
私達の先祖が使用した農耕用具、山林用具等の民具は、貴重な先人の汗と知恵が滲み出る生活遺産であるとともに、貴い文化遺産でもあります。 当資料館に収蔵されている 10,000点あまりの中から、2,595点が昭和57年4月21...
#ミュージアム
-
391. 牧野公園明治35年、高知県佐川町出身の植物学者・牧野富太郎博士が、東京染井で見つけたソメイヨシノの苗を送ってこられ、それを地元の有志が青源寺の土手などに植えたことがはじまりの公園。33.4973 133.28964
昭和33年に「牧野公園」の名前となり、中腹には牧野富太郎と佐川町出身の政治家・田中光顕の墓があります。
お花見スポットとしても知られ、日本の桜名所100選にも選ばれています。
明治35年、高知県佐川町出身の植物学者・牧野富太郎博士が、東京染井で見つけたソメイヨシノの苗を送ってこられ、それを地元の有志が青源寺の土手などに植えたことがはじまりの公園。 昭和33年に「牧野公園」の名前...
#花・植物
#公園
-
賛助会員392. 道の駅 ビオスおおがた入野松原の一角にあり、太平洋が一望できる道の駅の物産館「ひなたや」では、黒潮町や周辺地区の特産品、各種変わり種アイスなども販売。また、ひなたや食堂では、地元獲れの魚やカツオたたきバーガーが楽しめます。隣には、周辺地区の情報を発信する情報館が併設されています。歩いてすぐの砂浜には、県内外から多くのサーファーが訪れるサーフスポットです。33.035065 133.02704
入野松原の一角にあり、太平洋が一望できる道の駅の物産館「ひなたや」では、黒潮町や周辺地区の特産品、各種変わり種アイスなども販売。また、ひなたや食堂では、地元獲れの魚やカツオたたきバーガーが楽しめます...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
賛助会員393. 物産館 サンリバー四万十四万十市中心街にある大型産直市場。地元の新鮮野菜、土佐湾で獲れた魚の干物や加工品、四万十市を中心に高知県下の土産物などが充実。県外発送も可能。32.980793 132.94476
四万十市中心街にある大型産直市場。地元の新鮮野菜、土佐湾で獲れた魚の干物や加工品、四万十市を中心に高知県下の土産物などが充実。県外発送も可能。
#市場・直売所
#高知県産
#おみやげ
-
賛助会員394. 高知黒潮ホテル高知黒潮ホテルに併設された「黒潮温泉 龍馬の湯」は、県内最多級の効能を誇るたっぷり湯量が自慢の天然温泉施設です。33.558372 133.70505
地下1,300mから湧き出るアルカリ性の単純温泉は、お肌がツルツルになる〝美肌の湯〟として親しまれています。
高知黒潮ホテルに併設された「黒潮温泉 龍馬の湯」は、県内最多級の効能を誇るたっぷり湯量が自慢の天然温泉施設です。 地下1,300mから湧き出るアルカリ性の単純温泉は、お肌がツルツルになる〝美肌の湯〟として親し...
#温泉
#ホテル
-
賛助会員395. 土佐清水市観光協会土佐清水市内の総合観光案内の窓口。32.781464 132.93271
市内の宿泊施設や観光スポットなど情報提供可能。
市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。
(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットもご用意しています。)
土佐清水市内の総合観光案内の窓口。 市内の宿泊施設や観光スポットなど情報提供可能。 市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。 (英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓...
#観光案内所
-
396. 旧立川番所書院書院は前身である立川下名口番所(たじかわしもみょうくちばんしょ、立川関)までさかのぼり、『日本後紀』によれば延暦16年(797)に街道が整備され、丹治川すなわち立川(たじかわ)に駅が置かれたとあります。これより都と土佐国府をむすぶ官道の要衝として立川駅は利用されていました。33.849762 133.64838
官道を再整備して土佐藩主参勤交代の通路としたのは六代藩主 豊隆公の享保3年(1718)からで、立川番所は土佐路最後の藩主の宿所となりました。立川番所は参勤交代時の本陣として重要視され、岩佐口番所(北川村)、池川口番所(仁淀川町)とならんで土佐の三大番所の一つとなっていきました。
書院は前身である立川下名口番所(たじかわしもみょうくちばんしょ、立川関)までさかのぼり、『日本後紀』によれば延暦16年(797)に街道が整備され、丹治川すなわち立川(たじかわ)に駅が置かれたとあります。こ ...
#文化財・史跡
-
397. 立志社跡高知の中心地・帯屋町の一角にかつて存在した「立志社」は、明治7年に片岡健吉や板垣退助らによって設立された日本初の政社です。33.5602 133.54094
士族の生活救済や子どもたちの教育を目的とし、政治や社会の未来を語り合う討論会を開催。この場所を拠点に、教育機関「立志学舎」や商社、法律研究などさまざまな活動が展開されました。当時の社員は1,000人にも上り、その志はのちの自由民権運動へとつながります。
今は建物は残っていませんが、現地には案内板が設置されており、時代の息吹を感じる歴史散策が楽しめます。
高知の中心地・帯屋町の一角にかつて存在した「立志社」は、明治7年に片岡健吉や板垣退助らによって設立された日本初の政社です。 士族の生活救済や子どもたちの教育を目的とし、政治や社会の未来を語り合う討論会...
#文化財・史跡
-
398. 坂本龍馬先塋の地(才谷龍馬公園と坂本神社)才谷は龍馬の祖先である坂本家初代~三代までが暮らした場所。四代以降、坂本家は高知市内へ移り、「才谷屋」として商売を初め成功。七代のときに身分を買って武士になりました。33.633923 133.65317
公園の奥には、坂本家の祖先を祀る坂本神社があり、二代目彦三郎、三代目太郎左衛門の墓所があります。
坂本家十代目に当たる龍馬は、変名として「才谷梅太郎」と名乗っていたことがあります。
その名にちなんで、才谷龍馬公園には紅梅・白梅が植えられており、春先には見事に花を咲かせます。(見頃は2月中旬~3月上旬)
才谷は龍馬の祖先である坂本家初代~三代までが暮らした場所。四代以降、坂本家は高知市内へ移り、「才谷屋」として商売を初め成功。七代のときに身分を買って武士になりました。 公園の奥には、坂本家の祖先を祀 ...
#花・植物
#公園
#文化財・史跡
#銅像・記念碑
-
399. 道の駅 田野駅屋鉄道「ごめん・なはり線」田野駅と一体となった道の駅。地元の産品が集まる直販コーナーや軽食コーナーを併設し、小さな田野町のすべてがぎゅっと詰まった施設です。33.43024 134.00792
位置的にも高知県東部のほぼ真ん中となる当施設の情報発信コーナーでは、様々な「生」の情報が入手できます。
鉄道「ごめん・なはり線」田野駅と一体となった道の駅。地元の産品が集まる直販コーナーや軽食コーナーを併設し、小さな田野町のすべてがぎゅっと詰まった施設です。 位置的にも高知県東部のほぼ真ん中となる当施 ...
#道の駅・休憩所
#レストラン・食堂
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
400. JR安和駅須崎市にあるJR安和(あわ)駅は、目の前に広がる海の景観が人気の無人駅。33.367146 133.25883
駅のすぐそばには海が広がり、ホームに立つと、穏やかな波音とともに開放的な景色が迎えてくれます。
特に夕暮れ時には、列車と海、そして沈みゆく夕日が織りなす美しい風景が広がり、写真撮影スポットとしても人気です。
座面が少し斜めになっている「らぶらぶベンチ」も設置されています。
須崎市にあるJR安和(あわ)駅は、目の前に広がる海の景観が人気の無人駅。 駅のすぐそばには海が広がり、ホームに立つと、穏やかな波音とともに開放的な景色が迎えてくれます。 特に夕暮れ時には、列車と海、そし...
#景観(海)
-
401. 家地川公園毎年3月中旬から4月上旬にかけて、家地川ダムのダム湖の両岸の約300本のソメイヨシノが見ごろを迎え、多くの花見客が訪れます。33.16649 133.07321
最も見頃の時期に行われる「家地川桜まつり」では、郷土芸能や地元特産品の販売も行われます。
毎年3月中旬から4月上旬にかけて、家地川ダムのダム湖の両岸の約300本のソメイヨシノが見ごろを迎え、多くの花見客が訪れます。 最も見頃の時期に行われる「家地川桜まつり」では、郷土芸能や地元特産品の販売も ...
#花・植物
#公園
-
402. 大たびの滝海津見神社の裏手にあるこの滝の高さは12mほどで、滝壺の広さは、約15平方メートル、深さはどれほどあるのか判らない。水は、滝壺で二つに分かれ、更に数メートル累々たる巨岩の間に落下しています。33.747704 133.20135
海津見神社の裏手にあるこの滝の高さは12mほどで、滝壺の広さは、約15平方メートル、深さはどれほどあるのか判らない。水は、滝壺で二つに分かれ、更に数メートル累々たる巨岩の間に落下しています。
#景観(川)
-
403. 八王子公園八王子宮の隣にある八王子公園は、桜の名所として古くから知られ、桜のシーズンには多くの花見客で賑わいます。また、シーズン中はボンボリが点灯され、夜桜も楽しめます。33.611385 133.68793
八王子宮の隣にある八王子公園は、桜の名所として古くから知られ、桜のシーズンには多くの花見客で賑わいます。また、シーズン中はボンボリが点灯され、夜桜も楽しめます。
#花・植物
#公園
-
404. 長平庵のひょうたん桜(老桜樹)長平庵には中平備後守常定と併せて馬頭観音が祀ってあり、敷地内に常定の墓石もあります。33.389915 132.88867
境内にあるひょうたん桜(老桜樹)は町の天然記念物に指定されていて、3月下旬から4月上旬頃が見頃です。
長平庵には中平備後守常定と併せて馬頭観音が祀ってあり、敷地内に常定の墓石もあります。 境内にあるひょうたん桜(老桜樹)は町の天然記念物に指定されていて、3月下旬から4月上旬頃が見頃です。
#花・植物
-
405. 魚梁瀬丸山公園花の名所で、遊具のほか日帰り入浴温泉の森林保養センター、お食事処魚梁瀬杉の家などがあり、かつての木材の運搬に使われていた魚梁瀬森林鉄道も走っています。森林鉄道は乗車や運転の体験をすることができます。(日曜・祝日のみ)33.61387 134.11072
花の名所で、遊具のほか日帰り入浴温泉の森林保養センター、お食事処魚梁瀬杉の家などがあり、かつての木材の運搬に使われていた魚梁瀬森林鉄道も走っています。森林鉄道は乗車や運転の体験をすることができます。...
#公園
-
406. 岩屋川渓谷岩屋川は天狗の森と鳥形山のほぼ中間にある引割峠に源を発し、やがて仁淀川へと注ぐ四国カルスト県立自然公園の一画。春には新緑、秋には紅葉が奇岩・巨岩を彩り、土佐の名水40選にも選ばれた清流は滝となり淵となって、大自然の造形美を見せてくれます。近くには、平家落人伝説を伝える都の集落や、しだれ桜や秋葉まつりで有名な中越家や市川家、秋葉神社が点在し、上流部には国の天然記念物「大引割・小引割」も見られます。33.53182 133.0574
岩屋川は天狗の森と鳥形山のほぼ中間にある引割峠に源を発し、やがて仁淀川へと注ぐ四国カルスト県立自然公園の一画。春には新緑、秋には紅葉が奇岩・巨岩を彩り、土佐の名水40選にも選ばれた清流は滝となり淵とな ...
#景観(川)
-
407. 風の市高知自動車道・南国ICからすぐ、道の駅南国「風良里」内にある直販所。33.611122 133.64195
秋のタケノコ「四方竹」や山菜など、中山間地域ならではの特産品が並び、地元の方にはもちろん、県外からの観光客にも人気です。
高知自動車道・南国ICからすぐ、道の駅南国「風良里」内にある直販所。 秋のタケノコ「四方竹」や山菜など、中山間地域ならではの特産品が並び、地元の方にはもちろん、県外からの観光客にも人気です。
#市場・直売所
-
408. いの町紙の博物館いの町は古くから「紙の町」として栄えてきました。33.54787 133.42339
仁淀川の清流の水をふんだんに使って、良質な土佐和紙が製造されています。
いの町紙の博物館では、紙の歴史や原料から土佐和紙ができるまでの工程をパネルや現物でわかりやすく展示。
職人による伝統の技法「流し漉き」の実演、色紙やはがきを作れる「紙漉き体験」も人気です。
また、絵画・版画・美術工芸用などの土佐和紙をはじめ、各種紙製品を販売しています。
いの町は古くから「紙の町」として栄えてきました。 仁淀川の清流の水をふんだんに使って、良質な土佐和紙が製造されています。 いの町紙の博物館では、紙の歴史や原料から土佐和紙ができるまでの工程をパネルや現...
#ミュージアム
-
409. 馬路村魚梁瀬 西川渓谷魚梁瀬集落から千本山登山口までの県道370号千本山魚梁瀬線の石仙から西川に沿って続く渓谷。33.654495 134.08658
東川と西川の両渓流があり、いずれも清流に映える紅葉が素晴らしい景色です。
魚梁瀬集落から千本山登山口までの県道370号千本山魚梁瀬線の石仙から西川に沿って続く渓谷。 東川と西川の両渓流があり、いずれも清流に映える紅葉が素晴らしい景色です。
#景観(川)
-
410. 足摺岬観光案内所営業時は、観光ボランティア会の方が対応。32.72581 133.01976
市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。
(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットもご用意しています。)
営業時は、観光ボランティア会の方が対応。 市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。 (英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットもご用意しています。)
#観光案内所
-
411. 濱口雄幸像高知生まれの政治家で、第27代の内閣総理大臣 濱口雄幸の銅像が五台山公園に建立されています。33.54754 133.5744
風貌と篤実な人柄から〈ライオン宰相〉と呼ばれていました。
「政治は物質面だけではなく、国民の精神も豊かにするのが任務。そのためには政治家が袖を正さなければならない」と語り、大蔵大臣、内務大臣、内閣総理大臣、立憲民政党総裁などを歴任しました。
高知生まれの政治家で、第27代の内閣総理大臣 濱口雄幸の銅像が五台山公園に建立されています。 風貌と篤実な人柄から〈ライオン宰相〉と呼ばれていました。 「政治は物質面だけではなく、国民の精神も豊かにするの...
#銅像・記念碑
-
412. 安芸国虎の墓戦国時代、安芸地方を治めた豪族安芸氏。その最後の武将国虎は四国統一をめざす長宗我部元親との合戦に敗れ、部下の命と領民の安全をひきかえに淨貞寺に入り自刃しました。33.508472 133.89507
場内には、高さ1.4mの大きな五輪塔の国虎の墓があり、その両わきには、国虎に殉じた家老、有沢石見や黒岩越前の墓が立っています。
国虎の墓は、昭和3年県の有形文化財に指定され、また淨貞寺山門は、昭和39年市の有形文化財に指定されています。
戦国時代、安芸地方を治めた豪族安芸氏。その最後の武将国虎は四国統一をめざす長宗我部元親との合戦に敗れ、部下の命と領民の安全をひきかえに淨貞寺に入り自刃しました。 場内には、高さ1.4mの大きな五輪塔の国虎 ...
#文化財・史跡
-
413. 三嶋神社・神幸橋梼の木が多いこの地を、津野山郷の開祖・津野経高が梼原と名づけ、居城を築き梼原宮首に伊豆(静岡県)より三嶋神社を観請したと言われています。秋には、国の重要無形民俗文化財に指定されている津野山神楽が奉納され、境内には、津野家代々を祀る「津野神社」、樹齢約400年の「朝鮮松」、桂月大町芳衛書の「鎮座千年碑」、木で作られた「神馬」があります。33.39643 132.92781
三嶋神社のすぐ横には、坂本龍馬脱藩の道が通っています。
三嶋神社へ架けられた神幸橋(みゆきばし)は、梼原町の木材をふんだんに使用しており、美しく風情があります。
梼の木が多いこの地を、津野山郷の開祖・津野経高が梼原と名づけ、居城を築き梼原宮首に伊豆(静岡県)より三嶋神社を観請したと言われています。秋には、国の重要無形民俗文化財に指定されている津野山神楽が奉納...
#建築
#寺社
-
414. 中村時計博物館世界各国の時計約2,500点を集めた私設の博物館。ぜんまい式の懐かしい柱時計や懐中時計等が展示されています。33.57666 133.64522
世界各国の時計約2,500点を集めた私設の博物館。ぜんまい式の懐かしい柱時計や懐中時計等が展示されています。
#ミュージアム
-
415. 手結港土佐藩の家老の野中兼山によって完成した日本初の本格的「堀り込み港」で、建設から365年を経た石積みの港で、建設当時の岸壁が残る風情のある港です。33.52817 133.7572
1650~1657年の着工・完成と伝わっており、南北約110m、東西約50m、水深は干潮時で約3mという江戸時代初期では最大級の港でした。
海岸の岩礁地帯の入江を掘削して造られています。
近代化の波を経て、漁船が係留され今も使われ続けている現役の港です。
土佐藩の家老の野中兼山によって完成した日本初の本格的「堀り込み港」で、建設から365年を経た石積みの港で、建設当時の岸壁が残る風情のある港です。 1650~1657年の着工・完成と伝わっており、南北約110m、東西約50...
#景観(海)
-
416. 第28番札所 法界山 高照院 大日寺聖武天皇の勅願により行基が本尊の大日如来を刻み開創、その後弘法大師が本尊の縁日28日にちなみ、第28番札所に定めたといわれています。33.57789 133.70543
江戸時代には土佐藩の祈願所として栄えましたが、明治の廃仏毀釈により廃寺となり、明治17年(1884)に再興しました。
本尊の大日如来像と寺宝の聖観音立像はともに国の重要文化財。
大日如来像は、高さ147cmの寄木造で平安時代の作。聖観音像は、高さ171.5cmで平安時代の作。
聖武天皇の勅願により行基が本尊の大日如来を刻み開創、その後弘法大師が本尊の縁日28日にちなみ、第28番札所に定めたといわれています。 江戸時代には土佐藩の祈願所として栄えましたが、明治の廃仏毀釈により廃寺...
#寺社
-
賛助会員417. 大月町観光協会魅力あふれる町!大月町の観光情報を集めた観光案内所。32.828587 132.70932
町内にてイベントの開催や大月町の情報を県内外に発信しています。
魅力あふれる町!大月町の観光情報を集めた観光案内所。 町内にてイベントの開催や大月町の情報を県内外に発信しています。
#観光案内所
-
賛助会員418. 四万十町観光協会四万十町内の観光案内を行っています。33.21071 133.1366
まち歩き体験やレンタサイクル、コインロッカーなど、観光のお客様に便利にご利用いただけるよう整備しています。
無料の観光パンフレットや地図、イベント情報を掲示・配布しておりますので、観光のお客様以外にもお遍路さんや地元住民にもお越しいただいています。
訪日外国人旅行客の対応も可能です。
四万十町内の観光案内を行っています。 まち歩き体験やレンタサイクル、コインロッカーなど、観光のお客様に便利にご利用いただけるよう整備しています。 無料の観光パンフレットや地図、イベント情報を掲示・配 ...
#観光案内所
-
賛助会員419. 四万十市観光協会四万十市内の観光地や飲食店、宿泊施設の紹介をはじめとした観光案内全般を行っています。32.983925 132.94423
各種パンフレットや地図を配架しており、四万十川観光遊覧船のお得なチケット、Shimanto Ashizuri Bus Passのお取扱いもございます。
また、通年でレンタサイクル、夏季限定でライフジャケットの貸出をしています。
レンタサイクルは全部で5種類、約80台を取り揃えており、英語での貸出対応も可能です。
四万十市内の観光地や飲食店、宿泊施設の紹介をはじめとした観光案内全般を行っています。 各種パンフレットや地図を配架しており、四万十川観光遊覧船のお得なチケット、Shimanto Ashizuri Bus Passのお取扱いもございま ...
#観光案内所
-
420. 大心劇場安田町の山の中にある小さな映画館。33.465763 133.99481
ポスターや手書き看板など、昭和の雰囲気が懐かしく、味があります。
喫茶店「喫茶豆でんきゅう」もあります。
安田町の山の中にある小さな映画館。 ポスターや手書き看板など、昭和の雰囲気が懐かしく、味があります。 喫茶店「喫茶豆でんきゅう」もあります。
#アミューズメント
-
421. 大谷のクスノキ須崎市野見漁港から北へ約300mの須賀神社境内に、推定樹齢2000年を誇る巨大なクスノキがそびえています。根元周囲約25m、樹高約25mの大木で、大正13年(1924年)に国の天然記念物に指定された四国最大級のクスノキです。33.385883 133.3183
主幹には大きな空洞があり、その中に楠神様が祀られています。病弱な者も健康になると伝えられ、乳幼児の成長や健康祈願に訪れる人が多い霊験あらたかな御神木です。祠は空洞の中にあり、参拝者は中に入って祈願できるようになっています。
暴風により大きな基幹の一部が折れて補修されていますが、現在も大小数本の幹が残り、枝葉は健康で樹勢は旺盛です。2000年の歳月を生き抜いた生命力が、今も訪れる人々を見守り続けています。
須崎市野見漁港から北へ約300mの須賀神社境内に、推定樹齢2000年を誇る巨大なクスノキがそびえています。根元周囲約25m、樹高約25mの大木で、大正13年(1924年)に国の天然記念物に指定された四国最大級のクスノキです。 主...
#花・植物
-
422. 姫倉城跡-姫倉月見山月見山にある戦国時代の城跡。60mの断崖の上に築かれ、現在、本丸跡が残っています。33.539032 133.74402
月見山にある戦国時代の城跡。60mの断崖の上に築かれ、現在、本丸跡が残っています。
#文化財・史跡
-
423. 長沢の滝春は新緑、秋は紅葉の景色が美しい落差約34メートルの滝。33.430565 132.99539
滝口がハートの形に見えることから、恋のパワースポットとも!
滝の前に架かる橋や周辺の自然との調和が美しく、風情があります。
春は新緑、秋は紅葉の景色が美しい落差約34メートルの滝。 滝口がハートの形に見えることから、恋のパワースポットとも! 滝の前に架かる橋や周辺の自然との調和が美しく、風情があります。
#景観(川)
-
424. 桂浜観光案内所ガイドマップやパンフレットでより詳しく桂浜公園を知ることができます。33.499195 133.57489
ガイドボランティアがお困りごとにお応えします。
ガイドマップやパンフレットでより詳しく桂浜公園を知ることができます。 ガイドボランティアがお困りごとにお応えします。
#観光案内所
-
425. 仁淀川町観光協会高知県の奇跡の清流「仁淀川」の最上流域、愛媛県との県境に位置する町の観光案内所です。33.57454 133.16785
高知県の奇跡の清流「仁淀川」の最上流域、愛媛県との県境に位置する町の観光案内所です。
#観光案内所
-
426. 安並水車の里四万十川支流・後川の麻生に築かれた全長160m・幅11mの井堰を起点に、秋田・安並・佐岡・古津賀の四ヶ村へ水を引く「四ヶ村溝」。33.007126 132.93019
かつては鮮やかな“カッタン・コットン”の音とともに無数の水車が田に水を汲み上げていましたが、現在も数基が当時の姿を伝えています。
観光用に復元された水車群と、季節ごとに咲き誇るあじさいが織り成す風景は、静かな田園の趣をいっそう引き立てます。整備された水車公園を散策しながら、悠久の農業用水路と里山の彩りをお楽しみください。
四万十川支流・後川の麻生に築かれた全長160m・幅11mの井堰を起点に、秋田・安並・佐岡・古津賀の四ヶ村へ水を引く「四ヶ村溝」。 かつては鮮やかな“カッタン・コットン”の音とともに無数の水車が田に水を汲み上げ...
#花・植物
#景観(川)
-
427. 才谷屋跡才谷屋は郷士坂本家の本家で、三代目の弟・八兵衛守之が、寛文6年(1666年)に長岡郡才谷村から出て来て質屋を始め、後に酒屋や諸品売買業へと商いを拡大していきました。元禄から享保にかけて驚異的に発展し、城下屈指の豪商にまで成長。幕末は武士相手の質屋である「仕送屋」を営んでいました。33.55715 133.52277
才谷屋はもともと大浜姓を名乗っていたが、明和4年(1767年)初代の太郎五郎の墓を建てた時には坂本姓を刻んでいます。
才谷屋は郷士坂本家の本家で、三代目の弟・八兵衛守之が、寛文6年(1666年)に長岡郡才谷村から出て来て質屋を始め、後に酒屋や諸品売買業へと商いを拡大していきました。元禄から享保にかけて驚異的に発展し、城下 ...
#文化財・史跡
-
428. 円教寺の大イチョウ円教寺境内にあるイチョウは、推定樹齢500年、周囲5.7m、樹高約15m。33.39059 133.28233
市指定の天然記念物。
円教寺境内にあるイチョウは、推定樹齢500年、周囲5.7m、樹高約15m。 市指定の天然記念物。
#花・植物
-
429. 池川神社高知県仁淀川町池川土居地区の高台に鎮座する池川神社は、池川郷の産土神社として古くから地域を見守ってきました。建久2年(1191年)に安部肥前守藤原宗春らが当地に移り、同5年に神社を勧請したと伝えられています。33.60892 133.16995
毎年11月23日の秋季大祭では、土佐三大神楽の一つに数えられる池川神楽が奉納されます。文禄2年(1593年)頃には完成されていたとされ、420年以上の歴史を持つ土佐最古の神楽として雅を伝えています。
社家の安部家を中心に代々継承されてきた神事芸能で、記紀に因る詞章を持つ13演目から構成されています。
池川神社の社紋は「土佐柏」を使用しています。これは当神社が代々、国守の武運長久の祈祷所として奉仕してきたことから、天保年間...
高知県仁淀川町池川土居地区の高台に鎮座する池川神社は、池川郷の産土神社として古くから地域を見守ってきました。建久2年(1191年)に安部肥前守藤原宗春らが当地に移り、同5年に神社を勧請したと伝えられています。 ...
#寺社
-
430. 能勢達太郎生誕地碑達太郎は幼少時から英才の聞こえが高く、12歳のとき田野学館に入りました。15歳で高知へ出て藩校教授館に入り、さらに武市半平太の道場に入門しました。33.427456 134.01749
江戸へ遊学し、佐藤一斎・安積艮斎に学び、文久3年(1863年)入京し、名和宗助と変名しました。
また北添佶磨らと蝦夷地などを視察。禁門の変では長州藩の忠勇隊に属して戦うが敗北、真木和泉ら16人の同士と共に自刃しました。享年23。
この碑の隣には、土佐の国司だった紀貫之が京都に帰る途中、奈半の泊に立ち寄った事を記念して建てられた「那波泊」と書かれた石碑があります。
達太郎は幼少時から英才の聞こえが高く、12歳のとき田野学館に入りました。15歳で高知へ出て藩校教授館に入り、さらに武市半平太の道場に入門しました。 江戸へ遊学し、佐藤一斎・安積艮斎に学び、文久3年(1863年) ...
#銅像・記念碑
-
431. 小金滝「小金滝」は、天高く険しく切り立った岸壁から一直線に流れ落ちる水が美しい、落差80~100mを誇る四国でも最大級の滝です。33.7937 133.42497
その景色は、水量や季節により大きく変化し、梅雨や紅葉の季節には特に雄大さ美しさが際立ちますのでおすすめです。
「小金滝」は、天高く険しく切り立った岸壁から一直線に流れ落ちる水が美しい、落差80~100mを誇る四国でも最大級の滝です。 その景色は、水量や季節により大きく変化し、梅雨や紅葉の季節には特に雄大さ美しさが際 ...
#景観(川)
-
432. 奥物部ふるさと物産館2025年にリニューアルオープン。33.69583 133.87495
1階はレストラン、2階はフリースペースになっており、食事を楽しみながら美しい山々と物部川の景色を楽しめます。
地元の味が買えるお店や川魚が味わえるお店もあります。
2025年にリニューアルオープン。 1階はレストラン、2階はフリースペースになっており、食事を楽しみながら美しい山々と物部川の景色を楽しめます。 地元の味が買えるお店や川魚が味わえるお店もあります。
#市場・直売所
#レストラン・食堂
-
433. 藤村製絲記念館絹文化を支え、長きに渡って操業を続けてきた製糸工場の跡地に生まれた記念館。33.427917 134.02539
2005年に操業を停止した工場の跡地には、近代の製糸業に関する資料などが展示されています。
絹文化を支え、長きに渡って操業を続けてきた製糸工場の跡地に生まれた記念館。 2005年に操業を停止した工場の跡地には、近代の製糸業に関する資料などが展示されています。
#文化財・史跡
#ミュージアム
-
434. 臼碆黒潮が⽇本で⼀番最初に接岸する場所といわれ、渦を伴いながらの激しい流れは実に雄⼤。⾒事な花崗岩の断崖は、磯釣りのメッカとしても知られており、釣りバカ⽇誌の撮影にも使われました。32.733307 132.97644
また、漁師が豊漁と航海安全に恵まれるように作られた神社「龍宮神社」があり、花崗岩の断崖絶壁が広がるパワースポットになっています。
黒潮が⽇本で⼀番最初に接岸する場所といわれ、渦を伴いながらの激しい流れは実に雄⼤。⾒事な花崗岩の断崖は、磯釣りのメッカとしても知られており、釣りバカ⽇誌の撮影にも使われました。 また、漁師が豊漁と航 ...
#景観(海)
#ジオスポット
-
435. 無人島長平の像高知県香南市香我美町岸本出身の野村長平(1762-1821)は、天明5年(1785年)、米の運搬中に遭難し、絶海の孤島・鳥島で13年間を生き抜いた人物です。「無人島長平」「東洋のロビンソン・クルーソー」として知られています。33.5393 133.73694
冬の大西風に遭い、黒潮に乗って12日後に鳥島へ漂着。仲間は全員死亡し、単独生活を開始。アホウドリの肉と卵を食料に、卵の殻に雨水を溜めて生き延びました。
3年後、大坂と日向国からの漂流者が合流し、最大18名のコミュニティを形成。救助を諦めた一行は自力脱出を決意し、流木や漂着船の部材で9mの船を建造。岩盤を削って道を開き、船を海へ下ろすことに成功しました。
寛政9年(1797年)6月、14名全員で鳥島を脱出。長平は後の漂流 ...
高知県香南市香我美町岸本出身の野村長平(1762-1821)は、天明5年(1785年)、米の運搬中に遭難し、絶海の孤島・鳥島で13年間を生き抜いた人物です。「無人島長平」「東洋のロビンソン・クルーソー」として知られています。 ...
#銅像・記念碑
-
436. 岩崎弥太郎の銅像岩崎弥太郎の銅像は、三菱グループの創設者であるの彼の生家近くに海に背を向け、山を向いて立っているのが特徴です。33.526184 133.90076
幕末から明治にかけて活躍し、日本の近代化に大きく貢献しました。そんな彼の故郷に対する深い思いと、故郷安芸から世界に羽ばたいた偉大な功績を称えるために、この銅像が建立されました。
岩崎弥太郎の銅像は、三菱グループの創設者であるの彼の生家近くに海に背を向け、山を向いて立っているのが特徴です。 幕末から明治にかけて活躍し、日本の近代化に大きく貢献しました。そんな彼の故郷に対する ...
#銅像・記念碑
-
437. 道の駅 大月大月町の観光情報やイベント情報、また旬の食材、おみやげ、特産品、うまいものなどの大月ならではの情報を発信しています。32.828884 132.70943
大月町の観光情報やイベント情報、また旬の食材、おみやげ、特産品、うまいものなどの大月ならではの情報を発信しています。
#市場・直売所
#道の駅・休憩所
#高知県産
#おみやげ
-
438. 樫西海岸(弁天島)海食洞が特徴的な弁天島は、潮が引くと渡ることができます。32.786083 132.72386
浅瀬もあり、小さいお子様連れにも安心できるスポットです。
近くにキャンプ場もあり、夏場はキャンプを楽しむ人でにぎわっています。
海食洞が特徴的な弁天島は、潮が引くと渡ることができます。 浅瀬もあり、小さいお子様連れにも安心できるスポットです。 近くにキャンプ場もあり、夏場はキャンプを楽しむ人でにぎわっています。
#景観(海)
-
439. 白浜海水浴場東洋町は室戸阿南国定公園のほぼ中央、33.54235 134.29486
白浜海水浴場は、美しい遠浅の海水浴場です。
岸から約50メートル程浅瀬が続きます。
また湾になっていることもあり、外海が荒れても波は静かで、特に小さなお子様を連れた家族の方におすすめです。
東洋町は室戸阿南国定公園のほぼ中央、 白浜海水浴場は、美しい遠浅の海水浴場です。 岸から約50メートル程浅瀬が続きます。 また湾になっていることもあり、外海が荒れても波は静かで、特に小さなお子様を連れた ...
#景観(海)
#海あそび
-
440. 掛橋和泉邸掛橋和泉は那須常吉の次男で名を吉長といい、梼原村の神官の掛橋因幡に養われました。志士たちの旅費を借財してまで調達しました。享年28歳。かつての掛橋和泉邸は、現在、吉村虎太郎が務めた梼原村庄屋の屋敷地跡に移築されています。中二階の小部屋や、奥の間にある床の間右側には脱出口などがあります。33.391754 132.9291
掛橋和泉は那須常吉の次男で名を吉長といい、梼原村の神官の掛橋因幡に養われました。志士たちの旅費を借財してまで調達しました。享年28歳。かつての掛橋和泉邸は、現在、吉村虎太郎が務めた梼原村庄屋の屋敷地跡 ...
#文化財・史跡
-
441. 銚子滝33.812965 133.3796
#景観(川)
-
442. 桜の広場毎年春にはソメイヨシノが咲き誇り、お花見を楽しむ人たちでにぎわいます。33.57039 133.70592
3月下旬~4月上旬の17:30~22:00には、ぼんぼりが点灯し夜桜も楽しめます。
毎年春にはソメイヨシノが咲き誇り、お花見を楽しむ人たちでにぎわいます。 3月下旬~4月上旬の17:30~22:00には、ぼんぼりが点灯し夜桜も楽しめます。
#花・植物
#公園
-
443. 黒尊渓谷【紅葉の見ごろ】11月上旬~中旬33.127396 132.67662
四万十川の支流で最もきれいな支流黒尊川、その支流沿いにブナやクマササの原生林を有する黒尊渓谷では、夏は岩清水で涼をとり、秋は渓谷の紅葉を楽しめます。八面山、三本杭をたどる遊歩道は3時間半の道程です。
【紅葉の見ごろ】11月上旬~中旬 四万十川の支流で最もきれいな支流黒尊川、その支流沿いにブナやクマササの原生林を有する黒尊渓谷では、夏は岩清水で涼をとり、秋は渓谷の紅葉を楽しめます。八面山、三本杭をた...
#景観(川)
-
444. 白髪山(香美市)ナナカマドやダケカンバが群生する登山口から天然ヒノキの巨木を見ながら入山。コースも分かりやすく、ゆっくりと登山を満喫できます。山頂付近には、笹原のじゅうたんが広がり、頂上北側の大岩からは間近に三嶺、遠くに剣山、眼下には西熊渓谷を一望できます。33.809982 133.99307
ナナカマドやダケカンバが群生する登山口から天然ヒノキの巨木を見ながら入山。コースも分かりやすく、ゆっくりと登山を満喫できます。山頂付近には、笹原のじゅうたんが広がり、頂上北側の大岩からは間近に三嶺、...
#景観(山)
-
445. 牧野富太郎生誕地の碑司牡丹の酒造や数多くの古民家が残る上町地区の一角に生誕碑があります。33.499023 133.28665
牧野富太郎はここで、酒造業「岸屋」のひとり息子として生まれました。
司牡丹の酒造や数多くの古民家が残る上町地区の一角に生誕碑があります。 牧野富太郎はここで、酒造業「岸屋」のひとり息子として生まれました。
#銅像・記念碑
-
446. 鹿島ケ浦佐賀港一帯を鹿島ヶ浦とよび、港の入口に相対して、鹿島・巌島の二つの島が、美しい風景を描きだしています。島の周囲には岩礁が多く、絶好の磯釣り場となっています。33.072475 133.10886
佐賀港一帯を鹿島ヶ浦とよび、港の入口に相対して、鹿島・巌島の二つの島が、美しい風景を描きだしています。島の周囲には岩礁が多く、絶好の磯釣り場となっています。
#景観(海)
-
447. 韮ヶ峠龍馬脱藩の道についてはいくつかの説があり、沢村惣之丞が脱藩道筋を書いた文書「覚 関雄之助口供之事」によると、文久2年(1862年)3月26日、龍馬は四万川から韮ヶ峠を経て脱藩したことが記されています。33.474083 132.83809
今でも当時の面影が色濃く残っており、龍馬を敬愛する多くの人々がこの道を歩いています。 韮ヶ峠から和ヶ峠を越える宿場までの街道は、文化庁選定の「歴史の道百選」の一つとなっています。
龍馬脱藩の道についてはいくつかの説があり、沢村惣之丞が脱藩道筋を書いた文書「覚 関雄之助口供之事」によると、文久2年(1862年)3月26日、龍馬は四万川から韮ヶ峠を経て脱藩したことが記されています。 今でも当...
#文化財・史跡
-
448. 叶崎土佐清水市域の西端、大月町との境に近い岬で、先端に近く緑の中に白亜の灯台が建ち、さえぎるものもない大海原と、脚下には飛沫を上げて白く泡立つ岩礁が巧みに配置されています。いかにも南国土佐にふさわしい、明るくひらけた景勝の岬です。32.746742 132.80206
土佐清水市域の西端、大月町との境に近い岬で、先端に近く緑の中に白亜の灯台が建ち、さえぎるものもない大海原と、脚下には飛沫を上げて白く泡立つ岩礁が巧みに配置されています。いかにも南国土佐にふさわしい、...
#景観(海)
-
449. 八畳岩田中家へ遊びに来た坂本龍馬はこの岩の上にのぼり、良助と一緒になって酒などを飲み、将来について語り合いながらよく遠くの景色を見ていたと言われます。ここからは高知城を中心とした市街地、浦戸湾、五台山、そのむこうの海まで見通すことができます。33.597862 133.49544
田中家へ遊びに来た坂本龍馬はこの岩の上にのぼり、良助と一緒になって酒などを飲み、将来について語り合いながらよく遠くの景色を見ていたと言われます。ここからは高知城を中心とした市街地、浦戸湾、五台山、そ...
#景観(山)
-
450. 宿毛まちのえき林邸林家は近代日本で初めて、林有造、譲治、迶と三代続けて大臣を輩出し、親類の吉田茂(政治家)、竹内明太郎(小松製作所(現コマツ)創業者)らと共に近代日本の発展をリードした一家です。32.93816 132.73077
林邸は林有造の邸宅として明治22年(1889年)に建設され、幡多地域における自由民権運動の本拠地として重要な役割を担いました。
2017年に宿毛市へ寄贈され、翌年には地域の人達の活動や歴史が未来へ紡がれていく住民活動と交流の場、新たな歴史観光施設として生まれ変わり、カフェスペースも併設されています。
林家は近代日本で初めて、林有造、譲治、迶と三代続けて大臣を輩出し、親類の吉田茂(政治家)、竹内明太郎(小松製作所(現コマツ)創業者)らと共に近代日本の発展をリードした一家です。 林邸は林有造の邸宅とし ...
#建築
#カフェ・スイーツ
-
451. さかわ観光協会(うえまち駅)佐川町の観光案内や情報発信を行っています。33.49886 133.2879
佐川町内の観光案内パンフレットはもちろん近隣の市町村等の観光パンフレットもあります。
隣の旧浜口家住宅ではカフェや特産品・お土産物の販売も行っています。
佐川町の観光案内や情報発信を行っています。 佐川町内の観光案内パンフレットはもちろん近隣の市町村等の観光パンフレットもあります。 隣の旧浜口家住宅ではカフェや特産品・お土産物の販売も行っています。
#観光案内所
-
452. 興津海水浴場環境省選定の「快水浴場百選」に選ばれた美しい海水浴場です。33.16549 133.20683
遠浅で、家族で楽しめる海水浴場です。
環境省選定の「快水浴場百選」に選ばれた美しい海水浴場です。 遠浅で、家族で楽しめる海水浴場です。
#景観(海)
#海あそび
-
453. 吉村虎太郎の銅像吉村虎太郎は1837(天保8)年に津野山郷芳生野の庄屋に生まれました。24歳のときに土佐勤王党に加盟し、勤王の志に燃えて二度の脱藩を経て天誅組を組織し、総裁をつとめました。文久三年、大和(奈良県)で兵を挙げ五条代官を討ち取った後、追討軍と転戦、奈良十津川から吉野山へと至り、1863(文久3)年、27歳の若さで討ち死にしました。大政奉還まで4年、天誅組の行動は明治維新のさきがけとなりました。33.394226 133.02528
吉村虎太郎は1837(天保8)年に津野山郷芳生野の庄屋に生まれました。24歳のときに土佐勤王党に加盟し、勤王の志に燃えて二度の脱藩を経て天誅組を組織し、総裁をつとめました。文久三年、大和(奈良県)で兵を挙げ五条...
#銅像・記念碑
-
454. 妹背山標高404m、足摺宇和海国立公園の区域内にあります。古今物語に妹兄島として描かれ舞台となった沖の島の象徴的な山です。近年頂上に展望台を設置、まさに楽園の絶景。32.72779 132.5541
標高404m、足摺宇和海国立公園の区域内にあります。古今物語に妹兄島として描かれ舞台となった沖の島の象徴的な山です。近年頂上に展望台を設置、まさに楽園の絶景。
#景観(山)
-
455. 山内浩像龍河洞鍾乳洞入り口の階段手前に建っているのは、神秘的な龍河洞に関心を持ち、洞内探検に果敢に挑んだ山内浩の銅像。日本の洞穴学とケービングの元祖である山内は、高知県の教員として在職中の昭和6年、千変万化をきわめ延々4kmに及ぶ前人未踏の奥洞である龍河洞を発見しました。33.60321 133.74524
龍河洞鍾乳洞入り口の階段手前に建っているのは、神秘的な龍河洞に関心を持ち、洞内探検に果敢に挑んだ山内浩の銅像。日本の洞穴学とケービングの元祖である山内は、高知県の教員として在職中の昭和6年、千変万化 ...
#銅像・記念碑
-
456. 中浜万次郎の銅像日本の国際化に尽力したジョン万次郎こと中浜万次郎の銅像は足摺岬に立っています。32.72564 133.01958
中浜万次郎は土佐藩中ノ浜村(現在の高知県土佐清水市中浜)の出身。1841(天保12)年、14歳の時に乗り込んだ漁船が難破、無人島(伊豆諸島の鳥島)に漂着、143日間を生き抜き、偶然立ち寄ったアメリカの捕鯨船に救われ、アメリカに渡ることになりました。アメリカでの暮らしを通して英語や航海術等を学び、1851(嘉永4)年、日本(薩摩藩)に帰り着きます。ペリー来航で国中が揺れる中、万次郎の知識と能力は薩摩藩、土佐藩、江戸幕府などで重宝されました。
日本の国際化に尽力したジョン万次郎こと中浜万次郎の銅像は足摺岬に立っています。 中浜万次郎は土佐藩中ノ浜村(現在の高知県土佐清水市中浜)の出身。1841(天保12)年、14歳の時に乗り込んだ漁船が難破、無人島 ...
#銅像・記念碑
-
457. みどり市野菜や仁井田米、牛肉、豚肉、魚、新鮮な農畜産物をふんだんに使った手作り弁当や惣菜などが揃う四万十町の直販所。店内には購入した商品を食べられるスペースもあります。33.21231 133.13872
野菜や仁井田米、牛肉、豚肉、魚、新鮮な農畜産物をふんだんに使った手作り弁当や惣菜などが揃う四万十町の直販所。店内には購入した商品を食べられるスペースもあります。
#市場・直売所
#高知県産
-
458. 賀茂神社(多ノ郷)高知県須崎市多ノ郷甲に鎮座する賀茂神社は、地元の人々から「賀茂さま」と呼ばれ親しまれています。近年は須崎市のキャラクター「しんじょう君」をあしらったお守りで全国的に知られ、初詣や夏祭りなど地域の信仰の中心として古くから愛されてきました。33.41161 133.27728
「触ると幸せになる」といわれるしんじょう君のおへそをあしらった幸福お守りをはじめ、合格祈願、交通安全、学業成就など多彩なお守りを毎年製作しています。製作は11年目を迎え、神社の年間売り上げの約半分はしんじょう君お守りによるもので、屋根の修復など社殿の維持に役立っています。通常サイズ800円のほか、長さ約30cmの特大3,000円、約40cmの巨大1万円と、ユニークなサイズ展開も人気で...
高知県須崎市多ノ郷甲に鎮座する賀茂神社は、地元の人々から「賀茂さま」と呼ばれ親しまれています。近年は須崎市のキャラクター「しんじょう君」をあしらったお守りで全国的に知られ、初詣や夏祭りなど地域の信仰...
#寺社
-
459. 宿毛市立宿毛歴史館幡多地区は高知県の南西に広がる温暖な地域。海、山、川の恵みに抱かれて独自の文化を築き上げてきました。宿毛もまた、この幡多の地に根ざして歴史を重ねてきました。32.938774 132.73038
宿毛歴史館では、宿毛貝塚、曽我山古墳からの出土品、平安・室町・戦国時代の資料、さらに江戸時代から幕末・明治にかけての郷土の歴史を、展示、映像、ジオラマにより分かりやすく紹介しています。
また、「宿毛の21人」をはじめ、幕末から昭和に活躍した宿毛出身の偉人たちも、ゆかりの品とともに展示。昭和の吉田茂元首相、早稲田大学を設立した小野梓、実業家として活躍した竹内綱——。城下町宿毛から数多く世に出た英才たちの足跡に触れ、日本の近代化に果たした宿 ...
幡多地区は高知県の南西に広がる温暖な地域。海、山、川の恵みに抱かれて独自の文化を築き上げてきました。宿毛もまた、この幡多の地に根ざして歴史を重ねてきました。 宿毛歴史館では、宿毛貝塚、曽我山古墳か ...
#ミュージアム
-
460. 島村衛吉の碑と墓島村衛吉は天保5年(1834年)に郷士の家に生まれました。文久元年(1861年)土佐勤王党結成に加わり幹部として活躍しましたが、吉田東洋暗殺の疑いで武市半平太と共に投獄されました。33.53449 133.6727
拷問にも耐えて語ることなく、元治2年(1865年)獄中で命を落としました。
南国市下島浜にある「贈従四位 島村衛吉先生之碑」は三島村下島部落青年団が建立したもので、元は三島神社にあったと言われています。昭和43年に墓があるこの地に移され、墓所の東端に衛吉の墓がひっそりと建っています。
島村衛吉は天保5年(1834年)に郷士の家に生まれました。文久元年(1861年)土佐勤王党結成に加わり幹部として活躍しましたが、吉田東洋暗殺の疑いで武市半平太と共に投獄されました。 拷問にも耐えて語ることなく、元治2年...
#文化財・史跡
#銅像・記念碑
-
461. 佐川駅無人観光案内所JR佐川駅構内にある無人観光案内所。33.50011 133.2925
各種パンフレット有り。
デジタルサイネージで、佐川町の観光案内と牧野博士の紹介をしている。
コインロッカー有り(有料)
JR佐川駅構内にある無人観光案内所。 各種パンフレット有り。 デジタルサイネージで、佐川町の観光案内と牧野博士の紹介をしている。 コインロッカー有り(有料)
#観光案内所
-
462. 片岡健吉銅像日本の自由民権運動において中心的な役割を果たした政治家で、高知県議会議長や衆議院議長も務めた片岡健吉。33.55964 133.53204
銅像の作者は、坂本龍馬像などを作成した本山白雲。台字は吉田茂書。
日本の自由民権運動において中心的な役割を果たした政治家で、高知県議会議長や衆議院議長も務めた片岡健吉。 銅像の作者は、坂本龍馬像などを作成した本山白雲。台字は吉田茂書。
#銅像・記念碑
-
463. 安居渓谷 昇龍の滝平成13年に周りの植林を間伐することにより姿を現しました。落差が約60mあり、水量が多い頃の眺めは、とりわけ雄大です。33.674828 133.17726
平成13年に周りの植林を間伐することにより姿を現しました。落差が約60mあり、水量が多い頃の眺めは、とりわけ雄大です。
#景観(川)
-
464. 片岡直輝・直温生家津野町の偉人、日本の財政界に名を残した片岡直輝・直温兄弟の生家に間取りを似せて復元建設した建物。33.44645 133.19897
瓦葺き平屋建で、邸内では資料や動画等をつかって片岡兄弟の生涯について説明がされています。
生家横には四季折々の花々を楽しむことができる日本庭園が残り、くつろぎといやしの空間が広がります。
ほかにも東側には郷土資料館が建てられています。
津野町の偉人、日本の財政界に名を残した片岡直輝・直温兄弟の生家に間取りを似せて復元建設した建物。 瓦葺き平屋建で、邸内では資料や動画等をつかって片岡兄弟の生涯について説明がされています。 生家横には ...
#文化財・史跡
-
465. しまがわ市場(集落活動センター四万川)33.36066 132.98369
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
466. 内原野公園小高い丘陵地で、ツツジの名所。江戸時代中期、土佐藩の家老で安芸地方を領した五藤家によって整備されました。33.53652 133.91444
南麓には、広さ1万3,000平方メートルほどの弁天池が、小島を浮かべて静かな水面を横たえ、眺めに風致を添えています。
園内の小高いところに「延寿亭」と呼ばれる休憩所があります。 春には「つつじまつり」が開かれ、花見客が多く訪れます。
ツツジの見ごろは4月中旬。4月下旬から6月にかけては、しょうぶ・あやめも見ごろを迎えます。
小高い丘陵地で、ツツジの名所。江戸時代中期、土佐藩の家老で安芸地方を領した五藤家によって整備されました。 南麓には、広さ1万3,000平方メートルほどの弁天池が、小島を浮かべて静かな水面を横たえ、眺めに風致...
#花・植物
#公園
-
467. みはらのじまんや2010年に村内唯一の食料品店が閉店した後、買い物に困る地域の声に応えて「三原村拠点ビジネス推進協議会」を主体にオープンした『みはらのじまんや』(みはらのじまんや)。日用品、生鮮食品、野菜、お惣菜に加え、お弁当、お土産も揃います。32.913033 132.8452
「地元の味を求めて」足を運べば、三原村ならではの魅力に出会える買い物空間です。
「春のふるさと市」「開店記念祭」「歳末大売出」といったイベントも積極的に開催しており、買い物客のにぎわいや交流の創出に寄与。三原村に暮らす人たちに安心と活気をもたらしている大切な地域の拠点です。
2010年に村内唯一の食料品店が閉店した後、買い物に困る地域の声に応えて「三原村拠点ビジネス推進協議会」を主体にオープンした『みはらのじまんや』(みはらのじまんや)。日用品、生鮮食品、野菜、お惣菜に加え ...
#市場・直売所
-
468. 中岡慎太郎像中岡慎太郎は土佐藩出身の幕末の志士の一人で、陸援隊の隊長として、海援隊長の坂本龍馬とともに活躍しました。1867(慶応3)年11月15日京都河原町の近江屋で龍馬と過ごしていたところを刺客に襲われ、ともに命を落としました(享年30歳)。33.245735 134.17624
銅像は昭和10年、安芸郡青年団が主体となって建てたもので、本山白雲が作りました。
桂浜の坂本龍馬像や、高知城にある山内一豊像も本山白雲によるものです。
中岡慎太郎は土佐藩出身の幕末の志士の一人で、陸援隊の隊長として、海援隊長の坂本龍馬とともに活躍しました。1867(慶応3)年11月15日京都河原町の近江屋で龍馬と過ごしていたところを刺客に襲われ、ともに命を落と...
#銅像・記念碑
-
469. 多気坂本神社多気坂本神社は、古くからこの地にある歴史あふれる神社であり、武内宿禰命(たけうちすくねのみこと)と葛城襲津彦(かづらぎのそつたのみこと)を祭神とする延喜式神名帳にその名を記された古社です。33.43365 134.03035
神興橋は境内入口にあり、大正5年に藤村捕鯨株式会社により奉納された石製の橋です。
また、参道右側には手水舎があり、亀の形をした石製の手水鉢があります。これは大正9年(藤村製絲の創業時)に藤村製絲株式会社および藤村捕鯨株式会社の両社が奉納したものです。
多気坂本神社は、古くからこの地にある歴史あふれる神社であり、武内宿禰命(たけうちすくねのみこと)と葛城襲津彦(かづらぎのそつたのみこと)を祭神とする延喜式神名帳にその名を記された古社です。 神興橋は ...
#寺社
-
470. 物部川県下3大一級河川の1つで、香美市~香南市~南国市を流れ、山間部から美しい渓谷を経て太平洋に注ぐまでの、起伏に富んだ景観のよさと水量の多さは、多くの人々を惹きつけてやみません。33.644978 133.75746
アユ釣りのシーズンともなると、川のあちこちは釣り糸を垂らした人々であふれます。
県下3大一級河川の1つで、香美市~香南市~南国市を流れ、山間部から美しい渓谷を経て太平洋に注ぐまでの、起伏に富んだ景観のよさと水量の多さは、多くの人々を惹きつけてやみません。 アユ釣りのシーズンともな ...
#景観(川)
-
471. 土佐山田町平成日曜市(香美市)毎週日曜日の早朝から開かれる香美市の日曜市。33.603527 133.68622
新鮮な朝穫れの野菜から雑貨や総菜などのお店が並びます。
毎週日曜日の早朝から開かれる香美市の日曜市。 新鮮な朝穫れの野菜から雑貨や総菜などのお店が並びます。
#市場・直売所
-
472. 瀬戸川渓谷早明浦ダム上流の吉野川支流の瀬戸川にある渓谷。渓谷の中程には、「アメゴが登れず引き返す」と言われるアメガエリの滝があります。上流にはロックフィルダムの稲村ダムがあり、紅葉も素晴らしいです。33.720627 133.40422
早明浦ダム上流の吉野川支流の瀬戸川にある渓谷。渓谷の中程には、「アメゴが登れず引き返す」と言われるアメガエリの滝があります。上流にはロックフィルダムの稲村ダムがあり、紅葉も素晴らしいです。
#景観(川)
-
473. 轟公園清流四万十川を眼下に望む公園には、町のシンボルである石の風車をはじめ、フィールドアスレチックや屋外ステージがあります。33.182713 132.97238
4月中旬~5月には、およそ3,000本のツツジが見ごろを迎えます。
また、縄文・弥生時代の土器、石器を展示している郷土資料館やヤイロチョウの森ネイチャーセンターなども併設しています。
清流四万十川を眼下に望む公園には、町のシンボルである石の風車をはじめ、フィールドアスレチックや屋外ステージがあります。 4月中旬~5月には、およそ3,000本のツツジが見ごろを迎えます。 また、縄文・弥生時...
#公園
-
474. 神峯山「真っ縦」と呼ばれ、四国遍路の中でも屈指の難所といわれる神峯寺への参拝道。急峻な山道の途中には、約800本ものソメイヨシノが植えられている「桜の名所・九丁公園」があります。神峯寺からさらに登り神峯山の頂上にあるのが「神峯山・空と海の展望公園」。公園内には高さ23mの展望台があり、天気のいい時は室戸岬から足摺岬までを一望。展望台から見る景色は解放感にあふれ、空との一体感を感じられます。33.469822 133.97601
「真っ縦」と呼ばれ、四国遍路の中でも屈指の難所といわれる神峯寺への参拝道。急峻な山道の途中には、約800本ものソメイヨシノが植えられている「桜の名所・九丁公園」があります。神峯寺からさらに登り神峯山の頂...
#景観(山)
-
475. 塩見俊二像(塩見文庫)高知県選出の参議院議員として24年間に亘って活躍した塩見俊二は、知識を尊び読書を愛した人物です。塩見が私費で開設した「塩見文庫」(現・高知県立塩見記念青少年プラザ)の建物の前庭に、彼の功績を讃え、銅像が建立されています。銅像としては珍しく、椅子に深く腰を下ろしてくつろいだ姿勢で、その手にある本には「愛をもちて理想を成す」と刻まれています。33.563576 133.527
高知県選出の参議院議員として24年間に亘って活躍した塩見俊二は、知識を尊び読書を愛した人物です。塩見が私費で開設した「塩見文庫」(現・高知県立塩見記念青少年プラザ)の建物の前庭に、彼の功績を讃え、銅像 ...
#銅像・記念碑
-
476. 野市の三叉野市の三ツ又は町田堰(土佐山田町)からひいた物部川の水を、洪積台地で水の少なかった野市周辺の十善寺溝・町溝・東野溝に分水しているところで、近世野市開発の原点。江戸時代初め、野中兼山の養父直継が開き初め、兼山が完成させました。遊歩道あり。33.576073 133.69379
野市の三ツ又は町田堰(土佐山田町)からひいた物部川の水を、洪積台地で水の少なかった野市周辺の十善寺溝・町溝・東野溝に分水しているところで、近世野市開発の原点。江戸時代初め、野中兼山の養父直継が開き初...
#文化財・史跡
-
477. たのたの温泉泉質はナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉で、切り傷・火傷に効能があります。33.43077 134.0164
美肌成分が多く含まれているので、お肌がスベスベになります。
泉質はナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉で、切り傷・火傷に効能があります。 美肌成分が多く含まれているので、お肌がスベスベになります。
#温泉
-
478. さが谷三里マーケット(黒潮町)農家直売の新鮮な野菜やとれたての鈴漁港の魚、米や惣菜などを取りそろえ、みなさんが「ほっこり」できるマーケットを目指しています。33.13638 133.12418
地域の温かみを感じる直売所で、ぜひお買い物をお楽しみください。
農家直売の新鮮な野菜やとれたての鈴漁港の魚、米や惣菜などを取りそろえ、みなさんが「ほっこり」できるマーケットを目指しています。 地域の温かみを感じる直売所で、ぜひお買い物をお楽しみください。
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
賛助会員479. 土佐市観光協会土佐市の最新観光情報を窓口はもちろんのこと、各種SNSでも発信しています。33.4948 133.42424
お遍路さんの手荷物一時預かりを無料で行っています。
札所までの交通案内等、お気軽にお立ち寄り、お問い合わせください。
土佐市特産品の販売も行っており、御中元・御歳暮のギフト発送も可能です。
土佐市の最新観光情報を窓口はもちろんのこと、各種SNSでも発信しています。 お遍路さんの手荷物一時預かりを無料で行っています。 札所までの交通案内等、お気軽にお立ち寄り、お問い合わせください。 土佐市特産...
#観光案内所
-
賛助会員480. 吉村虎太郎邸明治維新の先駆け、天誅組を組織し、討幕に命を燃やした土佐の四傑のひとりである吉村虎太郎の生家。33.41147 133.02301
津野町文化的景観ガイダンス施設として復元されました。
邸内では、古文書やパネル、映像などで虎太郎の生涯と活躍の紹介がされています。
旬の食材を使った昼食や軽食もぜひご利用ください。
明治維新の先駆け、天誅組を組織し、討幕に命を燃やした土佐の四傑のひとりである吉村虎太郎の生家。 津野町文化的景観ガイダンス施設として復元されました。 邸内では、古文書やパネル、映像などで虎太郎の生涯 ...
#文化財・史跡
#和食
-
481. 勤王六志士の墓梼原町にゆかりの勤王志士である吉村虎太郎、那須信吾、那須俊平、前田繁馬、中平龍之介、掛橋和泉を分霊した墓地。幕末時代に尊皇攘夷論を唱え、国事に奔走して殉死しました。近くには一人一人の経歴などの説明もあります。33.39067 132.92824
梼原町にゆかりの勤王志士である吉村虎太郎、那須信吾、那須俊平、前田繁馬、中平龍之介、掛橋和泉を分霊した墓地。幕末時代に尊皇攘夷論を唱え、国事に奔走して殉死しました。近くには一人一人の経歴などの説明も...
#文化財・史跡
-
482. 西熊渓谷三嶺、白髪山など1,000mを超える山々がそびえる中、澄んだ渓流が森林をぬって走り、四季折々の美しい表情を楽しませてくれます。三嶺山系の西熊渓谷は水量も多く、自然の姿がそのまま残っており、自然休養林に指定されています。33.805008 133.96901
三嶺、白髪山など1,000mを超える山々がそびえる中、澄んだ渓流が森林をぬって走り、四季折々の美しい表情を楽しませてくれます。三嶺山系の西熊渓谷は水量も多く、自然の姿がそのまま残っており、自然休養林に指定さ...
#景観(川)
-
483. 奥大田渓谷吉野川の支流、奥大田川の上流部にある。切り立った渓谷の水は、四季を通じて澄みきっており、特に秋の紅葉は見事で焼えたように赤く川面に映えわたります。33.813908 133.72629
吉野川の支流、奥大田川の上流部にある。切り立った渓谷の水は、四季を通じて澄みきっており、特に秋の紅葉は見事で焼えたように赤く川面に映えわたります。
#景観(山)
#花・植物
-
484. 桃原の牡丹スギ推定樹齢1200年。33.808193 133.75645
老大木であるが樹勢がまだ盛んで、大きな枝が根本近くから分かれ、樹葉は短縮肥厚生してボタンの花を連想するようなところから牡丹スギと呼ばれ親しまれています。
根まわり10.6m、樹高31m。
推定樹齢1200年。 老大木であるが樹勢がまだ盛んで、大きな枝が根本近くから分かれ、樹葉は短縮肥厚生してボタンの花を連想するようなところから牡丹スギと呼ばれ親しまれています。 根まわり10.6m、樹高31m。
#花・植物
-
485. 鶴田塾(少林塾)跡山内容堂に登用された土佐藩の参政吉田東洋は、暴行事件で謹慎処分を受けましたが、謹慎中、この地で鶴田塾を開き後藤象二郎、板垣退助、岩崎弥太郎、福岡孝弟、間崎滄浪ら数多くの人材を育てました。参政復帰後、彼らの多くを藩の重要な役職に取り立てました。33.50159 133.54692
山内容堂に登用された土佐藩の参政吉田東洋は、暴行事件で謹慎処分を受けましたが、謹慎中、この地で鶴田塾を開き後藤象二郎、板垣退助、岩崎弥太郎、福岡孝弟、間崎滄浪ら数多くの人材を育てました。参政復帰後、...
#文化財・史跡
-
486. 稲村ダム稲村ダムは、吉野川の支流・瀬戸川に建設された四国電力唯一のロックフィルダム。本川発電所の上池として機能し、土・岩・砂利の3層構造が水を支えます。平家落人伝説が残る稲叢山の麓に位置し、満々と水をたたえた姿は壮観。ダム愛好家や登山者に人気のスポットです。33.74111 133.37036
稲村ダムは、吉野川の支流・瀬戸川に建設された四国電力唯一のロックフィルダム。本川発電所の上池として機能し、土・岩・砂利の3層構造が水を支えます。平家落人伝説が残る稲叢山の麓に位置し、満々と水をたたえ ...
#建築
-
487. 高知県立 鏡野公園日本さくら名所100選に選ばれた、県下有数の桜の名所。33.618793 133.71916
ソメイヨシノやヤエザクラなど多種の桜を楽しむことができ、全長200メートルのサクラトンネルは人気のスポットになっています。
桜のシーズン中は、ボンボリが点灯され夜桜を楽しむことができ、花便りを聞きつけた花見客たちで賑わいます。
公園内は「レクリエーション広場」と、ヤナセスギやセンダン、クスノキなどの森と遊歩道で構成された「緑のゾーン」があります。
日本さくら名所100選に選ばれた、県下有数の桜の名所。 ソメイヨシノやヤエザクラなど多種の桜を楽しむことができ、全長200メートルのサクラトンネルは人気のスポットになっています。 桜のシーズン中は、ボンボリ ...
#花・植物
#公園
-
488. 小村神社小村神社には、日本で唯一、完全な姿で伝わる最古の宝剣「金銅荘環頭大刀拵・大刀身(こんどうそうかんとうのたちこしらえ・たちみ)」が御神体として奉祀されています。33.54326 133.39293
この宝剣は、金銅と板金による精緻なつくりが特徴で、1958年に国宝に指定されました。一般公開は年に一度、11月15日の秋例大祭のみに限られています。
普段は見ることができないこの貴重な文化財のレプリカは、近隣の「村の駅ひだか」で展示されています。
小村神社には、日本で唯一、完全な姿で伝わる最古の宝剣「金銅荘環頭大刀拵・大刀身(こんどうそうかんとうのたちこしらえ・たちみ)」が御神体として奉祀されています。 この宝剣は、金銅と板金による精緻なつく ...
#寺社
-
489. 熊野神社(南国市)神社の参道約200メートルに渡ってソメイヨシノの桜のトンネルが続いています。33.56552 133.64415
3月下旬には桜色のぼんぼりで彩られます。
神社の参道約200メートルに渡ってソメイヨシノの桜のトンネルが続いています。 3月下旬には桜色のぼんぼりで彩られます。
#花・植物
-
490. 久木ノ森風景林【紅葉の見ごろ】11月上旬~11月中旬33.26006 132.98486
風景林。主な樹種:ヒノキ、ケヤキ、カエデ類。久木ノ森山は夏にはアメゴ釣り、キャンプ、水泳、秋には紅葉狩りと森林浴を行うには格好の場所となっています。
【紅葉の見ごろ】11月上旬~11月中旬 風景林。主な樹種:ヒノキ、ケヤキ、カエデ類。久木ノ森山は夏にはアメゴ釣り、キャンプ、水泳、秋には紅葉狩りと森林浴を行うには格好の場所となっています。
#花・植物
#景観(山)
-
491. ヤ・シィ海水浴(ヤ・シィパーク海水浴場)例年夏には海水浴場が開設されます!33.535587 133.75108
ロッカーやシャワー室が利用でき、浮き輪などのレンタルもあります。
例年夏には海水浴場が開設されます! ロッカーやシャワー室が利用でき、浮き輪などのレンタルもあります。
#景観(海)
#海あそび
-
492. 興津八幡宮中世の時代、土佐一条氏の尊信が厚かったと言われている神社で、県の無形民俗文化財の古式神事(毎年10月15日の秋祭りの御神幸に行われる宮舟(みやぶね)、花取踊、流鏑馬)が行われます。33.16766 133.20909
中世の時代、土佐一条氏の尊信が厚かったと言われている神社で、県の無形民俗文化財の古式神事(毎年10月15日の秋祭りの御神幸に行われる宮舟(みやぶね)、花取踊、流鏑馬)が行われます。
#寺社
-
493. (休館中)旧関川家住宅民家資料館国指定の重要文化財。33.587795 133.57396
文政2年(1819)の建築で、土佐の平地型豪農家の典型で肘屋造。
表門、主屋、道具倉、米倉等が残存しています。
国指定の重要文化財。 文政2年(1819)の建築で、土佐の平地型豪農家の典型で肘屋造。 表門、主屋、道具倉、米倉等が残存しています。
#ミュージアム
#文化財・史跡
-
494. 浮津海水浴場高知市南部に位置する浮津海水浴場は、穏やかな波と広々とした砂浜が特徴で、美しい景観も魅力の海水浴場です。33.03812 133.0399
遠浅で波が静かなため、お子様連れのご家族も安心して楽しむことができます。
シャワーやトイレ、売店なども完備されているので快適に海水浴を満喫できます。
高知市南部に位置する浮津海水浴場は、穏やかな波と広々とした砂浜が特徴で、美しい景観も魅力の海水浴場です。 遠浅で波が静かなため、お子様連れのご家族も安心して楽しむことができます。 シャワーやトイレ、 ...
#海あそび
#景観(海)
-
495. 芸西村伝承館芸西村は黒糖の名産地であり、サトウキビの絞り汁を煮詰める昔ながら伝統製法を守る活動をしています。33.52868 133.81946
館内にはサトウキビを絞る機械や絞った汁を煮詰めるかまどが据え付けられています。
伝統製法の体験も可能で、手作りの黒糖はお土産として持ち帰ることができます。
芸西村は黒糖の名産地であり、サトウキビの絞り汁を煮詰める昔ながら伝統製法を守る活動をしています。 館内にはサトウキビを絞る機械や絞った汁を煮詰めるかまどが据え付けられています。 伝統製法の体験も可能で ...
#ミュージアム
-
496. 香美市立美術館八王子宮のすぐ西隣、「プラザ八王子」の2階にある香美市立美術館は、地元の芸術文化を発信する憩いのスポット。33.61068 133.68762
企画展や収蔵品展が年間5〜6回開かれ、地元作家や郷土にゆかりのある作品が展示されます。入口にある石の風車が目印で、散策ついでに立ち寄る人も多く、アートを身近に楽しめる空間です。
隣接する福祉センターやボランティアセンターとともに、地域の交流拠点として親しまれています。
八王子宮のすぐ西隣、「プラザ八王子」の2階にある香美市立美術館は、地元の芸術文化を発信する憩いのスポット。 企画展や収蔵品展が年間5〜6回開かれ、地元作家や郷土にゆかりのある作品が展示されます。入口に ...
#ミュージアム
-
497. 田ノ口古墳県指定の史跡。西大方駅の北東約1km、国道56号線沿いの田ノ口小学校のすぐ東側山麓にある古墳時代後期(6世紀)の横穴式石室古墳。玄室の一部が残るのみ。須恵器とメノウ製の匂玉[まがたま]が出土しています。33.016064 132.99269
県指定の史跡。西大方駅の北東約1km、国道56号線沿いの田ノ口小学校のすぐ東側山麓にある古墳時代後期(6世紀)の横穴式石室古墳。玄室の一部が残るのみ。須恵器とメノウ製の匂玉[まがたま]が出土しています。
#文化財・史跡
-
498. 新宮馬之助生誕地馬之助は、幼い頃から絵の才能に恵まれ画家を志し河田小龍に入門しましたが、国内の政情の乱れと小龍の語る海外の流れに発憤。家業の陶磁器焼き継ぎの修行を名目に土佐を出たのち、勝海舟の塾に入門しました。33.56662 133.71335
その後、龍馬に従い亀山社中、海援隊に参加し、色白の美男ですぐに上気することから「赤づら馬之助」と呼ばれました。
維新後は北海道開拓に従事するが挫折。のちに海軍大尉に任じられています。
馬之助は、幼い頃から絵の才能に恵まれ画家を志し河田小龍に入門しましたが、国内の政情の乱れと小龍の語る海外の流れに発憤。家業の陶磁器焼き継ぎの修行を名目に土佐を出たのち、勝海舟の塾に入門しました。 そ ...
#文化財・史跡
-
499. 吉井源太翁生家吉井源太翁は製紙技術改良家で、その指導により、いの町を全国的な和紙の生産地に押し上げました。33.551613 133.42471
吉井源太翁は製紙技術改良家で、その指導により、いの町を全国的な和紙の生産地に押し上げました。
#建築
#文化財・史跡
-
500. 白山神社弘仁13年に弘法大師が足摺岬金剛福寺を開創の際、加賀国白山より勧請し、金剛福寺鎮護の社として創立しました。白山権現と称せられ、土地の産土神として信仰が厚く、土佐藩主山内氏も代々尊崇の誠をいたし、道路改修にも国役として工事を行ったといわれます。32.725006 133.01497
弘仁13年に弘法大師が足摺岬金剛福寺を開創の際、加賀国白山より勧請し、金剛福寺鎮護の社として創立しました。白山権現と称せられ、土地の産土神として信仰が厚く、土佐藩主山内氏も代々尊崇の誠をいたし、道路改 ...
#寺社
-
501. 山中家住宅本川地区の西部、長沢ダム湖上流の山間の越裏門に位置する県下最古の山間民家で、国の重要有形民俗文化財に指定されています。33.730366 133.23643
昭和6(1769)年の位牌が残っていることから、18世紀前半(江戸時代中期)の建築と推定されています。
本川地区の西部、長沢ダム湖上流の山間の越裏門に位置する県下最古の山間民家で、国の重要有形民俗文化財に指定されています。 昭和6(1769)年の位牌が残っていることから、18世紀前半(江戸時代中期)の建築と推定さ ...
#建築
#文化財・史跡
-
502. 大渡ダム仁淀川水系仁淀川にある重力式コンクリートダム。堤高96m、堤頂長325m。県内でも有数の茶産地にあり、ダム湖は時折霧がかかることから茶霧湖と名付けられ、春には大勢の見物客が訪れる桜の名所でもあります。33.545002 133.11555
仁淀川水系仁淀川にある重力式コンクリートダム。堤高96m、堤頂長325m。県内でも有数の茶産地にあり、ダム湖は時折霧がかかることから茶霧湖と名付けられ、春には大勢の見物客が訪れる桜の名所でもあります。
#景観(川)
-
503. 高知県立埋蔵文化財センター豊かな自然に恵まれた高知県には、先人たちの歴史と文化遺産が数多く残されています。これらを保護し後世に伝えていくために発掘調査を行い、その成果を遺物展示や各種講座によって広く公開しています。また、古代ものづくり教室では先人たちのものづくりの知恵と技術を体験することができます。33.57169 133.63559
豊かな自然に恵まれた高知県には、先人たちの歴史と文化遺産が数多く残されています。これらを保護し後世に伝えていくために発掘調査を行い、その成果を遺物展示や各種講座によって広く公開しています。また、古代...
#ミュージアム
-
504. 四万十ヤイロチョウの森ネイチャーセンター絶滅危惧種のヤイロチョウの保護・研究を目的とした自然保護施設です。33.183117 132.9726
生息環境の保全や生態調査に取り組んでおり、四万十の森に暮らす多様な生き物たちについてのパネル展示や、映像を通じて学ぶことができます。
また、専門家によるガイドツアーや自然観察会などイベントも開催されており、四万十の豊かな自然を体験できます。
絶滅危惧種のヤイロチョウの保護・研究を目的とした自然保護施設です。 生息環境の保全や生態調査に取り組んでおり、四万十の森に暮らす多様な生き物たちについてのパネル展示や、映像を通じて学ぶことができます ...
#ミュージアム
#体験学習
-
505. 野中兼山邸の碑江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。33.561558 133.53326
藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する等、大きな功績を上げました。
しかし、厳しすぎる姿勢が領民や上級武士の反感を買うなどして失脚、兼山の死後は野中家はお取り潰しとなりました。
高知城追手門の東側、堀の前に石碑があります。
江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。 藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する等...
#銅像・記念碑
-
506. 土佐藩砲台跡国指定の史跡で、須崎市街の南西寄り、海の近くのまちにあります。現在、遺構一帯が西浜公園とされていますが、防壁の石垣が昔のままに残り、幕末の非常時に沸騰した土佐藩の士気をしのぶことができます。33.387608 133.28369
国指定の史跡で、須崎市街の南西寄り、海の近くのまちにあります。現在、遺構一帯が西浜公園とされていますが、防壁の石垣が昔のままに残り、幕末の非常時に沸騰した土佐藩の士気をしのぶことができます。
#文化財・史跡
-
507. 岡本寧浦 塾舎跡安芸郡安田浦の乗光寺に、五代目住職の子として生まれた岡本寧浦は、土佐藩屈指の儒学者として名を馳せた人物。12代藩主山内豊資に知られ藩校教授館の教授となり、13代藩主山内豊熈の信任も受けました。高知城下新町に開いた家塾の門下には岩崎弥太郎、清岡道之助、中江兆民、河田小龍など千人を超えます。33.56237 133.54779
安芸郡安田浦の乗光寺に、五代目住職の子として生まれた岡本寧浦は、土佐藩屈指の儒学者として名を馳せた人物。12代藩主山内豊資に知られ藩校教授館の教授となり、13代藩主山内豊熈の信任も受けました。高知城下新 ...
#文化財・史跡
-
508. 定福寺・定福寺宝物殿724年に名僧行基により開山されたと伝えられる、歴史あるお寺。33.793045 133.76915
本尊阿弥陀如来坐像をはじめ、日本唯一と言われる六体の笑い地蔵、四国最古の聖徳太子像など多くの貴重な文化財が残されており、それらの保護のため2015年に宝物殿が建てられました。
紅葉スポットとしても知られ、秋には参道が見事に赤く染まります。
724年に名僧行基により開山されたと伝えられる、歴史あるお寺。 本尊阿弥陀如来坐像をはじめ、日本唯一と言われる六体の笑い地蔵、四国最古の聖徳太子像など多くの貴重な文化財が残されており、それらの保護のため2...
#寺社
-
509. 新居地区観光交流施設「南風」高知市中心部から車で約20分、サーフィンのメッカとして知られる仁淀川河口の土佐市新居地区に、観光交流施設【南風 -まぜ-】があります。太平洋の雄大な景色を一望できる絶景スポットとして、地元の方にも観光客にも愛されている施設です。33.458546 133.47697
施設の最大の魅力は、太平洋を見渡す抜群のロケーション。展望台からは、仁淀ブルーで有名な仁淀川が太平洋へと注ぐ雄大な景色や、サーファーたちが波と戯れる姿を眺めることができます。
館内の直販所では、高知県内の新鮮な地場産品を多数取り揃えています。地元で採れた野菜や果物、土佐の特産品など、お土産選びにも最適です。
ドライブの休憩スポットや高知観光の情報収集拠点として、気軽にお立ち ...
高知市中心部から車で約20分、サーフィンのメッカとして知られる仁淀川河口の土佐市新居地区に、観光交流施設【南風 -まぜ-】があります。太平洋の雄大な景色を一望できる絶景スポットとして、地元の方にも観光客に ...
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
510. 安芸市立書道美術館安芸市は古くから書道が盛んで、優れた書家を数多く輩出。その風土の中から昭和57年に全国初の公立書道美術館として開館しました。川谷横雲・尚亭兄弟や手島右卿などの安芸市出身の書家作品をはじめ、漢字・かな・篆刻などの第一線で活躍する書家の多種多様な作品を約1,600点収蔵。常設展では約100点を展示しています。毎年、公募展「安芸全国書展」を開催。33.519463 133.91316
安芸市は古くから書道が盛んで、優れた書家を数多く輩出。その風土の中から昭和57年に全国初の公立書道美術館として開館しました。川谷横雲・尚亭兄弟や手島右卿などの安芸市出身の書家作品をはじめ、漢字・かな・ ...
#ミュージアム
-
511. 芳奈の泊り屋県保護有形民俗文化財。32.973145 132.79256
泊り屋は、江戸時代から明治、大正時代にかけて若衆組(わかしゅうぐみ)の拠点となった建物。
当時の若者の風習を知るうえで貴重な遺産となっています。
宿毛市には4つの泊り屋が残っており、芳奈の泊り屋から500mほどの場所にある浜田の泊り屋は、国指定重要有形民俗文化財です。
県保護有形民俗文化財。 泊り屋は、江戸時代から明治、大正時代にかけて若衆組(わかしゅうぐみ)の拠点となった建物。 当時の若者の風習を知るうえで貴重な遺産となっています。 宿毛市には4つの泊り屋が残って...
#文化財・史跡
-
512. 錦山公園能津地区錦山の蛇紋岩地帯、約百町歩(百ヘクタール)にわたり、群生しています。白い花をつけ葉は花より後に出るツツジで、植物学者・牧野富太郎博士によって早くから紹介されました。33.547836 133.34827
能津地区錦山の蛇紋岩地帯、約百町歩(百ヘクタール)にわたり、群生しています。白い花をつけ葉は花より後に出るツツジで、植物学者・牧野富太郎博士によって早くから紹介されました。
#公園
#花・植物
-
513. 平山親水公園国分川水系休場ダム周辺の親水公園で、広場ゾーンと自然ゾーンに分かれ、四季折々に花や緑が美しい野鳥や水生生物観察などが楽しめる公園。また、桜の時期にはダム湖周辺に桜が咲き乱れ、お弁当を広げてお花見を楽しめます。33.650494 133.68785
国分川水系休場ダム周辺の親水公園で、広場ゾーンと自然ゾーンに分かれ、四季折々に花や緑が美しい野鳥や水生生物観察などが楽しめる公園。また、桜の時期にはダム湖周辺に桜が咲き乱れ、お弁当を広げてお花見を楽...
#花・植物
#公園
-
514. お馬神社お馬神社は、須崎市池ノ内にある二股杉の下に建てられ、縁結びにご利益があるとして親しまれています。33.39533 133.28416
お馬神社は、須崎市池ノ内にある二股杉の下に建てられ、縁結びにご利益があるとして親しまれています。
#寺社
-
515. 第27番札所 神峯寺太平洋を一望できる標高620mの神峯山の中腹にあり、景観の美しい寺として知られています。33.46751 133.97511
急坂の参道1kmほど続き、歩き遍路にとって屈指の難所とされてきました。
太平洋を一望できる標高620mの神峯山の中腹にあり、景観の美しい寺として知られています。 急坂の参道1kmほど続き、歩き遍路にとって屈指の難所とされてきました。
#寺社
-
516. 岡豊山歴史公園南国市を一望できる標高97mの岡豊山。33.594955 133.62248
その頂上にあったのが、四国を代表する戦国武将「長宗我部氏」の居城・岡豊城。
城址の一角には、現在歴史民俗資料館が建ち、城址全域は遺構を残しながら公園として整備されている。春には登り口から資料館までを彩る見事な桜も楽しめます。
南国市を一望できる標高97mの岡豊山。 その頂上にあったのが、四国を代表する戦国武将「長宗我部氏」の居城・岡豊城。 城址の一角には、現在歴史民俗資料館が建ち、城址全域は遺構を残しながら公園として整備され ...
#花・植物
-
517. 矢筈山標高1607m。初夏にはウグイスやカッコウの鳴き声が心地よく、山頂付近にはツルギミツバツツジ、トサノミツバツツジ、コメツツジが群生しています。開花期は5月中旬から6月上旬。南麓の笹渓谷も美しいです。33.92322 133.97383
標高1607m。初夏にはウグイスやカッコウの鳴き声が心地よく、山頂付近にはツルギミツバツツジ、トサノミツバツツジ、コメツツジが群生しています。開花期は5月中旬から6月上旬。南麓の笹渓谷も美しいです。
#景観(山)
-
518. 紀夏井邸跡県の史跡。紀夏井は、文徳・清和両天皇に仕えていましたが、866年(貞観8年)応天門の変に連座して土佐に流された紀夏井の住居跡。今も残る父養寺、母代寺という地名は、親孝行だった夏井が父母を弔うために建てた寺があったことが由来。33.58467 133.70459
県の史跡。紀夏井は、文徳・清和両天皇に仕えていましたが、866年(貞観8年)応天門の変に連座して土佐に流された紀夏井の住居跡。今も残る父養寺、母代寺という地名は、親孝行だった夏井が父母を弔うために建てた ...
#文化財・史跡
-
519. 大渡ダム公園(茶霧湖)雄大な大渡ダム周辺の13haと湖面道路沿線約10km間に、桜をはじめ、梅、山茶花、アジサイ、ツツジなどが植樹され、四季を通じて花に親しめる公園として整備されています。33.545948 133.11642
また「秋葉の宿」付近に子ども用のアスレチックがあり、親子で楽しめます。
ダムを眼下に見晴らせる高台には宿泊施設「秋葉の宿」がありご家族でのお食事やご宿泊、各種団体のご宴会や会議、合宿など多目的にご利用できます。
雄大な大渡ダム周辺の13haと湖面道路沿線約10km間に、桜をはじめ、梅、山茶花、アジサイ、ツツジなどが植樹され、四季を通じて花に親しめる公園として整備されています。 また「秋葉の宿」付近に子ども用のアス...
#花・植物
#公園
-
520. 北添佶麿邸跡北添佶麿は、日高村出身の幕末の志士。武市半平太を盟主とする土佐勤王党に参加し、坂本龍馬とも関わりながら、倒幕・攘夷を志し活躍しましたが、1864年に池田屋事件に遭遇し、死亡しました。33.53006 133.3426
JR岡花駅から国道を外れて西へ800mほど進むと、昭和44年3月に建立された「北添佶磨先生誕生之地」と刻記された碑があります。邸跡の現況は畑地となり、邸を語るものはありません。碑の脇に佶磨の経歴と、彼の和歌「おもひきやなき数にだに入らずして又も都の春に遭ふとハ」が彫られた2つの碑があります。
北添佶麿は、日高村出身の幕末の志士。武市半平太を盟主とする土佐勤王党に参加し、坂本龍馬とも関わりながら、倒幕・攘夷を志し活躍しましたが、1864年に池田屋事件に遭遇し、死亡しました。 JR岡花駅から国道を ...
#文化財・史跡
-
521. コスモスとかかしの里奈半利町平地区の、地域の方が手づくりしているコスモス畑。134.03596 33.408245
コスモスと一緒に海の絶景を見ることができ、畑のあちこちにいろんなかかしがいます。
海とコスモスとかかし、きれいな景色をほっこり楽しめます。
奈半利町平地区の、地域の方が手づくりしているコスモス畑。 コスモスと一緒に海の絶景を見ることができ、畑のあちこちにいろんなかかしがいます。 海とコスモスとかかし、きれいな景色をほっこり楽しめます。
#景観(海)
#花・植物
-
522. 第39番札所 延光寺神亀元年(724年)聖武天皇の勅願により行基菩薩が薬師如来を刻んで本尊とし、一寺を開創したのがはじまり。32.96131 132.77402
後に弘法大師が巡錫の際、日光・月光菩薩を安置し、再興しました。
延喜11年(911)に作られたという梵鐘は、重要文化財に指定されている寺宝。赤い亀が背中に乗せて、竜宮城から持ち寄ったものであるといわれています。
神亀元年(724年)聖武天皇の勅願により行基菩薩が薬師如来を刻んで本尊とし、一寺を開創したのがはじまり。 後に弘法大師が巡錫の際、日光・月光菩薩を安置し、再興しました。 延喜11年(911)に作られたという梵鐘は ...
#寺社
-
523. お龍・君枝の銅像高知県芸西村の琴ヶ浜松原に、坂本龍馬の妻「お龍(おりょう)」と妹「君枝」の姉妹像があります。33.51737 133.8033
君枝は海援隊士・菅野覚兵衛と結婚し、この地で暮らしていました。慶応3年(1867年)に龍馬が暗殺された後、お龍は妹が嫁いだ芸西村で一時期を過ごしたと伝えられています。
この像は姉妹の絆とともに、龍馬や覚兵衛を記念する目的で芸西村が建立したもので、琴ヶ浜松原野外劇場の西側にあります。高さ1.7メートルの銅像は、岩崎弥太郎像(安芸市)や維新の門(梼原町)を手がけた著名彫刻家・浜田浩造氏の作品。この姉妹は桂浜にある坂本龍馬像に向かって手をふっています。
高知県芸西村の琴ヶ浜松原に、坂本龍馬の妻「お龍(おりょう)」と妹「君枝」の姉妹像があります。 君枝は海援隊士・菅野覚兵衛と結婚し、この地で暮らしていました。慶応3年(1867年)に龍馬が暗殺された後、お龍は...
#銅像・記念碑
-
524. 塩見俊二像(土佐市民公園)政治への強い使命感と、尽きることのない教育に託した情熱をもって理想を追求し続けた塩見俊二。33.49493 133.42012
彼の遺跡を後世に伝えるため、土佐市公園内に銅像が建立されています。
元参議院議員であった塩見は、私財の全てを投じて塩見文庫を創設。
6万7千冊余の蔵書を高知県に寄贈するとともに、県と土佐市に青少年教育と文化振興のための巨額の資金を贈りました。
政治への強い使命感と、尽きることのない教育に託した情熱をもって理想を追求し続けた塩見俊二。 彼の遺跡を後世に伝えるため、土佐市公園内に銅像が建立されています。 元参議院議員であった塩見は、私財の全てを ...
#銅像・記念碑
-
525. ふるさと海岸(奈半利町)奈半利町ふるさと海岸は、海岸線約1.4kmの港湾海岸です。砂浜が定着するような離岸堤や階段型の護岸整備を行うとともに松の植栽や遊歩道も造られています。また、副次的な効果として離岸堤の背後にサンゴ礁が群生する現象も確認されるなど、地域の憩いの場となっています。33.4157 134.02573
ふるさと海岸を利用した「ちびっこトライアスロン」の会場にもなっています。
奈半利町ふるさと海岸は、海岸線約1.4kmの港湾海岸です。砂浜が定着するような離岸堤や階段型の護岸整備を行うとともに松の植栽や遊歩道も造られています。また、副次的な効果として離岸堤の背後にサンゴ礁が群生す ...
#景観(海)
-
526. 四万十緑林公園「四万十緑林文化都市・窪川」の町づくりの核施設として平成7年にオープンした公園。環境と調和を大切につくられた公園内には、ゴーカート場、アスレチック、野外ステージなど多くのレクリエーション施設があり、休日には多くの人で賑わっています。33.21323 133.12877
「四万十緑林文化都市・窪川」の町づくりの核施設として平成7年にオープンした公園。環境と調和を大切につくられた公園内には、ゴーカート場、アスレチック、野外ステージなど多くのレクリエーション施設があり、 ...
#公園
#花・植物
-
527. 村のえき/集落活動センター結いの里大川村の情報、グルメ、お土産がギュッと詰まった施設。33.78235 133.47458
土日祝日には、土佐はちきん地鶏を使った食堂や、月に1回ラーメンの日もあります。(11:00~LO13:30)
※営業日の詳細はHPをご覧ください。
物販コーナーでは、土佐はちきん地鶏や地元の新鮮な野菜、村のお土産等も購入できます。
村のマップやパンフレットも多数ご用意しております。
また、ドライブ中の休憩はもちろんのこと、ダム湖を抱く景色や豊かな自然には癒されます。
大川村の情報、グルメ、お土産がギュッと詰まった施設。 土日祝日には、土佐はちきん地鶏を使った食堂や、月に1回ラーメンの日もあります。(11:00~LO13:30) ※営業日の詳細はHPをご覧ください。 物販コーナーでは ...
#市場・直売所
#高知県産
#レストラン・食堂
#おみやげ
-
528. 鳥形山森林植物公園稀少な植生の宝庫・鳥形山。山に自生する植物や群生林を保護するために造られた公園内には遊歩道や展望台が整備されています。世界の植物学者・牧野富太郎博士がここで採集した、トリガタハンショウヅルやヒメキリンソウに出会えるかもしれません。33.49183 133.0669
稀少な植生の宝庫・鳥形山。山に自生する植物や群生林を保護するために造られた公園内には遊歩道や展望台が整備されています。世界の植物学者・牧野富太郎博士がここで採集した、トリガタハンショウヅルやヒメキリ...
#景観(山)
#公園
-
529. 安岡家住宅安岡家は文化4年(1807年)時の当主が郷士株を譲り受けた後、代々郷士職を勤めた家柄で、末裔には勤王の志士、覚之助・嘉助兄弟などがいました。33.5784 133.73553
主屋をはじめとする建物群が、旧郷士屋敷の雰囲気を色濃くとどめています。
安岡家は文化4年(1807年)時の当主が郷士株を譲り受けた後、代々郷士職を勤めた家柄で、末裔には勤王の志士、覚之助・嘉助兄弟などがいました。 主屋をはじめとする建物群が、旧郷士屋敷の雰囲気を色濃くとどめてい...
#文化財・史跡
-
530. 植木枝盛誕生の地の碑高知市中須賀のかつての生家跡近くに建立された植木枝盛誕生の地の碑は、自由民権運動を先導した思想家・植木枝盛の足跡を伝えます。33.558716 133.51343
安政4年(1857年)生まれの植木枝盛が構想した『東洋大日本国国憲按』は、最も民主的、急進的な憲法草案でありました。「自由は土佐の山間より出づ」は枝盛の残した言葉として有名です。
生誕100年にあたる昭和32年(1957年)に市民の浄財で建立され、令和3年(2021年)に現在地へ移設されました。高知観光で自由民権運動の歴史に触れられます。
高知市中須賀のかつての生家跡近くに建立された植木枝盛誕生の地の碑は、自由民権運動を先導した思想家・植木枝盛の足跡を伝えます。 安政4年(1857年)生まれの植木枝盛が構想した『東洋大日本国国憲按』は、最も ...
#銅像・記念碑
-
531. 四万十川ふるさと案内所JR江川崎駅構内にあり、列車やバス等を利用する観光客の方に対して観光案内を行っています。33.17807 132.78336
JR江川崎駅構内にあり、列車やバス等を利用する観光客の方に対して観光案内を行っています。
#観光案内所
-
532. 梶ヶ森標高1,399メートル、西に石鎚山系、東に剣山系、そして眼下に吉野川の流れを見る梶ヶ森のロケーションは実に雄大です。33.758606 133.75174
標高1,399メートル、西に石鎚山系、東に剣山系、そして眼下に吉野川の流れを見る梶ヶ森のロケーションは実に雄大です。
#景観(山)
-
533. いけがわ439交流館国道439号線沿いにあり、仁淀川の支流・土居川を眺めながら一息つける場所。地域住民により運営されている交流拠点で、農産物直販所やレストランなどを備えています。春はサクラ並木、夏は土居川で遊ぶ子どもたちの姿など、四季折々の風景が訪れた人の目を楽しませています。33.608067 133.17247
国道439号線沿いにあり、仁淀川の支流・土居川を眺めながら一息つける場所。地域住民により運営されている交流拠点で、農産物直販所やレストランなどを備えています。春はサクラ並木、夏は土居川で遊ぶ子どもたちの...
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
#レストラン・食堂
-
534. 竜串観光案内所営業時は、観光ボランティア会の方が対応。32.78871 132.867
市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。
(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットもご用意しています。)
営業時は、観光ボランティア会の方が対応。 市内の観光情報や観光スポットなどを紹介するパンフレットもご用意しております。 (英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語のパンフレットもご用意しています。)
#観光案内所
-
535. 毘沙門の滝【南国市】三段からなる滝の高さは30m。弘法大師が大津の港に着いた際、滝音に誘われて訪ねたのが、この毘沙門の滝と伝えられ、近くの堂には大師作と伝承される毘沙門天が祀られています。33.60378 133.5943
三段からなる滝の高さは30m。弘法大師が大津の港に着いた際、滝音に誘われて訪ねたのが、この毘沙門の滝と伝えられ、近くの堂には大師作と伝承される毘沙門天が祀られています。
#景観(川)
-
536. 義堂・絶海の像室町期、五山文学の双璧とうたわれた高僧。33.438644 133.08612
共に津野町出身で、夢窓疎石に師事していました。
義堂は関東管領足利基氏や将軍足利義満の信頼も篤く、政治顧問・文学者として大いに活躍しました。
絶海も鎌倉や京都の名刹で修行に励み、1368年より8年間、明に留学しました。
その際には太祖高皇帝(洪武帝)と直接詩のやりとりをし、帰国後も義満の信頼を集め、相国寺の従持や大内義弘反乱の説得などに活躍しています。
室町期、五山文学の双璧とうたわれた高僧。 共に津野町出身で、夢窓疎石に師事していました。 義堂は関東管領足利基氏や将軍足利義満の信頼も篤く、政治顧問・文学者として大いに活躍しました。 絶海も鎌倉や京都...
#銅像・記念碑
-
537. 風の里公園20基の風車が立ち並ぶ風の里公園。33.4505 133.11658
展望台からは、風車とともに山々の景色が見渡せ、天気の良い日には石鎚山や室戸岬まで見ることができます。
その他に風の広場、森林浴の森などが整備されており、気持ちのいい風に吹かれながら景色を楽しむことができます。
20基の風車が立ち並ぶ風の里公園。 展望台からは、風車とともに山々の景色が見渡せ、天気の良い日には石鎚山や室戸岬まで見ることができます。 その他に風の広場、森林浴の森などが整備されており、気持ちのいい風 ...
#公園
-
538. 松葉川渓谷松葉川温泉周辺の渓谷で、春から秋にかけて、渓流釣りや紅葉が楽しめます。33.313267 133.07042
松葉川温泉周辺の渓谷で、春から秋にかけて、渓流釣りや紅葉が楽しめます。
#景観(川)
-
539. 布施ヶ坂の茶畑津野山地域では六蔵茶といわれるお茶の生産が行われていました。そして現在も手入れの行き届いた美しい茶園が広がっています。中でも、布施ヶ坂の茶畑は、陽あたりがいい斜面に美しく並び茶畑の緑が、谷の感じをいっそうやわらかいものにしています。33.423275 133.10432
津野山地域では六蔵茶といわれるお茶の生産が行われていました。そして現在も手入れの行き届いた美しい茶園が広がっています。中でも、布施ヶ坂の茶畑は、陽あたりがいい斜面に美しく並び茶畑の緑が、谷の感じをい...
#景観(山)
-
540. 吉田茂像太平洋戦争後の混乱期に閣総理大臣を務めた(5期・2,679日)政治家です。新憲法制定をはじめ、戦後日本の政治・経済・外交の基礎を作り上げました。33.547276 133.67485
鼻眼鏡に葉巻、白足袋といった風采、時に物議を醸す発言など、個性豊かなイメージで知られます。
この銅像は当初、高知空港の南東にある「緑の広場」に建てられましたが、その後、高知龍馬空港のターミナルビル近くに移設されました。
太平洋戦争後の混乱期に閣総理大臣を務めた(5期・2,679日)政治家です。新憲法制定をはじめ、戦後日本の政治・経済・外交の基礎を作り上げました。 鼻眼鏡に葉巻、白足袋といった風采、時に物議を醸す発言など、個 ...
#銅像・記念碑
-
賛助会員541. 香南市観光協会土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線のいち駅構内にあり、旅行で訪れた方、お遍路さん、地元住民の皆様に日々ご利用いただいている観光協会です。33.56183 133.69809
のいち駅売店をはじめ、香南市ギフトカタログで香南市の特産品の山北みかんや地元で捕れたちりめんじゃこ、四季折々の商品を紹介・販売・発送もしています。
土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線のいち駅構内にあり、旅行で訪れた方、お遍路さん、地元住民の皆様に日々ご利用いただいている観光協会です。 のいち駅売店をはじめ、香南市ギフトカタログで香南市の特産品の山 ...
#観光案内所
-
賛助会員542. 土佐さめうら観光協会国道439号沿いにある道の駅「土佐さめうら」内にある。ここでは、土佐町の地元産品や民工芸品の展示・販売も行う。豊かな自然と早明浦ダムを生かした観光を目指し、「活力のあるまちづくり」活動を推進する嶺北の道案内や観光の見どころを発信しています。33.742626 133.54427
国道439号沿いにある道の駅「土佐さめうら」内にある。ここでは、土佐町の地元産品や民工芸品の展示・販売も行う。豊かな自然と早明浦ダムを生かした観光を目指し、「活力のあるまちづくり」活動を推進する嶺北の道...
#観光案内所
-
賛助会員543. 東洋町観光振興協会日本随一のサーフスポット「生見サーフィンビーチ」や、鮎釣りスポットで有名な「野根川」を有する東洋町。夏には白浜海水浴場に、四国最大級の海上アスレチックも出現。33.54217 134.29146
海、山、川に囲まれたこの町で、豊かな自然を活かした観光事業を発信しています!
様々なパンフレットやイベントのチラシを常設しています。
タブレットをおいているので、MAPや宿泊先への行き方もわかりやすくご案内できます。
日本人スタッフしかいませんが、翻訳アプリを使用し外国人観光客への対応も可能です。
町内各所にあるレンタルサイクルを観光協会にもご用意しています。
■レンタサイクルPIPPA
レンタサイクルの貸出あり。(要アプリダウンロード)
隣接す ...
日本随一のサーフスポット「生見サーフィンビーチ」や、鮎釣りスポットで有名な「野根川」を有する東洋町。夏には白浜海水浴場に、四国最大級の海上アスレチックも出現。 海、山、川に囲まれたこの町で、豊かな自 ...
#観光案内所
-
544. 越知町観光物産館 おち駅平成22年にオープンした越知町観光物産館 おち駅は、越知町で採れた新鮮な野菜や果物、加工品・越知町公式キャラクター『よコジロー』グッズなどを販売しています。33.53045 133.25081
土曜限定『おちかつサンド』日曜限定『土佐あかうしバーガー』おち駅限定の小夏ソフトクリームや月曜と水曜日限定の大判小判焼きなど、ここでしか食べれないものもお楽しみください。
また、施設内にはカフェスペースがあり、物産館で購入したコーヒーやソフトクリームなどを飲食できます。
施設内はフリーWiFiが利用でき、町内や近隣市町村の観光パンフレットなどもございますので、ゆっくりとご利用ください。
平成22年にオープンした越知町観光物産館 おち駅は、越知町で採れた新鮮な野菜や果物、加工品・越知町公式キャラクター『よコジロー』グッズなどを販売しています。 土曜限定『おちかつサンド』日曜限定『土佐あ ...
#市場・直売所
#高知県産
#カフェ・スイーツ
#おみやげ
-
545. 松尾のアコウ足摺岬周辺には亜熱帯の植物が生い茂るが、その代表格が松尾神社境内にあるアコウ。周囲9m、樹高25年、樹齢400年を誇るこの大樹は、大正10年、国の天然記念物に指定されています。32.73479 132.9858
足摺岬周辺には亜熱帯の植物が生い茂るが、その代表格が松尾神社境内にあるアコウ。周囲9m、樹高25年、樹齢400年を誇るこの大樹は、大正10年、国の天然記念物に指定されています。
#花・植物
-
546. 旧竹内家国指定重要文化財。建てられた当初外壁が茅で作られており、日本の古い農家の姿を示す貴重な例とされています。33.193195 132.9707
国指定重要文化財。建てられた当初外壁が茅で作られており、日本の古い農家の姿を示す貴重な例とされています。
#建築
#文化財・史跡
-
547. 野中兼山像江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。33.758533 133.59479
藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する等、大きな功績を上げました。
しかし、厳しすぎる姿勢が領民や上級武士の反感を買うなどして失脚、兼山の死後は野中家はお取り潰しとなりました。
生き残った娘・婉(えん)の生涯を、高知県出身の作家・大原富江が小説『婉という女』で描き、毎日出版文化賞と野間文芸賞を受賞しています。
江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。 藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する ...
#銅像・記念碑
-
548. 高板山「高板山(こうのいたやま)」は、「皇の居た山」に由来すると言われ、安徳天皇御陵跡があります。古来信仰の山であり、神池からの登山道には不動堂などもあります。33.766808 133.86775
春(4月9日)と秋(10月9日)に安徳天皇をしのぶ祭りが行われており、夕刻から火渡りが行われ、参拝者の突く鐘の音色が里にこだまします。
多種多様なツツジが群生しており、特に山頂付近のゴヨウツツジ(シロヤシオ)の樹齢300年を越す大木は見事。花の見ごろは5月で山一帯のツツジが楽しめます。また、秋にはツツジの紅葉が美しく色づきます。
「高板山(こうのいたやま)」は、「皇の居た山」に由来すると言われ、安徳天皇御陵跡があります。古来信仰の山であり、神池からの登山道には不動堂などもあります。 春(4月9日)と秋(10月9日)に安徳天皇をしのぶ...
#景観(山)
-
549. 大座礼山頂上付近の巨大なブナ原生林が壮大です。初心者や小学生でも楽しめる人気のある山です。33.82108 133.3943
頂上付近の巨大なブナ原生林が壮大です。初心者や小学生でも楽しめる人気のある山です。
#景観(山)
-
550. 桜浜海水浴場(土佐清水市 竜串)浜が桜色(ピンク色)に染まっていたので、桜浜と名付けられたといわれています。32.79048 132.8632
現在はピンク色は見られなくなりましたが美しい砂浜で、夏場にはウミガメが産卵に来る場所でもあります。
浜が桜色(ピンク色)に染まっていたので、桜浜と名付けられたといわれています。 現在はピンク色は見られなくなりましたが美しい砂浜で、夏場にはウミガメが産卵に来る場所でもあります。
#海あそび
#景観(海)
-
551. 加茂八幡宮宝永の大地震の時、津波により社殿が浸水し浮くという被害にあいましたが、津波が引くと寸分たがわず元の場所に戻ったという言い伝えが残っています。また、境内には「安政津波の碑」があり、大地震に備えるよう後世への警告を伝えています。33.022755 133.01457
鳥居には、「加茂神社」と「八幡宮」とあり、相殿の形で、八幡宮が祀られています。
宝永の大地震の時、津波により社殿が浸水し浮くという被害にあいましたが、津波が引くと寸分たがわず元の場所に戻ったという言い伝えが残っています。また、境内には「安政津波の碑」があり、大地震に備えるよう後...
#寺社
-
552. 梼原千百年物語り坂本龍馬を支えた那須信吾ら梼原の六志士。33.391376 132.92691
脱藩の道は、日本の未来を切り開いた希望の道。
藤原経高の入国から始まる千百年にわたる梼原の歴史も堪能できます。
坂本龍馬を支えた那須信吾ら梼原の六志士。 脱藩の道は、日本の未来を切り開いた希望の道。 藤原経高の入国から始まる千百年にわたる梼原の歴史も堪能できます。
#ミュージアム
-
553. 豊楽寺薬師堂豊楽寺(ぶらくじ)は正式には大田山大願院豊楽寺といい、神亀元年(724)名僧行基により創建されたものと伝えられています。また別名 柴折薬師とも称され、愛知県の鳳来寺の峰薬師、福島県の常福寺の嶽薬師と共に日本三大薬師の一つに数えられます。33.792007 133.72713
本堂である薬師堂は、四国最古の建造物で桁行、梁間ともに五間の単層入母屋(いりもや)造り、柿葺(こけらぶき、杉板の割板を敷きつめた技法)で勾欄(こうらん、手すり)付きの廻縁(まわりぶち、縁側)を有します。壁は板壁で前面中央の三間は板唐戸の観音開きになり、両脇の一間には連子窓がついています。屋根の勾配はゆるやかで、軒先の反りは美しく優雅です。特に内陣の須彌壇(しゅみだ...
豊楽寺(ぶらくじ)は正式には大田山大願院豊楽寺といい、神亀元年(724)名僧行基により創建されたものと伝えられています。また別名 柴折薬師とも称され、愛知県の鳳来寺の峰薬師、福島県の常福寺の嶽薬師と共に ...
#寺社
-
554. 中島信行生誕地信行は土佐市塚地の郷土の長男として生まれました。誕生地には、「維新の志士 従三位勲二等瑞宝章 男爵 中島信行生誕之地」と刻まれた石碑が建っています。昭和61年3月31日建立。33.47832 133.44278
信行は元治元年(1864年)11月に脱藩。慶応3年(1867年)1月に亀山社中に入り、海援隊にも加わりました。実務の才能が評価され、坂本龍馬の代理として使者を務めました。戊辰戦争前夜には陸援隊に入り高野山挙兵にも参加しました。
信行は土佐市塚地の郷土の長男として生まれました。誕生地には、「維新の志士 従三位勲二等瑞宝章 男爵 中島信行生誕之地」と刻まれた石碑が建っています。昭和61年3月31日建立。 信行は元治元年(1864年)11月に脱...
#文化財・史跡
-
555. 吾岡山文化の森公園国の特別天然記念物で南国市原産であるオナガドリをデザインテーマとした公園。豊かな緑に囲まれた子どもの広場には、ローラー滑り台などの遊具がいっぱい。太平洋が一望でき、近くを飛来する旅客機や空港発着の様子も眼下に見られます。33.56719 133.64389
国の特別天然記念物で南国市原産であるオナガドリをデザインテーマとした公園。豊かな緑に囲まれた子どもの広場には、ローラー滑り台などの遊具がいっぱい。太平洋が一望でき、近くを飛来する旅客機や空港発着の様...
#公園
-
556. 山内容堂公誕生之地 碑父は11代藩主の弟で、容堂は側室の子として生まれました。本家の藩主が急死したため15代藩主の座に就き、その政治手腕により薩摩の島津斉彬らと幕末の四賢候と評されました。慶応3年(1867年)に将軍慶喜に大政奉還を建白。酒と詩を愛し、自らを「鯨海酔候」と称しました。33.560963 133.5346
父は11代藩主の弟で、容堂は側室の子として生まれました。本家の藩主が急死したため15代藩主の座に就き、その政治手腕により薩摩の島津斉彬らと幕末の四賢候と評されました。慶応3年(1867年)に将軍慶喜に大政奉還を...
#銅像・記念碑
-
557. 大滝山日高村総合運動公園の西入口から、展望台を経由して直登するコース。ヒノキ林を抜け、しい、かしなどの急坂を進むと巨岩が見えてきます。頂上直下の広場には高圧鉄塔が立ち、ツツジ等が自生。頂上から少し北側に下った岩場からは加茂地区の平野を一望。頂上から南に100mほど登った広場の近くには石鎚山信仰の祠があります。岩の上からは遠く石鎚山や瓶ケ森が見えます。周辺に胎内くぐりの洞窟、金太郎の力石、山姥の洞窟などが点在。33.51597 133.34175
日高村総合運動公園の西入口から、展望台を経由して直登するコース。ヒノキ林を抜け、しい、かしなどの急坂を進むと巨岩が見えてきます。頂上直下の広場には高圧鉄塔が立ち、ツツジ等が自生。頂上から少し北側に下...
#景観(山)
-
558. (休業中)べふ峡温泉33.763744 134.03076
#温泉
#旅館
-
559. 本川新郷土館高知県いの町本川地区(旧本川村)の本川民俗資料館は、吉野川源流の山間に息づく独自の文化と歴史を紹介する施設です。建物にはいの町有林の杉とヒノキ、土佐しっくい、土佐和紙など地元の伝統素材を使用しています。33.7257 133.30708
大永3年(1523年)発祥の本川神楽は、500年以上続く土佐唯一の「夜神楽」です。11月中旬から12月上旬にかけて各集落の神社で奉納され、神楽面や衣裳、演目の展示を通じてその歴史を体感できます。
室町時代には既に多くの寺堂が建立され、茶の湯の風習もあった本川村。標高1150mの鷹ノ巣山遺跡から出土した弥生式土器(町指定文化財)は、西日本最高地の遺跡からの貴重な資料です。
焼畑農耕、林業、冬の営みなど、自給自足の山里の暮らしを ...
高知県いの町本川地区(旧本川村)の本川民俗資料館は、吉野川源流の山間に息づく独自の文化と歴史を紹介する施設です。建物にはいの町有林の杉とヒノキ、土佐しっくい、土佐和紙など地元の伝統素材を使用しています ...
#ミュージアム
-
560. 長生沈下橋キャンプやカヌーのメッカとして、夏場は多くの観光客が訪れる人気の沈下橋。全長120m、普通車の通行可能。33.194447 132.79105
キャンプやカヌーのメッカとして、夏場は多くの観光客が訪れる人気の沈下橋。全長120m、普通車の通行可能。
#景観(川)
#建築
-
561. 中島観音堂檜の一本造り、彫眼の彩色像の十一観音両像。鎮座されている本殿が開くのは、毎年7月下旬に開催される夏の大祭時のみ。推定樹齢1200年とも言われる金木犀と苔むした境内や、愛らしい地蔵が並ぶお堂は、おだやかな心へと導いてくれる安らぎ空間。33.750256 133.55484
檜の一本造り、彫眼の彩色像の十一観音両像。鎮座されている本殿が開くのは、毎年7月下旬に開催される夏の大祭時のみ。推定樹齢1200年とも言われる金木犀と苔むした境内や、愛らしい地蔵が並ぶお堂は、おだやかな心 ...
#寺社
-
562. 秋葉山毎年3月中旬から下旬は樹齢200年の「秋葉山の山桜」が見頃を迎える。初夏は森林浴、秋には渡り蝶のアサギマダラを見ることができ、一年を通して自然を堪能できます。晴れた日には、香南市を一望できる山頂から雄大な太平洋も望めます。また、山頂を目指す途中には、「塩の道」と呼ばれる歴史ある道に通じる「文代峠」へ向かう林道もあります。33.606125 133.75784
毎年3月中旬から下旬は樹齢200年の「秋葉山の山桜」が見頃を迎える。初夏は森林浴、秋には渡り蝶のアサギマダラを見ることができ、一年を通して自然を堪能できます。晴れた日には、香南市を一望できる山頂から雄大 ...
#景観(山)
-
563. 脱藩志士集合之地碑元治元年(1864年)8月14日、浜田辰弥(田中光顕)、井原広輔、池大六(山中安敬)、那須盛馬(片岡利和)、橋本鉄猪(大橋慎三)の5人の志士が赤土峠に集まり、脱藩したと言われています。33.516476 133.26315
赤土トンネルの入口から山道を登ればすぐの所に「脱藩志士集合之地」の碑があります。
文字は、佐川領主13代深尾隆太郎の筆。
「真心のあかつち坂にまちあわせいきてかへらぬ誓なしてき 田中光顕」
元治元年(1864年)8月14日、浜田辰弥(田中光顕)、井原広輔、池大六(山中安敬)、那須盛馬(片岡利和)、橋本鉄猪(大橋慎三)の5人の志士が赤土峠に集まり、脱藩したと言われています。 赤土トンネルの入口から山...
#銅像・記念碑
-
564. 中江兆民誕生の地の碑中江兆民(1847–1901)は、高知で生まれた思想家で、明治時代の自由民権運動を理論的に支えた重要人物です。その生まれ故郷が、ここ高知市にあります。33.56328 133.54662
土佐藩士の家に生まれた兆民は、若くして長崎や江戸でフランス学を学び、明治4年にはフランスに留学。帰国後は仏学塾を開き、民権思想を日本に広める活動に尽力しました。
明治14年には新聞『東洋自由新聞』を創刊し、自由と平等を重んじるフランス流の政治思想を広め、やがて“東洋のルソー”とも呼ばれるようになります。
その後も政界に進出し、初の衆議院議員選挙で当選しますが、理想と現実のギャップに失望し、まもなく辞職。晩年まで翻訳や執筆活動を続け、代表作にルソーの『民約 ...
中江兆民(1847–1901)は、高知で生まれた思想家で、明治時代の自由民権運動を理論的に支えた重要人物です。その生まれ故郷が、ここ高知市にあります。 土佐藩士の家に生まれた兆民は、若くして長崎や江戸でフラン...
#銅像・記念碑
-
565. 島ノ川渓谷四万十の支流の15km位の渓谷。33.35613 133.10268
3月1日よりアメゴ釣りが、5月15日よりアユの友釣りが解禁となります。
春は山菜、秋は紅葉がすばらしいスポットです。
四万十の支流の15km位の渓谷。 3月1日よりアメゴ釣りが、5月15日よりアユの友釣りが解禁となります。 春は山菜、秋は紅葉がすばらしいスポットです。
#景観(川)
-
566. 鮎の瀬公園ソメイヨシノ約80本の植えられている奈半利川沿いの公園春には、桜が咲き揃い、桜まつりが催されます。33.437687 134.02773
ソメイヨシノ約80本の植えられている奈半利川沿いの公園春には、桜が咲き揃い、桜まつりが催されます。
#公園
-
567. 上林暁文学館現在の黒潮町出身である上林暁は、昭和を代表する私小説家の1人。「明朗なる文学」をめざしながらも、貧窮と戦争、妻の発病とその死、そして自らの大患という不遇な目に遭いましたが、不屈の作家魂と努力、忍耐によって苦難を克服し、私小説、短編ひとすじに歩み続けました。33.022495 133.01321
文学館では、「七度生まれ変わるとも、文学をやりたい」と言い、まさに文学の鬼であったと言える暁の生涯を紹介しています。
現在の黒潮町出身である上林暁は、昭和を代表する私小説家の1人。「明朗なる文学」をめざしながらも、貧窮と戦争、妻の発病とその死、そして自らの大患という不遇な目に遭いましたが、不屈の作家魂と努力、忍耐に...
#ミュージアム
-
568. 村の案内所ひだか日高村の「村の駅ひだか」の駐車場内にある「村の案内所ひだか」です。133.35501 33.53156
日高村観光協会が運営しており、村内・広域の観光情報案内・村内体験観光の実施を行っています。
外国語のできるスタッフは常駐していませんが、翻訳ツールなどを使って可能な限り外国人観光客の対応も行っています。
日高村の「村の駅ひだか」の駐車場内にある「村の案内所ひだか」です。 日高村観光協会が運営しており、村内・広域の観光情報案内・村内体験観光の実施を行っています。 外国語のできるスタッフは常駐していませ ...
#観光案内所
-
569. 香北の自然公園アンパンマンミュージアムの裏山斜面には「香北の自然公園」がある。この公園は、香北町出身のキャスター福留功男さんの、ふるさとに寄せる思いによって生まれました。33.646362 133.78339
約70種類1万4千本もの草花が四季折々にお出迎え。休憩所からは、香北町の中心地を一望することができます。
秋には「フジバカマ」の花が咲き、旅する蝶「アサギマダラ」の吸蜜風景を見ることができるかも。
アンパンマンミュージアムの裏山斜面には「香北の自然公園」がある。この公園は、香北町出身のキャスター福留功男さんの、ふるさとに寄せる思いによって生まれました。 約70種類1万4千本もの草花が四季折々にお出迎 ...
#公園
#花・植物
-
570. 中濱万次郎生誕地・生家高知県土佐清水市中浜はジョン万次郎が14歳まで暮らした場所。木造平屋、茅葺屋根の生家は、現存している生家の写真をもとに土佐清水市内の有志の働きによって集められた募金などで復元されました。32.759342 132.96458
高知県土佐清水市中浜はジョン万次郎が14歳まで暮らした場所。木造平屋、茅葺屋根の生家は、現存している生家の写真をもとに土佐清水市内の有志の働きによって集められた募金などで復元されました。
#文化財・史跡
-
571. 日根野道場跡小栗流・日根野弁治が和術を教えていた道場。龍馬も14歳から19歳まで剣術の修行に打ち込んだ場所です。現在は道場跡を特定できるものはありませんが、築屋敷と呼ばれる場所に開かれたと伝えられています。33.55494 133.52496
周辺には頑丈な石垣や龍馬が泳いだ鏡川が流れており、当時の風景を思い起こさせます。
小栗流・日根野弁治が和術を教えていた道場。龍馬も14歳から19歳まで剣術の修行に打ち込んだ場所です。現在は道場跡を特定できるものはありませんが、築屋敷と呼ばれる場所に開かれたと伝えられています。 周辺には...
#文化財・史跡
-
572. 千本山登山口から西川に架かる千年橋を渡ると、すぐに千本山を代表する「橋の大杉」に出会えます。これは林野庁が指定している森の巨人たち100選に選ばれている杉で、千本山の顔ともいえる存在。樹齢は250年以上、樹高は54m、胸高直径は2m以上もあります。600mほど続く木道の終点から約400mほどで「親子杉」に着きます。ここから巨木が林立する景色に一変。親子杉はその名の通り、大きい杉と小さい杉が密着して生えています。33.674477 134.09671
登山口から西川に架かる千年橋を渡ると、すぐに千本山を代表する「橋の大杉」に出会えます。これは林野庁が指定している森の巨人たち100選に選ばれている杉で、千本山の顔ともいえる存在。樹齢は250年以上、樹高は54m...
#景観(山)
-
573. 庚申堂伝説では「野中兼山がこの地を開墾したとき、負傷者や病人が続出したので修験僧に命じて摂津国四天王寺から仏像を勧請させて祀った」といわれています。33.60748 133.6796
庚申信仰とは、道教、神道、仏教が習合したもので、室町時代以降広く普及しました。
境内にミカドアゲハの食草として知られるオガタマの木があり、市の天然記念物に指定されています。
伝説では「野中兼山がこの地を開墾したとき、負傷者や病人が続出したので修験僧に命じて摂津国四天王寺から仏像を勧請させて祀った」といわれています。 庚申信仰とは、道教、神道、仏教が習合したもので、室町時 ...
#文化財・史跡
-
574. 野村茂久馬翁の頌徳碑高知県の海運・陸運の発展に貢献し、土佐の交通王と呼ばれた実業家・野村茂久馬翁の頌徳碑。生まれ故郷である奈半利の田園を見渡す多気ヶ丘公園にあります。33.4332 134.0294
日露戦役には戦時輸送など、陸海に事業を拡げ、後に土佐の交通王とよばれ、高知県交通バスの前身である野村組自動車部、そして新高知重工業の前身である野村組工作所の創設者となり、四国のバス事業の統合、高知鉄道、土佐商船などの設立に力を尽くしました。
高知県の海運・陸運の発展に貢献し、土佐の交通王と呼ばれた実業家・野村茂久馬翁の頌徳碑。生まれ故郷である奈半利の田園を見渡す多気ヶ丘公園にあります。 日露戦役には戦時輸送など、陸海に事業を拡げ、後に土 ...
#銅像・記念碑
-
575. 法恩寺跨線橋奈半利貯木場の西側、旧街道の北側に位置し、三光院より旧街道へ至る石造アーチ橋(跨線橋)です。森林鉄道を通す際に三光院の高台の斜面を切り崩し、跨線橋が参道の役割をしました。昭和8年、立岡~奈半利線の開通に合わせて建造されました。33.41809 134.02538
奈半利貯木場の西側、旧街道の北側に位置し、三光院より旧街道へ至る石造アーチ橋(跨線橋)です。森林鉄道を通す際に三光院の高台の斜面を切り崩し、跨線橋が参道の役割をしました。昭和8年、立岡~奈半利線の開 ...
#文化財・史跡
#町並み
-
576. 「西の谷第二」バス停アニメ映画『竜とそばかすの姫』で、主人公すずが通学で使うバス停のモデルとなりました。33.573174 133.35448
アニメ映画『竜とそばかすの姫』で、主人公すずが通学で使うバス停のモデルとなりました。
#作品ゆかりの地
-
577. 大樽の滝深い緑に囲まれ、幻想的な雰囲気を醸す大樽の滝は、落差34m、日本の滝百選にも選ばれた県下屈指の名瀑です。33.521152 133.2428
四季折々の趣きに富み、春には桜花と山ツツジ、夏は納涼に、また秋の紅葉も一段と美しく、訪れる人々の目を楽しませてくれます。
4億年以上前の三滝花崗岩が織りなす壮大な景観は、訪れる人々を古代へといざないます。
世界的な植物学者・牧野富太郎博士が昭和9年に73歳で訪れた植物採取会の舞台としても知られ、学術的価値の高いスポットです。
また、土佐藩筆頭家老深尾公の足軽・篠原与助にまつわる古い伝説も残り、美女に化けた大蛇の主との戦いや篠原家に降りかかった災いの物語が今も語り継がれています。
毎年11月には篠原家 ...
深い緑に囲まれ、幻想的な雰囲気を醸す大樽の滝は、落差34m、日本の滝百選にも選ばれた県下屈指の名瀑です。 四季折々の趣きに富み、春には桜花と山ツツジ、夏は納涼に、また秋の紅葉も一段と美しく、訪れる人々の ...
#景観(川)
-
578. 谷干城生誕地(四万十町)四万十町恵美須神社の横にある自然石の碑。昭和9年(1834年)谷将軍銅像建設会が建立しました。33.210083 133.13182
干城は四万十町窪川出身の幕末の志士で、戊辰戦争では、板垣退助と共に土佐藩兵を率いて転戦。西南戦争では熊本鎮台司令長官として活躍しました。
その後は日本初の内閣に入閣するなど政治家としても活躍しました。
谷家は代々神道家・国学者の家で、その先祖には南学中興の祖の谷秦山がいます。干城は一時高知城下の高知市小高坂に居を構えた後、再び窪川に移りましたが、弘化3年(1846年)には父と共にまた小高坂に帰りました。
現在、高知市西久万に谷干城邸跡としてあるのは明治2年(1869年)12月に移転したものです。
四万十町恵美須神社の横にある自然石の碑。昭和9年(1834年)谷将軍銅像建設会が建立しました。 干城は四万十町窪川出身の幕末の志士で、戊辰戦争では、板垣退助と共に土佐藩兵を率いて転戦。西南戦争では熊本鎮台 ...
#文化財・史跡
-
579. 桜づつみ公園桜やアジサイなど約9,500本の季節の花々が咲きます。長さ世界一のうんてい(102m)などの遊具もあります。物部川や太平洋にも近く、公園内に野外ステージ「天然色劇場」があります。33.538773 133.6897
桜やアジサイなど約9,500本の季節の花々が咲きます。長さ世界一のうんてい(102m)などの遊具もあります。物部川や太平洋にも近く、公園内に野外ステージ「天然色劇場」があります。
#公園
#花・植物
-
580. のいちあじさい街道1.2kmの遊歩道沿いに約19,000株もの色とりどりのあじさいが一斉に咲き誇る姿は圧巻です。33.585697 133.69698
見頃は5月下旬から6月下旬まで。同時期に蛍も飛びます。
1.2kmの遊歩道沿いに約19,000株もの色とりどりのあじさいが一斉に咲き誇る姿は圧巻です。 見頃は5月下旬から6月下旬まで。同時期に蛍も飛びます。
#花・植物
-
581. 魚梁瀬ダム奈半利川水系奈半利川にあるロックフィルダム。堤高115m、堤頂長202m。国内屈指の多雨地帯である奈半利川流域では最大規模のダムで、堤高は四国で最も高い。33.592777 134.1122
奈半利川水系奈半利川にあるロックフィルダム。堤高115m、堤頂長202m。国内屈指の多雨地帯である奈半利川流域では最大規模のダムで、堤高は四国で最も高い。
#景観(川)
-
582. 蓮池の樟蓮池西ノ宮八幡宮の神木で本殿の裏にあります。 樹高は約27mで、地上約10mまでは直立し、樹勢は旺盛で四方に伸び、均整を保ち整っています。太さは9.6mで、樹齢は約800年と推定されています。県指定の天然記念物。33.49019 133.40775
蓮池西ノ宮八幡宮の神木で本殿の裏にあります。 樹高は約27mで、地上約10mまでは直立し、樹勢は旺盛で四方に伸び、均整を保ち整っています。太さは9.6mで、樹齢は約800年と推定されていま ...
#花・植物
-
583. 津野町郷土資料館日常生活で使っていた農具や民具など、津野町内の民俗資料を約3,000点所蔵しています。2階には新土居遺跡や永野遺跡などから出土した石器や土器、化石なども多数展示しています。33.4475 133.20016
日常生活で使っていた農具や民具など、津野町内の民俗資料を約3,000点所蔵しています。2階には新土居遺跡や永野遺跡などから出土した石器や土器、化石なども多数展示しています。
#ミュージアム
-
584. 秋葉の宿33.54237 133.1142
#旅館
#温泉
#キャンプ場
#キャンプ
-
賛助会員585. 本山町立 大原富枝文学館高知県出身の文学家・大原富枝の今日までの歩みと、作品を展示室で紹介。33.758488 133.58937
生原稿など貴重な資料展示に加えて、代表作「婉という女」にスポットを当てた大原富枝の世界を展開。
大原富枝作品などの読書、ビデオ資料の観賞ができます。
大原富枝の心を表現するための茶室を設置。茶道愛好家の方々にも開放しています。
高知県出身の文学家・大原富枝の今日までの歩みと、作品を展示室で紹介。 生原稿など貴重な資料展示に加えて、代表作「婉という女」にスポットを当てた大原富枝の世界を展開。 大原富枝作品などの読書、ビデオ資料 ...
#ミュージアム
-
賛助会員586. 西土佐四万十観光社四万十市西土佐地域のありとあらゆる観光情報を網羅。四万十・川の駅カヌー館内にあり、カヌースクール、キャンプ場、屋形船、サイクリングの案内などもしています。33.16873 132.79234
四万十市西土佐地域のありとあらゆる観光情報を網羅。四万十・川の駅カヌー館内にあり、カヌースクール、キャンプ場、屋形船、サイクリングの案内などもしています。
#観光案内所
-
587. 八代の舞台いの町の東部の八代八幡宮の境内にあり、11月5日の神祭に、地区の青年により芝居が奉納されます。33.559834 133.46304
いの町の東部の八代八幡宮の境内にあり、11月5日の神祭に、地区の青年により芝居が奉納されます。
#文化財・史跡
-
588. 入野海水浴場暑い夏がやってきました!33.015385 133.01198
夏に海は外せないですよね☆
ご家族やご友人、お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。
暑い夏がやってきました! 夏に海は外せないですよね☆ ご家族やご友人、お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。
#海あそび
#景観(海)
-
589. レストパークいのレストパークいのは「おいしい!は土佐の國から」をテーマに地元農家さんのつくる産直野菜や旬の果物、花や苗、各種地場産品、お米など様々な商品が販売されています。33.550102 133.44086
また、おふくろの味が自慢の「ごはん家」も併設されており、手ごろな価格でモーニングから定食までメニューも豊富です。
レストパークいのは「おいしい!は土佐の國から」をテーマに地元農家さんのつくる産直野菜や旬の果物、花や苗、各種地場産品、お米など様々な商品が販売されています。 また、おふくろの味が自慢の「ごはん家」も ...
#市場・直売所
#レストラン・食堂
-
590. 北原ふるさと市「花の市」としても有名な直販所。JA女性部員が育てた野菜、果物、花などが販売されています。33.48665 133.38141
「花の市」としても有名な直販所。JA女性部員が育てた野菜、果物、花などが販売されています。
#市場・直売所
-
591. 開成館跡幕末、殖産興業と西洋風の科学教育の振興と富国強兵を目的として建設された開成館。事業廃止後は迎賓館となり、明治4年、薩摩の西郷隆盛、大久保利通、長州の木戸孝允、杉孫七郎と、板垣退助、福岡孝弟らによる廃藩置県にもつながる会談が行われました。高知市小津町には「開成門」が残されています。33.556183 133.55153
幕末、殖産興業と西洋風の科学教育の振興と富国強兵を目的として建設された開成館。事業廃止後は迎賓館となり、明治4年、薩摩の西郷隆盛、大久保利通、長州の木戸孝允、杉孫七郎と、板垣退助、福岡孝弟らによる廃...
#文化財・史跡
#銅像・記念碑
-
592. あいの里まつばら(集落活動センターまつばら)33.31623 132.97243
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
593. 蓮池城址(城山公園)蓮池城は、平重盛家人の土佐守護蓮池家綱が居城としたのに始まるといわれていますが、はっきりしたことは分かっていません。土佐七雄に数えられる大平氏をはじめ戦国武将が、数々の興亡を繰り返した城です。33.493374 133.41505
現在、城址は城山公園となり、桜やあじさいの名所として市民に親しまれています。
蓮池城は、平重盛家人の土佐守護蓮池家綱が居城としたのに始まるといわれていますが、はっきりしたことは分かっていません。土佐七雄に数えられる大平氏をはじめ戦国武将が、数々の興亡を繰り返した城です。 現在 ...
#花・植物
#公園
#文化財・史跡
-
594. 神峯山空と海の展望公園神峯山の山頂にあり、高さ23mの展望塔からは、天気がよければ室戸岬から足摺岬、石鎚山系まで一望できる360度の雄大なパノラマビューが広がります。33.469727 133.97607
神峯山の山頂にあり、高さ23mの展望塔からは、天気がよければ室戸岬から足摺岬、石鎚山系まで一望できる360度の雄大なパノラマビューが広がります。
#公園
#景観(海)
-
595. ふれあいの里 柳野(集落活動センター 柳野)地元農産品や加工品の販売、地元の食材で作る煮物や田舎寿司、そしてうどんやそばのなつかしいおふくろ料理を食べることができます。33.62155 133.24005
※お食事は数に限りあり。予約不可ですので、ご了承ください。
アニメーション映画「竜とそばかすの姫」のモデル地になりました。
地元農産品や加工品の販売、地元の食材で作る煮物や田舎寿司、そしてうどんやそばのなつかしいおふくろ料理を食べることができます。 ※お食事は数に限りあり。予約不可ですので、ご了承ください。 アニメーション ...
#市場・直売所
#レストラン・食堂
-
596. 須留田八幡宮高知県に位置する須留田八幡宮は、かつて歌舞伎が奉納の宮芝居として興行され、その名残である「回り舞台」が最近まで残っていました。33.549244 133.72116
この宮は、土佐の絵師である絵金(金蔵、1812~76年)ゆかりの地としても知られています。絵金は高知城下で生まれ、幕末から明治初期にかけて数多くの芝居絵屏風をのこし、地元高知では「絵金さん」の愛称で長年親しまれてきました。
彼の歌舞伎や浄瑠璃のストーリーを極彩色で絵画化した芝居絵屏風は、同時代の絵画のなかでも一段と異彩を放つものです。絵金は「生活の中の美」として、夏祭りの間に神社や商店街の軒下に飾られ、提灯や蝋燭の灯りで浮かび上がる画面は、見る者に強い印象を残します。
須留田 ...
高知県に位置する須留田八幡宮は、かつて歌舞伎が奉納の宮芝居として興行され、その名残である「回り舞台」が最近まで残っていました。 この宮は、土佐の絵師である絵金(金蔵、1812~76年)ゆかりの地としても知ら ...
#寺社
-
597. 京間の大イチョウ仁淀川下流の堤防上にある大きなイチョウで、土佐市の天然記念物に指定されています。33.501015 133.4341
樹高は最大のもので約21m、幹回り2.5m前後の大木3本をはじめ、大小多数の立木が周囲約17mの円陣内に密生しています。
それぞれ独立した木に見えますが、堤防の嵩上げ工事の際に数メートル以上が埋まった状態であるため、根っこは繋がっています。
樹齢の推定は困難ですが、高岳親王にまつわる伝承とともに、古木として有名です。
仁淀川下流の堤防上にある大きなイチョウで、土佐市の天然記念物に指定されています。 樹高は最大のもので約21m、幹回り2.5m前後の大木3本をはじめ、大小多数の立木が周囲約17mの円陣内に密生しています。 それぞれ独...
#花・植物
-
598. 石見寺山四万十市東山の一角にある石見寺山に整備されたハイキングコース。約4kmのコース沿いには、ミニ八十八ヵ所が奉られ石仏と寺名・本尊を示す白札を設置。登山口から山頂までの間には、一條氏時代には京の比叡山延暦寺に模して鎮守の寺とした石見寺があります。山頂の展望台からは、四万十市街地から太平洋へとそそぐ四万十川や宿毛湾、四国山地の山々を一望。33.015717 132.95424
四万十市東山の一角にある石見寺山に整備されたハイキングコース。約4kmのコース沿いには、ミニ八十八ヵ所が奉られ石仏と寺名・本尊を示す白札を設置。登山口から山頂までの間には、一條氏時代には京の比叡山延暦寺...
#景観(山)
-
599. 河田小龍生誕地画人としてだけではなく、儒学などの広い知識を持っていた小龍のもとには多くの門人が集まりました。その中には亀山社中・土佐海援隊で活躍した長岡謙吉、近藤長次郎、新宮馬之助らがいます。33.55934 133.54494
11年にも及ぶ漂流生活ののちアメリカから帰国した中浜(ジョン)万次郎から聞いた外国の話を『漂巽紀畧』をまとめました。安政元年(1854年)の冬に小龍と会った龍馬は、世界状勢を聞き、大いに啓発されたといいます。
画人としてだけではなく、儒学などの広い知識を持っていた小龍のもとには多くの門人が集まりました。その中には亀山社中・土佐海援隊で活躍した長岡謙吉、近藤長次郎、新宮馬之助らがいます。 11年にも及ぶ漂流生活...
#文化財・史跡
-
600. 水原秋桜子句碑地元俳人・田村吾亀等らが発起し土佐清水市等が協力して建立。32.725407 133.02068
昭和38年10月下旬に、同人誌「馬酔木」の同人数名と足摺岬を訪れた時の句です。
「岩は皆渦潮しろし十三夜」
地元俳人・田村吾亀等らが発起し土佐清水市等が協力して建立。 昭和38年10月下旬に、同人誌「馬酔木」の同人数名と足摺岬を訪れた時の句です。 「岩は皆渦潮しろし十三夜」
#銅像・記念碑
-
601. 仮谷忠男像高知県土佐清水市以布利出身の政治家・刈谷忠男は、三木内閣の建設大臣に就任した後、本四連絡橋架設、激じん災害対策緊急整備事業の制度化などに尽力しました。その激務に志半ばで倒れた彼を偲び、ゆかりの人達の声掛けによって県内外に寄付を募り、銅像が完成しました。鹿島公園から、右手を胸前に掲げて清水港沖の海を見渡しています。32.777702 132.96046
高知県土佐清水市以布利出身の政治家・刈谷忠男は、三木内閣の建設大臣に就任した後、本四連絡橋架設、激じん災害対策緊急整備事業の制度化などに尽力しました。その激務に志半ばで倒れた彼を偲び、ゆかりの人達の...
#銅像・記念碑
-
602. 谷重遠の墓(谷秦山の墓)国指定の史跡。谷重遠(1663~1718)は秦山と号し、山崎闇斉の門人で、土佐南学の最高峰となった人物。谷泰山は学問の神、とりわけ受験の神として信仰を集め、合格すると小旗をもってお礼参りをする人が多くいます。谷干城は秦山の子孫。33.613644 133.68051
国指定の史跡。谷重遠(1663~1718)は秦山と号し、山崎闇斉の門人で、土佐南学の最高峰となった人物。谷泰山は学問の神、とりわけ受験の神として信仰を集め、合格すると小旗をもってお礼参りをする人が多くいます。 ...
#文化財・史跡
-
603. 鉢ヶ森安徳天皇がここで行宮(あんぐう、会の御所)を営んでいたときに、山の主と言われる物がいて、たびたび恐ろしい異変が起こり、鎮めようと持っていた御兜の鉢を山上に埋め、山祇の命草野姫の命をお祭りして朝夕礼拝されたことが名前の由来とされています。33.725327 133.77614
それ以来、妖怪変化はなくなり、長くこの地に住まわれた、と言われています。
安徳天皇がここで行宮(あんぐう、会の御所)を営んでいたときに、山の主と言われる物がいて、たびたび恐ろしい異変が起こり、鎮めようと持っていた御兜の鉢を山上に埋め、山祇の命草野姫の命をお祭りして朝夕礼拝...
#景観(山)
-
604. 宇佐漁港アニメ映画『竜とそばかすの姫』に登場する港のモデルとなった場所です。33.451855 133.45131
隣接する宇佐しおかぜ公園はホエールウォッチングの出発場所にもなっています。
アニメ映画『竜とそばかすの姫』に登場する港のモデルとなった場所です。 隣接する宇佐しおかぜ公園はホエールウォッチングの出発場所にもなっています。
#景観(海)
-
605. 山田堰物部川の本流にある灌漑用堰。江戸時代の前期、野中兼山が奉行となって構築したもので、堰堤は左岸の神母木[いげのき]から右岸の小田島まで斜めに川面を横ぎり、延長約350m、幅11m、高さ1.5m。山田堰跡の西岸上段には兼山を祠る春野神社があります。33.612087 133.71262
物部川の本流にある灌漑用堰。江戸時代の前期、野中兼山が奉行となって構築したもので、堰堤は左岸の神母木[いげのき]から右岸の小田島まで斜めに川面を横ぎり、延長約350m、幅11m、高さ1.5m。山田堰跡の西岸上段 ...
#文化財・史跡
-
606. 雲の上の市場地元の野菜やスイーツを販売している道の駅。33.38785 132.94296
同じ建物に、雲の上の温泉、プール、食堂があります。
地元の野菜やスイーツを販売している道の駅。 同じ建物に、雲の上の温泉、プール、食堂があります。
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
607. 元親飛翔之像長宗我部元親の居城跡・岡豊山にある高知県立歴史民俗資料館のメインシンボルとして、平成27年5月に施設前に建立されました。戦国時代から安土桃山時代にかけての土佐国の戦国大名として、元親は土佐を統一した後、織田信長・豊臣秀吉といった天下人に翻弄されながらも、四国大部分の統一を成し遂げました。33.59576 133.62302
長宗我部元親の居城跡・岡豊山にある高知県立歴史民俗資料館のメインシンボルとして、平成27年5月に施設前に建立されました。戦国時代から安土桃山時代にかけての土佐国の戦国大名として、元親は土佐を統一した後、...
#銅像・記念碑
-
608. 本山さくら市自然豊かな本山町や嶺北地域で採れた新鮮な野菜やお米、土佐あかうしや土佐ジローの卵などが並ぶ産直市。33.75959 133.59036
手作りのお寿司やお惣菜も人気です。
自然豊かな本山町や嶺北地域で採れた新鮮な野菜やお米、土佐あかうしや土佐ジローの卵などが並ぶ産直市。 手作りのお寿司やお惣菜も人気です。
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
609. 桑の川の鳥居杉桑の川地主神社の石段両脇にそびえる2本の杉は、地上5mのところで連結して鳥居のような形になっています。33.66403 133.5951
樹齢は約300年で、結びつきが強いことから縁結びのご利益があるともいわれています。県指定の天然記念物。
桑の川地主神社の石段両脇にそびえる2本の杉は、地上5mのところで連結して鳥居のような形になっています。 樹齢は約300年で、結びつきが強いことから縁結びのご利益があるともいわれています。県指定の天然記念物。
#花・植物
-
610. 姫野々城跡姫野々城は半山城とも呼ばれ、長らく土佐の有力国人・津野氏の居城で、この山麓に土居と城下町を構えて暮らしていました。33.44471 133.2169
標高193mの高台に位置し、主郭は畝状竪堀群に囲まれているのが特徴で、それにより城が守られていました。
城山一帯に兵舎や武器庫跡、帯状曲輪、城八幡を持つ典型的な中世の山城の特徴が見られ、主郭部からは多数の青磁器等が見つかっており、城での生活の跡がうかがえます。
天文14年(1545)には城を舞台に津野基高と一条房基の激しい攻防が繰り広げられました。
1600年の津野氏滅亡に伴い城は放棄されたため、その後荒らされることも少なく、中世の山城の特徴を今日まで留めています。
姫野々城は半山城とも呼ばれ、長らく土佐の有力国人・津野氏の居城で、この山麓に土居と城下町を構えて暮らしていました。 標高193mの高台に位置し、主郭は畝状竪堀群に囲まれているのが特徴で、それにより城が守ら...
#文化財・史跡
-
611. 石立山標高1708m。登山の途中、ビャクシンの群落、ブナ、ウラジロモミなどの天然林風景、岩場からの展望も良いです。33.78401 134.05357
石灰岩の断崖、捨身嶽も見逃せません。春は新緑とツツジなどの開花、秋は紅葉が美しいスポットです。
周辺にも新緑と紅葉の名所、別府峡、高の瀬峡があります。
標高1708m。登山の途中、ビャクシンの群落、ブナ、ウラジロモミなどの天然林風景、岩場からの展望も良いです。 石灰岩の断崖、捨身嶽も見逃せません。春は新緑とツツジなどの開花、秋は紅葉が美しいスポットです。...
#景観(山)
-
612. 高知県バリアフリー観光相談窓口高齢の方や障害のある方など、誰もが高知県観光を楽しめるお手伝いをさせていただきます。33.560165 133.54256
事前予約制で車いすやシルバーカー、ベビーカーも貸し出しています。
高齢の方や障害のある方など、誰もが高知県観光を楽しめるお手伝いをさせていただきます。 事前予約制で車いすやシルバーカー、ベビーカーも貸し出しています。
#観光案内所
-
613. 高岡神社窪川駅の北西。33.221786 133.12483
窪川の産土神として栄え、江戸時代までは四国霊場の岩本寺を別当寺としていた。社宝に大太刀や筑紫鉾、甲胄、長宗我部元親の銘の残る棟札などがある。
窪川駅の北西。 窪川の産土神として栄え、江戸時代までは四国霊場の岩本寺を別当寺としていた。社宝に大太刀や筑紫鉾、甲胄、長宗我部元親の銘の残る棟札などがある。
#寺社
-
614. あいあい広場ナスやピーマン、ミョウガ、オクラなど旬の新鮮な野菜などが揃う直販所。33.424557 134.0233
奈半利町や室戸市羽根の業者から卸す手作り弁当、中芸地区や室戸市でとれた新鮮な魚などを求めるお客さんで朝から賑わいます。
6月上旬から店頭に並ぶスイカ「姫まくら」が有名です。
ナスやピーマン、ミョウガ、オクラなど旬の新鮮な野菜などが揃う直販所。 奈半利町や室戸市羽根の業者から卸す手作り弁当、中芸地区や室戸市でとれた新鮮な魚などを求めるお客さんで朝から賑わいます。 6月上旬か ...
#市場・直売所
-
615. 御在所山古来霊山とされ、女人禁制の修験者の山でした。山頂には韮生大山祇神社が鎮座しており、大山祇命を祭神とし、安徳天皇、平教盛をも合わせて祀っています。33.702034 133.82314
山の名前の由来は、門脇宰相教盛卿の墓があり、その墓をあがめ尊び、御の字をそえて「御宰相の塚」と言ったので、山の名も、いつしか御宰相山といわれるようになり、後々「五在所」または「御在所」、あるいは「五山所」といろいろに呼ばれるようになったと言われます。
古来霊山とされ、女人禁制の修験者の山でした。山頂には韮生大山祇神社が鎮座しており、大山祇命を祭神とし、安徳天皇、平教盛をも合わせて祀っています。 山の名前の由来は、門脇宰相教盛卿の墓があり、その墓を ...
#景観(山)
-
616. 岡本弥太の詩碑香我美町出身の詩人・岡本弥太の詩碑。詩碑には「白牡丹図」が刻まれています。33.538925 133.74405
香我美町出身の詩人・岡本弥太の詩碑。詩碑には「白牡丹図」が刻まれています。
#銅像・記念碑
-
617. 田宮虎彦「足摺岬」文学碑足摺岬の椿のトンネルを抜けると、白亜の灯台の近くに、田宮虎彦の名作『足摺岬』を記念した石碑が立てられています。32.72407 133.02028
「砕け散る荒波の飛沫が崖肌の巨巌いちめんに雨のように降りそそいでいた」と刻まれています。
足摺岬の椿のトンネルを抜けると、白亜の灯台の近くに、田宮虎彦の名作『足摺岬』を記念した石碑が立てられています。 「砕け散る荒波の飛沫が崖肌の巨巌いちめんに雨のように降りそそいでいた」と刻まれています。
#銅像・記念碑
-
618. 為松公園四万十市街の西側に盛り上がった、古城山一帯を占める市民公園。 中村城跡。約500本の桜のほか、セキチク、ツツジ等が植栽されています。32.996964 132.9295
公園内には、天守閣を形どった四万十市立郷土資料館があります。
四万十市街の西側に盛り上がった、古城山一帯を占める市民公園。 中村城跡。約500本の桜のほか、セキチク、ツツジ等が植栽されています。 公園内には、天守閣を形どった四万十市立郷土資料館があります。
#花・植物
#公園
-
619. 長者の大イチョウ国道439号から長者地区に入ってすぐの角にその威容を現すのがこの大銀杏です。元は三本立ちで樹高40mの見事なものだったそうですが、文化年間(1816)にその一幹を十王堂の改築用材に使用。その後火災や台風被害に遭いながらも、樹勢はますます旺盛になり今日に至っています。根回り11.6m、樹高15m。県指定天然記念物。33.500526 133.133
国道439号から長者地区に入ってすぐの角にその威容を現すのがこの大銀杏です。元は三本立ちで樹高40mの見事なものだったそうですが、文化年間(1816)にその一幹を十王堂の改築用材に使用。その後火災や台風被害 ...
#花・植物
-
620. 出井甌穴高知県道4号線を松田川沿いに上流に進んだ愛媛県境にほど近い場所。出井溪谷の砂岩・泥岩からなる岩床に、渦巻く急流により浸食されてできた大小200個以上の甌穴が並びます。昭和40年、高知県の天然記念物に指定。33.08901 132.67201
高知県道4号線を松田川沿いに上流に進んだ愛媛県境にほど近い場所。出井溪谷の砂岩・泥岩からなる岩床に、渦巻く急流により浸食されてできた大小200個以上の甌穴が並びます。昭和40年、高知県の天然記念物に指定。
#文化財・史跡
-
621. 大荒の滝【紅葉の見ごろ】11月中旬~11月下旬33.706245 133.80956
二匹の龍が大竜巻に乗って舞い降りたという伝説を今に残す「大荒の滝」の周辺には、手つかずの豊かな自然が残されており、轟音をあげて落下する40m余りの滝は、雨の多い季節には大瀑布となって迫力を増します。
紅葉の名所でもあり、展望所からは滝と赤く色づいた山々を一望することができます。
【紅葉の見ごろ】11月中旬~11月下旬 二匹の龍が大竜巻に乗って舞い降りたという伝説を今に残す「大荒の滝」の周辺には、手つかずの豊かな自然が残されており、轟音をあげて落下する40m余りの滝は、雨の多い季節 ...
#景観(川)
-
622. 入田ヤナギ林(曼珠沙華)四万十川下流にかかる通称・赤鉄橋の上流、約1kmほどの右岸にあるヤナギの自然林。32.9954 132.91934
9月中旬から下旬ごろ、木漏れ日の森の中で、曼珠沙華(ヒガンバナ)が一面に咲き誇ります。
四万十川下流にかかる通称・赤鉄橋の上流、約1kmほどの右岸にあるヤナギの自然林。 9月中旬から下旬ごろ、木漏れ日の森の中で、曼珠沙華(ヒガンバナ)が一面に咲き誇ります。
#花・植物
-
623. 生見サーフィンビーチ全国でも知名度の高いビーチで「サーファーの聖地」とも呼ばれています。海岸は全長約1000mあり、 どの季節でも波のコンディションがよく、サーフィン初心者から上級者まで楽しめます。33.52458 134.283
全国でも知名度の高いビーチで「サーファーの聖地」とも呼ばれています。海岸は全長約1000mあり、 どの季節でも波のコンディションがよく、サーフィン初心者から上級者まで楽しめます。
#景観(海)
#海あそび
-
624. 浜口雄幸生家記念館高知県出身で初めて内閣総理大臣となった浜口雄幸の記念館です。現在の高知市の五台山にある山村に生れた雄幸の生家を復元したもので、勉強部屋などがあり政権活動に関する資料などが展示されています。33.538353 133.58833
高知県出身で初めて内閣総理大臣となった浜口雄幸の記念館です。現在の高知市の五台山にある山村に生れた雄幸の生家を復元したもので、勉強部屋などがあり政権活動に関する資料などが展示されています。
#ミュージアム
-
625. 琴平神社(土佐市)高知県土佐市清滝に鎮座する琴平神社は、天保2年(1831年)に清滝寺上方の山中から現在地へ移転・再建されました。かつては清滝寺の鎮守でしたが、明治初年の神仏分離により独立し、現在は清滝第一部落の氏神として守られています。33.51265 133.40977
本殿は一間社入母屋造り平入りのこけら葺きで、正面に一間の向拝を備えた格式ある造り。高知県内の近世社寺建築では数少ない形式で、小規模ながら江戸後期の地域の建築技術を示す貴重な文化財です。
全体の構造から細部の彫刻まで意匠が美しく、学術的・歴史的価値が高いと評価されています。長年の風雨や白蟻による損傷のため、平成10年(1998年)に全面解体修理が完了しました。
境内には幕末から明治初期にかけての金...
高知県土佐市清滝に鎮座する琴平神社は、天保2年(1831年)に清滝寺上方の山中から現在地へ移転・再建されました。かつては清滝寺の鎮守でしたが、明治初年の神仏分離により独立し、現在は清滝第一部落の氏神として守 ...
#寺社
-
626. 間崎滄浪邸跡滄浪は幼少時から頭がよく、細川潤次郎・岩崎馬之助らとともに三奇童とよばれました。33.565536 133.53935
16歳で江戸に遊学し、19歳の時に高知城北・江ノ口村に塾を開き、門下生に中岡慎太郎や吉村虎太郎らがいます。
1861年に土佐勤王党に加盟し、江戸に出てからは坂本龍馬をはじめ多くの志士と交流しました。
藩政改革を目指しましたが、山内容堂の怒りに触れ、1863年に平井収二郎らとともに自刃しました。
滄浪は幼少時から頭がよく、細川潤次郎・岩崎馬之助らとともに三奇童とよばれました。 16歳で江戸に遊学し、19歳の時に高知城北・江ノ口村に塾を開き、門下生に中岡慎太郎や吉村虎太郎らがいます。 1861年に土佐勤 ...
#文化財・史跡
-
627. 高知空港 緑の広場トリム広場をはじめ、遊具のある広場が4カ所あります。33.53716 133.68166
高知龍馬空港周辺にあり、飛行機を間近で見られます。
弥生時代の集落跡も見られるやよい広場もあります。
トリム広場をはじめ、遊具のある広場が4カ所あります。 高知龍馬空港周辺にあり、飛行機を間近で見られます。 弥生時代の集落跡も見られるやよい広場もあります。
#公園
-
628. 安田まちなみ交流館・和安田町商店街にある旧柏原家住宅、旧市川医院を修復し、安田まちなみ交流館・和として活用しています。33.43731 133.98012
旧柏原家住宅は大正から昭和初期の土佐東部の建築様式で、当時豊富にあった魚梁瀬の天然木材がふんだんに使われていて、土間でつながった旧市川医院は旧柏原家住宅とほぼ同時期の外観洋風医院建築様式の建物です。
髙松順蔵や石田英吉など郷土が輩出した幕末明治維新の先人たちの顕彰などを通じた交流人口拡大事業の中心施設として活用しています。
安田町商店街にある旧柏原家住宅、旧市川医院を修復し、安田まちなみ交流館・和として活用しています。 旧柏原家住宅は大正から昭和初期の土佐東部の建築様式で、当時豊富にあった魚梁瀬の天然木材がふんだんに使 ...
#建築
#ミュージアム
-
629. 樋口真吉邸跡真吉は武市半平太の土佐勤王党に呼応し、西部のまとめ役になりました。勤王運動に関する日記『遣倦録』は貴重な資料で、その中に、脱藩直前の坂本龍馬の記載があります。「坂竜飛騰」という四文字だけですが、龍馬という人物を見抜いた言葉であり、龍馬も真吉を非常に信頼していました。32.99483 132.93225
中村病院横を右折すればすぐ左手に樋口真吉邸跡の標柱があります。平成13年中村市(現四万十市)教育委員会によって新しく建てかえられました。
周辺には行余館跡(藩校跡)などの史跡(碑)も残されています。
真吉は武市半平太の土佐勤王党に呼応し、西部のまとめ役になりました。勤王運動に関する日記『遣倦録』は貴重な資料で、その中に、脱藩直前の坂本龍馬の記載があります。「坂竜飛騰」という四文字だけですが、龍馬...
#文化財・史跡
-
630. 南国SA(下り)高知市街地や安芸・室戸方面、また四万十や足摺方面へ向かう際の最後の休憩スポットとして多くのドライバーに利用されています。33.600723 133.61516
施設内には高知県の豊かな食の魅力を凝縮したレストランやフードコート、お土産コーナーが充実。カツオのたたき定食や土佐赤牛を使った料理など、ご当地グルメを堪能できるのはもちろん、芋けんぴやミレービスケットなどの高知ならではのお土産も豊富に取り揃えています。
高知市街地や安芸・室戸方面、また四万十や足摺方面へ向かう際の最後の休憩スポットとして多くのドライバーに利用されています。 施設内には高知県の豊かな食の魅力を凝縮したレストランやフードコート、お土産コ ...
#おみやげ
#レストラン・食堂
#道の駅・休憩所
-
631. 山荘しらさ西日本最高峰「石鎚山」と「瓶が森」の中ほど、標高1,400mの場所に位置する『山荘しらさ』が2021年4月にリニューアルオープン。33.769207 133.18347
宿泊以外にもカフェやショップを併設。
登山やサイクリング、トレイルランニングなど、アクティビティの拠点としてご利用いただけます。
西日本最高峰「石鎚山」と「瓶が森」の中ほど、標高1,400mの場所に位置する『山荘しらさ』が2021年4月にリニューアルオープン。 宿泊以外にもカフェやショップを併設。 登山やサイクリング、トレイルランニングなど、...
#コテージ・グランピング
#景観(山)
#カフェ・スイーツ
-
632. 芸西村文化資料館・筒井美術館1階「芸西村文化資料館」では、江戸中期から昭和初期頃まで使われていた漁具・農具・民具などを展示。33.527298 133.80911
また地曳網漁法やハウス園芸の模型もご覧いただけます。
芸西村出身の幕末の志士なども紹介しています。
2階「筒井美術館」には、芸西村出身の洋画家筒井広道氏の絵の変遷が確認できる内容となっています。
1階「芸西村文化資料館」では、江戸中期から昭和初期頃まで使われていた漁具・農具・民具などを展示。 また地曳網漁法やハウス園芸の模型もご覧いただけます。 芸西村出身の幕末の志士なども紹介しています。 2階「 ...
#ミュージアム
-
633. 歴史ふれあい広場2022年に整備された、宿毛市の歴史を学べる広場。32.93944 132.72803
野中兼山遺族幽閉之地の碑、林有造翁像など、銅像や記念碑が立っています。
2022年に整備された、宿毛市の歴史を学べる広場。 野中兼山遺族幽閉之地の碑、林有造翁像など、銅像や記念碑が立っています。
#公園
#銅像・記念碑
-
634. 越知町立横倉山自然の森博物館4億年前、赤道付近にあった横倉山。その当時栄えたサンゴ礁の化石やトリケラトプスを始めとする世界の代表的な化石を通して、生物の進化や地球の歴史について実感できる”地球学博物館”。日本唯一の”アカガシの原生林”が残り、植物の宝庫でもある横倉山の牧野富太郎博士ゆかりの植物なども紹介。源平の戦いに敗れてここまで落ち延びてきたという「安徳天皇潜幸伝説」についても知ることができます。「体験コーナー」もあります。33.535393 133.24193
4億年前、赤道付近にあった横倉山。その当時栄えたサンゴ礁の化石やトリケラトプスを始めとする世界の代表的な化石を通して、生物の進化や地球の歴史について実感できる”地球学博物館”。日本唯一の”アカガシの...
#ミュージアム
-
635. サングリーンコスモス ふれあい市人気の高糖度トマト(季節限定)や仁淀川流域でとれた野菜・果物はもちろんのこと、花きや鮮魚、その他民芸品まで、豊富に品揃え。33.53326 133.36833
また、イベント時は店頭でカツオのたたきの実演販売も行われます。
人気の高糖度トマト(季節限定)や仁淀川流域でとれた野菜・果物はもちろんのこと、花きや鮮魚、その他民芸品まで、豊富に品揃え。 また、イベント時は店頭でカツオのたたきの実演販売も行われます。
#市場・直売所
-
636. 八王子宮室町時代、近江国から山田氏の家臣、野口総左衛門が勧請したと伝えられ、野中兼山が中井川を掘る際に、現在の北本町に移築しました。33.611286 133.68806
閑静な環境の中に静穏な佇まいを見せる境内、そして隣の八王子公園は、鏡野公園と並ぶ桜の名所として古くから知られ、夏期と秋期の大祭には、県内外からの多くの人で賑わいます。
室町時代、近江国から山田氏の家臣、野口総左衛門が勧請したと伝えられ、野中兼山が中井川を掘る際に、現在の北本町に移築しました。 閑静な環境の中に静穏な佇まいを見せる境内、そして隣の八王子公園は、鏡野公 ...
#寺社
-
637. 第38番札所 金剛福寺弘仁13年、嵯峨天皇の勅願によって弘法大師が三面千手観音を本尊として今から約1200年前に建立したもので、当時より格式の高い南海の名刹として栄え、多数の参拝者があります。32.72593 133.01857
弘仁13年、嵯峨天皇の勅願によって弘法大師が三面千手観音を本尊として今から約1200年前に建立したもので、当時より格式の高い南海の名刹として栄え、多数の参拝者があります。
#寺社
-
638. 篠山愛媛県との県境に位置し、標高1065mの山頂には篠山神社が祀られています。山岳コースとして人気を集め、アケボノツツジが咲き誇る4月下旬から5月上旬にかけては、県内外から登山客が訪れます。愛媛県側の駐車場付近にある白滝、虹ヶ滝の二つの滝は水量豊かでスケールが大きいです。33.055695 132.65904
愛媛県との県境に位置し、標高1065mの山頂には篠山神社が祀られています。山岳コースとして人気を集め、アケボノツツジが咲き誇る4月下旬から5月上旬にかけては、県内外から登山客が訪れます。愛媛県側の駐車場付近 ...
#景観(山)
-
639. 宿毛貝塚宿毛貝塚は、幡多地域における最も重要な文化遺産のひとつです。縄文時代中期から後期に形成された貝塚で、1957年(昭和32年)に国指定史跡に指定されています。32.936028 132.71367
ここは当時の暮らしの跡というだけにとどまらない、信仰の場所だったという説もあり、縄文土器、石器、獣骨、魚骨、貝類、さらに人骨も出土しました。明治後半に郷土史家寺石正路によって学術的に紹介された後、1949年(昭和24年)には高知県教育委員会によって発掘調査が行われ、東と西の二つの貝塚から縄文人骨も発見されています。
東貝塚と西貝塚は約60m離れており、周辺に住居跡があったという可能性も指摘されています。指定地のうち西貝塚は1978年(昭和53年)に公有化された後 ...
宿毛貝塚は、幡多地域における最も重要な文化遺産のひとつです。縄文時代中期から後期に形成された貝塚で、1957年(昭和32年)に国指定史跡に指定されています。 ここは当時の暮らしの跡というだけにとどまらない ...
#文化財・史跡
-
640. 岩黒山標高1746m。頂上からの眺めは360度に展開し、石鎚連山の高峰や瀬戸内海が見渡せます。連山の春、夏の緑、秋の紅葉が美しい山です。33.75069 133.15703
標高1746m。頂上からの眺めは360度に展開し、石鎚連山の高峰や瀬戸内海が見渡せます。連山の春、夏の緑、秋の紅葉が美しい山です。
#景観(山)
-
641. 鹿持雅澄邸跡高知県指定の史跡。国学者、歌人の鹿持雅澄(1791~1858年)は生涯をこの地で送りました。家老・福岡孝則の知遇を得て、藩校教授館の写本係となり、注力した万葉集研究は「万葉集古義」として結実。邸跡には古井戸が残存するのみ。周辺に頌徳碑、墓所もあります。33.56729 133.50746
高知県指定の史跡。国学者、歌人の鹿持雅澄(1791~1858年)は生涯をこの地で送りました。家老・福岡孝則の知遇を得て、藩校教授館の写本係となり、注力した万葉集研究は「万葉集古義」として結実。邸跡には古井戸が ...
#文化財・史跡
-
642. 南国土佐を後にしての歌碑歌手・ペギー葉山さんが歌い1959年に大ヒットした『南国土佐を後にして』は、太平洋戦争の時代に郷土出身の鯨部隊(旧日本陸軍第40師団歩兵第236連隊)が遠く離れた戦地でふるさとを偲んで歌った歌が原曲。はりまや橋公園東側に平成24年建てられた歌碑には歌詞が刻まれ、午前8時半から午後8時半まで1時間おきに歌声が流れ、そばに建てられた親子鯨が曲に合わせて潮を吹く仕掛けとなっています。33.559875 133.54317
歌手・ペギー葉山さんが歌い1959年に大ヒットした『南国土佐を後にして』は、太平洋戦争の時代に郷土出身の鯨部隊(旧日本陸軍第40師団歩兵第236連隊)が遠く離れた戦地でふるさとを偲んで歌った歌が原曲。はりまや橋...
#銅像・記念碑
-
643. 越知町観光協会越知町観光協会は、越知町の魅力をたくさんの方々に知っていただく為に、様々な活動を行っています。33.530483 133.25092
より魅力的なご案内ができるよう努めてまいりますので、お気軽にお立ち寄りください。
越知町観光協会は、越知町の魅力をたくさんの方々に知っていただく為に、様々な活動を行っています。 より魅力的なご案内ができるよう努めてまいりますので、お気軽にお立ち寄りください。
#観光案内所
-
644. 岡豊別宮八幡宮岡豊城跡のすぐ北の山頂にあります。長宗我部元親の信仰が厚く、出陣の際には必ずここで戦勝を祈願したと伝えられます。かつては長宗我部氏ゆかりの品を多く所蔵していましたが、大正年間の大火で大半が焼失しました。現在は元親が画工真重に命じて作らせたという三十六歌仙の画額14枚と、出陣の際使用したと伝えられる熊蜂の盃があるのみです。(ともに県立歴史民俗資料館保管)33.601257 133.62616
岡豊城跡のすぐ北の山頂にあります。長宗我部元親の信仰が厚く、出陣の際には必ずここで戦勝を祈願したと伝えられます。かつては長宗我部氏ゆかりの品を多く所蔵していましたが、大正年間の大火で大半が焼失しまし...
#寺社
-
645. 弘田龍太郎歌碑安芸市を訪れた人が、安芸市自慢の風物に触れられるように市内10ヶ所に曲碑が建立されています。そのうち7ヶ所には音声センサーがあり、童謡を聞くことができます。33.518772 133.91217
安芸市を訪れた人が、安芸市自慢の風物に触れられるように市内10ヶ所に曲碑が建立されています。そのうち7ヶ所には音声センサーがあり、童謡を聞くことができます。
#銅像・記念碑
-
646. 岡御殿岡御殿は天保十五年(1844年)に建築され、藩主が参勤交代や東部巡視の時の本陣として使用していました。33.426723 134.00923
敷地内には御殿・茶の間・土蔵・御成門などの建物が保存復元され、藩政末期の岡御殿の雰囲気を伝えています。
また、岡御殿の西側にあるのが西の岡邸で、岡家の分家として製材や回船業をする豪商の家で、脇本陣として随勤の重臣などの宿泊に当てられていました。
岡御殿は天保十五年(1844年)に建築され、藩主が参勤交代や東部巡視の時の本陣として使用していました。 敷地内には御殿・茶の間・土蔵・御成門などの建物が保存復元され、藩政末期の岡御殿の雰囲気を伝えています。 ...
#建築
#文化財・史跡
-
647. 横浪県立自然公園横浪半島は土佐湾中央部から東側へ突き出た半島で、高知県を代表する海岸景勝地です。一帯は県立自然公園に指定され、リアス式海岸の美しい地形と豊かな自然環境が保護されています。33.40714 133.40373
古くから人々の信仰を集めた横浪半島には、四国八十八ヶ所第36番札所の青龍寺や、「土佐の宮島」と称される国指定重要文化財の鳴無神社が鎮座しています。
鳴無神社の参道は海に向かって延び、社殿からは波穏やかな浦ノ内湾を望むことができます。自然の美しさと信仰が一体となった景観は、文化的価値も高く評価されています。
海浜には国の天然記念物に指定された地層が見られ、希少性と学術性において優れた自然環境を有しています。豊かな自然が信仰ととも ...
横浪半島は土佐湾中央部から東側へ突き出た半島で、高知県を代表する海岸景勝地です。一帯は県立自然公園に指定され、リアス式海岸の美しい地形と豊かな自然環境が保護されています。 古くから人々の信仰を集めた ...
#景観(海)
#公園
-
648. 一條神社一條神社は、土佐一條氏の遺徳を偲ぶ有志によって御所跡(一部)に建立され、一條氏歴代の霊を祀っています。32.99333 132.9342
一條氏は応仁の乱(室町時代末期の1467~1477年)を避けて京都から移って来た一門で、4代に渡って四万十市 中村の経済・文化の発展に尽力しました。
毎年11月の「一條大祭」では、京都の下鴨神社からいただいたご神火による提灯行列など3日間さまざまな行事が行われます。
一條神社は、土佐一條氏の遺徳を偲ぶ有志によって御所跡(一部)に建立され、一條氏歴代の霊を祀っています。 一條氏は応仁の乱(室町時代末期の1467~1477年)を避けて京都から移って来た一門で、4代に渡って四万十...
#寺社
-
649. 土佐望月温泉 姫若子の湯高知の市街地にありながら、一歩足を踏み入れればそこは大正浪漫の薫る別世界。33.564182 133.56828
土佐望月温泉 姫若子の湯は、県内最大級の空を仰ぐ開放的な露天風呂を備えた天然温泉施設です。
遮るもののない東の空に大きく開けたロケーションは、豊かな陽光、時には穏やかな月の光を浴びながら、癒しのひとときをお楽しみいただけます。
高知の市街地にありながら、一歩足を踏み入れればそこは大正浪漫の薫る別世界。 土佐望月温泉 姫若子の湯は、県内最大級の空を仰ぐ開放的な露天風呂を備えた天然温泉施設です。 遮るもののない東の空に大きく開け ...
#温泉
-
650. 中濱萬次郎翁記念碑正五位が贈られた記念に出生地である土佐清水市に建てられた中濱萬次郎記念碑。米ひきの失敗を咎められて飛び出した先で、漁師になるきっかけとなる出会いがあったというエピソードから手前には石臼が置かれています。日本人として初めてアメリカに渡り、西洋の知識や情報を持ち帰った萬次郎は、当時の日本に多大な功績を残しました。32.75794 132.96417
正五位が贈られた記念に出生地である土佐清水市に建てられた中濱萬次郎記念碑。米ひきの失敗を咎められて飛び出した先で、漁師になるきっかけとなる出会いがあったというエピソードから手前には石臼が置かれていま...
#銅像・記念碑
-
651. 程野の滝滝の高さは60m~100m。幅約4キロの絶壁から4本の滝(東滝、西滝、権現滝、大樽の滝)がほぼ等間隔に流れ落ちる全国的にも珍しい滝。土佐の名水40選にも指定されています。33.71267 133.34605
滝の高さは60m~100m。幅約4キロの絶壁から4本の滝(東滝、西滝、権現滝、大樽の滝)がほぼ等間隔に流れ落ちる全国的にも珍しい滝。土佐の名水40選にも指定されています。
#景観(川)
-
652. 林有造像逓信大臣、農商務大臣となる一方、終始、故郷の宿毛発展に尽した政治家・林有造の徳を称え、建設された銅像。初代の高知県知事で、板垣退助の片腕として中央政界でも波乱の生活を送った有造は、片岡健吉らと立志社を創設し、自由民権運動に参加。宿毛に帰ってからは、新田築造などの宿毛発展策を推進しました。32.9247 132.70227
逓信大臣、農商務大臣となる一方、終始、故郷の宿毛発展に尽した政治家・林有造の徳を称え、建設された銅像。初代の高知県知事で、板垣退助の片腕として中央政界でも波乱の生活を送った有造は、片岡健吉らと立志社...
#銅像・記念碑
-
653. 上街公園この地の豪族本山氏の土居屋敷の跡であり、町の指定文化財。藩政時代には参勤交代の藩主が投宿したともいわれ、土地代々の領主が居宅を構えました。その名残は石垣がわずかに残るのみ。現在は住民憩いの場として姿を変え、春には桜が咲き、花見客で賑わう公園となっています。33.757416 133.58693
この地の豪族本山氏の土居屋敷の跡であり、町の指定文化財。藩政時代には参勤交代の藩主が投宿したともいわれ、土地代々の領主が居宅を構えました。その名残は石垣がわずかに残るのみ。現在は住民憩いの場として姿...
#公園
#花・植物
-
654. 沖の島磯釣りやマリンスポーツの島として人気。島は花崗岩から成り、至る所に断崖や急斜地が見られます。母島地区と弘瀬地区を中心に大小五つの集落で形成され、支所や漁協・郵便局・小中学校・診療所などの施設があります。32.72856 132.55655
磯釣りやマリンスポーツの島として人気。島は花崗岩から成り、至る所に断崖や急斜地が見られます。母島地区と弘瀬地区を中心に大小五つの集落で形成され、支所や漁協・郵便局・小中学校・診療所などの施設がありま...
#景観(海)
-
655. 枝川古墳群須恵器のほかに人骨も出土し注目された横穴式石室墳で、1966年に発掘されました。いの町の文化財に指定されています。33.551994 133.46346
須恵器のほかに人骨も出土し注目された横穴式石室墳で、1966年に発掘されました。いの町の文化財に指定されています。
#文化財・史跡
-
656. 津野親忠の墓県指定の史跡。津野親忠は、長宗我部元親の三男で、高岡郡の半山城主津野勝興の養子となりました。天正14年(1582)、元親の長男信親が豊後戸次川の戦で戦死したので家督相続の問題がおこり、親忠を立てようとした吉良親実、比江山親興等は棟言して切腹させられました。33.582714 133.67786
親忠はこの地に幽閉され関ヶ原の戦いで敗れた長宗我部盛親の謀略により、29歳で自害させられました。後に墓の上に社殿を建て津野神社として祀られ、墓標の五輪塔は50m北の墓地に移されました。
県指定の史跡。津野親忠は、長宗我部元親の三男で、高岡郡の半山城主津野勝興の養子となりました。天正14年(1582)、元親の長男信親が豊後戸次川の戦で戦死したので家督相続の問題がおこり、親忠を立てようとした吉良 ...
#文化財・史跡
-
657. 木造金剛力士立像高知県に伝わる谷地仁王門の金剛力士像は、かつて谷地の法華寺(廃寺)に安置されていた仏教彫刻です。阿形像が約204cm、吽形像が200cmの堂々たる像高を誇り、ヒノキの寄木造、彫眼の彩色像として制作されました。33.49092 133.32965
肉身部を朱色、裳を黒色で彩色したこの像は、全体的にバランスが良く、特に顔面と上半身は力強い表現に満ちています。ただし下半身はやや上体との均衡を欠き、指の表現も五本とも同形同大で変化に乏しいことから、未完成とも言われています。
それでも地方の金剛力士像としては秀作と評価されており、制作時期は室町時代かやや後の時代と推定されています。中央の様式を取り入れながらも、地方の仏師による独自の工夫が見られる貴重な文...
高知県に伝わる谷地仁王門の金剛力士像は、かつて谷地の法華寺(廃寺)に安置されていた仏教彫刻です。阿形像が約204cm、吽形像が200cmの堂々たる像高を誇り、ヒノキの寄木造、彫眼の彩色像として制作されました。 肉身 ...
#銅像・記念碑
-
658. 第29番札所 国分寺天平13年(西暦741年)聖武天皇の勅願により僧行基が開創。天下泰平等を願う祈願所として金光明四天王護国之寺と呼ばれてきました。後に弘法大師(空海)が中興し、四国八十八ヶ所霊場となりました。33.59861 133.64046
土佐日記の作者、紀貫之が国司として滞在した地として知られ、戦国時代の長宗我部氏、江戸時代に入り山内藩主より寺領が与えられ伽藍が維持されてきました。
境内全域が国の史跡。金堂・梵鐘・木造薬師如来像2体が国の重要文化財に指定。
天平13年(西暦741年)聖武天皇の勅願により僧行基が開創。天下泰平等を願う祈願所として金光明四天王護国之寺と呼ばれてきました。後に弘法大師(空海)が中興し、四国八十八ヶ所霊場となりました。 土佐日記の作者、紀 ...
#寺社
-
賛助会員659. ゆすはら雲の上観光協会梼原町は、高知県と愛媛県の県境にある小さな町です。33.391556 132.92686
この小さな町に、歴史、森林・自然、隈研吾建築など、見どころが詰まっています。
案内所では、翻訳システムを使用することで外国の方も対応が可能となっており、多言語の観光パンフレット(英語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語)も用意しています。
また、森林・自然ガイドツアー、隈研吾建築ガイドツアーなど(要予約)があります。
梼原町は、高知県と愛媛県の県境にある小さな町です。 この小さな町に、歴史、森林・自然、隈研吾建築など、見どころが詰まっています。 案内所では、翻訳システムを使用することで外国の方も対応が可能となって ...
#観光案内所
-
660. 坂本家初代・太郎五郎の墓坂本家初代・太郎五郎の墓は、石の観音扉が付いた石殿に入っています。墓の側面には、山城国の生まれで、畿内の欄を避けて弘治・永禄(1555年~1570年)の頃に移り住んだことが刻まれています。33.63241 133.64594
南国市才谷にある初代から三代目までの墓を建てたのは、六代目の坂本直益で、この人物が坂本という名字を使い始めました。太郎五郎の名前は、長宗我部検地帳にも記載されています。
坂本家初代・太郎五郎の墓は、石の観音扉が付いた石殿に入っています。墓の側面には、山城国の生まれで、畿内の欄を避けて弘治・永禄(1555年~1570年)の頃に移り住んだことが刻まれています。 南国市才谷にある初 ...
#文化財・史跡
-
661. トンボ自然公園世界初のトンボ保護区。群れ飛ぶトンボのほか、スイレンやハナショウブなど、四季の花もおすすめ。園内の「四万十川学遊館あきついお」では四万十のアカメなど、世界のトンボ標本や淡水・海水魚が見られます。32.98989 132.90874
世界初のトンボ保護区。群れ飛ぶトンボのほか、スイレンやハナショウブなど、四季の花もおすすめ。園内の「四万十川学遊館あきついお」では四万十のアカメなど、世界のトンボ標本や淡水・海水魚が見られます。
#公園
#花・植物
-
662. 柏島観光情報発信センター柏島を訪れる多くの観光客が最初に立ち寄る、観光案内所兼販売施設です。柏島観光の際は、まずここの駐車場に車を停めるのが基本となっています。島内の飲食店、宿泊施設、ダイビングショップなど、柏島観光に必要な情報がすべて揃う便利な拠点です。32.767708 132.62717
柏島観光の際は、この観光案内所の駐車場を利用するのが基本です。車を停めたら、島内の観光情報をここで収集してからスタートしましょう。
観光案内だけでなく、柏島オリジナルグッズや軽食の販売も行っており、休憩スポットとしても最適です。周辺地域の観光パンフレットも豊富に用意されています。
柏島を訪れる多くの観光客が最初に立ち寄る、観光案内所兼販売施設です。柏島観光の際は、まずここの駐車場に車を停めるのが基本となっています。島内の飲食店、宿泊施設、ダイビングショップなど、柏島観光に必要...
#観光案内所
-
663. 唐浜休憩所安田町の姉妹都市であるスペイン・モンテフリオをイメージしたヨーロッパ風の休憩所。33.44198 133.96548
海の景色と波の音を楽しめる写真スポットです。
安田町の姉妹都市であるスペイン・モンテフリオをイメージしたヨーロッパ風の休憩所。 海の景色と波の音を楽しめる写真スポットです。
#景観(海)
#道の駅・休憩所
-
664. 安田八幡宮安田町役場の西方に鎮座する安田八幡宮は、戦国時代の領主・安田三河守によって創建されたと伝えられる歴史ある神社です。鎌倉時代に安田に移住した椎宗氏が安田を領有し、地名から安田氏を名乗り、領地の鎮守として安田八幡宮を造営しました。安田家代々の氏神として特に信仰が厚く、度々神殿の新築や改装が行われ、社領も寄進されてきました。33.43895 133.98056
足摂津彦命・気長足姫命・応神天皇を祭神とし、昔から安田・西島・唐浜・東島・中山・馬路の総鎮守として崇敬されています。参道の玉垣を構成する石柱には、八幡宮に信仰を寄せる寄進者の名や、天明35年(1815年)、天保13年(1843年)、嘉永元年(1848年)などの寄進年月が刻まれ、山形屋・久保屋・松屋 ...
安田町役場の西方に鎮座する安田八幡宮は、戦国時代の領主・安田三河守によって創建されたと伝えられる歴史ある神社です。鎌倉時代に安田に移住した椎宗氏が安田を領有し、地名から安田氏を名乗り、領地の鎮守とし...
#寺社
-
665. 日ノ浦あじさい街道越知町鎌井田日ノ浦地区では、地区が一丸となって黒石小学校から日ノ浦集会所までの道沿いにあじさいを植える取り組みを続けてきました。こつこつと増やし育ててきたあじさいも今では約2万株を数え、延長も約10km超えになり、「日ノ浦 あじさい街道」として毎年6月中旬から7月上旬になると色鮮やかな花が楽しめます。33.587574 133.22975
越知町鎌井田日ノ浦地区では、地区が一丸となって黒石小学校から日ノ浦集会所までの道沿いにあじさいを植える取り組みを続けてきました。こつこつと増やし育ててきたあじさいも今では約2万株を数え、延長も約10km超 ...
#花・植物
-
666. 林譲治像自由民権運動家としても活躍した明治・大正期の政治家・林有造の次男。汚職に満ちた環境にありながらも、節義を曲げなかった譲治を敬愛する人びとによって、郷里の地に銅像が建てられました。戦後、吉田内閣で内閣書記官長に就任し、外交官出身で内政や党務に弱い吉田を、大野伴睦(自由党幹事長)とともに補佐。実父が宿毛市出身の吉田と、同市出身の林の組み合わせから、世間からは「宿毛内閣」と呼ばれました。32.93904 132.72575
自由民権運動家としても活躍した明治・大正期の政治家・林有造の次男。汚職に満ちた環境にありながらも、節義を曲げなかった譲治を敬愛する人びとによって、郷里の地に銅像が建てられました。戦後、吉田内閣で内閣...
#銅像・記念碑
-
667. 皇太子殿下御歌(歌碑)当時の皇太子殿下(平成天皇)が昭和51年7月27・28日と自然公園大会で土佐清水市の足摺岬に立ち寄られたあと、昭和52年の歌会始の時に読まれた歌を記念して、歌碑として建立されました。32.727 133.0212
当時の皇太子殿下(平成天皇)が昭和51年7月27・28日と自然公園大会で土佐清水市の足摺岬に立ち寄られたあと、昭和52年の歌会始の時に読まれた歌を記念して、歌碑として建立されました。
#銅像・記念碑
-
668. 森林生態学習館「グリーン・パークほどの」にある学習施設。33.70849 133.3646
課外学習やレクリエーション、研修などに利用いただけます。
「グリーン・パークほどの」にある学習施設。 課外学習やレクリエーション、研修などに利用いただけます。
#ミュージアム
-
669. 伊野直販所季節ごとに、いの町内や近隣市町村の新鮮な野菜や果物、花き等が店内に並びます。33.548264 133.43088
季節ごとに、いの町内や近隣市町村の新鮮な野菜や果物、花き等が店内に並びます。
#市場・直売所
-
670. 宮の前公園秋には150万本のコスモス公園一面に咲き誇ります。33.536114 133.24495
毎年の恒例行事である「コスモスまつり」も行われます。
秋には150万本のコスモス公園一面に咲き誇ります。 毎年の恒例行事である「コスモスまつり」も行われます。
#花・植物
#公園
-
671. 中津明神山中津明神山(標高1541m)頂上には笹原が広がり、鳥居や祠、平家落人の城跡と伝えられる「名野川城跡」の立札があります。四方に眺望が広がり、頂上まで車でのぼることも可能。頂上近くには四国の雨量観測を行う国土交通省の雨量レーダーがあります。33.57359 133.04704
中津明神山(標高1541m)頂上には笹原が広がり、鳥居や祠、平家落人の城跡と伝えられる「名野川城跡」の立札があります。四方に眺望が広がり、頂上まで車でのぼることも可能。頂上近くには四国の雨量観測を行う国 ...
#景観(山)
-
672. 田中光顕屋敷跡の碑佐川町から東へ国道33号線を15分あまり歩いた山手にある、佐川勤王の中心人物である田中光顕・大橋慎三・山中安敬らの屋敷跡に立つ碑。周囲は公園になっています。33.5014 133.29987
佐川町から東へ国道33号線を15分あまり歩いた山手にある、佐川勤王の中心人物である田中光顕・大橋慎三・山中安敬らの屋敷跡に立つ碑。周囲は公園になっています。
#銅像・記念碑
-
673. 中岡慎太郎像(北川村)脱藩を決意し北川村を後に旅立つ慎太郎の姿を表しています。33.45678 134.05692
室戸岬にある中岡慎太郎像とは趣が異なり、躍動感とエネルギーに満ちた印象的な姿です。
1999(平成11)年に生誕160年を記念して全国からの募金によって建立されました。
この石碑の中には建立記念誌、北川小・中学校の文集がタイムカプセルとして埋蔵され、生誕200年(2038)の年に取り出されることになっています。
脱藩を決意し北川村を後に旅立つ慎太郎の姿を表しています。 室戸岬にある中岡慎太郎像とは趣が異なり、躍動感とエネルギーに満ちた印象的な姿です。 1999(平成11)年に生誕160年を記念して全国からの募金によって ...
#銅像・記念碑
-
674. 宝鏡寺跡県の史跡。中世、付近一帯を統治した香宗我部氏の菩提寺跡。寺跡の北300mの八幡宮あたりが居城の香宗城跡。33.555206 133.7198
県の史跡。中世、付近一帯を統治した香宗我部氏の菩提寺跡。寺跡の北300mの八幡宮あたりが居城の香宗城跡。
#文化財・史跡
-
675. 有井庄司の墓県指定の史跡。元弘の乱(1331年)で土佐に流された尊良親王(後醍醐天皇の第一皇子)をかくまった鎌倉時代の勤王家有井庄司の墓。33.040848 133.07149
鎌倉幕府滅亡後、帰京した親王から死亡した有井氏を悼み五輪塔が送られました。
県指定の史跡。元弘の乱(1331年)で土佐に流された尊良親王(後醍醐天皇の第一皇子)をかくまった鎌倉時代の勤王家有井庄司の墓。 鎌倉幕府滅亡後、帰京した親王から死亡した有井氏を悼み五輪塔が送られました。
#文化財・史跡
-
676. 清流四万十の里 十和温泉四万十川のほとりに佇む「十和温泉」は、雄大川の流れを眼下に望む最高のロケーションを誇ります。33.2313 132.84691
浴室の窓からは四万十の緑が広がり、静寂に包まれた癒しのひとときを過ごせます。
四万十川のほとりに佇む「十和温泉」は、雄大川の流れを眼下に望む最高のロケーションを誇ります。 浴室の窓からは四万十の緑が広がり、静寂に包まれた癒しのひとときを過ごせます。
#温泉
#旅館
-
677. かざぐるま市JA女性部が運営する直販所。旬の野菜や果物、花、加工品などが魅力です。33.580658 133.66252
店舗には加工所も併設しており、手作り弁当やお寿司、惣菜なども人気です。
また、季節に合わせたイベント(母の日・父の日・新米まつりなど)も随時開催しています。
JA女性部が運営する直販所。旬の野菜や果物、花、加工品などが魅力です。 店舗には加工所も併設しており、手作り弁当やお寿司、惣菜なども人気です。 また、季節に合わせたイベント(母の日・父の日・新米まつ ...
#市場・直売所
-
678. 箸拳発祥の地高知の伝統的なお座敷遊びである箸拳。32.93701 132.72932
嘉永2年(1849)の頃、宿毛の船宿である大黒屋丑松方に宿泊した九州の船頭によって薩摩拳が伝えられ、それが箸拳となって普及しました。
高知の伝統的なお座敷遊びである箸拳。 嘉永2年(1849)の頃、宿毛の船宿である大黒屋丑松方に宿泊した九州の船頭によって薩摩拳が伝えられ、それが箸拳となって普及しました。
#銅像・記念碑
-
679. 北川村文化観光公社95%が山。そんな自然がいっぱいある北川村の魅力を紹介している。33.44849 134.04199
ここは、モネと中岡慎太郎の面影残る山里であり、現在、柚子玉がフランスへ向けて輸出もされている、日本でも有数の柚子の産地でもある。
観光案内は、お電話やHP等からのお問合せのみ対応しています。
95%が山。そんな自然がいっぱいある北川村の魅力を紹介している。 ここは、モネと中岡慎太郎の面影残る山里であり、現在、柚子玉がフランスへ向けて輸出もされている、日本でも有数の柚子の産地でもある。 観光 ...
#観光案内所
-
680. ふれあいの市 マルナカ野市店JA高知県女性部土佐香美地区野市支部が、マルナカ店内にコーナーを設けて運営しています。33.56307 133.7014
朝とれたての農産物や手作りの加工品があり種類も豊富。
生産者1人ひとりのプレートを置いているので、「顔の見える直販」として信頼性も高く人気です。
JA高知県女性部土佐香美地区野市支部が、マルナカ店内にコーナーを設けて運営しています。 朝とれたての農産物や手作りの加工品があり種類も豊富。 生産者1人ひとりのプレートを置いているので、「顔の見える ...
#市場・直売所
-
681. 野村茂久馬像日露戦役には戦時輸送など、陸海に事業を拡げ、後に土佐の交通王とよばれた野村茂久馬の銅像が、丸の内緑地公園の東北角に佇んでいます。安芸郡奈半利村に生まれた茂久馬は、高知県交通バスの前身である野村組自動車部、そして新高知重工業の前身である野村組工作所の創設者となり、四国のバス事業の統合、高知鉄道、土佐商船などの設立に力をつくしました。33.559856 133.53336
日露戦役には戦時輸送など、陸海に事業を拡げ、後に土佐の交通王とよばれた野村茂久馬の銅像が、丸の内緑地公園の東北角に佇んでいます。安芸郡奈半利村に生まれた茂久馬は、高知県交通バスの前身である野村組自動...
#銅像・記念碑
-
682. 小野梓記念公園宿毛市出身の小野梓は、大隈重信と共に立憲改進党を創立し、早稲田大学の前身である東京専門学校を設立しました。32.93701 132.72887
35歳の若さで病気のため亡くなりましたが、多くの功績を残しました。
彼の生誕150年を記念してつくられた公園内には、彼の胸像とともに、小松製作所創始者・竹内明太郎、冨山房創始者・坂本嘉治馬の像も建立されています。
宿毛市出身の小野梓は、大隈重信と共に立憲改進党を創立し、早稲田大学の前身である東京専門学校を設立しました。 35歳の若さで病気のため亡くなりましたが、多くの功績を残しました。 彼の生誕150年を記念してつく ...
#公園
#銅像・記念碑
-
683. 早明浦ダム吉野川水系吉野川にある重力式コンクリートダム。33.756668 133.55055
堤高106m、堤頂長400m。
長岡郡本山町と土佐郡土佐町・大川村にまたがり、総貯水量3億1600万立法メートルを誇ります。
四国四県を潤し、四国の水瓶とも例えられます。
吉野川水系吉野川にある重力式コンクリートダム。 堤高106m、堤頂長400m。 長岡郡本山町と土佐郡土佐町・大川村にまたがり、総貯水量3億1600万立法メートルを誇ります。 四国四県を潤し、四国の水瓶とも例えられます。
#景観(川)
-
684. 寒風山標高1763m。33.812374 133.26178
ササ原の頂上からの周囲の展望が素晴らしく、四国山地や法皇山脈の高い峰々、西条市の臨海工業地帯、瀬戸内から中国山地まで遠望できます。
ブナ・ナンゴクミネカエデ・ベニドウダン・コメツツジ・ツクシシャクナゲ等が四季を通して楽しめます。
標高1763m。 ササ原の頂上からの周囲の展望が素晴らしく、四国山地や法皇山脈の高い峰々、西条市の臨海工業地帯、瀬戸内から中国山地まで遠望できます。 ブナ・ナンゴクミネカエデ・ベニドウダン・コメツツジ・ツク...
#景観(山)
-
685. 後藤象二郎誕生地の碑1838年(天保9年)に象二郎はこの地で生まれました。生家は馬廻150石の上士。義理の叔父吉田東洋の死後、その志を継いで土佐藩の近代化につとめ、長崎では勤王党の坂本龍馬と手を握り、山内容堂に説いて大政奉還を実現。維新以後は民権運動にも関係しました。33.55646 133.53723
1838年(天保9年)に象二郎はこの地で生まれました。生家は馬廻150石の上士。義理の叔父吉田東洋の死後、その志を継いで土佐藩の近代化につとめ、長崎では勤王党の坂本龍馬と手を握り、山内容堂に説いて大政奉還を実 ...
#銅像・記念碑
-
686. 八田堰江戸時代初期の土佐藩の執政、野中兼山が灌漑のために、慶安元年(1648)から6年の歳月を費やして仁淀川に造った堰(の跡)。33.52811 133.43098
現在の堰は昭和に入って改修されたものです。
江戸時代初期の土佐藩の執政、野中兼山が灌漑のために、慶安元年(1648)から6年の歳月を費やして仁淀川に造った堰(の跡)。 現在の堰は昭和に入って改修されたものです。
#文化財・史跡
-
687. 熊野神社(四万十町)鎌倉時代の初め、平家方の落人で紀州熊野権現の別当、田那部旦僧の子永旦が熊野より勧請したのが起こりと伝えられています。33.19185 132.97151
別当の長楽寺に安置されてあった、木造如来形立像と木造地蔵菩薩立像が伝存していて、県の指定文化財になっています。
鎌倉時代の初め、平家方の落人で紀州熊野権現の別当、田那部旦僧の子永旦が熊野より勧請したのが起こりと伝えられています。 別当の長楽寺に安置されてあった、木造如来形立像と木造地蔵菩薩立像が伝存していて、 ...
#寺社
-
688. 波川公園仁淀ブルーの愛称で知られる仁淀川のほとりにある親水公園。夏には川遊びにやってくる大勢の人で賑わいます。河原が広く、高知市内からも近いことから、流域の利用者数は随一。国道沿いにあり、すぐ近くにスーパーやコンビニ、宿泊施設もあるためキャンプや水遊びをするには最適。浅瀬もあるため水浴びをすることができます(ただし川の中央に近付くほど川底が深く、流れも速くなるので注意が必要)。33.548985 133.41508
すぐそばにある「水辺の駅にこにこ館」ではバーベキュー道具の貸し出しや、食材の提供も行っています。
仁淀川橋からは仁淀川の雄大な景色を望むことができます。
毎年5月3日~5日に行われるイベント「神のこいのぼり」の遊泳会場になっ ...
仁淀ブルーの愛称で知られる仁淀川のほとりにある親水公園。夏には川遊びにやってくる大勢の人で賑わいます。河原が広く、高知市内からも近いことから、流域の利用者数は随一。国道沿いにあり、すぐ近くにスーパー...
#景観(川)
#公園
-
689. 高松順蔵・千鶴の墓千鶴は坂本龍馬の長姉で、親戚である高松順蔵の元へ嫁ぎました。順蔵は文武両道に秀で人徳もあったため、近隣の石田英吉や清岡道之助、柏原禎吉など多数の若者から慕われました。33.44073 133.98064
安田小学校の左手道ばたに「高松小埜・千鶴の墓所」への案内板があります。
千鶴は坂本龍馬の長姉で、親戚である高松順蔵の元へ嫁ぎました。順蔵は文武両道に秀で人徳もあったため、近隣の石田英吉や清岡道之助、柏原禎吉など多数の若者から慕われました。 安田小学校の左手道ばたに「高松 ...
#文化財・史跡
-
690. 徳弘孝蔵(董斎)邸跡文化4年(1807年)8月15日、中須賀の地に保孝(号石門)の長男として生まれた徳弘董斎は、西洋流砲術の先駆者として幕末の土佐に新風を吹き込み、さらに南画の大家としても知られる二刀流の才人でした。33.557743 133.51361
75歳を迎えた明治14年(1881年)5月25日に世を去るまで、砲術指南役や画家として多くの門弟を育成し、国内外に大きな影響を残しました。
昭和56年(1981年)春に子孫の不慮の火災事故により籍が途絶えたのち、生誕地は地域住民の憩いの場として中須賀公園に整備されました。
幕末土佐の技術革新と美術文化の融合を象徴する史跡として、多くの方に訪れていただきたいスポットです。
文化4年(1807年)8月15日、中須賀の地に保孝(号石門)の長男として生まれた徳弘董斎は、西洋流砲術の先駆者として幕末の土佐に新風を吹き込み、さらに南画の大家としても知られる二刀流の才人でした。 75歳を迎え ...
#文化財・史跡
-
691. 筒上山標高1859m。登山道の周囲にはササ原、キレンゲショウマの群落が広がり、頂上からの眺望も良いです。33.73263 133.16075
標高1859m。登山道の周囲にはササ原、キレンゲショウマの群落が広がり、頂上からの眺望も良いです。
#景観(山)
-
692. 近藤長次郎邸跡高知市水道町、河田小龍塾跡から北へ進んだ道端に、近藤長次郎邸跡の碑が建立されています。天保9年(1838年)、餅菓子・饅頭屋の息子としてこの地に生まれた長次郎は、「饅頭屋長次郎」とも呼ばれました。少年時代から近隣の坂本龍馬と親交を持ち、後に河田小龍、勝海舟の門下に入ります。長州藩の外国船砲撃事件の調停や、亀山社中周旋役としてユニオン号購入を成功させるなど、龍馬を支える重要な役割を果たしました。しかし、長州から得た報賞金による独断でのイギリス留学計画が社中規定に反したため露見し、慶応2年(1866年)に29歳で切腹。龍馬がその死を深く惜しんだ天才志士の足跡を、この碑が今に伝えています。33.5564 133.52307
高知市水道町、河田小龍塾跡から北へ進んだ道端に、近藤長次郎邸跡の碑が建立されています。天保9年(1838年)、餅菓子・饅頭屋の息子としてこの地に生まれた長次郎は、「饅頭屋長次郎」とも呼ばれました。少年時代 ...
#文化財・史跡
-
693. 日高村立能津小学校アニメ映画『竜とそばかすの姫』に登場する廃校を使った集落活動センターのモデルとなりました。33.55968 133.3368
本物は現役の小学校です。
※内部の開放はしておりませんので、敷地内への立ち入りはご遠慮ください。
アニメ映画『竜とそばかすの姫』に登場する廃校を使った集落活動センターのモデルとなりました。 本物は現役の小学校です。 ※内部の開放はしておりませんので、敷地内への立ち入りはご遠慮ください。
#作品ゆかりの地
-
694. 板垣退助の墓自由民権運動で知られる板垣退助は、1837(天保8)年に土佐藩中島町(現在の高知市本町)に生まれました。33.58369 133.56247
板垣らが設立した立志社を中心とした自由民権運動は全国に広がり、「自由は土佐の山間より出づ」と言われました。
明治15年4月6日、暴漢に刺された際に口にした「板垣死すとも自由は死せず」の言葉が有名で、自由民権運動はその後の憲法発布、国会開設へ繋がっていきました。
明治33年の政界引退後は社会改良運動に尽くし、大正8(1919)年7月16日に83歳で死去しました。
自由民権運動で知られる板垣退助は、1837(天保8)年に土佐藩中島町(現在の高知市本町)に生まれました。 板垣らが設立した立志社を中心とした自由民権運動は全国に広がり、「自由は土佐の山間より出づ」と言われ ...
#文化財・史跡
-
695. 古津賀古墳土佐くろしお鉄道鉄橋の下流で、弥生時代中期~古墳時代に営まれた遺跡です。32.984325 132.95686
当時の人々の川のかかわりや、それに対する信仰の一部が見える祭祀遺跡です。同じ祭祀遺跡に佐岡遺跡、具同中山遺跡群等があります。
土佐くろしお鉄道鉄橋の下流で、弥生時代中期~古墳時代に営まれた遺跡です。 当時の人々の川のかかわりや、それに対する信仰の一部が見える祭祀遺跡です。同じ祭祀遺跡に佐岡遺跡、具同中山遺跡群等があります。
#文化財・史跡
-
696. 中岡慎太郎遺髪墓地禅宗寺院。戦国時代に北川郷を支配していた北川玄蕃頭の菩提寺で、江戸時代は八ヶ寺の末寺をもっていましたが、相次ぐ火災のため現在は山門のみ残っています。慎太郎は4歳になると、この寺の住職禅定和尚について読書を学んだと伝えられています。33.45689 134.05798
境内の墓地には、慎太郎の遺髪を納めた墓碑、両親・妻兼ら家族、慎太郎の義兄北川武平次、野根山二十三士に加わった新井竹次郎の養父新井林左衛門などの墓があります。
禅宗寺院。戦国時代に北川郷を支配していた北川玄蕃頭の菩提寺で、江戸時代は八ヶ寺の末寺をもっていましたが、相次ぐ火災のため現在は山門のみ残っています。慎太郎は4歳になると、この寺の住職禅定和尚について ...
#文化財・史跡
-
697. 平井収二郎・加尾誕生地土佐勤王党に参加し、尊王攘夷運動に奔走した平井収二郎、その妹の加尾はこの地に誕生しました。収二郎の切腹を聞いた坂本龍馬は、「平井の収二郎ハ誠にむごいむごい、いもふとおかおがなげき、いか斗か」と、姉乙女への手紙に書き記しています。龍馬にとって痛恨事であったとともに、龍馬と平井兄妹との親密な関係を察することができます。33.56133 133.51277
土佐勤王党に参加し、尊王攘夷運動に奔走した平井収二郎、その妹の加尾はこの地に誕生しました。収二郎の切腹を聞いた坂本龍馬は、「平井の収二郎ハ誠にむごいむごい、いもふとおかおがなげき、いか斗か」と、姉乙...
#文化財・史跡
-
698. 白髪山(本山町)高知に二つある白髪山の一つで、別名を奥白髪山。自生のシャクナゲ(5月下旬から6月)やオオヤマレンゲ(6月中旬)が見られます。また、根下がりヒノキや頂上の白骨林も見どころ。登山途中にはオブジェ風の倒木などが目を楽しませます。33.816097 133.59032
高知に二つある白髪山の一つで、別名を奥白髪山。自生のシャクナゲ(5月下旬から6月)やオオヤマレンゲ(6月中旬)が見られます。また、根下がりヒノキや頂上の白骨林も見どころ。登山途中にはオブジェ風の倒木など...
#景観(山)
-
699. 五社神社【三原村】創祀年代は不詳ながら、古記によれば大永三年(1523)に再興された三原神社。以来、三原郷の総鎮守として地域の人々から厚く崇敬されてきました。32.92236 132.84647
寛政八年(1796)に火災により焼失しましたが、同地に再建。約200年にわたって数度の改築が行われ、明治五年(1872)には郷社に列せられ、幣帛共進指定も受けています。昭和二十一年(1946)には神社制度の改革に伴って宗教法人となりました。
創祀年代は不詳ながら、古記によれば大永三年(1523)に再興された三原神社。以来、三原郷の総鎮守として地域の人々から厚く崇敬されてきました。 寛政八年(1796)に火災により焼失しましたが、同地に再建。約200年 ...
#寺社
-
700. 藤林寺藤林寺は応仁の乱を逃れて中村(現四万十市)に下向した元関白一条教房公の子、房家公の菩提寺です。毎年8月16日には、市無形文化財に指定されている「ヤーサイ」(夜祭、野菜祭)が行われます。最初に「竹回し」と言われる行事が行われ、大竹数十本が土俵の回りを回る様子は豪快です。その後、奉納盆踊、チビッ子相撲等があり、近隣から多くの人出があり夜遅く迄にぎわいます。32.94783 132.79408
藤林寺は応仁の乱を逃れて中村(現四万十市)に下向した元関白一条教房公の子、房家公の菩提寺です。毎年8月16日には、市無形文化財に指定されている「ヤーサイ」(夜祭、野菜祭)が行われます。最初に「竹回し」と...
#寺社
-
701. 二十三士殉節地幕末の土佐藩士・清岡道之助、以下二十三士が処刑された場所。33.430305 134.01707
昭和5年天皇御大典記念として、町青年団が建てたもので、碑面には、田野町出身の故浜口雄幸元内閣総理大臣の書が刻まれています。
幕末の土佐藩士・清岡道之助、以下二十三士が処刑された場所。 昭和5年天皇御大典記念として、町青年団が建てたもので、碑面には、田野町出身の故浜口雄幸元内閣総理大臣の書が刻まれています。
#文化財・史跡
-
702. 板垣退助誕生地の碑自由民権運動で知られる板垣退助は、1837(天保8)年に土佐藩中島町(現在の高知市本町)に生まれました。33.558113 133.53705
板垣らが設立した立志社を中心とした自由民権運動は全国に広がり、「自由は土佐の山間より出づ」と言われました。
明治15年4月6日、暴漢に刺された際に口にした「板垣死すとも自由は死せず」の言葉が有名で、自由民権運動はその後の憲法発布、国会開設へ繋がっていきました。
自由民権運動で知られる板垣退助は、1837(天保8)年に土佐藩中島町(現在の高知市本町)に生まれました。 板垣らが設立した立志社を中心とした自由民権運動は全国に広がり、「自由は土佐の山間より出づ」と言われ ...
#銅像・記念碑
-
703. 野中神社(お婉堂)江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。33.611225 133.67073
藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する等、大きな功績を上げました。
しかし、厳しすぎる姿勢が領民や上級武士の反感を買うなどして失脚、兼山の死後は野中家はお取り潰しとなりました。
兼山の没後、四女の婉は医者をしながら、谷泰山から儒学、神道を学び、誇りであった父兼山を祀るため、1708年、野中家の遺品を売却し、兼山の旧臣であった古槇氏とともに祖先の祠室を建立しました。この野中神社はお婉堂と呼ばれ、当時の面影をそのままに、ひっそりとした佇まいを見せて...
江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。 藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する等...
#寺社
-
704. かがみ温泉RIO高知市鏡地区にある、山々の緑と鏡川の景色を望む温泉。春は桜、秋にはいちょうの紅葉も楽しめます。33.602623 133.47374
高知市鏡地区にある、山々の緑と鏡川の景色を望む温泉。春は桜、秋にはいちょうの紅葉も楽しめます。
#温泉
-
705. 八坂神社八坂神社は、1392年(元中9年・明徳3年)11月7日に、落人武士と伝わる井上治部によって勧請されたと伝えられています。33.68426 133.34125
境内には、ヒノキやコウヤマキなどの木々が群生しており、見事な景観を作り出しています。長い歴史を持つ社は、深い森の中で静かにその歴史を紡ぎ続けています。
八坂神社は、1392年(元中9年・明徳3年)11月7日に、落人武士と伝わる井上治部によって勧請されたと伝えられています。 境内には、ヒノキやコウヤマキなどの木々が群生しており、見事な景観を作り出しています。長い ...
#寺社
-
706. JAグリーンはた宿毛店 産直ぴかいち文旦や小夏、ブロッコリー、オクラなど、春夏秋冬、様々な特産品が揃う直販所。32.934196 132.72556
おすすめ商品は、月・水・金曜日に入荷する豚肉と、近海でとれた鮮魚です。
柑橘類が豊富で、特に2月から入荷する「宿毛文旦」は全国から注文のある人気商品です。
文旦や小夏、ブロッコリー、オクラなど、春夏秋冬、様々な特産品が揃う直販所。 おすすめ商品は、月・水・金曜日に入荷する豚肉と、近海でとれた鮮魚です。 柑橘類が豊富で、特に2月から入荷する「宿毛文旦」は ...
#市場・直売所
-
707. 浜口雄幸旧邸雄幸は旧制第三高等学校在学中、高知市五台山唐谷の水口家から浜口家に養子に来ました。その後、東京帝国大学を卒業し政界に進み、土佐出身の最初の内閣総理大臣となりました。邸前には「なすことのいまだ終らず春を待つ」の雄幸直筆の碑が建っています。33.43412 134.01813
雄幸は旧制第三高等学校在学中、高知市五台山唐谷の水口家から浜口家に養子に来ました。その後、東京帝国大学を卒業し政界に進み、土佐出身の最初の内閣総理大臣となりました。邸前には「なすことのいまだ終らず春...
#文化財・史跡
-
708. 中筋川ダム渡川水系中筋川にある重力式コンクリートダム。堤高73.1m、堤頂長217.5m。本格的な景観設計が導入され、堤体は左右対称で落ち着きがある。平成13年度土木学会デザイン賞優秀賞。32.927223 132.81055
渡川水系中筋川にある重力式コンクリートダム。堤高73.1m、堤頂長217.5m。本格的な景観設計が導入され、堤体は左右対称で落ち着きがある。平成13年度土木学会デザイン賞優秀賞。
#建築
-
709. こまどり温泉33.553905 133.94273
#温泉
#レストラン・食堂
-
710. 横倉山約1,000mの山嶺で、珍しい植物、生物が生息し、高知県出身の植物学者・牧野富太郎博士の研究の地であったことでも知られています。33.535637 133.2077
県の史跡であり、横倉山県立自然公園に指定されています。
また、安徳天皇が隠れ住んだとされる平家伝説の地でもあり、宮内庁が管轄する安徳天皇御陵参考地や、数え23歳で亡くなるまで過ごしたと言われる行在所跡があります。
他にも源氏の追っ手が襲来した際、安徳天皇の避難場所にされたと言われる平家穴や、杉原神社、横倉宮等ゆかりの地が多数あります。安徳天皇も飲んだとされる湧き水「安徳水」は、昭和60(1985)年に環境庁の「全国名水百選」に指定されています。
源平の戦いに敗れた安徳天皇を擁する平 ...
約1,000mの山嶺で、珍しい植物、生物が生息し、高知県出身の植物学者・牧野富太郎博士の研究の地であったことでも知られています。 県の史跡であり、横倉山県立自然公園に指定されています。 また、安徳天皇が隠れ...
#景観(山)
#寺社
#文化財・史跡
#作品ゆかりの地
-
711. 横倉宮日本最古の4億年前の石灰岩から成る高さ約80メートルの断崖の上に建つ横倉宮。平清盛の四男で勇将として名を馳せた平知盛が、安徳天皇を玉室大神として祀った神社です。33.535877 133.20784
本殿は春日造り、拝殿は流造りとなっており、明治期には“御嶽(みたき)神社”、さらに古くは横倉山修験道の“上ノ宮”と称されています。
背後の断崖は敢えて危険を冒して断崖の先端に足を運ぶ人にちなみ、“馬鹿か否かを試す”という意味も含め「馬鹿試し」と呼ばれています。
石灰岩の岩上には、高知県出身の世界的植物学者・牧野富太郎博士の発見・命名による“横倉山タイプ植物”の「ヨコグラノキ」や「イワシデ」、「ヒナシャジン」などが自生しています。
日本最古の4億年前の石灰岩から成る高さ約80メートルの断崖の上に建つ横倉宮。平清盛の四男で勇将として名を馳せた平知盛が、安徳天皇を玉室大神として祀った神社です。 本殿は春日造り、拝殿は流造りとなっており ...
#寺社
-
712. JAグリーン四万十店ブランド米「しまんと農法米」をはじめ、旧中村市内でとれた旬の野菜や果物、魚介類、高知のブランド肉などが揃っています。32.986633 132.94008
ブランド米「しまんと農法米」をはじめ、旧中村市内でとれた旬の野菜や果物、魚介類、高知のブランド肉などが揃っています。
#市場・直売所
-
713. 帰全山公園蛇行する吉野川に囲まれるようにある県指定の自然公園。春には、桜やシャクナゲが咲き誇ります。入り口には、藩政時代の政治家で南学者としても知られる野中兼山の像が建ち、園内には兼山の母、秋田夫人の墓があります。通称「シャクナゲ公園」とも呼ばれ、4月中旬頃から5月初旬にかけてシャクナゲが咲き誇り、訪れる人を魅了しています。33.757725 133.59526
蛇行する吉野川に囲まれるようにある県指定の自然公園。春には、桜やシャクナゲが咲き誇ります。入り口には、藩政時代の政治家で南学者としても知られる野中兼山の像が建ち、園内には兼山の母、秋田夫人の墓があり...
#公園
#花・植物
-
714. 井ノ岬温泉土佐ユートピアカントリークラブ内にある井ノ岬温泉は、弱アルカリ性低調性低温泉で神経痛や冷え性など効能効果があり、健康増進に良いと言われています。33.054016 133.03769
土佐ユートピアカントリークラブ内にある井ノ岬温泉は、弱アルカリ性低調性低温泉で神経痛や冷え性など効能効果があり、健康増進に良いと言われています。
#温泉
-
715. 田野学館跡安政元年(1854年)安芸郡奉行所の敷地内に建てられた藩校。設立の目的は安芸郡の子弟たちの教育および海岸警備の兵隊育成で、中岡慎太郎はここで武市半平太や間崎滄浪と出会い影響を受けました。33.433853 134.01112
岩崎弥太郎が、父と親族とのもめ事の件で投獄された場所もここであり、阿波(徳島県)から引き渡された二十三士もここに投獄されました。
現在は高知県立中芸高等学校が建っています。
安政元年(1854年)安芸郡奉行所の敷地内に建てられた藩校。設立の目的は安芸郡の子弟たちの教育および海岸警備の兵隊育成で、中岡慎太郎はここで武市半平太や間崎滄浪と出会い影響を受けました。 岩崎弥太郎が、父...
#文化財・史跡
-
716. 杉原神社横倉山修験の中ノ宮として創建され、社は金峯山[きんぷせん]三所蔵王権現と称されていましたが、明治4年(1871)杉原神社と改称されました。33.53695 133.209
本殿は明治8年(1875年)改築、本殿周囲の彫刻は門井宗吉作。
境内には樹齢約500年から600年の巨杉を始め多くの杉がうっそうと茂り、独特の雰囲気を醸し出しています。本殿周囲の彫刻は精巧で素晴らしく、みどころのひとつです。横倉山修験道の中ノ宮にあたります。
横倉山修験の中ノ宮として創建され、社は金峯山[きんぷせん]三所蔵王権現と称されていましたが、明治4年(1871)杉原神社と改称されました。 本殿は明治8年(1875年)改築、本殿周囲の彫刻は門井宗吉作。 境内には ...
#寺社
-
717. 西黒森標高1861m。33.793858 133.20668
春・夏の緑、秋は紅葉が美しい。春は瓶ヶ森との間の鞍部でアケボノツツジ等の花も楽しめます。
標高1861m。 春・夏の緑、秋は紅葉が美しい。春は瓶ヶ森との間の鞍部でアケボノツツジ等の花も楽しめます。
#景観(山)
-
718. 片岡健吉の生家跡明治時代の自由民権家である片岡健吉は、土佐藩士として戊辰戦争に参加後、イギリスに留学。33.558224 133.53766
帰国後は立志社社長をつとめ、終始自由民権運動の先頭に立ちました。
第1回衆議院選挙以降当選を重ね、衆議院議長としても活躍。
また同志社社長として教育の発展にも尽力しました。
明治時代の自由民権家である片岡健吉は、土佐藩士として戊辰戦争に参加後、イギリスに留学。 帰国後は立志社社長をつとめ、終始自由民権運動の先頭に立ちました。 第1回衆議院選挙以降当選を重ね、衆議院議長とし ...
#文化財・史跡
-
719. 平家平標高1693m。33.79618 133.33505
全周囲が開かれた尾根からの見晴らしが美しく、国体の山岳競技コースにも使われた登り応えのある山。
頂上からの眺望が良く、コメツツジ群落やブナ林等が楽しめます。
標高1693m。 全周囲が開かれた尾根からの見晴らしが美しく、国体の山岳競技コースにも使われた登り応えのある山。 頂上からの眺望が良く、コメツツジ群落やブナ林等が楽しめます。
#景観(山)
-
720. 土曜市(仁淀川町)33.57418 133.16693
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
721. 日曜市(四万十市)32.9927 132.93329
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
722. 金曜憩いの市(宿毛市)32.9358 132.71924
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
723. 種崎海水浴場例年、海の日から8月末日まで種崎観光協会が開設しています。33.50329 133.57076
例年、海の日から8月末日まで種崎観光協会が開設しています。
#海あそび
#景観(海)
-
724. 二十三士公園春には満開の桜で、お花見ができます。33.430336 134.01707
駐車スペースや遊具もあり、トイレや温泉施設も近くにあることから、キャンプには最適の場所になっています。
幕末の土佐藩士・清岡道之助、以下二十三士が処刑された場所であることから記念碑が建てられ、公園にはその名が付けられています。
春には満開の桜で、お花見ができます。 駐車スペースや遊具もあり、トイレや温泉施設も近くにあることから、キャンプには最適の場所になっています。 幕末の土佐藩士・清岡道之助、以下二十三士が処刑された場所で ...
#花・植物
#公園
#文化財・史跡
-
725. 安徳天皇御陵伝説地安徳天皇擁する平家一門が源氏の追っ手から逃れて、ここで暮らしたと伝わる仁淀川町別枝都地区。33.51348 133.05283
安徳天皇は、1195年(建久6年)8月22日に18歳の若さで逝去されたと言い伝えられており、1933年(昭和8年)に安徳天皇御陵伝説地の指定を受けた御陵墓がこの地にあります。
御陵墓は“皇陵塚”と称され、毎年旧暦8月22日には住民によって都の太鼓踊りが行われています。
また、安徳天皇の乳母とされる女性も屋敷跡地から、この地に改葬されています。
安徳天皇のお守り役も務めた京都山城の国金子城主・平重詮(しげのり)は、源氏の追っ手から逃れるため中山重則(しげのり)、山内神助と名前を変えて暮らし、その後、西森姓に改姓した子孫が現在も系譜 ...
安徳天皇擁する平家一門が源氏の追っ手から逃れて、ここで暮らしたと伝わる仁淀川町別枝都地区。 安徳天皇は、1195年(建久6年)8月22日に18歳の若さで逝去されたと言い伝えられており、1933年(昭和8年)に安徳天皇御 ...
#文化財・史跡
-
726. 日曜市(宿毛市)32.9288 132.70767
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
727. 土曜市(宿毛市)32.9288 132.70767
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
728. 大豊町観光開発協会高知県の嶺北地域にある、吉野川と山地に囲まれた自然あふれる大豊町。「おいでよおおとよプロジェクト」を立ち上げ、四国山地の中央部・大豊町の観光やイベントの情報を発信しています。33.76428 133.66417
高知県の嶺北地域にある、吉野川と山地に囲まれた自然あふれる大豊町。「おいでよおおとよプロジェクト」を立ち上げ、四国山地の中央部・大豊町の観光やイベントの情報を発信しています。
#観光案内所
-
729. ふるさと市(香美市)33.603687 133.68715
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
730. 久礼城跡土佐久礼駅の西側、国道56号線沿いにある、土佐一条氏の重臣佐竹氏の居城跡。佐竹氏はのちに長宗我部氏の軍門に下り、大阪夏の陣で長宗我部盛親と命運をともにしました。33.32803 133.22218
土佐久礼駅の西側、国道56号線沿いにある、土佐一条氏の重臣佐竹氏の居城跡。佐竹氏はのちに長宗我部氏の軍門に下り、大阪夏の陣で長宗我部盛親と命運をともにしました。
#文化財・史跡
-
731. 四万十町郷土資料館豊富な遺産や遺跡出土品や古文書の資料、四万十の漁具や川船等を展示しています。33.18347 132.97287
豊富な遺産や遺跡出土品や古文書の資料、四万十の漁具や川船等を展示しています。
#ミュージアム
-
732. 本山町観光協会板垣退助の先祖ゆかりの地である本山町にあり、周辺のオススメスポットを発信。また、気軽に楽しく参加できる企画もしており、さまざまな学習や体験メニューを用意しています。33.759697 133.59
板垣退助の先祖ゆかりの地である本山町にあり、周辺のオススメスポットを発信。また、気軽に楽しく参加できる企画もしており、さまざまな学習や体験メニューを用意しています。
#観光案内所
-
733. 立川PA(下り)33.817646 133.66527
#おみやげ
#レストラン・食堂
#道の駅・休憩所
-
734. 佐川の大樟県指定の天然記念物。33.514008 133.2896
佐川で来歴の古い神社とされる諏訪神社の境内にあり、高さ36m、周囲8m、岩盤上の根元まわりは12mあります。樹齢800年(推定)。
人目につく平地に面した山麓の巨木として珍しい神樹です。
県指定の天然記念物。 佐川で来歴の古い神社とされる諏訪神社の境内にあり、高さ36m、周囲8m、岩盤上の根元まわりは12mあります。樹齢800年(推定)。 人目につく平地に面した山麓の巨木として珍しい神樹です。
#花・植物
-
735. 日曜市(須崎市)33.38984 133.28732
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
736. 鵜来島日本有数の透明度を誇る海に囲まれ、高知県の最西端に位置します。島内は道路が無く車が1台も無いので、時が止まったような感覚が味わえます。海水浴、ダイビング、磯釣りなど、マリンレジャーを存分に楽しめます。32.802177 132.48956
日本有数の透明度を誇る海に囲まれ、高知県の最西端に位置します。島内は道路が無く車が1台も無いので、時が止まったような感覚が味わえます。海水浴、ダイビング、磯釣りなど、マリンレジャーを存分に楽しめます。
#景観(海)
-
737. 横倉山織田公園横倉山の南斜面遊歩道、登山口近くにある公園。春には園内に約100本のボタンザクラが咲き、登山道沿いのアジサイやツツジが花を開く。花見やバードウオッチングに訪れる人の多いスポット。33.535564 133.22377
横倉山の南斜面遊歩道、登山口近くにある公園。春には園内に約100本のボタンザクラが咲き、登山道沿いのアジサイやツツジが花を開く。花見やバードウオッチングに訪れる人の多いスポット。
#公園
#花・植物
-
738. 紙のまちいの町の町並みいの町の市街地には、いまもむかしの面影を残す紙問屋の商家や漆喰壁の民家が点在し、時代を映す豪壮な商家の町並みに、紙の町として発展した栄華の跡を偲べます。33.5491 133.42479
いの町の市街地には、いまもむかしの面影を残す紙問屋の商家や漆喰壁の民家が点在し、時代を映す豪壮な商家の町並みに、紙の町として発展した栄華の跡を偲べます。
#町並み
-
739. 木曜市(須崎市)33.390945 133.29091
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
740. 笹ヶ峰標高1131m。高知平野や太平洋の眺望が見どころ。山頂はアセビやオンツツジが多く、四季を通じてハイキングコースに最適。33.692913 133.55981
標高1131m。高知平野や太平洋の眺望が見どころ。山頂はアセビやオンツツジが多く、四季を通じてハイキングコースに最適。
#景観(山)
-
741. 野根の朝市(東洋町)地元主婦のグループ・野根キッチンが運営する土曜の朝市で、地元産の野菜や魚、加工品などが店先に並びます。第2、第4土曜日のみ販売されている、古くから東洋町に伝わる郷土料理「こけらずし」はすぐに売り切れてしまう人気商品。33.503387 134.26913
地元主婦のグループ・野根キッチンが運営する土曜の朝市で、地元産の野菜や魚、加工品などが店先に並びます。第2、第4土曜日のみ販売されている、古くから東洋町に伝わる郷土料理「こけらずし」はすぐに売り切れて ...
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
742. 金林寺薬師堂高知県東部の山間にひっそりとたたずむ金林寺は、高野山真言宗に属し、平安時代後期に創建されたと伝わる由緒ある寺院です。地域の信仰を支える拠点として、長い年月を重ねてきました。33.55078 134.04678
薬師堂は、桁行3間・梁間4間という構造で、外陣と内陣を備えた造り。寄棟造・銅板葺の屋根と、室町時代中~後期の建築様式をよく残しています。中でも永正15年(1518年)に造られたとされる厨子は、当時の工匠の技を今に伝える貴重な遺品。
また、垂木を使わずに板軒で仕上げるという独自の技法は、簡素ながらも檜や杉といった上質な木材を活かした優美な外観を生み出しています。16世紀初頭以前に遡る建築としては四国中・南部でも極めて稀であり、この地域...
高知県東部の山間にひっそりとたたずむ金林寺は、高野山真言宗に属し、平安時代後期に創建されたと伝わる由緒ある寺院です。地域の信仰を支える拠点として、長い年月を重ねてきました。 薬師堂は、桁行3間・梁間4...
#寺社
-
743. 高岡日曜市(土佐市)33.496773 133.42337
#おみやげ
#高知県産
#市場・直売所
-
744. 四万十川野鳥自然公園四万十川河口近くの間崎地区にある、自然豊かな遊水地を囲む公園。公園内には誘致林や浮島が整備され、オオヨシキリ、セッカ、ホオジロ等をはじめとする草地・荒地性の野鳥が生息。三棟ある観察小屋からは四季折々の野鳥を見ることができます。32.939938 132.97157
四万十川河口近くの間崎地区にある、自然豊かな遊水地を囲む公園。公園内には誘致林や浮島が整備され、オオヨシキリ、セッカ、ホオジロ等をはじめとする草地・荒地性の野鳥が生息。三棟ある観察小屋からは四季折々...
#公園
-
745. 桐見ダム(桐見湖)仁淀川支流坂折川に築造された治水ダム。坂折川流域は霧が多く良質の茶の産地としても知られています。県立自然公園横倉山の麓にあり、横倉山の眺望が楽しめる展望広場、湖水に突き出した大桐広場等ダム湖の周囲は公園として整備されています。33.523396 133.21391
仁淀川支流坂折川に築造された治水ダム。坂折川流域は霧が多く良質の茶の産地としても知られています。県立自然公園横倉山の麓にあり、横倉山の眺望が楽しめる展望広場、湖水に突き出した大桐広場等ダム湖の周囲は...
#景観(川)
#建築
-
746. 陣ヶ森標高1029m。県立自然公園にも指定されており、四季を通じて周囲の景観はすばらしいです。アセビ群生あり。33.690186 133.42462
標高1029m。県立自然公園にも指定されており、四季を通じて周囲の景観はすばらしいです。アセビ群生あり。
#景観(山)
-
747. 一条教房墓高知県指定の史跡。一条教房は、応仁の乱を逃れ、家領のあった幡多庄に下向し、土佐一条氏の始祖となりました。為松公園北側の登山道沿いにある五輪塔。32.998337 132.92995
高知県指定の史跡。一条教房は、応仁の乱を逃れ、家領のあった幡多庄に下向し、土佐一条氏の始祖となりました。為松公園北側の登山道沿いにある五輪塔。
#文化財・史跡
-
748. 宿毛城跡宿毛山内氏の居城跡。現在は石鎚神社が立っています。32.941345 132.7297
この城は山内一豊の甥、安東可氏(あんどうよしうじ)が山内姓を許され、1601(慶長6)年から宿毛6千石の居城としました。別名を松田城といい、元和の一国一城令により廃城となりました。
宿毛山内氏の居城跡。現在は石鎚神社が立っています。 この城は山内一豊の甥、安東可氏(あんどうよしうじ)が山内姓を許され、1601(慶長6)年から宿毛6千石の居城としました。別名を松田城といい、元和の一国一城 ...
#文化財・史跡
-
749. 長谷渓谷澄んだ空気とおいしい水と、四季折々の色彩が美しい長谷渓谷。知る人ぞ知る秘境で、夏にはシャワークライミング(沢登り)体験が人気を博しています。33.490105 133.22598
澄んだ空気とおいしい水と、四季折々の色彩が美しい長谷渓谷。知る人ぞ知る秘境で、夏にはシャワークライミング(沢登り)体験が人気を博しています。
#景観(川)
-
750. 本山城跡戦土佐七守護の一人・本山氏の居城跡。本山氏は一時高知平野に進出、土佐、吾川両郡を制するが、長宗我部氏に滅ぼされました。33.7555 133.58788
城跡は上街公園の南の山上にあり、現在は城山公園となっています。
戦土佐七守護の一人・本山氏の居城跡。本山氏は一時高知平野に進出、土佐、吾川両郡を制するが、長宗我部氏に滅ぼされました。 城跡は上街公園の南の山上にあり、現在は城山公園となっています。
#文化財・史跡
-
751. 馬路村天保の民家馬路村指定文化財。馬路村で現存する最も古い天保年間の民家に属し、県下の山村型民家としても古い形式を残しています。33.55759 134.0474
馬路村指定文化財。馬路村で現存する最も古い天保年間の民家に属し、県下の山村型民家としても古い形式を残しています。
#建築
-
752. 不破八幡宮本殿現在の本殿は永禄元年(1558)頃再建されたもの。国の重要文化財。室町時代の建築様式が色濃く漂っている本殿は三間社流造りで、屋根はこけら葺き。32.980686 132.9374
現在の本殿は永禄元年(1558)頃再建されたもの。国の重要文化財。室町時代の建築様式が色濃く漂っている本殿は三間社流造りで、屋根はこけら葺き。
#寺社
-
753. 国見山標高1470m。樹齢150年以上のヒノキに覆われ、山頂一帯の白骨林は絶景。片道約1時間の手頃な登山が楽しめ、ヒノキの林とシャクナゲの花の取り合わせが見どころです。33.641098 133.42667
標高1470m。樹齢150年以上のヒノキに覆われ、山頂一帯の白骨林は絶景。片道約1時間の手頃な登山が楽しめ、ヒノキの林とシャクナゲの花の取り合わせが見どころです。
#景観(山)
-
754. 虚空蔵山虚空蔵山の頂上は、室戸岬から足摺岬まで太平洋を一望でき、幾重にも重なる四国山地の山並みを目の前にすることができるすばらしい眺望です。33.45866 133.30594
虚空蔵山の頂上は、室戸岬から足摺岬まで太平洋を一望でき、幾重にも重なる四国山地の山並みを目の前にすることができるすばらしい眺望です。
#景観(山)
-
755. 氏仏堂仁淀川町椿山地区の中央にある氏仏堂は、屋根の葺き方や堂内部の装飾などに特徴があるお堂で、内部の彫刻には平家ガニがあしらわれてます。33.675323 133.14435
この堂内には梁が逗子を上から押さえつけ、その下には古来より開けることを禁じた“不開(あかず)の箱”が置かれており、梁を動かし氏仏堂を解体しない限り開けられないことから、平家に伝わる宝刀や落人が奉持した氏仏像が収められているなど、様々な言い伝えが残されています。
仁淀川町椿山地区の中央にある氏仏堂は、屋根の葺き方や堂内部の装飾などに特徴があるお堂で、内部の彫刻には平家ガニがあしらわれてます。 この堂内には梁が逗子を上から押さえつけ、その下には古来より開けるこ ...
#文化財・史跡
-
756. 野中兼山墓江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。33.548695 133.53699
藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する等、大きな功績を上げました。
しかし、厳しすぎる姿勢が領民や上級武士の反感を買うなどして失脚、兼山の死後は野中家はお取り潰しとなりました。
墓所は娘・婉の建立による。高知市指定史跡文化財。
江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。 藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する等...
#文化財・史跡
-
757. 津野山舞台高知県指定の有形民俗文化財。四万川の円明寺、越知面の三嶋五社神社、宮野々の白尾神社の3か所にある農村舞台。33.401062 132.88405
※廻り舞台の扉は施錠されていますので、外観のみ見学可能です。
高知県指定の有形民俗文化財。四万川の円明寺、越知面の三嶋五社神社、宮野々の白尾神社の3か所にある農村舞台。 ※廻り舞台の扉は施錠されていますので、外観のみ見学可能です。
#文化財・史跡
-
758. 河戸堰河戸堰は、国道56号線の宿毛大橋の上流200mにあり、長さ184m・幅20mの石塁で松田川の水をせき止め両岸に水門を構えます。長宗我部時代(戦国~安土桃山時代)に宿毛大関が築かれ、藩政時代に野中兼山の指導を受けた3代領主山内節氏が完成させました。32.940514 132.73163
河戸堰は、国道56号線の宿毛大橋の上流200mにあり、長さ184m・幅20mの石塁で松田川の水をせき止め両岸に水門を構えます。長宗我部時代(戦国~安土桃山時代)に宿毛大関が築かれ、藩政時代に野中兼山の指導を受けた3代 ...
#文化財・史跡
-
759. 香山寺市民の森香山寺山の一帯に整備された市民公園。32.974514 132.92482
ハイキングや森林浴に最適のスポットとして知られています。
園内には、弘法大師ゆかりの香山寺をはじめとする名所旧跡も点在しています。
また、4月には市の花である藤が開花し訪れた方の心を和ませてくれます。
香山寺山の一帯に整備された市民公園。 ハイキングや森林浴に最適のスポットとして知られています。 園内には、弘法大師ゆかりの香山寺をはじめとする名所旧跡も点在しています。 また、4月には市の花である藤が ...
#景観(山)
#公園
-
760. 久保谷山自然林(春分峠)県道322号の四万十町と梼原町の境界が春分峠。樹齢100~150年の自然林が一望できる春分峠から見渡す風景は素晴らしく、多くのハイキング客が訪れています。33.316128 133.03033
県道322号の四万十町と梼原町の境界が春分峠。樹齢100~150年の自然林が一望できる春分峠から見渡す風景は素晴らしく、多くのハイキング客が訪れています。
#景観(山)
-
761. 高野の廻り舞台4年に1回行われる高野農村歌舞伎の舞台で、明治6年(1873年)に建築され、舞台裏でハンドル操作により舞台を回転させる「鍋蓋上廻し式皿廻し式舞台」です。33.39206 132.97803
昭和52年(1977年)国指定重要有形民俗文化財となりました。
4年に1回行われる高野農村歌舞伎の舞台で、明治6年(1873年)に建築され、舞台裏でハンドル操作により舞台を回転させる「鍋蓋上廻し式皿廻し式舞台」です。 昭和52年(1977年)国指定重要有形民俗文化財となりました。
#文化財・史跡
-
762. 中平善之進像両手を広げて仁王立ちになり、はやりたつ民衆を押し止める庄屋・中平善之進の銅像。宝暦の時代、藩の制度により窮乏した津野山の農民達を救おうとし、打首の刑に処せられた善之進の遺徳を偲んでつくられました。国道を挟んで対する位置には、善之進の霊を祭った風神鎮塚が建てられています。33.392082 132.97795
両手を広げて仁王立ちになり、はやりたつ民衆を押し止める庄屋・中平善之進の銅像。宝暦の時代、藩の制度により窮乏した津野山の農民達を救おうとし、打首の刑に処せられた善之進の遺徳を偲んでつくられました。国...
#銅像・記念碑
-
763. 五社神社【東洋町】1632(寛永9)年、一面の砂浜であった白浜を、浪人を集めて開発した明神忠右衛門を祀る神社。33.54473 134.29099
毎年4月末に行われる大祭は、神社前で神輿とだんじりがぶつかり合い迫力満点です。
1632(寛永9)年、一面の砂浜であった白浜を、浪人を集めて開発した明神忠右衛門を祀る神社。 毎年4月末に行われる大祭は、神社前で神輿とだんじりがぶつかり合い迫力満点です。
#寺社
#文化財・史跡
-
764. 佐喜浜の経塚法華経経典を経筒に納め土中に埋め、現世未来の御利益を祈り衆生の済度を希求したもの。県内最古の古碑であり県の史跡に指定されています。33.39423 134.20444
法華経経典を経筒に納め土中に埋め、現世未来の御利益を祈り衆生の済度を希求したもの。県内最古の古碑であり県の史跡に指定されています。
#文化財・史跡
-
765. 堂ケ森標高857m。戦国の公家大名一条氏の時代に開かれた霊山。6.4haにわたってモミ、ツガ、シイノキ、アカガシ等が混交する天然林が広がり風景林に指定されています。頂上近くまで車で入ることができます。33.159348 132.87651
標高857m。戦国の公家大名一条氏の時代に開かれた霊山。6.4haにわたってモミ、ツガ、シイノキ、アカガシ等が混交する天然林が広がり風景林に指定されています。頂上近くまで車で入ることができます。
#景観(山)
-
766. 黒森山標高1017m。ふもとから山頂まで車で行くことができます。道の勾配もなだらか。四国山地の山々の眺望に加え、天気が良ければ太平洋も見渡せます。かつて松山街道が通っていました。33.594124 133.21355
標高1017m。ふもとから山頂まで車で行くことができます。道の勾配もなだらか。四国山地の山々の眺望に加え、天気が良ければ太平洋も見渡せます。かつて松山街道が通っていました。
#景観(山)
-
767. 福田寺武市半平太の釈放を求め決起し、奈半利河原で斬首された野根山二十三士の墓の他、石田英吉が建立した二十三士の碑や武市半平太像もあります。33.42837 134.0137
浄土宗西山派で、境内に建つ薬師堂には平安時代末期の作と思われる破損仏を始め、数体の仏像が安置されています。
武市半平太の釈放を求め決起し、奈半利河原で斬首された野根山二十三士の墓の他、石田英吉が建立した二十三士の碑や武市半平太像もあります。 浄土宗西山派で、境内に建つ薬師堂には平安時代末期の作と思われる破 ...
#寺社
#文化財・史跡
-
768. 仁井田のヒロハチシャの木根回り8.5m、幹囲4.8m、樹高14m。33.277195 133.15106
ヒロハチシャノキは、暖地の山中にまれに自生する落葉高木で、5月下旬に直径1cmほどの、香りの強い乳白色の花を開き、10月ごろ丸い黄色の実をつけます。
根回り8.5m、幹囲4.8m、樹高14m。 ヒロハチシャノキは、暖地の山中にまれに自生する落葉高木で、5月下旬に直径1cmほどの、香りの強い乳白色の花を開き、10月ごろ丸い黄色の実をつけます。
#花・植物
-
769. 月山神社32.762146 132.75096
#寺社
-
770. 長谷寺(まき寺)槇牧山平等院長谷寺(しんぼくざんびょうどういんちょうこくじ)と言い、臨済宗妙心寺派の末寺で、本尊は十一面観音。33.595913 133.8248
伝説によれば、神亀4(727)年、行基によって開かれ、はじめ物部村中津尾(現香美市物部町)にあり、のち芸西村に移り、さらに現在地に移転してきたものといわれ、もとは吸江寺に属しました。
明治4(1871)年廃寺となりましたが、同12年大修理を加え、同16年3月再興しました。
現本堂は、貞享2(1685)年に再建されたものです。
寺は香南市史跡、地蔵菩薩像は香南市保護有形文化財、梵鐘は高知県保護有形文化財に指定(S60.4.2指定)されています。
槇牧山平等院長谷寺(しんぼくざんびょうどういんちょうこくじ)と言い、臨済宗妙心寺派の末寺で、本尊は十一面観音。 伝説によれば、神亀4(727)年、行基によって開かれ、はじめ物部村中津尾(現香美市物部町)に...
#文化財・史跡
-
771. 成山和紙の里公園紙を漉く技術を伝えた新之丞の碑があり、土佐七色紙の発祥地として知られる成山。天気がいい日には仁淀川や太平洋・室戸岬方面まで見渡すことができ、ハイキングコースとして親しまれています。33.570423 133.407
紙を漉く技術を伝えた新之丞の碑があり、土佐七色紙の発祥地として知られる成山。天気がいい日には仁淀川や太平洋・室戸岬方面まで見渡すことができ、ハイキングコースとして親しまれています。
#公園
-
772. 野中兼山遺族の墓野中兼山は、江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。32.94016 132.72661
藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士を登用する等、大きな功績を上げました。
しかし、厳しすぎる姿勢が領民や上級武士の反感を買うなどして失脚、兼山の死後は野中家はお取り潰しとなりました。
兼山の正妻市や長男清七、次男欽六、五男希四郎、三女寛、五女将、六男貞四郎などの墓が林立し、草におおわれ、厳しい幽閉の生活を送った兼山一族の悲劇を今に伝えています。伊賀家初代可氏とその家族の墓もあります。
野中兼山は、江戸時代、初期の土佐藩で奉行として30年に渡り活躍した人物です。祖母は初代藩主・山内一豊の妹・合(ごう)でした。 藩政改革の命を受けて、堤防建設、新田開発、港の建築を行い、能力次第で下級武士...
#文化財・史跡
-
773. 千屋家墓地千屋家は和食の庄屋で、龍馬の下で活躍した千屋寅之助(菅野覚兵衛)はここの出身です。龍馬とは文久2年(1862年)頃に出会い、勝海舟の塾に入りました。龍馬の死後、お龍の妹君枝を妻としたことから、お龍は千屋家で世話になった時期があります。33.521294 133.81557
この墓地には、寅之助の父祖などの墓があります。寅之助と君枝の墓は東京にあります。
千屋家は和食の庄屋で、龍馬の下で活躍した千屋寅之助(菅野覚兵衛)はここの出身です。龍馬とは文久2年(1862年)頃に出会い、勝海舟の塾に入りました。龍馬の死後、お龍の妹君枝を妻としたことから、お龍は千屋家 ...
#文化財・史跡
-
774. 唐の谷の滝佐喜浜川の支流にある高さ30mの名瀑。33.40779 134.17798
佐喜浜川の支流にある高さ30mの名瀑。
#景観(川)
-
775. 純信堂文政12年(1829年)現在の土佐市市野々に生まれ、「坊さんかんざし買うを見た」のよさこい節で有名な純信を祀ったお堂。33.451485 133.33734
文政12年(1829年)現在の土佐市市野々に生まれ、「坊さんかんざし買うを見た」のよさこい節で有名な純信を祀ったお堂。
#文化財・史跡
-
776. 白王八幡宮安徳天皇擁する平家一門が源氏の追っ手から逃れて、ここで暮らしたと伝わる仁淀川町別枝都地区。33.502407 133.05023
安徳天皇が、平家一族の武運と再興を祈り建立したと言われるのが白王八幡宮です。
“白王”は“皇”の字を割いて2字としたもので、源氏に見つかることを恐れ、秘密にするためだったと伝わっています。
近くにある上名野川地区の安徳天皇ゆかりの地に黒王には黒王神社があります。これは白王八幡宮が“皇”であることを、ひいては安徳天皇の所在を覆い隠すため、白王と黒王で対立せしめたのではないかとみられています。
安徳天皇擁する平家一門が源氏の追っ手から逃れて、ここで暮らしたと伝わる仁淀川町別枝都地区。 安徳天皇が、平家一族の武運と再興を祈り建立したと言われるのが白王八幡宮です。 “白王”は“皇”の字を割いて2字...
#寺社
-
777. 森林公園「遊湯の里」四万十川源流・日野地川の渓谷にある松葉川温泉周辺に整備された公園。川のせせらぎを聞きながら歩く遊歩道では、ゆったりとした森林浴が楽しめます。毎年4月頃になると約120本の桜が植えられた広場に多くの花見客が訪れます。33.310352 133.0705
四万十川源流・日野地川の渓谷にある松葉川温泉周辺に整備された公園。川のせせらぎを聞きながら歩く遊歩道では、ゆったりとした森林浴が楽しめます。毎年4月頃になると約120本の桜が植えられた広場に多くの花見客 ...
#公園
#花・植物
-
778. 上久喜の花桃地域の新しい名所となるよう、15年架けて植えられた花桃の木。春になると、赤、白、ピンクの花を咲かせます。33.55404 133.15585
近くには、国の登録有形文化財でもある「久喜沈下橋」もあります。
地域の新しい名所となるよう、15年架けて植えられた花桃の木。春になると、赤、白、ピンクの花を咲かせます。 近くには、国の登録有形文化財でもある「久喜沈下橋」もあります。
#花・植物
-
779. 高知駅アンパンマン列車ひろば高知駅の中にあるアンパンマン列車ひろば。33.567326 133.54364
改札内の大階段を上がると、四国の風景を背景にアンパンマン列車の模型が走るメインオブジェが来場者を迎えます。
8000系アンパンマン列車とアンパンマントロッコのミニチュア車両もあり、記念撮影もできます。
※見学には乗車券や入場券などが必要です。
高知駅の中にあるアンパンマン列車ひろば。 改札内の大階段を上がると、四国の風景を背景にアンパンマン列車の模型が走るメインオブジェが来場者を迎えます。 8000系アンパンマン列車とアンパンマントロッコのミニ ...
#アミューズメント
#作品ゆかりの地
-
780. 引地橋の花桃春になると、約100本の花桃の木が、白やピンクのかわいらしい花を咲かせます。すぐそばには仁淀川が流れています。33.564774 133.15126
春になると、約100本の花桃の木が、白やピンクのかわいらしい花を咲かせます。すぐそばには仁淀川が流れています。
#花・植物